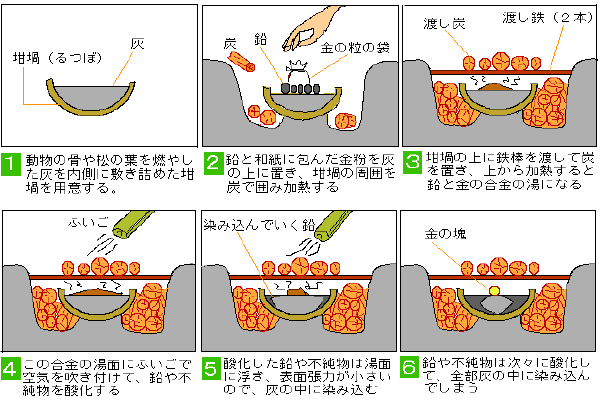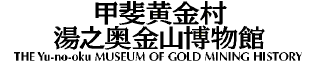印刷金山での作業|灰吹(はいふき)
灰吹
灰吹法の技術の歴史は非常に古く、西アジアでおよそ紀元前2000年くらいからあるとされているが、この技術が日本に伝えられたのはなぜか非常に遅く、記録によると戦国時代の1533年に博多の豪商である神谷寿禎が朝鮮の桂寿、宗丹を日本に招いたことに始まり(「石見銀山日記」「李朝実録」)、これが石見銀山での銀の精錬法としてもたらされ、この銀の灰吹がやがて金の精錬にも応用されるようになったといわれている。
灰吹とは、磨り臼や回転臼などによる粉成作業、そして汰り分けの工程を経て、鉱石から単体分離した金をさらに精製することである。
つまり前述の2工程のみでは取り除ききれず、金に付着したままの多少の石英や金そのものに含まれているヒ素や珪素などの不純物を取り除き、金の純度を高める重要な作業である。
坩堝(るつぼ)に動物の骨灰や松葉灰などを塗り固め、その上に和紙に包んだ金と、金と同様かまたはその半分くらいの量の鉛を置く。
和紙に包んだ金と鉛を溶かし合金の湯にするため、木炭を熱源として鞴(ふいご)で風を送り加熱する。
合金の湯ができたところで更に風を送りつづけ、この温度を1000℃近くまで上げる必要があるが、風を強く送ると逆に表面が冷やされて温度が上がりにくくなってしまうため、このときの風の強さは、そよ風程度でなければならない。
木炭に空気を吹き付けてこの温度を上げていくと、合金の湯に酸素がぶつかり、酸素と結合して鉛が酸化するが、この酸化鉛は非常に比重が軽いため、金と鉛の合金の上に浮き、浮いてきた酸化鉛は最初に塗り固めた骨灰の中に染み込んでいく。
いずれの金でも、熔けた状態では表面張力が非常に大きく、それは金と鉛の合金の場合も例外ではなく、灰の中に染み込むことができず、灰の上面に残る。

ところが、酸化鉛の場合は、とたんに表面張力が今までの10分の1ほどになってしまい、非常に濡れやすい状態となり、灰の間に染み込んでいく。
金は安定した金属で、表面張力も大きいまま変化しないため酸化しないが、金に付着していた石英分や砒素などの不純物は、鉛と同じように酸化され中へ染み込んでいく。
一部は灰の中へ染み込み、そうでないものは温度が上がる上方へ逃げて空中に揮発するため、純度の高い金だけが粒状になって坩堝に残る。
この技術が導入される以前は、産金した状態の金は精製する方法がなく、純度が低いまま使用されていたことになり、また産金地域によって品位もばらつきがあったため、国内や外国と取引する上での支障は免れなかったものと思われる。
こうした灰吹の登場は、日本全体の経済すら安定させる効果も含まれていた。
なお、黒川金山では、発掘調査時に溶融物付着土器片が22点出土し金粒が付着している土器も発見されている。中山金山でも発掘調査以降の研究と検証により金の溶融物付着土器が確認された。
近年の研究により、湯之奥3金山では「灰吹き」は行われていないことが分かっている。理由は、比較的自然金の状態でも純度の高い甲斐の金については精錬をそこまで必要とせず、また、その作業は「かわらけ」の上で金を熔かすというシンプルなものであったことが分かってきている。
図解灰吹