八、昆虫類
季節を象徴する、蝶類・蝉類・トンボ類・カブト虫類さらにはバッタ・コウロギ類は非常に多種類で詳述できないが、例をあげれば次のとおりである。(一)蝶の類
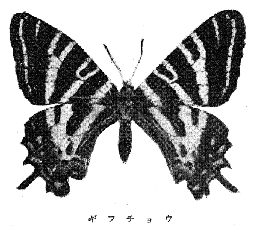
|
クロアゲハ・ミヤマカラスアゲハ・カラスアゲハ・オナガアゲハ・アゲハチョウ・キアゲハ・モンキアゲハ・アオスジアゲハ・ヒメギフチョウ・ウスバシロチョウ・ギフチョウ等12種で、食草からして北限と思われる蝶に、モンキアゲハ・アオスジアゲハ・ギフチョウがあり、ギフチョウは隣町の南部町が北限とされていたが町内身延山山林内にすみ雌は、幼虫の食草であるカンアオイを探して産卵する。
イ、シロチョウ科 7種
ヤマキチョウ・モンシロチョウ・ツマキチョウ・スジグロスジチョウ・ツマグロキチョウ・モンキチョウ・スジボソヤマキチョウ。
ウ、ヤダラチョウ科 1種
アザギマダラは1属1種の大型の優美な蝶で、あまり羽ばたかないで流れるように滑空し、羽はビニール様で特徴があり町内では大垈地内でよく見られる。
エ、タテハチョウ科 32種
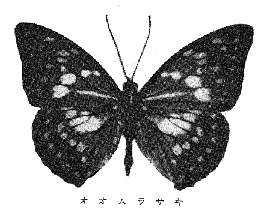
|
現在国蝶として75円の郵便切手となりその優美の姿とともに一般に親しまれている。
タテハチョウ科の蝶は、羽を立てると羽裏は樹皮に似ており優美さに欠けるが羽表はいずれも美しく、湿地に多く柳の葉を食草としているコムラサキの雄は、羽表から紫の幻想的な光を放ち、また優雅な鳥クジャクの羽根によく羽表が似ているクジャクチョウや、羽表が猛獣の豹の模様によく似ている。ヒョウモンドキをはじめ豹のつく蝶も9種ほど生息し、タテハチョウ科の蝶は低地から高地までの広範囲に及び他の蝶に比較し成虫越冬するものが多い。
オ、ジャノメチョウ科 12種
キマダラヒカゲ・ジャノメチョウ・ヒメジャノメ・コジャノメ・クロヒカゲヒメウラジャノメ稀有(けう)なものでツマジロウラジャノメ・ウラナミジャノメ・クロヒカゲモドキ・ヒメキマダラヒカゲ・キマダラモドキ・ヒメヒカゲ等が分布している。
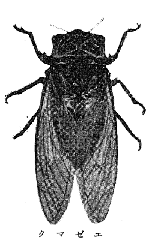
|
アカシジミ・ウラナミアカシジミ・ゴマシジミ・オオゴマシジミ・オオミドリシジミ・ミドリシジミ・ウラギンシジミ・オナガシジミ・シジミチョウ・トラフシジミ・コツバメ・ムラサキシジミ・ベニシジミ・ルリシジミ・ヤマトシジミ・ゴイシシジミ・ウラナミシジミ・ツバメシジミ・数少ないものにフジミドリシジミ・ウラジロミドリシジミ等20種が分布している。
キ、セセリチョウ科 11種
ミマヤセセリ・ヒメキマダラセセリ・チャバネセセリ・キバネセセリ・クロセセリ・アオバセセリ・ホソバセセリ・アカセセリ・ダイミョウセセリ・ミヤマチョウバネセセリ秋季西南に向って渡りをするイチモンジセセリ等である。
ク、テングチョウ科 1種
テングチョウは1科1種で発生は年1回6月ごろである。
(二)蝉の類
蝉の類では次の1目、1科、11種があげられる。|
名 称
|
鳴声、呼名、生息地
|
| 一 半 翅 目 (一) |
|
| 1 ハルゼミ | 「ギーン、ギーン、ギーン」と鳴き松林に多いので「マツゼミ」と呼ばれている。 |
| 2 エゾハルゼミ | 山地にすみ「ヨーギン、ヨーギンヒヒーン」と鳴き地方により「ミヨーギン」とも呼ばれている。 |
| 3 ニイニイゼミ | 「ニイー、ニイー」と鳴くので鳴声よりその名が生れており、小型の |
| 4 アブラゼミ | 「テンプラ」をあげるとき、油の煮たつ音に鳴声が似ているので、この名が生れたといわれている。 |
| 5 ヒグラシ | 一般には「カナ、カナ」または、キン、キン、キンと鳴くといわれている。 |
| 6 エゾゼミ | 北海道に非常に多い |
| 7 コエゾゼミ | エゾゼミに非常によく似ているが小型で、標高1,000メートル以上の高山に分布している。 |
| 8 ミンミンゼミ | 鳴声よりその名が生まれている。「ミーン、ミーン」と5・6声連呼する |
| 9 ツクツクボウシ | 鳴声からその名が生れている。「ホーシ」が先で「ツク、ツク」があとであるがこれを繰り返すので「ツクツクボーシ」と言われているのである。 |
| 10 クマゼミ | 黒い大型の |
| 11 チッチゼミ | 本邦産 |
(三)トンボの類
ヤンマのなかまでは、オニヤンマ・コシボソヤンマ・コオニヤンマ等が分布し、トンボのなかまには、シオカラトンボ・コシアキトンボ・ショウジョウトンボ・ナツアカネ・アキアカネ・シオヤトンボ・アオハダトンボ等が分布の主なるものである。(四)カブト虫の類
カブトムシ・カナブン・アオカナブン・クロカナブン・シロテンハナムグリ・コガネムシ・ヒメコガネ・ドウガネブイブイ等がコガネムシ科の主なものである。ノコギリクワガタ・ミヤマクワガタ・ヒラタクワガタ・アカアシクワガタ・コクワガタ等がクワガタムシ科で、ゾウムシ科にコクゾウムシ・コフキゾウムシ・ヒメシロコブゾウムシ・オトシブミ科にトロハマキチョッキリ・オトシブミ等が主なるもので、コマダラカミキリ・シロスジカミキリ・ヤマカミキリ・トラフカミキリ・キボシカミキリ等はカミキリムシ科で農作物に多大の被害を与えている。
(五)バッタ、コウロギの類
バッタ科にショウリョウバッタ・キチキチバッタ・カワラバッタ・イナゴ・トノサマバッタ等が分布している。コウロギ科にスズムシ・マツムシ・クサヒバリ・マダラスズ・ミツカドコウロギ・エンマコウロギ・カネタタキ・オカメコウロギ等が主なものである。
カマドウ科にマダラカマドウマ・キリギリス科にキリギリス・ウマオイムシ・クツワムシ・ツユムシ・セスジッユムシ等で、カマキリ科にオオカマキリ・カマキリ・コカマキリ・ハラビロカマキリ・ナナフシ科にナナフシ、ケラ科にケラ、ゴキブリ科にチャバネゴキブリ・クロバネゴキブリ等が分布している主なもので、クツワムシは本町が生息の北限である。

