三、哺乳類
鳥類の生息上好適条件をもつ本地域は、その生活に共通条件を有する獣類の分布の上にも理想的な天地である。 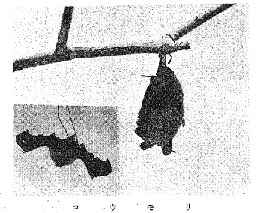
|
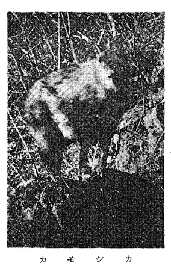
|
(一)カモシカは身延町の飛地1,989メートルの七面山、安倍峠一帯と東方の五宗山、三ッ石一帯の針葉樹林、草木帯付近の山岳中の岩石地帯及び断崖に好んで生息する草食性、日本特有の動物でヒツジににていてよく肥え、体高60センチメートルぐらいで、体長は1メートルぐらい、尾は短かく、頭に2本の角がある。全身灰黒色で、毛はやわらかく、密生している。
性質はきわめておとなしく、4、5月頃一仔を産むも産数が少なく、また高山の懸崖に住む関係で、雪崩のため墜落死、圧死等の災厄により年々減少の一途を辿っているので、この保護のため大正9年に天然記念物に指定され、さらに昭和30年に特別天然記念物に指定された珍獣で、菊科および豆科の草木類を好んで食べ、秋冬にはブナ・クリ・ナラ等の実を食べ生息している。
(二)ハクビシンは、昭和29年3月身延町樋之上地内で発見されたのが最初であるが実際には昭和24年頃から生息していた。
珍獣で台湾以外で見出されたのは初めてである。
どうして町内に分布したか、それが人為的分布か自然分布か動物界におけるなぞの一つであり、近年繁殖し西八代郡一帯(富士川東)の山野や町内相又地内でも見られ、初秋から初冬の間に、落花生・柿の実・ミミズ等を採食する。ジャコウ猫科動物である。
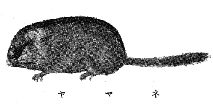
|
四、爬(は)虫類
晩秋から春さきまでの間、土中・岩石のき裂・石垣等でおもに越冬、ときおり草屋根等でも越冬し、春さきより晩秋までの間、山野から人家の周辺に生息する蛇類中マムシは、マムシ科で卵胎生である。游蛇科にシマヘビ・アオダイショウ・ヤマカガシ・ヒバカリ・ジムグリ・シロマダラの6種があり、シロマダラは稀有の種類であって、体長約50センチメートル、打紐のごとく、頭胴に淡白色の地に38条の黒褐色の帯斑がある。
カナヘビ科にカナヘビがあり、トカゲに似た尾の細長いものであるが、一般にトカゲと誤認されている。トカゲはトカゲ科である。
五、両生類
爬虫類と同様越冬するがその期間は多少長く、初冬から春さきまででヤマアカガエル・ニホンアカガエル・トノサマガエル・シエレーゲルアオガエル・ツチガエル・カジカガエル・モリアオガエル・ウシガエル等はアカガエル科に属し、アマガエル科にニホンアマガエル・ヒキガエル科にニホンヒキガエル等があり、この3科は無尾目で、サンショウウオ科のハコネサンショウウオ、イモリ科のイモリ等が生息している。 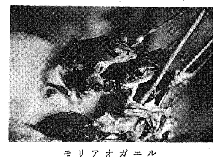
|
4月から6月に大きい泡状の卵塊を、沼、池等の水辺の樹上や草むらの上に産む、ふ化したおたまじゃくしは、卵塊の中でしばらく発育したのち、水中に落ちて成長する。水かきはよく発達し、吸盤は大きく、吸着力は他のカエルより強力である。
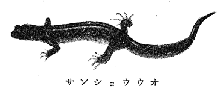
|
イモリ科のイモリは沼沢地に住むが雨天の場合は薮の上に登って昆虫を捕食する寄習がある。
カジカガエルは、普通カジカと呼ばれておるが、鰍(カジカ)はさかなであり本種は河鹿蛙と呼ぶのが正しいのである。
各河川の清流の石の上で「クーイツ、クーイツ」と可憐な鳴声でよく知られている。ウシガエルは、食用にするために、大正10年頃アメリカから輸入されたカエルで、町内の沼でときおり見ることがあり、鳴声は小牛に似ており、体は大きくニホンヒキガエルの2倍位である。
六、魚類
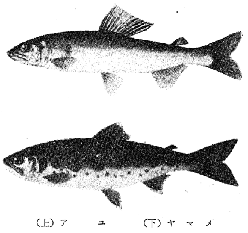
|
富士川・相又川・波木井川・大城川・御持川・桑柄沢川・その他町内の小河川にアユ・ウグイ・ヤマメ・アブラハヤ・フナ・コイ・モロコ・オイカワ・カジカ・ホウテク・メダカ・スナモグリ・ドジョウ・ウナギ・ナマズ等が主なものでライギョも時おり見ることができる。
相又川、波木井川には年々アユが放流され、更にこの2川にはヒメマス、ニジマスを年数回漁業団体等が放流し釣り人を楽しませている。
七、甲 (かく)類
(かく)類
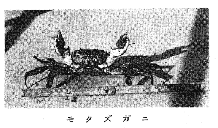
|
町内にはサワガニ・モクズガニ・アメリカザリガニ等が水辺の石の下や、土中に穴を掘り生息し一般にカニと呼ばれるのはサワガニである。
モクズガニは、身延を北限とするカニで、サワガニより数倍大きく、昭和17年頃までには容易に捕えることができたが近年は魚類同様な条件で激減し、時おり見かけることができるのみである。モクズガニは、全身灰黒色で、歩脚5対は灰黒色の短毛に覆われており、第1対の歩脚つけねには1センチメートルから2センチメートル位の毛が密生している。

