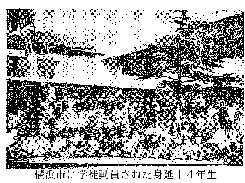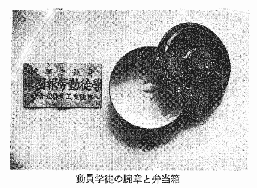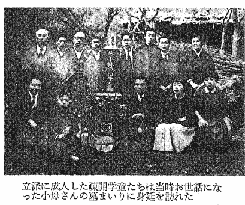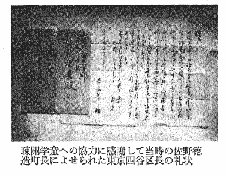四、学徒動員と身延中学校
このような状況下で、早くから学生生徒も勤労奉仕として出征兵士の家を慰問し、家事、援農などの作業が行なわれていたが、昭和18年6月25日の「学徒動員体制確立要綱」発令、19年の「学徒総動員令」布告により、全国の中学生から大学生までの学徒はペンを銃にハンマーにかえて前線にまた軍需工場へと「出陣」して行ったのである。県立身延中学校でも、5年生100名が先ず愛知県半田市の中島飛行機半田組立工場へ、次いで4年生約150名が横浜市の日産重工業株式会社へ、3年生約150名が川崎市の東京航空計器株式会社へ動員され、慣れない手に工作機械を操(あやつ)って兵器の生産に従事した。
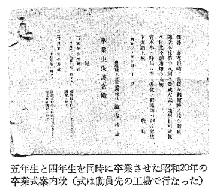
|
また、2年生と1年生は町内で松根掘りや援農活動・杉皮や丸太の搬出など、大人とかわらぬ重労働に汗を流して働らいた。
昭和20年には身延中学校の講堂も工場疎開のため、三井精機株式会社の工場となって工作機械がすえつけられ、プールも屋根をとりつけて倉庫に改造するなど、学園の様相も一変した。
その中から、予科練など、特攻隊につながる兵役へ志願し出征して行く生徒もあいつぎ、国のすみずみまで戦争に直結する切迫した空気が支配していた。
大野には軍艦を失った海軍の兵士数十名が泊りこんで援農活動や山仕事をするという奇異な情景もみられ、否定しがたい敗色が日にまし濃厚になっていったのである。
五、空襲の激化
日本の本土にいよいよ敵機の空襲による危険が迫るにつれ国内においては防空体制が強化されていった。各家庭ごとに、または共同で防空壕がほられ、バケツや火叩きが準備され、学校でも町内でもさかんに防火訓練が行なわれ、アメリカ軍の上陸にそなえて竹槍の訓練まで行なわれた。
また夜は一条の光ももらさないよう厳重な燈火管制が行なわれ敵機に備えたのであるが、マリアナ海域が敵の手におちて一大基地ができた昭和19年(1944)秋から空襲は本格化し、サイパン基地を飛び立ったB29爆撃機は軍事施設、航空機生産工場、輸送機関を的確に集中爆撃して潰滅させるとともに、一般民衆の戦意喪失をねらって黄リン・油脂・エレクトロンの焼夷弾による無差別じゅうたん爆撃が行なわれ、木造家屋の密集する日本の都市は次々に焼野原と化していった。
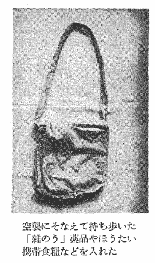
|
また、全国では206都市のうち98市が空襲と艦砲射撃で被爆し福井市の96%焼失を最高に、平均焼失率40%で全国都市家屋の30%強にあたった。
地方都市では甲府・浜松・日立市が70%以上焼失し、また京浜・阪神・中京地区も60%に及んだ。
マリアナ基地からの爆撃のほか硫黄島・沖縄からの来襲が加わり、さらに7月以降は艦載機も大挙来襲して非戦闘員をも低空射撃するようになった。
昭和20年1月以降の来襲米機は約4万5千機にのぼり、この空襲で死傷者66万5千人をかぞえ、国富の損失は現在の貨幣価値に換算すれば70兆円以上といわれている。
そして焼失家屋は全国住宅の2割にあたる230万戸、被災者は1千万人をこえたのである。
当時の身延町家庭防火群規約を左にかかげる。
身延町家庭防火群規約
第一条 身延町防空支部各部落詰所長ハ敵機襲来シ焼夷弾、瓦斯弾等投下ニ依リ生ズル家庭防火、防毒ノ危害ヲ尠カラシムル為メ家庭防火群ヲ設置シ其ノ完壁ヲ期スルモノトスル。
第二条 家庭防火群ハ各部落毎ニ常時家庭ニ在リ各世帯ノ婦人ヲ似テ編成シ各部落名ヲ附シ波木井家庭防火群、塩沢家庭防火群、新宿家庭防火群、身延家庭防火群、支院家庭防火群、梅平家庭防火群、大野家庭防火群トス。
第三条 各部落家庭防火群ハ是ヲ隣保組合毎ニ分ケ其ノ名称ヲ附シタル〇〇防火組トス。
第四条 家庭防火群ニハ群長一名、副群長一名、組長若干名ヲ置キ婦人会、女子青年団及其ノ他婦人団体ノ幹部ヲ以テ之ニ充ツ。
第五条 群長ハ防空支部長並ニ各部落詰所長ト連絡ヲ計リ組長並各群員指導ノ任ニ当ル、副群長ハ群長ヲ補佐シ群長事故アル場合ハ之ヲ代理ス、組長ハ防空下令アリタル場合ハ組員ヲ督励シ家庭防火防毒ノ任ニ当ルモノトス。
第六条 各家庭防火群員ハ常ニ自己家庭ニ防空防火用水槽、バケツ、金盥、消火器、水道ノ施設アルモノハ金具附キ水道用ホース(長サ一〇米以上ノモノ)並ニ防火土嚢等ヲ設備シ防空下令アリタル場合ハ直ニ軽装ニテ出動出来得ル様準備シ置クモノトス。
第七条 各家庭防火群員ハ防空下令アリ敵機襲来シ焼夷弾、瓦斯弾等投下アリタル場合ハ直チニ出動シ焼夷弾ナル場合ハ組合員中其ノ一人ハ空缶、金盥、バケツ等金属性具ヲ乱打シ、瓦斯弾投下シタル場合ハ板、木片等ヲ乱打シ「焼夷弾」或ハ「瓦斯弾」ト連呼シ一般ニ周知ス。他ノ防火群員ハ土嚢其ノ他防火防毒用備品ヲ以テ消火防毒ニ努メ被害ヲ最少範囲ニ止メ猶被害拡大ノ虞レアルト認メタルトキハ直チニ詰所長ニ通報シ各部落防火班ト協力シ防火防毒ノ任ニ当ルモノトス。
六、学童疎開
これよりさき、政府は空襲による最悪の事態を考慮して軍需生産等に従事できない大都市の老幼婦女子は地方は疎開させることとした。
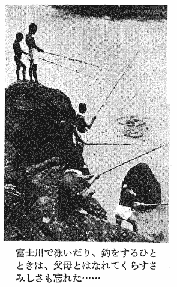
|
|
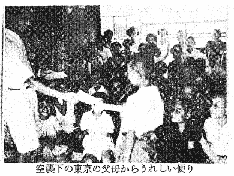
|
集団疎開児童の範囲は国民学校初等科(小学校)3年以上6年までで保護者の申請によることとなっていたが、緊迫した空気を反映して1、2年生の児童も集団疎開に加わっていた。
山梨県にもおよそ3,800名が疎開したのであるが、本町へも19年(1944)8月東京都芝区三光、四谷区第4、5、6、7の5国民学校の児童1,233名と教師39名、寮母65名が集団疎開してきた。
これらの疎開児童は身延駅、総門、門内の各旅館及び山内各宿坊に分宿し、引率教師が寮長となり寮母は東京からのものと現地から志望した婦人で児童の保健、衣食住のことについて面倒をみ教科は身延国民学校の責任となったので都の訓導は身延国民学校兼任となった。
夏休みが終るころにはすっかり疎開の体制も整い9月に入ってからは朝のうちは学寮で自習(各学年が混入しているので個人指導)それが終ると身延山内や富士川の河原を利用して体操や手旗信号の訓練、かけ足など大日本少年団や軍隊生活のような規律ある生活を送るようになった。
また午後は四谷第4は身延国民学校(現在の身延小学校)四谷第5は身延中学校(現在の高校)へ集まって教室や運動場を利用したのであるが、当時の児童の体力ではかなりつらいものであったらしく宿舎に残る児童も相当あったという。また三光は本山休憩所を教室にあて第6第7は祖山中学や宿舎で授業をした。
このようにして都会に住む両親から離れて疎開した児童の苦難の生活が続いたのであるが、戦局の悪化とともにあらゆる物資が欠乏したなかで集団疎開をうけ入れた旅館、宿坊の苦労も大へんなものであった。
発育ざかりの児童のため食糧の確保にはあらゆる努力が払われた。付添の教師は近村は勿論、遠く中巨摩までもリュックサックを背に協力を求めた。
また、周辺の村々の学校や愛国、国防婦人会の人達の協力で乏しいなかから食糧が調達され、配給量の少ない学童食を補ったりした。
常食としては、朝、晩は大豆(3〜5割)入りの麦飯に味噌汁、昼はホウトウであったがこれらは質的には当時としてはむしろ恵まれたものであった。
ときに暗く沈みがちな児童を励ましながら馴れない土地で子供とともに歯をくいしばって耐えていたのであった。
こうしたなかで翌20年3月から5月にかけて相次ぐ東京のじゅうたん爆撃で児童の出身地四谷区(現在の新宿区四谷)も灰燼に帰したためそれからは父母達の身延への往来が頻繁となり興奮と悲壮感に満ちた親子の対面に戦争の苛烈さをしみじみと感じさせた。
この年8月15日、日本が無条件降伏したことを知ると学寮の児童たちは可憐にもみな泣き伏してしまい異郷でうけた敗戦の悲しみは子供心に深く刻まれたのであった。
終戦後もしばらくは疎開学童の体制は解体できずに続けられたがそれでも敗戦の虚脱状態から徐々に立ちあがるに従い、父母が子供を引取りにきて文字どおり櫛の歯をひくように人数が減ってゆき、これに伴い学寮も統合されたが結局、11月19日帰京壮行式をあげ、すべての児童の引揚げが終ったのである。この間に町民は自分達も乏しい中から餅や履物や副食物を携えて学寮を慰問に訪れた。
東京の父母のもとを離れたまだ幼い子供達にとって「ほしがりません勝つまでは」を合言葉として耐え抜いた苦難の疎開生活のなかにも受入側の温かい心遣いが通じ合い当時の疎開児たちが成長して当時分宿した旅館などへ揃ってお礼に来て泊り、過ぎし日を偲び合い、また姉のようにやさしい寮母だった人がその後病のため故人となられたことを聞いて、分宿した疎開児全員で費用を出し合って墓碑を建て墓前にそれぞれの成長を報告するなど、涙ぐましい事実をみるにつけ苦しいなかにも人間愛の失われなかった尊いものを感ずるのである。(第16編参照)
七、ポツダム宣言、原爆、そして8月15日
本土の主要都市が空襲によって廃虚と化し、戦争遂行の能力は極度に低下していったなかにあって、軍部特に陸軍の本土決戦論と政府首脳のソ連を仲介としての和平論が対立して空しく日時を費していた。このころ連合国側は、ベルリン郊外のポツダムにおいて昭和20年7月17日(1945)アメリカ・イギリス・ソ連の首脳によってドイツ降伏後のヨーロッパの処理について討議が行なわれていたが、この会議の進行中の7月26日アメリカ・イギリス・中華民国の3国によって日本に無条件降伏を勧告する「ポツダム宣言」が発表された。
その内容は、
1、日本国民を欺瞞し、世界征服の挙に出させた権力および勢力の除去。
2、平和、安全、正義の新秩序が出来、戦争遂行能力の破砕が確認されるまで連合国が占領する。
3、日本国の主権は、本州、北海道、九州および四国と連合国の指定する小島に局限される。
4、日本軍隊の完全武装解除。
5、戦争犯罪人の処罰と、民主主義的傾向の復活強化の障礙(がい)の除去。
6、日本経済と産業の維持の保証、再軍備産業の禁止。
となっており右の条件が達成された暁には、占領軍は撤退すると述べ最後に次のように無条件降伏か潰(かい)滅かの即時決定を迫った。 吾等は日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、且つ右行動における同政府の誠意に付き適当且つ充分なる保障を提供せんことを同政府に対し要求す。
右以外の日本国の選択は迅速且つ完全なる壊滅あるのみ。
このようなポツダム宣言が通告されてからも日本はソ連の和平仲介に一縷(る)の望みを託し、また国体護持を固執する一部軍部の強硬論に押されてこれに応じようとしなかったのである。右以外の日本国の選択は迅速且つ完全なる壊滅あるのみ。
政府首脳が空しくソ連からの回答を待っていた8月6日、運命の原子爆弾が投下され広島は閃光と爆煙におおわれて一面廃虚と化した。
この1発の原爆によって市の60%が破壊しつくされ、罹災者176,987名で全市の60%に当り、死者および行方不明者は92,333名、重傷9,428名、軽傷37,997名に達した。
しかし、原爆病によってその後も死亡者が続出し結局死者は15万人を越えたとされている。
翌8月7日トルーマンアメリカ大統領は広島に投下したのは原子爆弾であること、日本が降伏しない場合は更に原爆攻撃を加えることを声明した。
大本営は、原爆を確認しながらもこれを新型爆弾と称して国民の動揺を防ぐことにつとめたが「ポツダム宣言」が発せられた際の「迅速且つ完全なる壊滅」が、かくも早く実現したことに大きな衝撃をうけた。さらに9日には長崎にも第2弾が投下されまたも7万4千人にのぼる犠牲者を出した。
日本国内が原爆投下で大混乱におちいっている8月8日夜、ソ連は突如参戦を通告してきた。
これはさきのヤルタ協定にもとづく予定の行動であったのであるが、8月9日午前零時を期してソ連軍は一斉に満州・朝鮮・樺太の国境線を突破して進攻してきたのである。
このソ連の参戦は、日本首脳部の戦争遂行についての希望のきずなを完全に断つこととなり、以後日本降伏に関する具体的な動きが慌だしくはじまった。
すなわち11時ごろから開かれた最高指導者会議、午後2時半より開かれた閣議において「ポツダム宣言」受諾についてそれぞれ討議されたのであるが、鈴木首相、東郷外相、米内海相等が受諾を是とするのに対し陸相および陸、海総長は断固戦争継続を主張したため、結論を得るに至らず、結局午後11時50分より開かれた深夜の御前会議にもちこまれたのであるが、これまた意見の一致をみるに至らず10日午前2時30分「ポツダム宣言」を受諾して戦争を終結するという天皇の裁断によって決せられたのである。
朝6時「ポツダム宣言」受諾の電報はスウェーデン、スイスを通じて米・英・ソ・華の4か国に伝えられた。
それは、「天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含しおらざることの了解の下に、ポツダム宣言を受託す。本件に関する明確なる意志が速かに表明せられんことを切望す」であった。
これに対し、4カ国の回答は「天皇の地位は降伏条項の実施のため、その必要と認める措置を執る連合軍司令官の制限のもとに置かれること、最終的な日本国の政府の形態は、「ポツダム宣言」に遵(したが)い、日本国国民の自由に表明する意思に依り決定せらるべきこと」というものであった。
この回答は天皇の地位について曖昧(あいまい)なものであったから国体護持を固執する抗戦論者は強く反発し首脳部のなかでも再び動揺がおこった。
このようななかで8月14日午前10時50分最後の御前会議が開かれ、天皇は10日の裁断と同じ決定を下すとともに、8月15日正午に天皇自ら終戦の放送を行なうことも決定された。
この直後抗戦と主張する一部軍人によるクーデターが起ったが、大事に至らず鎮圧され阿南陸相は責任を負って自刃した。
翌8月15日正午には日本の歴史上かってなかった天皇の「玉音放送」が予定どおり行なわれたのであった。
これまで「尽忠報国」「一億玉砕」一筋を説かれてきた国民には、この聞きとりにくい放送にすぐさまその意味をくみとれない者も少くなかった。
こうして日本は「ポツダム宣言」を受諾して降伏した。
植民地のすべてを失い、軍隊が解体されることが明らかになり、またこの戦争を推進してきた指導者もやがて排除されるはずであった。
明治以来の大日本帝国は、天皇の地位を国民の意思にゆだねたまま、ここに崩壊し蘆溝橋事件から8年、満州事変からかぞえれば実に14年にわたる戦争の時代はここに終止符が打たれたのである。
なお、この14年間に妻子や年老いた父母を後に残して戦死した本町出身者は379名(平均年齢27歳)であるが、この数はほぼ現在の大野区の総人口に匹敵し、しかもその遺骨さえ遺族のもとへ帰らなかった者もあり、戦争がいかに痛ましいものであるかをもの語っている。
また、この379名の中には、うら若い生命を戦場に落とした4名の従軍看護婦も含まれている。
| 本町出身の戦没者一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||
|