二、連合軍の反攻と戦局の転換
真珠湾奇襲攻撃はアメリカ、イギリスを一層結束させることとなり、わけてもアメリカは「真珠湾を忘れるな」の合言葉でイギリスとともに対日宣戦を布告し、昭和17年1月1日には26ヶ国からなる連合国が枢軸国に対抗して結束することが宣言された。アメリカは強大な経済力・工業力に物をいわせて急速に反撃の態勢を整えていった。
すなわち昭和17年(1942)4月18日には東京をはじめ川崎・横須賀・名古屋・四日市・神戸などの初空襲を手はじめに、5月8日の珊瑚海海戦につづいてミッドウェー海戦によって反撃のきっかけを掴んだ。6月4日から5日にかけてのミッドウェー海戦は山本連合艦隊司令長官みずから指揮する主力部隊戦艦7・空母1・南雲忠一中将指揮の機動部隊戦艦2・空母4・攻略部隊戦艦2・空母1・重巡洋艦8などを主体として艦艇総数350隻、飛行機1,000機、将兵10万の大部隊に対しアメリカはニミッツ太平洋艦隊司令長官指揮の3空母、7重巡洋艦を主力をする機動部隊で行なわれたのであるが、この作戦に関する日本の暗号がアメリカ側に解読されてしまったことによって、日本艦隊の作戦は重大な蹉跌(さてつ)を来たし敵の航空機によって4空母・1重巡洋艦・322機の飛行機、3,500名の兵員を失ってミッドウェー攻略戦は惨敗に終った。
この敗戦は、その後のわが軍の作戦行動に重大な影響を及ぼすこととなり攻守処を変える端緒となったのである。
なおこの作戦に呼応して行なわれたアリューシャン作戦は、本県出身の山崎大佐の指揮する部隊によって6月7、8日にわたってキスカ・アッツの両島が占領されている。守勢に回った日本軍は次第に制海・制空権を失っていった。昭和17年(1942)8月7日アメリカ軍がガダルカナル島に上陸してからの同島の攻防戦は凄惨を極め、補給の絶えた日本軍はまた飢餓との戦いでもあった。香港攻略戦に勇名を馳せ、後に軍神と仰がれた若林東一中尉が「あとに続くものを信ず」のことばを遺して壮烈な戦死を逐げたのもこの地であった。日本軍は物量を誇るアメリカ軍に敗れて、昭和18年(1943)2月1日から7日にかけて同島を撤退していった。
三、悲惨な敗戦へ
日本軍がミッドウェー海戦・ガダルカナル戦において敗北し、戦局に重大な転機を迎えたころ、ヨーロッパにおいてはそれまで破竹の勢で進攻していったドイツ軍が、昭和17年7月から昭和18年2月(1942〜1943)にかけてのスターリングラード攻防戦において大敗北を喫してソ連に反撃の機会を与えていたのである。南東太平洋諸島において物量に物をいわせて反撃に出たアメリカ軍のために次第に圧倒されはじめたころ、国内においては東条内閣の独裁がますます強化され、議会政治は形式的に存続するだけで翼賛政治一本となり憲兵隊や特高警察によってきびしい言論統制が行なわれ、戦争目的に向って国民思想の統一が推し進められていった。
また占領地政策を推進させるため大東亜省を新設し、フィリピン・ビルマなどには親日的指導者を中心に独立を認めて日本に協力させる体制を整える反面、マレー・スマトラ・ジャワ・ボルネオ・セレベスは日本の領土として重要資源の供給地とすることを決め、昭和18年(1943)11月5日には日本・中国(汪政権)・タイ・満州・フィリピン・ビルマの指導者および自由インド仮政府首班が参加して、東京において大東亜会議を開き大東亜の解放と共存共栄・独立親和・文化昂揚・互恵の原則での経済発展、人種差別の撤廃や文化交流・資源の開放により、世界の進運に貢献の五原則を宣言して結束の強化がはかられていた。
このようななかで戦局は日増しにきびしさを加え、昭和18年(1943)4月17日の山本連合艦隊司令長官の戦死は、前線将兵はもとより国内においても大きな衝撃であった。
また山本元帥戦死の直後の5月29日には、本県出身の山崎保代大佐が指揮するアリューシャン列島のアッツ島守備隊も玉砕した。
アメリカは、マッカーサーの指揮する米濠の陸軍とハルゼーの指揮する海軍によって、次々と日本軍の占領地を奪回し、また相次ぐ海空戦で日本の戦力を消耗させていった。
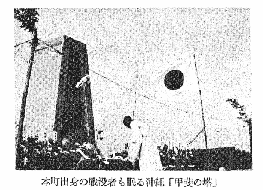
|
国内ではそのため、東条内閣が総辞職して小磯内閣に変ったが、戦局はますます急迫をつげ、間もなくフィリピンも奪われ3月27日には硫黄島も玉砕した。
一方ビルマ方面においてもインパール作戦が強行されたが、3,000メートルの山脈を越えてインド領内へ進攻するこの作戦は補給が続かず、イギリス軍の反撃にあって無残な敗北に終ったのである。
また中国戦線は広大な大陸に100万に及ぶ大軍が展開していたが、
アメリカ軍は、日本の南方占領地区を次々に奪回して、昭和20年4月1日には英機動部隊も含めて1,457隻の艦艇と母艦機1,727機の援護のもとに、18万3千の大軍を沖縄に上陸させた。
日本軍は牛島満中将指揮の陸軍7万、海軍8千に男女中等学校生徒を含む2万5千の義勇隊であった。
この沖縄防衛線において本町出身の9名の兵士が戦死しており、現在沖縄本島具志頭(ぐしかみ)村に建立された「甲斐の塔」に、多くの県出身戦死者とともに合祀されている。
昭和40年11月には、遺族と町民を代表して町長、議長が参拝している。
沖縄戦没者氏名
| 帯金 | 依田高寿 | (伍長) | ||
| 大島 | 牛田正一 | (伍長) | ||
| 下八木沢 | 芦沢金保 | (伍長) | ||
| 清子 | 遠藤六郎 | (伍長) | ||
| 下山 | 吉中一三 | (伍長) | ||
| 身延 | 望月宗一郎 | (伍長) | ||
| 大城 | 手塚勘治 | (伍長) | ||
| 相又 | 遠藤泰正 | (伍長) | ||
| 下山 | 佐野高次郎 | (伍長) | ||
この防衛戦でひめゆり部隊のいたましい最期など数多くの悲惨な場面もあって、沖縄の悲劇は今もなお人々の胸に深く刻まれているのである。
こうして日本は海外の拠点をことごとく奪回され、また大陸の戦局も極めて急迫した状態となって敗色はますます濃厚となっていったのであるが、一方枢軸国イタリアはすでに昭和18年(1943)9月連合国に降伏し、20年(1945)5月にはドイツも降伏して、日本は文字通り孤立無援で世界を相手とする窮地に立たされることとなった。

