第六編 産業と経済
第一章 江戸時代の産業と経済
第一節 世情と産業
一、検地
検地とは、土地の境界、面積などを測って等級や石高をきめて、貢租の基礎と責任者を明らかにした封建時代の土地調査であり、竹入(さおいれ)、縄入(なわいれ)ともいわれた。この土地調査は、古代から行なわれたもので、律令制度下では田籍、田図がつくられ、鎌倉時代には、大田文(おおたぶみ)がつくられた。また、荘園では、検証や内検が行なわれた。室町中期以降形成された大名領国でも、検地が行なわれた。これらは、各荘園、各領地によってまちまちであって、土地の広狭や石高、貫高、刈高などいろいろに示された。 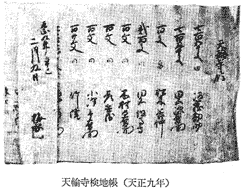 |
慶長元和以降各地で、検地が行なわれた。享保11年(1726)には、関東、大和などで検地が行なわれ、新検地条目がつくられた。江戸時代に入ると、太閤検地を古検とよび、享保以降のものを新検とよんだようである。新検では、6尺(1.8メートル)四方を一歩と改めたが、畝・反・町については、太閤検地にならった。
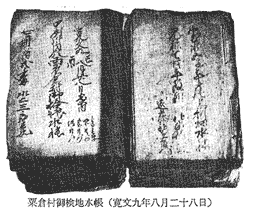 |
天正17年(1589)、徳川家康が検地を行なった時に、東西両河内領に属していた本町の検地は、行なわれなかったようであるが、慶長5年(1600)、家康が甲斐の国の再管領になると、慶長6年(1601)から、慶長11年(1606)まで、大大的に検地を行なった。本町においても、その当時検地が行なわれたようであるが、それを裏付ける古文書がほとんどなく、わずかに山梨県史編纂(さん)会が集めた資料で、日野村跡部蔵としるされた慶長9年(1604)の村高帳が、現在山梨県立図書館に蔵されているだけで、その中に、本町内の旧村別の石高がしるされている。この記録については、開田の歴史のところに記載してある。本町においては、この外寛文・享保の検地などが行なわれた。
二、検地帳
検地の結果をしるした地籍の基本帳で、水帳ともいわれている。これは、検地すべき田畑屋敷などを列記した「地引帳」によって実測して手帳にしるし、それをもとにして、「野(の)帳」「清野(せいの)帳」をつくり、清野帳によって、検地帳をつくったのである。そして、一筆ごとに字、上下田、面積、高、百姓名をしるしたのである。分付百姓は、抱えの地主的百姓の下の、隷(れい)属的農民であったと思われる。検地帳によって、記載された人名が、年貢負担者で、これがいわゆる本百姓であったと考えられていたが、記載者の全部が、年貢を負担したものでなく、また、すべてが本百姓でもなく、負担者は、別につくられた名寄(なよせ)帳の記載者であると考えられるようになった。農民は、検地帳によって、その土地に完全に縛りつけられることになって、幕府並びに藩体制確立の基礎を、維持する最も重要な帳簿であった。
三、名寄帳
名寄帳は、江戸時代になって、検地帳から抄録して一村総反別のうち、百姓一人前の持高の田畑を記録して、地主の名を書き集めたもので貢租公課の基となったものである。四、代官と貢租
代官は、鎌倉時代から室町時代にかけて領家、本所、武家等が主君に代って、事務を扱ったものである。郡代が国内の民政を掌(つかさど)り警察に当ったのに対し、租税の徴収を任務としたものであるが、江戸幕府は、幕府直轄地を管理するものとして、郡代、代官をおいて、ともに租税、警察、訴訟などの民政をつかさどらせたので、各藩もこれにならって代官制度をとるところもあった。江戸時代には、年貢収納の方法の一つとして、検見(けみ)という方法があった。毛見または、毛取法ともいわれ、地代を納入するために、毎年または臨時に収穫高を検定する方法があって、代官がこれにあたった。検見には、定免(じょうめん)と検見の二つがあった。室町時代、農民は百姓請によって、定租法(定免)をかちとった地方も多かったようである。定免とは、その土地の過去数年または十数年間の租額を平均して、租率を定め、一定年間きめられた定率によって、租税を収める方法である。官と農民が相対して免を決定するものを相対定免といった。免とは税率のことである。定免が原則として農作物の豊凶を問わず定額の租税を、納めなければならなかったから、寛永年間(1624−1644)農民は、この定免で苦しめられた。しかし、幕府は定免をゆるやかにするどころか、享保(1716−1736)以後、定免制を強化して定免の確立につとめた。
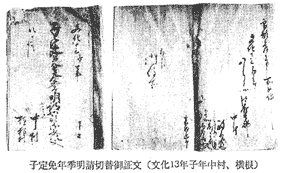 |
それから、室町時代には、年貢は穀物または銭で納められ、穀物で納めるものを分米といい、銭で納めるものを分銭といった。江戸時代には、雑税の一種の小物成(こものなり)というものがあって、山年貢、山手米、山小物成、野銭、野手役、茶役、池役、御林下草永、河岸役として課せられた。なお、小物成の一種の運上というものがあった。商工業、漁業や狩猟、運送などについて、一定の税率で賦課された。一定の税率でなく、免許をとって、金銭で納めるものを冥加(みょうが)といった。運上浮役は、年期を限り、額も一定しなかったので浮役となした。また口米という付加税があって、代官所の費用にあられた。年貢小物成運上冥加などに付加されるものを口永といって、銀または銭で納められた。これにあわせて口米永(くまいえい)と称した。元和2年(1616)将軍秀忠は、口米を年貢1俵(3斗5升)(63.2リットル)ときめた。享保10年(1725)には、原則として、幕府へ納入させ、代官所へは別に幕府から支給したようである。なお、本町には年貢にともなう古文書が数多くありその一部を掲載したので参照されたい。
五、苅生畑(焼畑)
かりう畑または、苅立畑ともいわれた。焼畑は、山の傾斜面の灌木や雑草を伐り倒して、これを焼いて、蕎麦(そば)や粟、稗、大豆などを蒔いたものであるが、肥料は、焼いた時残った灰だけであるから、収量はごくすくなく、2・3年作れば、収穫がほとんどないので、大部分放棄してしまった。そして、苅生畑からとれる農産物は、百姓たちの食い継ぎの足(た)しにすぎなかった。嘉永2年(1842)相又村年貢割付帳に、高6石1斗4升5合
刈生畑 24町5反6畝7歩−2分5厘
此取米 4石4斗7升7合
とあり、水田のすくない、しかも山地の傾斜面の多い本町には、多くの苅生畑があったと推測される。また、このようなやせ地の畑にも税が課せられていた。
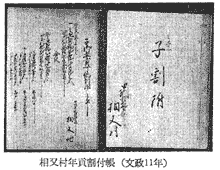 |
六、大小切税法その他
河内地方には、武田氏以来「大小切税法」があった。これは、明治の新税法に受けつがれるまでつづいた。この税法は、貢租全体の3分の1を小切と称し、1両について付米4石1斗4升替で金納させ、のこる3分の2を大切と称し、その3分の2を米納とし、あとの3分の1を御張紙値段(おはりがみねだん)で金納させたものである。これは、毎年国中相場といって甲府・鰍沢・勝沼・黒沢の四カ所に張紙した平均値段をもって上よりこれを定めたのである。そのほか、五街道の問屋、本陣、その他宿宿の給米、宿方入用にあてた伝馬米入用米(高100石に6升の割)また、江戸城中の御台所の人夫の給米にあてる6尺米(高100石に2斗の割)など、幕領へ課した高掛物があり、江戸浅草の米蔵の年貢を上納する時の諸雑費にあてるため、御蔵米を、高100石に付永250文を負担する掛物があった。本町の皆済目録の中に小切、大切、御張紙値段、山手船頭米、水車運上、口米、公納公米、口永、御伝馬入用、6尺、御蔵前入用などがみえて、当時の姿を裏付けしている。
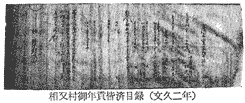 |
(詳しくは第三編にゆずる。)
七、村役人
役人は、郡代・代官の支配下にあって、村の村管理にあたった在村農民の官吏であって地方(ぢがた)三役、または村方三役ともいわれ、年貢の取立と上納を主な任務とした。庄屋(名主)・組頭・百姓代が、この三役をつとめたものである。庄屋のことを関西では庄屋・関東では名主といい、東北北陸方面では肝煎(きもいり)とよんだ。名主は、地方三役の筆頭であって、租税の収納、村の百般の監督、それに農耕の指導や、人事について支配した。しかし、村民には領主への服従を教えながら領主、役人からは年貢未納の責任をとわれ、処罰されることもあったので、中には百姓一揆(き)の指導者となった者もすくなくない。徳川幕府は封建社会を維持するために、経済面では貢租の徹底的収納をねらい、さらに米麦など五穀や雑穀などの増産によって、貢租高の向上を企図して、徹底的に農民から搾取した。また行政面では、奉公、代官、郡代や村役人五人組などによって幕政、藩政の徹底を期したのである。加えるに、農産物の生産を主とする農民の生産主力労力である人馬の供出までしたので、農民の生活は、貢租と課役で終始したといっても過言ではあるまい。「菜種油と農民は、しぼればしぼるほどしぼれる」とは、この時代の姿を如実に表現したことばではなかろうか。

