第二節 産業経済と農民のすがた
一、幕府の体制確立と農民
前に述べたように検地や、郷村制などの制度によって幕府は、政治経済面で完全にその体制を確立した。「農は国の大本なり」と称して、農業の重要性を強調し、また「士農工商」といって農民の社会的地位を高くかかげながら、庶民の大部分を占める農民を幕府体制確立の犠牲にし、確実に封建社会の枠桁(わくけた)の中へ封じこめて、土地に縛りつけ身うごきできない状態に追いこんだのである。また幕府では経済体制確立のために、未開拓の土地を開墾させて石高をふやし、年貢高をふやすことなどにつとめるなど、摂取をねらいながら、農業の振興をはかった。本町においても、寛文9年(1669)9月8日甲州河内領下山未改新田御検地水帳、天保9年(1839)相又西之入新田開発など、多くの古文書があることから、数多くの場所で開田が行なわれたと推測される。なお詳細は開田の項にある。二、幕府の殖産興業政策と産業
国史連絡甲斐郷土史の中に、「当代に入り、特に幕府の保護奨励もあったので、産業は全国的に発達し、当国の如きも見るべきものがあった。中にも、葡萄(ぶどう)・製紙・蚕糸・織物・煙草(たばこ)・甘草等特筆すべきものがある」と、見えている。このように、江戸中期以後幕府は、生産物をふやし産業を盛んにして農民の貧窮を救うため、また、幕府の財政を豊かにするため、農民に市場めあての作物などをつくらせ、また製紙・蚕糸・織物なども奨励して、殖産興業に力を入れはじめた。製紙は、平安時代にはじまり、武田家の保護によって漸(ようや)く発達して、徳川時代になると一層隆盛になった。市川(西八代郡)は、良質の紙を多く産出した。毎年幕府から御用紙の命をうけた。幕府は、運上紙取立役人をおいて取立ての事をつかさどらせた。寛政5年(1793)、運上紙を金納と定めた。村役人は、隔年に御用紙を取集めて、束紙のきり口に朱判を押すことにした。岩間・西島などでも良紙をつくったので、運上紙取立役人がおかれた。幕府は、製紙の原料である三椏(みつまた)の栽培を保護育成したのでますます盛んになった。
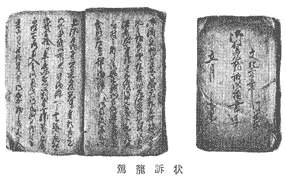 |
さて、紙の原料である三椏、楮は、ほとんど市川、西島の紙漉(かみすき)業者によって使用され、紙漉業者は、仲買人から問屋の手を経て買い入れたのである。市川、西島の人々は、御用紙の生産をしていたため特権意識がつよく、原料生産者の農民に三椏、楮の売買をめぐって、圧力を加えたので、むずかしいトラブルが生じていた。
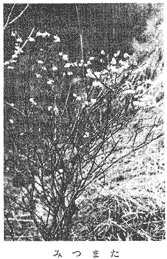 |
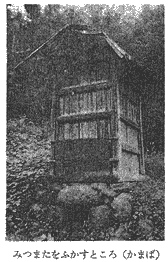 |
本町においては、三椏、楮の栽培が換金の重要な財源として、昭和の初期までつづけられた。そして昭和20年頃まで、一部の山畑に僅かに名残をとどめていた。なお、大正5年(1916)大河内村取調書によると、「文化九年(1812)に家庭工業として、紙漉帯金三十一軒、九滝六軒、角打二軒、大島十六軒あり、明治年間一軒もなしと」あり、文政11年(1828)から明治3年(1870)まで、約42年間の甲州相又村御年貢割付帳(相又区所蔵)によれば、各年に紙漉船役、1升8合が割付けられている。本町内の身延下山豊岡地区にも、紙漉きが行なわれていたことが推測される。
このように、本町内においても、紙漉が行なわれたのは、製紙の原料である三椏、楮が自家で生産され、また仲買人の手を経ないで容易に入手できることなどからではないかと思われる。

