三、永世小作地の由来
この永世小作地の発生が、もし、地券保持者が当初身延山久遠寺にこの土地(永世小作地)を寄付したことによって、このような制度が創設されたとすれば、結果的には、法律上今日においては違法行為に類するかも知れない、という見方もでてくる。何故ならば、当該土地においては、今日もなお(身延山久遠寺以外の立場から眺めて)土地に関する法律上の制約(登記事項)を受ける必要がなく、土地の売買・譲渡・質入れ等が、身延山久遠寺でいう永世小作権利上の行為ではあっても、実質上行なわれているからである。
名義のみ身延山久遠寺所有地として、実質上は、地券保持者が、法的な制約も受けずに、その土地における、売買・譲渡・質入れ等の行為を一切行ない得ることは、そのように都合良くするために寄付した(結果的にみて)ものと解されても仕方がないものである。
しかし、そうした考えは、明治7年(1874)5月9日山梨県における寺院寄付地処分稟議書及びその指令の中に記されている。
貢租高掛リハ縄受人ニテ取扱、作得ノミ寄付ノ分ハ寺院又ハ縄受人名ノ券状申受ルモ寄付人ノ適意ニ任ス積
を見れば、たとえそれが、寄付であったとしても、永世小作地制度の中に毛頭、そのような考え(都合良くするため)はなかったことが証明される。ただし、この稟議書の中にも「作得ノミ寄付ノ分」と述べて、土地の収益物を寄付する分については、寄付した者の意志に任せるといっているし、更に詳しくこれを解釈すれば、永世小作地つまり、久遠寺私墾地当時は、身延山久遠寺元境内上地つまり旧寺領内の耕地・屋敷地の土地内で、貢租高掛(公租課出)は縄受人(後の地券保持者)にて取扱い、作得(土地の収益)のみ受付していた分の「地券」(明治維新政府が、土地私有の権利を保証、証明するために発行した証券)は、寺院又は縄受人(後の地券保持者)の名儀で申受けるのであるが、これは、寄付人の適意(意志)に任せる、というのであって、上地前、寺領内において、身延山久遠寺から耕地を借受け(身延山久遠寺私設の縄受人)収益を寄付(小作入付ではなく寄付行為)していた分の土地については、その寄付人の意志に任せる、と読みかえて解釈した場合(ただし、この際の貢租高掛りは、縄受人にて取扱負担してはいない、朱印免租地であった)にのみ、寄付人(土地の寄付主は、鎌倉時代の波木井南部六郎実長であり、ここでは、作得の寄付人の意に解す)つまり後の「永世小作地券保持者の意志に任せて、地券の名(持主の名)を決定する」という意味が生まれ、永世小作権保持者が、当該土地を、身延山久遠寺名儀にするという意志が働くことによって、寄付したといいかえられるのである。
しかし、身延山久遠寺永小作地においては、そのような、解釈は成立しないのである。それは、山梨県が社寺上地に関し、明治10年(1877)2月28日付発した。「社寺上地の収税額稟議書」の中に
(要略)
甲斐国、山梨、八代、巨摩、都留、社寺領無代価下渡ノ分
一、耕地、宅地、段別八百弐参七町四段九畝参四歩
(内訳但書)
身延村壱ヶ村ノ儀戸籍人民有之、一村寺領村ニシテ成規ニ依リ無代価下渡ノ分、一昨九年ヨリ民有地第一種ニ編入、同年地券帳へ組入…(以下略)
と、記されているが、この際の、地券組入分は、払い下げ分のことであって、身延町方住民(後の永小作権保持者を含めて)の家屋有之地、つまり屋敷地を主として、住民各自に払い下げられたものであり、今日の身延山久遠寺の総門内に所在する民有地並びに塩沢区、新宿(清住町)区の民有地が、その対象であったと思われる。甲斐国、山梨、八代、巨摩、都留、社寺領無代価下渡ノ分
一、耕地、宅地、段別八百弐参七町四段九畝参四歩
(内訳但書)
身延村壱ヶ村ノ儀戸籍人民有之、一村寺領村ニシテ成規ニ依リ無代価下渡ノ分、一昨九年ヨリ民有地第一種ニ編入、同年地券帳へ組入…(以下略)
次いで、
「当県下社寺領上地田畑宅地ノ内、縄受賞流地及荒地起返私墾地等ノ証有之故ヲ以テ、成規ニ依リ無代価下渡ノ分、昨十年ヨリ民有地第一種ニ編入…(以下略)」
と、記されているが、身延山久遠寺私墾地の地券発行であって、成規により無代価下渡である限りにおいては、当時の官衙が、民間の意志に基づいて、その私墾地を、久遠寺所有地に決定したと思われない。この私墾地が後の永世小作地の主体となったのである。
この際、官衙において、住民(後の永世小作地権保持者)に対して、私墾地の「地券」を下げ渡し、一たん、各自の所有地となったものを、身延山久遠寺に寄付し、地券の名儀書替えを行なったとすれば、確かに、身延山久遠寺の永世小作地は、今日の永世小作地権権利保持者の寄付地でなければならないが、これを扱った山梨県官衙の書証に基づけば、その跡は見られないのである。
そうしてみると、前述のような、身延山久遠寺の永世小作の特異なあり方は、身延山久遠寺独自の立場から考案され編出されて、その制度を設置したように思われる。
ところが、身延山久遠寺独自で、考え、創設したとすれば、現在から見ても、久遠寺自体に、何の利益するところがないと思われる、このような制度を、いかなる意図があって設置したか了解に苦しむものである。
それを理由付けて、一宗の総本山の体面を保つためといい、総本山久遠寺の周囲の土地を他人に買収されないためともいい、または、将来、その土地を身延山久遠寺が活用するためとも、あるいは公共用地に使用する場合、身延山久遠寺所有地にして置いた方が都合が良いから……等々、いわれているが、これは、創設当初の趣旨が明らかでないところから、種々憶測され、説明されて来たものであって、このような説が生まれて来る限りにおいては、そうした意味を含んでいるに違いないが、最も重視すべきは、なぜ、そのような条件(身延山久遠寺が直接利益するところのない)で、創設しなければならなかったという理由である。
身延山永世小作制度が、一般の永小作制と異なった存在にあるとすれば、そこにその理由が秘められているようである。
恐らく、身延山久遠寺の私墾地そのものに基因するものであることは、疑う余地はないのであるが、察するに、当時、官衙がいうところの荒蕪(ぶ)起返私墾地或は一般的な私費開墾地という解釈をとりながらも、身延山久遠寺では、更に私墾地の意味を、深く掘り下げて、その土地における由緒歴史を総合考慮に入れて意義付けし、解釈をしていたように思われるのである。
それは、この私墾地の耕作権利を名付けて「永代小作」とせず、「永世小作」とした点に、創設当初の配慮の跡が見られ、深甚の意味が含有されているからである。
(一般に永小作は永代小作と呼び、永世小作とは呼ばない。)
この永世小作の永世は、天平年間における「墾田永世私有令」から取った永世であって、小作は私有の文字を置き替えたものである。
この法令は天平15年(743)に布告されたものであって、新しく開墾した土地は、永久に私有することができるという法律である。
身延山久遠寺の建立の基礎をなした現在の聖域は、かつて、甲斐源氏の後裔である、波木井六郎実長の、荘園の一部であった。
それは、清和源氏、新羅三郎義光が、甲斐国司職に就いて以来、源家が甲斐国一円を開発するに当って、代々、その一族を国内の要地に分散し、居館を構築、その地方を支配せしめ、数世紀にわたって、墾田・牧畜・農耕等に専念努力、精励した結果、「墾田永代私有令」に基づき、それぞれ、荘園(私有の土地)の確立を得たものであって、その一族である甲斐南部光行の子、波木井六郎実長に至り、現在の身延山久遠寺の土地、当時蓑夫の里の13里(鎌倉時代の面積)の四方に境を立てて、文永11年甲戊(1274)10月24日付の寄進状を認(したた)め、日蓮聖人へ寄付したものである。
従って、波木井実長の荘園(私有地)の一部であった「蓑夫の里」は、そのまま身延山久遠寺に受け継がれたのであるが、日蓮聖人御入山当時を考察してみるに、いわゆる蓑夫の里は無禄・無高・無所得の荒蕪(ぶ)の地であったことがうかがわれるのである。
それは、寄進主波木井実長が、鎌倉幕府の御家人であり、そのような土地でなければ、寄付することができなかったからである。
寄進状に
慶応4年(1868)身延山久遠寺が、官衙(甲府総轄)に提出した租山由緒書に、
「境内之内、山林追々切開山畑出来仕候
只今有石高弐参八石八斗五升九合弐勺」
て記しているのを見れば、寄進以来、約600年の間に「追々切開」かれた「山畑」がわずかに、28石8斗5升9合2勺であれば、いかに、身延山久遠寺の土地の開墾・開拓が至難であり、長い時間と、多くの労力とを要したか、明治維新、境内を上地するまでは、荘園寺領として下知管理の権を御朱印によって掌握はしていたものの、それに費した努力は並大抵のものではなかったことは想像するに難くない。只今有石高弐参八石八斗五升九合弐勺」
明治3年(1870)12月4日付発令された
「諸国社寺由緒之有無不拘、失印除地等、今度社寺領、現在之境内ヲ除ク外一般上地被仰付」の、大政官布告は、開発途上にあった身延山久遠寺の寺領(この寺領は全域が当時としては「現在之境内」であり、当然上地から除かるべき性格のものであった。)を、根こそぎ上地という理由の下に召し上げてしまったのである。
これは、身延山開創以来、久遠寺々領の土地開発に捧げた、僧俗一体、父租伝来の汗の結晶が、一朝にして無に帰したようなものであって、実に、驚きの一語に尽きたであろう。当時、身延山久遠寺・塔中・各坊・町方農家を含めて、つちかわれていた幾多の慣習は、600年にわたる信頼と愛情、これを結ぶ信仰によって築き上げたものであった、だから「自分が裸になることは、山が裸になることだ」という実感が、ひしひしと身延町方住民の心を、ゆすぶったに違いない。
ただし、それは幸いにして、数年後、法令の定めるところにより、明治9年(1876)元境内上地(旧寺領)の内、「家屋有之地」の土地が、町方個人に払い下げになり、住民各自の所有地となった。次いで翌10年(1877)「荒地起返私墾地」は、上地後、一握の土も残っていなかった身延山久遠寺の所有地として認められたのである。
それは、当初、田畑原野合反別、44町3反6畝19歩あり、その内訳は、
田 反別 参町五畝拾壱歩
畑 反別 四拾町六反四畝廿七歩
宅地 反別 参畝弐歩
原野 反別 参畝廿八歩
荒地 反別 五畝拾壱歩
合計、地価金8,408円98銭であった。畑 反別 四拾町六反四畝廿七歩
宅地 反別 参畝弐歩
原野 反別 参畝廿八歩
荒地 反別 五畝拾壱歩
身延山久遠寺では、この土地の「地券」の発行をまって、永世小作委任申付という、いわゆる永世小作制度を設定し、過去数世紀にわたる、開拓の労苦の姿を今にとどめ、その土地を、寺(久遠寺)と人(塔中・町方)とともども、譲り抜こうとする方法を講じたのである。
であるから、身延山久遠寺の永世小作は、一般に知られている永小作又は永代小作と表現は似ているが、内容がまるで違うものであって、特に、ここでは「永世小作」として、区別するゆえんでもある。
この永世小作制度は、その運営にあたって、当時、国が発行した地券制度の規則にのっとり、その趣旨を充分生かして実施したものであった。
ただし、その土地の所有権は、身延山久遠寺が、永世確保し、その土地の進退人を永世小作権利の持主、つまり永世小作権利保持者として、地上権の権利証であるところの永世小作委任申付証を交付したのである。
(表) 記
一、 進退人
地価
右地所永世小作委任申付候事
但 正租課出ハ自弁タルヘキ事
明治 年 月 日
久遠寺
(裏)
現今小作進退人ト雖時盛衰ニ依テ売買致者ハ久遠寺並ニ戸長ニ於テ実施検査ヲ遂可受許可モノトス。
この証状の裏書に売買と記されているが、これは決して、土地そのものの売買ではなく、永世小作委任申付の権利であることは、一目瞭然であって、この永世小作の権利内容の性格から、土地そのものの評価と同等の価値を生み、この権利の売買・質入譲渡等の行為が行なわれるようになったのである。一、 進退人
地価
右地所永世小作委任申付候事
但 正租課出ハ自弁タルヘキ事
明治 年 月 日
久遠寺
(裏)
現今小作進退人ト雖時盛衰ニ依テ売買致者ハ久遠寺並ニ戸長ニ於テ実施検査ヲ遂可受許可モノトス。
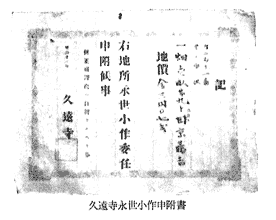 |
それは、当然であって、小作権は賃借権であり、永小作における小作は物権であるからである。
このことは、当初にも述べたが、永世小作権利保持者は、これを充分に熟知していて、小作人という考えは毛頭持っていない。
かえって、身延山久遠寺の私墾地を所有する資格であるという意味に解している。言いかえれば、身延山久遠寺の私有地を、所有する権利が永世小作委任申付であると認識しているのである。
これは、身延山久遠寺の永世小作制度の上からみれば、正しい見方であって、豪(ごう)も疑いを差しはさむ余地はないのである。
一般的にいえば、日本国民が、土地を所有するという考えは、国の承認によってその所有権を認められて始めてその土地を所有するという、観念に結びつくのであるが、身延山久遠寺の永世小作制度上における永世小作権利者が、その土地を所有するという考え方は、国の承認により、その土地の所有権を認められた身延山久遠寺の、私有地の一部を所有し得る権利を、身延山久遠寺に認められて永世小作委任申付の権利を、保持することにより、始めて、その土地を所有するという理念につながるのである。
それは、その土地が身延山久遠寺私有の所有地である限りにおいては、何等不合理ではないのである。
四、永世小作地の現況と将来
身延山久遠寺永世小作制度の内に組み入れられている土地は、田・畑・原野・荒地・宅地等の私墾地を主体としているものの、更に堂敷地・屋敷地・境内地・墳墓地・山林等の地目の土地をも含んでいる。これは、古くから各土地の価値判断に応じて使用され、その利用の仕方は、千差万別であり、原型を崩さぬ限りにおいて、これを規制しなかったからである。
こうしてみると、明治維新の土地改革において、身延山久遠寺が設けた永世小作制度は、実に、その後80年を経て、昭和22年に施行された自作農創設特別措置法の趣旨にも適応するものであったといえる。
ただ、土地の法律上の所有権のあり方だけであって、それとても、土地の所有権の有無にかかわらず、第三者に対応して、その価値判断には何等の支障も来たさなかったから、身延山久遠寺の永世小作は、命脈を保ち、今日もなお、残っているゆえんでもあろう。
しかしながら、この永世小作地の内、農地であって、地券保持者以外の第三者に耕作権(地券保持者自身が耕作していた場合を除き)を、獲得された土地は、当然、昭和22年の自作農創設特別措置法の適用を受け、政府に買い上げられ、耕作人に売り払われたことは、言をまたないのであるが、身延山久遠寺の事業計画(戦時中一時休止していた)に、組み入れられていた永世小作の一部の土地は、耕作人(元永世小作券保持者)の協力により、「自作農創設特別措置法第5条第5号の規定による使用目的変更」の承認を昭和23年2月4日(県農委状第741号)受け、更に「農地法第7条第1項第3号の指定」を昭和29年3月12日(山梨県指令農地第3−127号)に指定され、次いで「農地法第20条に基づく許可申請」を昭和33年12月8日付承認許可されて、久遠寺が経営する身延山聖園の新たなる土地開発への基礎となっている。

