第四節 中学校教育
一、下山中学校
第二次世界大戦の敗戦の疲弊のどん底のなかに、民主的平和国家の再建をめざして、いわゆる、六・三・三・四制を中心とする学制改革がなされ、昭和22年3月教育基本法・学校教育法が公布された。続いて4月新制中学は、全国津々浦々にまで開設された。全国の新制中学校がそうであるように、本町中学校も小学校の一隅を間借りして校舎とし、中学校という名称のもとにとにかく旧町村に一中学校すなわち下山・身延・豊岡・大河内の各中学校が発足した。
(一)沿革
昭和22年4月10日新学制実施に伴い、下山小学校(明治42年建築の校舎)2階講堂を3教室に区切り、下山村立下山中学校として発足した。昭和23年11月3日、村民の一致協力により中学校独立校舎(現小学校南校舎)が落成し、山梨県知事を始め、多数名士の臨席のもと、村民挙げて盛大な落成式ならびに祝賀行事が行なわれた。ちなみに中学校独立校舎としては県下第2番目の建築であった。またこの日を学校記念日に制定した。
 |
昭和34年1月26日 新校舎(現校舎)を1,200万円の建築費をもって、移転新築落成、はじめて、中学校として独立した校舎、校庭をもつに至った。この日を新しく学校記念日に制定した。
昭和34年5月11日 教育委員望月栄の指導により、PTA会員、生徒の奉仕により螢雪園、洗心池が構築され、中庭が整備された。
昭和36年7月10日 二ヵ年の継続事業でプールが竣工した。
昭和38年3月29日 技術科教室並びに給食室竣工、4月より完全給食を開始した。
昭和42年7月31日 屋内運動場が総工費1,976万円で竣工した。
昭和43年1月25日 山梨県教育委員会より統計教育研究校に指定され「学習指導時における統計資料の継続的活用」のテーマで公開研究発表を行なった。昭和43年度、引続き指定を受け、昭和43年10月22日「学級活動をより充実させるための統計資料の活用」のテーマで公開研究発表を行なった。
昭和44年3月31日 統計教育研究の成績良好により文部大臣より表彰された。
昭和44年11月1日 山梨県教育委員会指定の統計研究校(第3年目)となり、「学級づくりをより効果的にするための統計資料の活用」のテーマで当校で山梨県統計教育研究大会を行ない、県下に公開発表を行なった。
(二)校長・PTA会長
| 年度 | 校長名 | 職員数 | 生徒数 | 学級数 | PTA会長名 | 備考 |
| 昭和22 | 佐野国太郎 | 7 | 108 | 3 | 山内椿房 | |
| 23 | 7 | 148 | 4 | |||
| 24 | 望月稠春 | 8 | 169 | 5 | 望月惟臣 | |
| 25 | 8 | 176 | 5 | |||
| 26 | 9 | 174 | 6 | |||
| 27 | 10 | 173 | 6 | 佐野悟郎 | ||
| 28 | 10 | 190 | 6 | |||
| 29 | 10 | 196 | 6 | 山本岳乗 | ||
| 30 | 10 | 199 | 6 | 佐野為雄 | ||
| 31 | 10 | 186 | 6 | |||
| 32 | 土橋隆四郎 | 10 | 173 | 6 | 石川剛 | |
| 33 | 8 | 152 | 5 | 網野正一 | ||
| 34 | 7 | 143 | 4 | 遠藤泰明 | ||
| 35 | 7 | 154 | 4 | |||
| 36 | 8 | 192 | 5 | 上平浅蔵 | ||
| 37 | 望月諦三 | 10 | 214 | 6 | 松木栄 | |
| 38 | 11 | 213 | 6 | 川村藤十郎 | ||
| 39 | 依田金晴 | 10 | 195 | 6 | 芦沢忠男 | |
| 40 | 高山巌 | 10 | 199 | 6 | 遠藤宝作 | |
| 41 | 11 | 181 | 6 | |||
| 42 | 12 | 173 | 6 | 秋山智孝 | ||
| 43 | 12 | 164 | 6 | |||
| 44 | 12 | 177 | 6 | 広島慶明 |
二、身延中学校
(一)沿革
昭和22年4月10日学制改革実施にともない、身延国民学校は廃止され、新しく修業年限六ヵ年の身延小学校と、修業年限三ヵ年の身延中学校が誕生した。校舎は旧国民学校の一部を小学校とともに使用する。ちなみに時の教育予算は114,449円であった。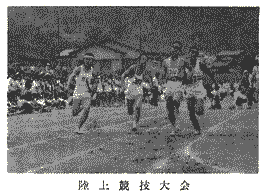 |
昭和25年2月20日 支会カリキュラム部主催の公開授業を実施した。
昭和28年3月5日 武道場竣工式を挙行する。三船十段の実技披露と講演会を開催した。
昭和29年9月2日 プール工事が竣工した。
昭和29年11月22日 身延山短期大学教育実習生入所式を行なう。(以後身延山短期大学の教育実習校として今日にいたる。)
昭和30年4月 文部省指定の産業教育実験学校となる。
昭和30年2月 プール落成式典を挙行した。(長さ25メートル幅15メートル深さ1メートル)
昭和30年9月13日 校旗、校歌を制定し、同月17日発表会を実施した。(作詞、辰己利郎、補訂米山愛紫、作曲森義八郎)
昭和31年2月11日 産業教育実験学校全国公開授業を実施した。
昭和33年9月8日 生徒会発表会をおこなった。
昭和36年12月5日 屋内運動場竣工式典を盛大に挙行した。
昭和37年2月23日 学校給食を開始した。
昭和38年8月5日 県下中学校柔道選手夏期強化合宿訓練をおこなった。
(二)校長・PTA会長
| 年度 | 校長名 | 職員数 | 生徒数 | 学級数 | PTA会長名 | 備考 |
| 22 | 鮎川省三 | 11 | 233 | 6 | 青鹿新太郎 | |
| 23 | 12 | 333 | 7 | 佐野肇 | ||
| 24 | 佐野国太郎 | 14 | 417 | 9 | ||
| 25 | 14 | 394 | 9 | |||
| 26 | 13 | 369 | 9 | |||
| 27 | 佐野忠雄 | 13 | 375 | 9 | 田中不二雄 | |
| 28 | 13 | 375 | 9 | 望月房則 | ||
| 29 | 15 | 412 | 9 | 遠藤久雄 | ||
| 30 | 14 | 392 | 10 | 佐野一男 | ||
| 31 | 15 | 389 | 10 | 鴨狩広 | ||
| 32 | 望月稠春 | 13 | 337 | 9 | 一宮市松 | |
| 33 | 12 | 299 | 8 | 松野久男 | ||
| 34 | 12 | 288 | 8 | 深沢忠雄 | ||
| 35 | 12 | 317 | 8 | 片田為丸 | ||
| 36 | 13 | 368 | 9 | 近藤嘉一 | ||
| 37 | 14 | 390 | 9 | 望月秀雄 | ||
| 38 | 望月正一 | 14 | 377 | 9 | 池上荒一 | |
| 39 | 15 | 339 | 9 | 佐野初雄 | ||
| 40 | 土橋隆四郎 | 14 | 322 | 9 | 沢村清一 | |
| 41 | 14 | 317 | 9 | 池上正 | ||
| 42 | 井上熊雄 | 15 | 314 | 9 | 藤田大六 | |
| 43 | 14 | 282 | 8 | 下里是忠 | ||
| 44 | 14 | 271 | 8 | 高村大衛 |
(三)体育後援会
ア 沿革及び事業の大要敗戦後10年、経済生活の安定、食糧事情の好転に伴い各種のスポーツは戦前にまして盛んになった。学校の課外体育クラブの活動も盛んにおこなわれるようになった。このころまではPTAの野球の同好者が集まって野球部の後援をしてきたのであるが、それがきっかけで他の体育クラブを総括した形の体育後援会組織が独立して発足したのは、昭和32年4月であった。
会則を決め、会費は口数を決めて徴収した。課外体育クラブの活動だけでなく、学校行事として行なう校内体育行事(競歩大会・運動会等)にも積極的に物心両面の支援活動をしてきた。会則の第2条には次のように目的が明記されている。
「本会は生徒の健康増進、体位向上、および、会員の親睦をはかる」と。
また目的達成のための事業として(1)生徒の健康増進および体位向上のための諸事業ならびに後援、(2)体育に関する調査研究、(3)その他目的達成のために必要な事項。
なお、昭和44年度からは身延小中学校体育後援会として再編成された。したがって、小学校部、中学校部という形で運営していくことになった。過去十数年にわたる活動の成果は多大であった。
歴代会長は別表のとおりである。
| 歴代会長 |
| 年度 | 氏名 |
| 32 |
佐野一男
|
| 33 |
鴨狩広
|
| 34 |
一宮市松
|
| 35 |
松野久男
|
| 36 |
田中万造
|
| 37 | |
| 38 | |
| 39 |
矢野定吉
|
| 40 | |
| 41 | |
| 42 |
高村大衛
|
| 43 | |
| 44 |
岡本平八郎
|

