第七節 華道、茶道、箏曲
一、華道(第四章第八節私塾参照)
種部かつ(華道家元池の坊)昭和元年(1826)より教授をしている。毎年3月家元主催の東京都美術館の華道展に出品し、家元より総華督の称号を許されている。
山田一雪(松山古流社中)
師範者だけで月1度研究会をし、また野外稽古等もしている。門下生30人を数える。
池上一照(日本華道古流家元顧問)
昭和16年(1941)古遠州流生花に入り、21年日本華道古流に入門、師範、正師範、会頭職を経て43年1月顧問職を許されている。現在は梅平の自宅で華道指導に携っているとともに、研究会を開きまた流展に参加して研究に余念がない。
門下生の師範坂本一操は昭和30年頃より華道の研究に入り、現在自宅で同好者と稽古に研究に没頭して、42年度の流展に準優勝して家元からその努力を認められた。
上杉一友
昭和31年より、青年学級・婦人学級・青年団等を指導したが、現在は大島青年学級生とともに、農村にふさわしい活花の研究に身をうちこんでいる。
前田一京
昭和32年頃から、大河内婦人会・下山婦人会・下山青年団・塩之沢・大島・角打の各婦人会の指導に寧日ない活動をつづけている。
二、茶道
山田宗由(裏千家今日庵社中)年2度茶会を行っている。
今村和子(裏千家今日庵準教授)
昭和40年12月まで茶道教室を開いていたが家事の都合で現在は休止している。
青沼節代(裏千家今日庵師範)
大野にて茶道教室をひらいている。
三、箏曲
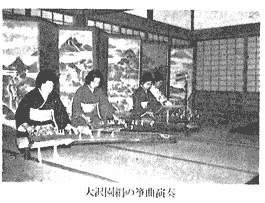 |
情操教育の一端にもと思いをはせて昭和28年から町内有志や、身延高校生を指導している。37年1月身延山年頭会の式典に奉納演奏をして以来毎年つづけている。
野村秀浩(しゅうこう)(浩子)
昭和32年8月準師範免許
昭和35年6月師範免許
昭和35年4月の開軒記念演
奏会をはじめ、たびたび演奏会を開催している。
現在30余名の門弟とともに、その道に精進している。
佐野秀(しゅう)七七(なな)(七七子)
昭和24年3月高橋秀清に師事し、昭和36年12月家元秀冽社正師範を免許された。昭和36年9月お茶の水池の坊学園に入学し、目下秀冽社大師範を目ざし勉強中。
昭和37年から東京都本郷で、昭和38年から郷里身延でも教授している。門下生は合計40名である。

