第八編 厚生
第一章 保健衛生
第一節 概説
保健衛生思想の優劣はその国の文化のバロメーターといってもよい。わが国の保健衛生思想は明治初年以来文化の進展につれて、ここ約百年の間に目覚ましい発展向上をとげた。本町における保健衛生の変遷もわが国の保健衛生の発展と軌を一にしている。
江戸時代までは、病気に対しては古来より行なわれていた民俗信仰による呪術(まじない)とか、加持祈祷とか、漢方医学等による治療が行なわれていた。本町においてもおおむねこのような姿であった。今なお町内の所々に祀られ、往古の名残りをとどめている出産・疱瘡(ほうそう)その他に関する諸神仏や、疫病流行に対して、部落の入口に〆切りといい呪符(じゅふ)を掲げる風習があったことなどに、それらをうかがうことができる。
江戸後期に蘭(らん)学者によって始められた西欧の科学的な医術により、次第にこれらの俗信呪術は影をひそめるようになるが、保健衛生の歩みは遅々として進まなかった。よく例にひかれる明治4年(1871)甲府県庁より出された疫病神退散状は当時の事情を物語っている。
寛政9年(1797)幕府の典医石坂宗哲により甲府医学所が開かれ、明治元年(1868)に至るまで医師の養成、医術の研さん、患者の治療等が行なわれた。明治元年同所は廃止となり、同年佐渡町に新たに県病院が建築され、同9年(1876)錦町へ移転、洋風建築の偉容を誇った。しかしながら、へき地である河内地方においては、特殊な人はいざ知らず一般人は県病院の恩恵にあずかることは至難であった。
明治初年の県の衛生面における施策の重点は、病院と種痘と大掃除にあったように思われる。種痘がわが国で行なわれるようになったのは安政5年(1858)5月、江戸の開業医82名が、西洋医学普及のためジェンナー式種痘を行なう目的で設立した種痘所に始まる。これは万延元年(1860)幕府直轄となり、更に明治政府にひきつがれるのである。英国のジェンナーが種痘をはじめたのが1796年であるから、種痘所の設立は62年後になる。さて県は明治4年(1871)2月には種痘局を設け山梨・八代・巨摩の3郡に出張所を置いた。南巨摩郡下の出張所は切石と南部であった。
県は警察力を用い警官に種痘の取締まりをさせた。衛生思想の低い当時としては、権力で実施する以外に方法がなく、後年まで衛生関係の所管が警察にあった理由もここにあった。
県政六十年史によれば、明治10年(1877)には県衛生課がおかれ、明治10年、12年に県下に伝染病が猖獗(しょうけつ)を極め、県庁・開業医協力して予防法、摂生法について県民を指導し、疫病に対する恐怖から急速に大衆の関心を衛生に赴(おもむ)かせたとあるが、本町において当時どのようなことが行なわれたか不明である。
平区の市川家所藏の辞令に
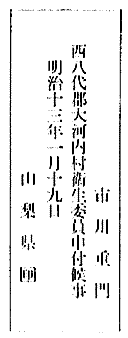 |
明治22年(1889)には、日本赤十字社山梨県支部が設立され、市町村に至るまで赤十字活動が及んで来た。
明治24年(1891)には伝染病予防法が制定され、次いで衛生に関する諸法令が施行されるとともに衛生上の取締まりが強化され、開業医の医療活動と相まって一般の衛生思想も次第に向上した。
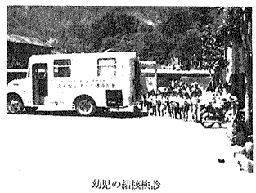 |
戦後連合軍司令部は衛生行政に重点をおき、予防医学的立場から行政機構の改革を行なった。すなわち、従来の取締まり行政は指導行政に改められ、主管も警察の手を離れ、県は衛生部の下に医務課・予防課・公衆衛生課・医薬課をおき、細菌対策、衛生思想の普及、予防接種の実施、環境衛生の向上に努めた。本町においても連絡を密にして衛生行政上遺憾のないよう努力して来た。町民もまた取締まられる受身の立場から脱して、自主的立場に立って保健衛生の向上に努めるようになり、予防医学に重点がおかれるようになって来た。
現在町で実施している保健衛生活動は次のとおりである。
一、各種予防接種
1 急性灰白髄炎(ポリオ生ワク投与)春秋2回
2 日本脳炎予防注射 2回 追加1回
3 ツベルクリン注射
4 BCG接種
5 腸チフス、パラチフス予防接種 3回 追加1回
6 ジフテリア予防接種 3回 追加3回
7 百日咳予防接種 3回 追加1回
8 インフルエンザ予防接種 2回
9 種痘 春秋2回
10 狂犬病予防接種 春秋2回
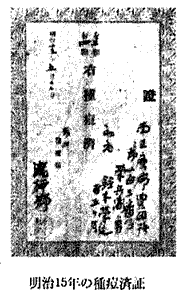 |
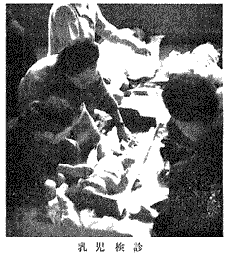 |
二、各種予防検診
1 妊婦検診 6月、11月の農繁期を除く毎月
2 乳児検診 6月、11月の農繁期を除く毎月
3 老人検診 年1回
4 三歳児検診 年1回
5 特別乳幼児検診 年1回
6 子宮癌検診 年2回
7 住民検診(結核検診)
8 成人病検診 年1回
9 検便 寄生虫検便 その他
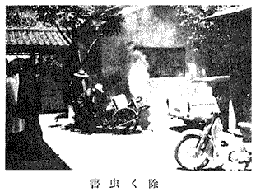 |
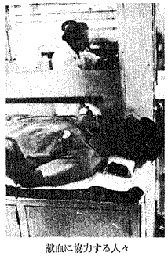 |
三、献血
四、防疫予防消毒
1 春の大掃除、便所下水等の蚊、蝿の発生駆除(乳剤による)
2 蚊、蝿の最盛期駆除(油剤による)
2 蚊、蝿の最盛期駆除(油剤による)
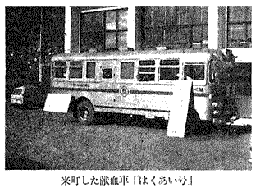 |
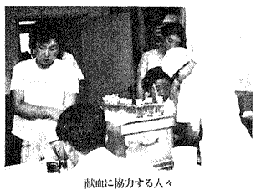 |
昭和四十四年度に住民課から各家庭へ配付した計画予定表は次のとおりである。(表1)
| 表1 昭和44年度計画予定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

