第二節 川水、井戸から水道へ
一、飲用水の利用のうつりかわり
人間の身体の3分の1は水分であり、水は人間生活にとって必要欠くことのできない重要なものである。ギリシャの哲人ターレスは万物は水なりといっており、昔から水神として祀られ神聖視されて来たのも当然である。「身延の者は声が良い、良いはずだ、南天山の水飲む」とは甲州盆唄の一節であるが、旧身延だけでなく身延町一帯は四川を中心とする清らかで豊かな沢水や湧水に恵まれていて、永い歳月われわれの先祖を育ててでくれた。
本町における飲用水は従来湧水を利用するもの、井戸水と川水を併用するもの等種々あった。川水は伝染病の伝染経路となり、赤痢やチフスの集団発生に見舞われ、ために村財政の逼迫(ひっぱく)することもあった。地区により事情は異なるが衛生思想の普及にともない、井戸の数も比例して増加し、川水の使用は次第に減少して来た。古老の言から下山大工町を例にとれば、明治の末頃には約50戸の部落に井戸四つしかなく、いきおい部落の中央を縦貫する堰の水を利用せざるを得なかった。一つの井戸を14.5軒で使用することもあった。現在井戸の数は35に増加しているばかりでなく全戸が下山簡易水道に加入している。井戸の数の増加は、衛生思想の普及や経済力の向上等に原因するものであるが、このようなことはひとりこの部落ばかりでなく他部落においても同様である。現在では井戸端会議というような風景は全然見られなくなったが、当時は学童や嫁の夕方の仕事は水汲みで、手桶をかつぎ棒で運搬した。井戸はほとんどがつるべ井戸であったので、年中行事として井戸替えや縄うちが行われ、時に水神祭も行なわれた。大正末期になると手押しポンプが普及し、戦後はモーターポンプが普及した。大正時代になると部落で共同の水道設備をするところも現われた。大正5年(1916)下山山額区では、県の助成金を得て、竜雲寺参道1本杉の湧水を水源とする鉄管の簡易水道を敷設し、部落の4ヵ所にタンクを設け共同で使用した。昭和12年(1937)日本軽金属株式会社の発電工事のため湧水が枯渇して現在は使用していない。昭和5年(1930)身延山では水圧日本一を誇る消火用を兼ねた本格的水道を設備し又昭和17年(1942)には大城区では川の水を利用して部落の上に貯水池をつくり全戸へ給水した。しかしこれらは町全体から見ればほんの一部にすぎなかった。
二、町内水道施設普及状況
昭和32年新水道法が施行されるに至り、漸(ようや)く近代的な水利用がなされるようになった。新水道法は、明治32年(1890)以来67年間水道行政を規制して来た旧水道条例を改正して、水道の敷設および管理を適正かつ合理的にし、水道事業を保護育成して清浄で豊富低廉な水の供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するために定められたもので、これにより上水道は厚生省、下水道は建設省、工業用水は通産省の専管となり水道行政は目覚ましい発展を見るに至った。
本町における水道施設は合併後急速に改善され、町では、5戸以上の共同によるものを助成対象としているが、実に42の多きに達し、身延町人口の約80パーセント以上が給水を受けている。これは全国平均74.7パーセントをはるかに上まわっている。
本町における簡易水道の概況は表2のとおりであるが、主たるものには下山簡易水道・小原島簡易水道・身延簡易水道・角打簡易水道・中央簡易水道がある。
下山簡易水道 建設委員長は佐野為雄で、早川右岸の富士川伏流水を井戸ケーシング径250ミリメートル、深さ33メ−トルボーリングした。最大揚水能力1日1,200立方メートル、日本ブロイガーモーター水中ポンプロ径80ミリメートル揚水量600リットル、7.5馬力で配水ポンプ室に導入し、配水ポンプはトリシマ製KM型口径75ミリ、6段タービン、揚水能力80メートル、揚水量630リットル、20馬力の電動機で配水池に送水している。
施設および運営状況について見ると、
| 消毒設備 | SB型自動塩素滅菌機2台 | |
| 配水池 | 鉄筋コンクーリト造り、120立方メートル | |
| 配水管 | 直径150ミリメートル〜75ミリメートル | |
| 消火栓 | 地下式単口直径65ミリメートル、34基、地上式2基 | |
| 給水戸数 | 一般380戸、工場2、学校2、保育園1 | |
| 水道料金 | 基本料金330円(10立方メートル)超過料金1立方メートルにつき15円 | |
| 年間経費 | 収入250万円、支出内訳は、償還金90万円、電気料80万円、管理費85万円 |
| 表2 簡易水道施設一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央簡易水道 水源は2ヵ所で、第1水源は鷹取山4,186番地、身延川上流の表流水を毎秒10リットル、鉄筋コンクリート造り取水枡(ます)で取水する。送水管直径100ミリメートル〜75ミリメートル、延長3,210メートルで梅平1区2911番地の着水池に送水する。第2水源は昭和43年8月志摩之沢の地元慣行水利権を取得し、1日最大400立方メートルの表流水を取水堰堤で取水し、着水池に導入する。浄水設備は、着水池、撹拌渠(きょ)、混和渠(きょ)、沈でん池2池、急速ろ過装置の順で、1日最大浄水能力800立方メートル、配水池は鉄筋コンクリート造りで、1日最大有効貯水量150立方メートルで梅平1円に配水する。
設備および運営状況について見ると、
| 消毒設備 | SB型塩素減菌機2台 | |
| 配水設備 | 直径150ミリメートル〜100ミリメートル、延長3,700メートル | |
| 消火栓 | 地下式単ロ 直径65ミリメートル 14基 | |
| 給水戸数 | 一般200戸、高等学校・小中学校・保健所・電々公社外3会社 | |
| 水道料金 | 基本料金300円(15立方メートル)超過料金1立方メートルにつき15円 | |
| 年間経費 | 収入200万円、支出は、償還金70万円、一般管理費100万円である。 |
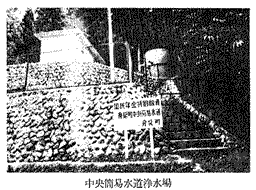 |
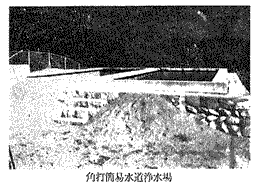 |
設備および運営状況は
| 消毒設備 | SB型塩素自動減菌機1台、簡易点滴機1台 | |
| 配水施設 | 直径150ミリメートル〜75ミリメートル、延長2,840メートル | |
| 消火設備 | 地下式単口 直径65ミリメートル、19基 | |
| 給水戸数 | 一般250戸、身延駅・町営住宅・幼稚園 | |
| 水道料金 | 基本料金250円(12立方メートル)超過料金1立方メートルにつき10円 | |
| 年間経費 | 収入140万円、支出は、償還金42万円、一般管理費50万円 |
設備及び運営状況は下のとおりである。
| 消毒設備 | SB型自動塩素減菌機2台 | |
| 配水設備 | 延長2,300メートル、直径100ミリメートル〜75ミリメートル | |
| 消火設備 | 地下式単口消火栓直径65ミリメートル 12基 | |
| 給水戸数 | 一般140戸 | |
| 水道料金 | 基本料200円(10立方メートル)超過料金1立方メートルにつき15円 | |
| 年間経費 | 収入120万円、支出は、償還金33万円、一般管理70万円 |
| 表3 5水道昭和43年度財政状況 | ||||||||||||||||||||||||
|
三、小規模水道への補助制度とその改正
本町のように小部落が散在するところでは大規模の水道を設備することは困難である。生活改善をするためには、どうしても水道の改善が必要であるが町では小部落の要望にこたえて、簡易水道の普及と公衆衛生の向上を図るために、身延町簡易水道助成規則を定め、昭和36年4月1日より施行している。これは、国県の補助対象とならない、給水人口100人未満の水道に事業費の七分の一を補助するものであったが、経済事情の変動、議会の要望等もあって、44年4月1日より給水人口20人以上または給水世帯5世帯以上について四分の一を補助することに改められた。
簡易水道補助規定
身延町規則第六号
小規模簡易水道事業補助金交付規則抄
小規模簡易水道事業補助金交付規則抄
(越旨)小規模簡易水道施設を設置する事業主体に対して町長が適当と認めるものに予算の範囲内において補助金を交付する。
第三条 この規則の対象となる事業及び補助率は次のとおりとする。
第三条 この規則の対象となる事業及び補助率は次のとおりとする。
| 1 | 、給水人口が二〇人以上又は給水世帯が五世帯以上のもので飲用する原水を滅菌の上、配水管より給水する施設 |
| 2 | 、補助率は本工事費の四分の一以内とする。 |
(補助金交付申請)
第四条 補助金の交付を受けようとするものは補助金交付申請書に事業計画書・収支予算書・水質検査書・受益者名簿等を添付する。
四、水道統合への構想
町内42ヵ所の水道の多くは小規模であり、維持管理を適正にすることが困難な実状にある。また、生活水準の向上につれて、水の需要は年々増大し、将来水不足を来たすことは火を見るよりも明らかで、中には建設当初の予想を突破して、既に水不足を来たしているものもある。町当局においてはこれに対処して、既設水道の改良と水源の開発、各水道の統合等により経営を合理化し、公衆衛生の向上を図るべく、水道統合計画の構想をすすめている。
下山簡易水道は、事業開始以来10年にして、需用量が増大し、夏季には一部地域で時間給水をせざるを得ない状況で、地元協力会と協力して第二水源を確保し、給水の万全を図るべく計画中である。
角打簡易水道は地域の発展とともに、今後使用量の増加はさけられないので、現宮沢水源の取水施設を拡張して、浄水施設の近代化を図り、塩之沢・帯金等へも給水する広域水道を計画している。
身延・中央両水道は、門内、梅平と給水地域が異なっているが、これを一本化し、波木井全域の小規模水道をも吸収するという構想がある。それには、現身延川水源では水量不足であるので、上流雨乞の滝より取水し、北沢水源と志麻之沢水源とを併用し、一日最大水量を2,000立方メートルとし、観光センター、行政センターとして都市化現象の進む町中央地区の水道行政の万全を期する。
以上のような計画が実現には、当然水道専門の課の設置も必要となって来るものと予想される。
五、身延山の水道
従来身延山の飲料水は昔ながらの懸樋(かけひ)の水で、雨や雪の日の断水は珍しくなかった。雨季には泥水そのままを飲むようであったが、昭和6年の宗祖650遠忌記念事業の一つとして防火用の水道を建設した。設計者は当時の東京市水道局工事課長工学士小野基樹で、東京岩田工務所の請負により、落差は上の山貯水池から祖師堂裏まで100メートル、水圧は76.5キログラム、鉄管は水源地から貯水池までは100ミリメートル、貯水池から祖師堂その他各所へは150ミリメートル、延長1,273メートル、消火栓は祖師堂4ヵ所・宝蔵1ヵ所・本院3ヵ所・計8ヵ所、その他簡易室内消火栓4ヵ所を備え、工費は約2万円を要したということで、山内寺院・南部警察署・身延消防隊総出動で放水試験をしたところ、祖師堂の屋根を越す十分な水圧があり、予期以上の結果をおさめたと身延教報に記されている。昭和43年には、老朽したため大改修がなされた。七面山の水道は従来池の水を手桶で汲んでいた。昭和26年頃は簡易ポンプが設けられた。所要個所に配管送水されたが、参拝者の増加と干ばつによる池水の水位低下に競(きょう)々たる状態であった。昭和43年老朽した送電施設は鉄塔3相送電に改修され、強カポンプの使用が可能になったので、登山道上の滝の上の湧水を揚水することになり、43年度秋工事を完了した。水質は極めて良好、年間を通じて温度は7〜8度である。集水タンク地下1.5メートル、貯水タンク地下2.5メートル、全長500メートル、厳寒を考慮し平均20センチメートル埋込み、揚水高約150メートル、毎分75立方メートルの揚水が可能となり、参拝者の利便、衛生面の充実は見るべきものがある。

