第三節 環境衛生と衛生組合の活動
健康を保持するための第一の要件は環境衛生の整備にある。環境衛生の目的は生活環境を衛生的に保つにある。われわれの住居や飲食物を清潔にし有害なものを取り除き、健康で文化的な生活を営むためには、上下水道や塵介、し尿の処理を適切にし、蚊、蝿等を撲減するための環境衛生活動が必要となってくる。県や町村がこれに力を入れるのは当然であり、本町における活動の現況については第一節に述べたとおりである。本町における環境衛生活動は、明治以来役場の指導のもとに主として衛生組合がこれに当たって来た。衛生組合は古老の言によれば明治7、8年頃(1874−5)に出来たということである。前述の市川重門の衛生委員の辞令が明治13年(1880)であるから上の言葉は信頼できると思う。衛生組合の組織は地区により多少の違いはあるが、組合費は各戸を単位とし組合長は各部落の組から選出された衛生委員の互選によるもので、区長が兼ねる場合もあった。会費若干を出し活動費に充て、事業は大掃除の励行、蚊、蝿の駆除、伝染病発生時の消毒、隔離病舎への奉仕等であり、役員は大掃除には警官・村の衛生委員・役場衛生係・区長等と同行し組合員の戸別検査に立ち合い、下水清掃、畳はもちろん床下の清掃、障子のサンや破れの有無に至るまで点検、時に再三の注意を聞かぬ場合、警察は科料を課し、環境衛生の整備、衛生思想の普及に努めた。
戦後は家庭の衛生思想の向上に伴い加えて公民館活動や婦人会活動が活発となり、衛生組合活動の余地が少なくなって行く傾向にある。
終戦直後駐留軍は、特に衛生行政を厳重にし、DDTを散布し、蚊、蝿、蚤の駆除を徹底的に行ない便所便槽の密閉を命令し、町村は改善するものには3分の1の補助を行なった。
後に蚊、蝿を撲滅する運動が各所におこり、本町においては保健所のモデル地区として昭和31年相又上下部落を指定しこの運動を推進した。
また、塩沢部落でも昭和38年頃から害虫駆除、衛生向上に部落ぐるみでとりくみ、蝿や蚊のいない模範部落として町や杜会福祉協議会より補助・奨励を受けている。
また、婦人会は婦人解放・男女同権の思潮の中にあって、むしろ男性以上の意欲をもって文化生活のための学習をおこない、環境衛生の向上に努め台所改善に意欲を燃やした。代表的な事例として大庭婦人会支部では、いち早く毎月積立貯金や無尽をおこない、順次に台所改善を行なった。
し尿処理については、身延門内では住民が共同で合併前からリヤカーで業者にくみ取りを依頼し町でも助成していた。昭和36年頃から業者の衛生車による処理が増加しつつある。戦後は寄生虫駆除の立場から清浄野菜栽培が叫ばれるようになり、農家自身においても、し尿を肥料として使用することが少なくなり、金肥にたよりつつある現状である。
塵芥処理については、適当な場所がないために部落の外れや沢や河原に捨てる悪習があった。東京オリンピック以来町婦人会は国土美化運動の一環として、他人の迷惑や公衆衛生を顧りみず、塵芥を捨て放しにしておく場所に塵芥(ごみ)捨て禁止の立札を立て、或はこれらを焼却するなど、塵芥を適切に処理する運動をおこなっている。
身延門内や梅平では、業者に依頼し共同で塵芥集めを行っており、町は昭和38年大野トンネル口に塵芥処理場を建設し焼却に当たっているが、消費生活時代の今日、塵芥は日一日増加の一途をたどるばかりである。
また、狂犬病や野犬による作物の害を防ぎ、環境衛生をはかるため昭和44年度県知事に犬のけい留命令を受けるよう申請、認可され、5月1日より10月31日まで県条例により町内における犬の放し飼いが禁止された。
町では保健所と協力してこの期間中に野犬・不用犬の捕獲・薬殺を徹底し、犬による公害の絶滅を期している。
一、塵芥処理場について
昭和38年に大野トンネル北口に80万円で、一日焼却能力3トンの塵芥焼却炉を建設し一般の使用に供したが、効率が悪く管理も不充分で町民や議員から度々改良が叫ばれた。40年より町の臨時職員1人が専門に焼却に当り、集荷は町内民間業者が有料で主として身延門内、梅平方面の塵芥を集荷している。また、これ以外の地区は自家用車などで焼却場へ搬入しているものもあるが、多くは沢や空地に捨てたり、焼いたりしている。甚だしいものは公然と河川や堤防に投棄して環境衛生上、または水防上にも大きな問題となっている。
町議会・当局とも塵芥焼却問題の抜本的解決のため、今より規模の大きい焼却場を建設すべく努力し、議会厚生常任委員会は昭和43年、先進町村を視察して町長に早期建設を要望、昭和44年度町予算には300万円の建設予算を計上したが、適当な建設場所には付近住民の反対が強く、苦慮した結果、昭和44年7月の町議会で峡南衛生組合への加入が決定され、六郷・中富・下部の各町と本町で協力して大規模な(1日約20トン処理可能なもの)焼却場を建設することになったので、長い間批判の的になってきた現焼却炉も45年度には廃止される見込みとなった。しかしその他には町の中心から外れている各部落の焼却炉設置奨励とこれに対する町費助成、清掃法に基づく特別清掃地域指定による不法投棄の規制、町の手による集荷体制など、今後解決さるべき問題は多く、し尿処理問題とならんで町の環境衛生と美化の面から2つの大きな課題である。
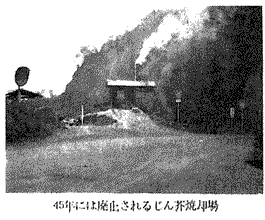 |
二、し尿処理
昭和30年代に入るとし尿が肥料として消費処理される率はきわめてすくなくなり、多くの住民がし尿の処理に悩むようになった。町内にもこの頃からし尿の汲取りと処理を業とするものが現われ、また他地区の営業者も入ってくるようになった。
ところが、肝心の汚物を衛生的に処理する施設がなく、当初から富士川の河原が投棄場所として利用されたので、悪臭、不潔・危険が新しい「公害」となり、至るところで住民の反対を呼び、投棄場所も何回か変ったが、現在では丸滝部落先の河原に投棄しており、付近の住民よりハエの大発生、悪臭の苦情が絶えず、最近ではこの中にあやまって落ちる人が出るなど、早急な改善を迫られるにいたった。
町では早くよりし尿処理場建設を考え、昭和40年には南部、富沢両町にもよびかけて3町共同処理場を作る計画も立てたが、建設場所の問題で挫析した。その後町議会の厚生常任委員会もこの問題をとり上げ、各地の施設を視察研究した結果、43年9月の議会では、中富・下部・六郷の三町衛生組合の所有する処理場を利用してこれに投棄し、町としては特別清掃地域指定を受けて河川投棄の規制・指定業者および料金認可の権限を確立して衛生的処理をはかるよう勧告し、これを受けて町当局も3町衛生組合と折衝して了解を得るなど具体的な準備をすすめ、後述のように実現にこぎつけたのである。
現在単独で処理場を建設するには数千万円の財政負担(国庫補助は3分の1)には到底堪えられず、また、その後の維持運営費も大幅な赤字が予想される。本町の場合業者による汲み取りは約800戸以上と推定され、逐次農村部でも業者に依存する率はふえるとしても、他面浄化槽の普及による減少もあり、単独維持は実際上不可能といえる。他町の例をみても、数町が協力して広域的に処理しているのが通例で、それでもなお年々赤字に悩んでいるのが実情である。
また、新たに処理場を設ける場合、塵芥焼却場以上に用地の確保が困難であり、むしろ既設の施設に加入する方が賢明であり、経済的でもあると考えられる。
最近中富町と身延町間の国道は完全舗装化が進みつつあり、新早川橋の完成により時間距離が大幅に短縮されたので、この面から広域行政の一つとして下部・中富・六郷3町衛生組合への加入が検討され、昭和44年7月、町議会で正式加入促進が議決された。これによりし尿・じん芥・火葬の3つをあわせ4町による共同処理が実現することとなり、大きく1歩前進をとげた。
門内の旅館、観光業者からは、自家用浄化糟では完全に浄化のできない場合があり、道路傍の側溝が汚染されることを防ぐため下水道の施設を要望しており、都市化、観光開発に伴って今後解決されるべき懸案といえよう。

