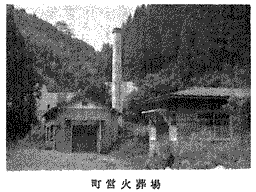第七節 火葬場
古来日本人の風習は土葬がたてまえであったため、農村においては最近にいたるまで火葬場の必要はなかった。本町においても同様であり、止むなく火葬にしなければならない時の場所は大体習慣上きまっていた。多くは早川・富士川・大城川等の河原が臨時の火葬場となった。しかし旧身延町では地域の関係上火葬の必要があったので比較的早くから火葬場が設けられた。望月是本の発案により当時としては、比較的よく整った火葬場が梅平の勝沢地内にできたが、荒廃したので町は昭和37年3月火葬室・待合室291,500円、火葬炉900,000円、計1,191,500円をもって、木造平屋建、屋根亜鉛引並トタンの火葬場を建設した。
建設後台風災害等にもあったが逐次設備も改良あるいは復旧され、現在ではおおむね良好な使用状況である。
年間使用回数は
| 町内約50件 |
使用料(1体)3,000円 |
| 町外約10件 |
使用料(1体)5,000円である。 |
しかし、昭和44年9月、広域行政の方針にもとづき峡南衛生組合への加入が決定され、身延町内の火葬も4町共同の霊柩車により六郷町地内の火葬場へ送迎して行なうことになり、料金1件4,000円も町費で支弁することが議決されたので、現在の火葬場は遠からず廃止される運命にある。
  
|