第六節 町内の保健施設と医療機関
一、江戸末期の医療機関
江戸期以前については詳しいことは不明であるが、下山高橋家所蔵の文書によれば、同家の先祖高橋伊織、高橋祐甫、高橋斉宮亭等が延享・宝暦・明和の頃医業を営み、多くの門弟を育成したことが知られる。門弟誓約書数通の中の一つを見ると
一、御家荘之秘書今蜜々蒙御伝受僕謹而頓首亦何幸過之哉凡其旨一字一句猥不可出干口外也仮令雖為子孫門輩其人而莫可伝之者也
右之条々於相背者可奉蒙我皇朝日本大小神祇并氏神御罰者也命不成事而去ル中夏中旬廿三日天命卒給図而為五七忌日幸呈貴公
明和八辛卯六月廿八日
佐野平質
恭著花押
呈 高橋祐甫英賢
高橋斉宮亭
玉机
とあり、当時の医術修行の厳しさを知ることができる。また、種痘治療について明和八辛卯六月廿八日
佐野平質
恭著花押
呈 高橋祐甫英賢
高橋斉宮亭
玉机
種痘伝書之事
小児痘瘡前 徴候見顕スル者ハ先殺虫剤ヲ投スベシ又
徴候見顕スル者ハ先殺虫剤ヲ投スベシ又 羅女児下剤良法トス種痴ノ法ハ以芫菁膏貼尺沢ニ発砲ヲ破開シ痘痂以四五痂発泡ノ瘡口ニ置キ其瘡口ヲ美恵仁恵ニテ貼シ一七日過初発ナリ初
羅女児下剤良法トス種痴ノ法ハ以芫菁膏貼尺沢ニ発砲ヲ破開シ痘痂以四五痂発泡ノ瘡口ニ置キ其瘡口ヲ美恵仁恵ニテ貼シ一七日過初発ナリ初 ヨリ点見マデ殺虫発汗宜起張ヨリ落痂マデ殺虫利尿也痘後衰弱ノ徴候見ル寸ハ強壮剤可用
ヨリ点見マデ殺虫発汗宜起張ヨリ落痂マデ殺虫利尿也痘後衰弱ノ徴候見ル寸ハ強壮剤可用
刹虫方□海人草大 活ヰ甘草小
活ヰ甘草小
刹虫方□海人草大
| 蛤羅女児下剤 | 大黄大中 蛤羅二リン六毛 大黄五ト |
| 殺虫発汗 | 殺虫方中ニ接骨花中四勺葵大ヲ加フ |
| 殺虫利尿方 | 殺虫方中ニ杜 |
長河顕司
伝
高橋伊織国手
当時の処方を知ることができる。高橋家は明治になると高橋治作が獣医を営み豊岡南部方面に至るまで施療した。この外下山においては松木東宣が儒医であったことが伝えられている。伝
高橋伊織国手
身延においては田中見竜があり文化年間刊行の断毒論に署名が見られるという。断毒論については不明である。
二、明治以後の医療機関
明治以後の医療機関を見ると、下山地区においては儒医早川貞哉がある。漢学塾を開くかたわら医療をおこなった。後年下山医院を開いた望月伝一、山内歯科医院を開いた山内椿房は塾生である。後年、一時下八木沢に移り貞哉の男恭太郎は陸軍軍医となり、後父業を継いで大島に開業後下山に移った。また、望月遜は、明治38年に下山に開業、大正2年、下八木沢に移転開業した。身延地区においては田中見竜の孫見斉が幕末より明治20年(1887)頃まで開業、次いで遠藤源十郎が総門内に開業、大正年間には井出徳治が元町に開業し終戦頃まで営業した。その外、明治44年より昭和5年まで大野に開業した黒坂芳七郎、戦時中疎開し終戦後しばらくの間上町に開業した田村女医、身延高校横に開業した鎌上医院がある。大河内地区については明治30年(1897)頃儒医伴金嶺が八木沢に開業、次いで37.8年(1904・5)頃早川貞哉が同所に開業、更に40年(1907)頃漢方医曽谷貞祐が開業し曽谷医師は主として煎薬を投薬したということである。土地も狭く人口もすくない下八木沢に何故多くの開業医があったかは興味ある問題であり、或は地域の教育に関する関心度に関係があるのかも知れない。塩之沢においては明治37年頃大西南海が開業、帯金においては幕末から明治初年にかけ私塾のかたわら漢方医を開業した望月幸左衛門、甲府空襲後疎開し開業した得業士久保貴作がある。大島においては、明治30年頃早川恭太郎が開業、大正10年(1921)には同地出身小笠原武雄が開業、戦後角打に綱脇医院が開業した。
三、町内医療機関の現況
本町における医療機関は身延山病院を始め多くの開業医があり今その概略を記すと、(一)医院
下山療院 内科・小児科、昭和5年(1930)11月3日開業、医師望月惟臣外職員3名。明治45年(1912)先代望月伝一東京より転住、下山荒町に開業後大庭1871番地に移る。昭和5年死亡、望月惟臣が継承して今日に至る。
遠藤医院 内科・昭和32年10月1日梅平1280番地に開業、医師遠藤恒栄
先代遠藤源十郎の後を継承し、一時身延保健所長となり休院したが32年再開する。
身延山病院 内科・小児科・外科・脳神経外科・産婦人科・放射線科。昭和21年5月24日開業、院長中島文夫、医師4、薬剤師1、看護婦24、栄養士1、事務員9、その他15、ベッド数135床。
身延山八十三世日謙上人財団法人身延一乗病院を創設、26年4月身延山病院と改称。梅平地区に外来診療所を開き従来の病棟は附属療養所となったが、後結核患者の減少に依り療養所を廃止し、40年6月町役場前に建坪1,235.5平方メートル総工費8,300万円をもって鉄筋4階建の病院を新築し今日に至る。
高橋医院 内科・小児科・眼科・昭和26年6月1日開業。医師高橋公男外職員2名、ベッド数4床。
昭和26年6月1日、梅平2,256番地に開業、31年1月15日、梅平2408番地に移転した。
佐野医院 内科・外科 昭和12年1月6日、大野781番地に開業、医師佐野一男外職員2名、ベッド数10床。
昭和15年に身延町外二ヵ村衛生組合(組合長市川政則)の隔離病舎を併設し、伝染病の治療に努めた。
阪本医院 内科・産婦人科、昭和24年8月、角打1245番地に開業、医師阪本睦郎外職員2名、ベッド数4床。
(二)歯科医院
古屋歯科医院 歯科一般、大正10年(1921)6月11日下山に開業、歯科医師古屋慶信、技工師1。本町に初めて歯科医を開業したのは古屋医師で、最初身延総門に開業後現地に移った。当時郡下の開業歯科医は僅か4人、南部1、鰍沢2、下山1であったという。身延山出張所、身延駅前出張所、静岡県大間診療所等を開き診療に当たったが現在は廃す。
山内歯科医院 大正14年(1925)5月下山に開業、歯科医師山内椿房、医師2、看護婦4、助手1、技工師1。
本郡出身歯科医師の第1号という。初め岐阜県高山市に開業、大正14年帰郷開業、昭和6年3月角打に出張所開設、36年分院として改称診療に従事す。
山内歯科医院分院 歯科医師山内皓央、看護婦3、事務員1。
望月歯科医院 昭和12年(1937)2月11日塩沢に開業、歯科医師望月民部、看護婦1、その他1。
石部歯科医院 昭和41年5月17日梅平に再開業、歯科医師石部武彦、技工師1、事務員2、昭和16年(1941)6月歯科医師石部正朗が現地に開業したが、39年死亡のため一時休院した。
(三)医薬類似行為
按摩師、鍼灸師、柔道整復師等は、本来の医業ではないが、日本においては古くから民間に広く行なわれて来ており、これら医薬類似行為については昭和22年に法令により営業が許された。本町においては昭和25年大野に青沼達明が青沼整骨院を開業し、昭和21年身延町に秋山信一が一乗鍼灸道場を開いたのを始め、按摩師を営む者8名がある。
(四)伝染病舎
伝染病舎は一般に避病舎と呼ばれて来た。明治30年(1897)に公布され、昭和34年に改正された伝染病予防法第7条には、伝染病患者を伝染病院、隔離病舎その他適当な場所に隔離しなければならない旨定められている。従って市町村は有事の際を考えて、あらかじめ隔離病舎を建築しておかねばならない。
伝染病予防法施行以来町村においては財政上の理由から、民家を借用するような場合もあったようである。
本町でも明治30年の赤痢大流行の後各村に伝染病隔離病舎が建設されているが、明治31年6月身延村長より知事に提出している隔離病舎設置願がこの間の事情をもの語っている。
伝染病隔離病舎設備認可願
南巨摩郡身延村
右者近来赤痢病大に流行致シ昨明治三十年ノ如キ実ニ惨状ヲ呈シタルモ畢意患者隔離の方法相立タサルヨリ出テタルモノ殊ニ本年ノ如キモ既ニ各地ニ発生致候ニ付テハ先以テ隔離病舎設備ノ必要ヲ感シ居ルニ付先ニ本村字寺平ニ病舎設備出願致シ置キ候処本村ノ如キ地勢遠隔一ツノ病舎ニテ万一患者点々ト発生ノ徴候アリセバ到底隔離ノ完キヲ得ザルハ地位上自然ノ結果免ルル能ハサル次第ニ御座候斯テハ誠ニ遺憾ニ堪ヘザル次第ニ付更ニ大野組ニ本年県令第十号御趣意ニ基キ設備致シ度候間御認可被成下度別紙書類相添へ此段願上候也
明治三十一年六月廿一日 右村長
右者近来赤痢病大に流行致シ昨明治三十年ノ如キ実ニ惨状ヲ呈シタルモ畢意患者隔離の方法相立タサルヨリ出テタルモノ殊ニ本年ノ如キモ既ニ各地ニ発生致候ニ付テハ先以テ隔離病舎設備ノ必要ヲ感シ居ルニ付先ニ本村字寺平ニ病舎設備出願致シ置キ候処本村ノ如キ地勢遠隔一ツノ病舎ニテ万一患者点々ト発生ノ徴候アリセバ到底隔離ノ完キヲ得ザルハ地位上自然ノ結果免ルル能ハサル次第ニ御座候斯テハ誠ニ遺憾ニ堪ヘザル次第ニ付更ニ大野組ニ本年県令第十号御趣意ニ基キ設備致シ度候間御認可被成下度別紙書類相添へ此段願上候也
明治三十一年六月廿一日 右村長
遠藤 緑
山梨県知事伯爵清棲家教殿
この時は大野山本遠寺が字西裏に敷地を提供し地元の大野区からも願書が出されている。建築見積り設計書によると事務室(兼医務室、調剤室)16.5平方メートル、賄所兼小使室13.2平方メートル、快復室13.2平方メートル、別棟ノ重症患者室13.2平方メートル、軽症患者室13.2平方メートル、小使室9.9平方メートル、その他物置・消毒所・便所・浴室等で総面積325平方メートル、建築費465円3銭5厘である。竣工は同年9月10日である。下山においては、最初仲町裏に設け後に上沢に移転した。昭和3年(1928)には関島8078番地に移転した。当時の村会議決書によれば、総額961円54銭、2棟で病舎は瓦葺、事務室はトタン葺となっている。この施設は昭和35年廃止となった。
身延においては塩沢地区に設けられていたが昭和15年(1940)身延・大河内・豊岡三町村組合立の隔離病舎を大野佐野医院内に設立した。
このとき地元大野区長をはじめ区民は地域の環境が害されることをおそれて強く反対し連名による陳情書を提出するなどのことがあった。
しかし数カ月にわたり関係者間で話し合いが行なわれた結果漸く8月に至り建設についての了解が成立、12月16日地鎮祭を行なう運びとなったのである。
豊岡においては町役場に保存されている仮避病舎取調書によると、相又・清子・横根に設けられたことが知られる。
大河内においては、八木沢・丸滝・角打に設けられていたが、後に村営に移行した。
ア、身延町外2ヵ村衛生事務組合
昭和15年身延町会々議録によれば、前記の身延・豊岡・大河内の三町村組合立の隔離病舎が設けられたことが知られる。
すなわち、
昭和拾五年四月十六日本町会ヲ本町役場ニ開ク。
議案第十八号 身延町外二ヵ村衛生事務組合設立ノ件
議案第十九号 身延町外二ヵ村衛生事務規定認定ノ件
議案第二〇号 身延町外二ヵ村衛生事務組合会議員選挙ノ件
が上提され、議案第十八号 身延町外二ヵ村衛生事務組合設立ノ件
議案第十九号 身延町外二ヵ村衛生事務規定認定ノ件
議案第二〇号 身延町外二ヵ村衛生事務組合会議員選挙ノ件
衛生ニ関スル一切ノ事務ヲ共同処理スル為メ身延町大河内村豊岡村三カ町村衛生事務組合ヲ設立スルモノトス
理由
本案議決ヲ要スル其ノ理由ハ隣接大河内村、豊岡村ト共同衛生事務ノ処理ト併テ完備セル隔離病舎ヲ建設伝染病予防ニ努ムルニ因ル
とある。理由
本案議決ヲ要スル其ノ理由ハ隣接大河内村、豊岡村ト共同衛生事務ノ処理ト併テ完備セル隔離病舎ヲ建設伝染病予防ニ努ムルニ因ル
規約は、
身延町外二ケ村衛生事務組合規約
第一条 本組合ハ身延町外二ケ村衛生事務組合ト称ス
第二条 本組合ハ下ノ参町村ヲ以テ組織ス
身延町 大河内村 豊岡村
第三条 本組合ハ衛生ニ関スル一切事務ヲ共同処理ス
其ノ概目左ノ如シ
一、伝染病予防
二、隔離病舎ノ経営維持
三、罹病者ノ治療其他
四、其他法令ニ依リ本組合ノ事務ニ属スルモノ
となっており、その他「組合会議員定数8・身延3・大河内3・豊岡2」が定められ、「組合長一・委員三名ヲ置ク。会計ハ組合長所属ノ町村ノ収入役」となっている。第二条 本組合ハ下ノ参町村ヲ以テ組織ス
身延町 大河内村 豊岡村
第三条 本組合ハ衛生ニ関スル一切事務ヲ共同処理ス
其ノ概目左ノ如シ
一、伝染病予防
二、隔離病舎ノ経営維持
三、罹病者ノ治療其他
四、其他法令ニ依リ本組合ノ事務ニ属スルモノ
なお
第十二条 本組合ニ於テ建設スル避病舎ノ費用ハ寄付金補助金ヲ以テ之レニ当テ尚不足アル場合ハ組合内各町村ニ分賦ス
第十三条 支出比率 身延三 大河内三 豊岡二
となっており、組合長に市川政則が就任した。これよりさき昭和7年、南部警察署管内8ヵ町村の76衛生組合をもって峡南衛生組合連合会が結成され7月28日結成総会を開催した。
会長には南部警察署長西山豊治郎、副会長には大河内村長望月望が就任している。
連合会当時の旧4ヵ町村別衛生組合の状況を次表に掲げる。
| 役 員 名 簿 (現身延町区域のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ、身延町外2町共同伝染病舎
時代の進展に伴い、隔離病舎を使用するものが少なくなり、高度の医療施設を有する病舎を利用する者が多くなった。一方町村においても、不治の病気のために病舎を建設し維持することは経済上からも好ましいことではない。さりとて一度患者が発生するや鰍沢・富士宮等遠隔の病院に入院することもまた並大低ではない。ここにおいて3町(身延・南部・富沢)共同伝染病舎が計画され、昭和41年4月設立が許可され、昭和42年度補助金の交付をうけて、近代的病舎が身延山病院構内に建設された。事業概要および関係規約は下のとおりである。
身延町外二町共同伝染病舎
建築状況
| 1、総工費 | 6,850,000円(内補助金4,004,080円) | ||
| 2、敷地面積 | 198平方メートル | ||
| 3、建築延面積 | 244.28平方メートル | ||
| 4、病床数 | 12床 | ||
| 5、建築構造 | ブロック建築2階建 | ||
| 6、着工月日 | 昭和42年11月15日 | ||
| 7、完成月日 | 昭和43年3月25日 | ||
| 8、建物内容 |
|
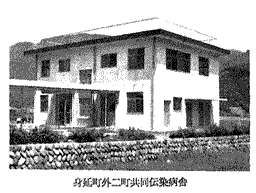 |
(組合の名称)
第一条 この組合は、身延町外二町共同伝染病舎組合(以下「組合」という)と称する。
(組織する団体)
第二条 この組合は、左の地方公共団体をもって組織する。
身延町、南部町及び富沢町
(組合の共同処理する事務)
(組合の共同処理する事務)
第三条 この組合が共同処理する事務は、次のとおりとする。
一、伝染病舎の設置及び廃止に関すること。
二、伝染病舎の運営管理に関すること。
一、伝染病舎の設置及び廃止に関すること。
二、伝染病舎の運営管理に関すること。
(組合の事務所の位置)
第四条 この組合の事務所は、山梨県南巨摩郡身延町役場におく。
(組合の議会の組織及び選任方法)
第五条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という)の定数は、五名とする。
2、前項の組合議員は、南部町及び富沢町の町長並びにこの組合を組織する町議会議長をもってあてる。
3、組合議員の任期は、町長及び町議会議長の在任期間とする。
2、前項の組合議員は、南部町及び富沢町の町長並びにこの組合を組織する町議会議長をもってあてる。
3、組合議員の任期は、町長及び町議会議長の在任期間とする。
(組合の執行機関)
第六条 この組合に組合長及び監査委員をおく。
2、組合長には、身延町長をあてる。
3、監査委員は二名とし、南部町長及び富沢町長をあてる。
2、組合長には、身延町長をあてる。
3、監査委員は二名とし、南部町長及び富沢町長をあてる。
(組合の補助機関)
第七条 この組合に副組合長及び収入役をおく。
2、副組合長は一名とし、議会の承認を得て組合長が選任する。
3、収入役には身延町収入役をあてる。
2、副組合長は一名とし、議会の承認を得て組合長が選任する。
3、収入役には身延町収入役をあてる。
第八条 この組合に必要な事務局長及び事務吏員をおく。
事務局長及び事務吏員は組合長が任免する。
(組合の経費の支弁方法)
(組合の経費の支弁方法)
第九条 この組合の経費は、この組合を組織する各町において下の各号によって負担する。
一、建築費は、南部町が三十万円、富沢町が二十万円を負担し、残額を身延町が負担する。
二、その他組合の運営に要する経費は、組合の議会の定めるところにより負担する。
一、建築費は、南部町が三十万円、富沢町が二十万円を負担し、残額を身延町が負担する。
二、その他組合の運営に要する経費は、組合の議会の定めるところにより負担する。
附則
1、この規約は、知事の許可があった日から施行する。
2、この病舎の建設前に伝染病の発生した場合は、なお従前の例による。
2、この病舎の建設前に伝染病の発生した場合は、なお従前の例による。
(五)その他
文化の変転期にあっては新旧の習慣、制度の混淆(こう)することが多く、医療の面においてもそれが見られる。すなわち医師としての資格はなく、法令上施療してはならないが、本人の恵まれた天分や経歴上から特殊技術をもって人助けを行なった人がある。松木平重郎、昭和19年(1944)没、下山仲町の人、本業は農・漢方医術・灸に詳しく病に苦しむ人が来れば無料にて診療し、多くの人々から感謝され慕われた。心理的療法も得意で、時に突如大音声をもって病者を一喝することもあった。
深沢竜一、帯金の人、昭和40年没、講道館柔道6段、旧制県立身延中学校柔道教師、整復技術に優れ、脱臼骨折等の患者が来ると無料にて施療し、人々から感謝された。
大坪重雄、角打の人、昭和35年没、優れた整復技術をもって木材業の傍ら多数の患者を無料で治療した。

