第二章 社会福祉
第一節 社会福祉と社会福祉協議会
日本国憲法は第25条に「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、これに対する国の義務として次に「国はすべての生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と国民の生活を保障している。しかしながら、いかなる時代、いかなる社会にあっても、その生活環境、生活条件の相違や被災などにより、社会的弱者の存在を避けることはできない。社会事業は、これらの不幸を救済し、弱者を保護する活動として起ったものであり、古代から現在に至るまでこの理念に変りはないが、近来特に社会福祉と呼ばれるようになったことは、慈恵的・恩恵的な施策から、国家社会の当然の義務として、劣者弱者を向上せしめる施策の意味と解すべきであろう。広い意味では百般の行政がすべて社会福祉のためのものであるが、ここで取りあげる社会福祉とは狭義の意味で、貧しい者・病める者・困窮者の福祉を増進し、一定のレベルまで引き上げて行こうとする施策と解すべきであろう。時代の変遷とともに言葉のもつ内容も変ってきたが、昔から社会の三悪といわれてきた貧乏・病気・犯罪等をなくしてより住みよい社会を築こうとする運動それを社会福祉といっても過言ではあるまい。
さて身延町の場合、当然身延山久遠寺の創立とともに、宗教的慈恵的になんらかの形で社会事業が行なわれたであろうことは想像に難くないが、今これを具体的に説明する資料はない。記録の一片に大正13年(1924)10月身延山久遠寺は巨額の金と土地を寄付して勅定紺綬褒章を拝受したとあり、あるいは大正中期財団法人普洽(ごう)会を設け社会事業施設助成を志す等の例もあった。
近世明治39年(1906)1月先駆者により民間社会事業施設として、貧困者・行路病人・身上相談・死亡者助葬等、およそ困るという人を収容する身延山功徳会が設立され、また、同年11月民間救癩(らい)施設として全国にただ一つの身延深敬園が創設されたことは県下における最も古い施設として特筆されるべきものである。
一方社会的には、方面委員制度が昭和2年(1927)3月、山梨県告示をもって設置され、法令による方面委員活動が開始された。当時の方面委員は一町村両三名であった。大河内村では市川政則・望月朝次郎であったが、昭和4年になり小林月渓が任命された。その後昭和七年救護法が施行され昭和11年(1936)方面委員会制定、昭和12年(1937)7月日華事変勃(ぼつ)発、軍人救護法強化、昭和13年(1938)社会事業法が生まれ、昭和16年(1941)12月8日太平洋戦争に突入、20年(1945)8月15日敗戦に至るまで、国・県の施策と相まって目まぐるしい変遷の中で社会福祉推進の事業が行なわれて来たのである。
昭和21年11月3日、日本国憲法が発布され、新しい民主政治の線に沿うべく、生活保護法に基づく社会福祉施策が進展したが、昭和21年制定された民生委員会は、昭和22年新たに児童福祉法の制定とともに民生委員が児童委員を兼ねることとなった。さらに、昭和23年民生委員法が施行されるに至った。社会福祉施設としては、前記財団法人身延深敬園・社会福祉法人身延山功徳会がある、児童福祉施設として、秋山智孝設立の下山立正保育園・西尾貫遂設立の大野山保育園・沢村清一設立の大島保育園等がある。
中央・県・郡の段階に、およそ社会福祉を志す団体・施設がそれぞれ大同団結して社会福祉協議会を結成、地域社会福祉の増進に寄与することとなり、昭和26年旧身延町にあっては藤田喜太郎、大河内村は佐野祥盛、下山村にあっては望月惟臣、豊岡村は鴨狩庸雄がそれぞれ会長となり、敬老会・慰霊祭・歳末助け合い運動等の住民福祉推進に努めて来たが、昭和30年2月下山・身延・豊岡・大河内の1町3ヵ村合併により、社協もまた合併して深沢忠雄が会長となり、ついで昭和34年長谷川寛慶が会長となり創立以来敬老会・慰霊祭・歳末助け合い運動・共同募金推進・法務省主唱の社会を明るくする運動参画・児童遊園地造成援助等の事業にきめ細かに取組んで来た。昭和35年には助け合い金庫を創設、当初は2万円の基金が、現在は20数万円となり、これを1口5,000円の無利子で貸し出し、利用件数50件に及んでいる。
また昭和38年7月より、心配ごと相談所を開設し、常任相談員と社協常務理事が、民生委員および社協理事より選任された相談員とともに、毎金曜日に相談に当たり、多大の効果を収めている。
その外町内子供クラブ幹部の指導者講習・老人クラブ設立運営指導援助、青年団・婦人会・子供遊園地における部落単位運動競技会の援助等を行なっているが、資金面にあっては、県下でも最初の町民全戸加入を目指してほぼ達成、篤志家寄付・町助成金等をもってこれに当て、助け合い金庫の資金増額・衛生行政への積極的参加等、地域社会福祉協議会の本務遂行のため真剣な研究努力が続けられている。
ちなみに本町よりは創立当初の県社会福祉協議会会長に綱脇竜妙が就任、その後長谷川寛慶が副会長に就任したことがあり、南巨摩郡社会福祉協議会には藤田喜太郎・深沢忠雄・長谷川寛慶が会長に就任、県・郡・単位社会福祉活動においても見るべきものがあった。
なお社会福祉功労者として表彰を受けた主なる方々は下の通りである。
| 綱脇龍妙 | 勲四等旭日小綬章 藍綬褒章 厚生大臣賞3回 宮内省・内務大臣賞 山梨県知事賞2回 | |
| 小林月渓 | 勲五等瑞宝章 厚生大臣賞3回 山梨県知事賞 全国社会福祉協議会長賞 | |
| 市川政則 | 厚生大臣賞 | |
| 長谷川寛慶 | 厚生大臣賞 山梨県知事賞2回 全国社会福祉協議会長賞 | |
| 石川金雄 | 厚生大臣賞 山梨県知事賞 | |
| 綱脇さだ | 山梨県知事賞 | |
| 綱脇美智 | 山梨県知事賞 | |
| 市川みやじ | 山梨県知事賞 | |
| 小林今代 | 山梨県知事賞 | |
| 坂口起一 | 山梨県知事賞 | |
| 秋山智孝 | 山梨県知事賞 |
一、財団法人身延深敬園(じんきょうえん)
明治39年(1906)7月身延山に参拝した綱脇竜妙は、久遠寺境内三門付近に蝟(い)集している癩(らい)患者が困憊(ぱい)の態(てい)にあるのを発見し、幾多の聞くに絶えない哀話を耳にするに及んで、宗教に生きんか、社会救済事業に生きんかと煩悶懊悩(はんもんおうのう)のまま数日を空しく過した。眼前にこの悲惨極まりない同胞の姿を見ては、生命を賭(と)しても助けんものと決意し、宗教上の布教目的実現は一時これを保留するも止むなしとし、一身を犠牲にする覚悟を定めたのであった。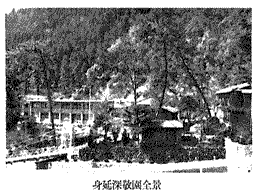 |
師は一面においてこの一事業のため、終生の目的たる宗教上の修行に照らし、社会に対し、根本的救済の真使命を果たさんとするの一念を、未だ貫徹し得ないことを、切に遺憾としている。が、ひるがえって考えればまたこの癩患者救護という事業に一生を捧げたことには毫末も悔ゆるところなく、かえってこれに奮励することを第一義とし、信仰を更に深く体験せしめんとする仏陀の意志を認め、これを天職となしてますます精進しているのである。ことに癩患者は、社会一般の見るような偏癖あるものでなく、慈愛をもってこれに向えばすこぶる真摯従順、よく規律を守り、特に信仰には、普通人より更に徹底し易いなど、彼等の深く愛すべく敬すべきを悟って、この事業を通しても仏教の真諦(たい)に達せられることを信ずるに至ったのである。
しかし深敬園経営費の大部分はただ勧募に待つ外はないので、その精力の大半を、この資金募集に費さざるを得なかった。この事業は綱脇竜妙によって初めて創設されたものであるから、先輩ないし先覚者の指導後援は固よりなく、徹頭徹尾、独立独歩もって今日あらしめたのである。この努力はいつしか一般の認めるところとなり、宮内省より年々御内帑(ど)金を下賜せられ、明治42年以来年々内務省より奨励金の下付を受け、後には国庫補助金の形式で下付されることとなり、篤志家からも陰に陽に多大の援助をうけられるようになって今日に及んでいる。
創立以来年々増改築があり、特に昭和42年診療棟鉄筋ブロック2階建延べ450平方メートルを予算1,653万円を以て増築し、敷地3,901平方メートル、建坪2,936平方メートルの広大に及び、園長綱脇龍妙と、事務長以下職員18名で、現在患者83名、内男50名女33名が収容されており、最高年齢者は73歳、最低22歳のいずれも男である。
因(ちなみ)に創立当初よりの収容状況は次の通りである。
1 入園者数 1,436人
男 1,109人
女 327人
2 死亡者数 239人
3 退園者数 1,114人
男 878人
女 236人
男 1,109人
女 327人
2 死亡者数 239人
3 退園者数 1,114人
男 878人
女 236人
二、社会福祉法人身延山功徳会
明治39年(1906)1月の創立にかかり、創立者長谷川寛善が身延山二王門裏大杉の下に死んでいた一老婆を見てこれを憐れみ、手厚く葬った。これを機に、身延山功徳会を創設し自ら会長となり、行路病者救護・死亡人取扱いないし旅費なき参詣者の無料宿泊・旅費給与等の事業を経営するに至ったのである。当時の建物は木造丸太造りのわずかに4、5名を収容した施設であったが、順次増築して、昭和6年(1931)日蓮聖人六百五十遠忌の記念事業が行なわれるに当って、全国から蝟(い)集した浮浪者で収容者100名を越えたこともあった。よき援助者としては下山郵便局長芦沢九左衛門があった。創立当初は乞食の親方とさげすまれたが、大正9年県より社会事業として補助金を下付されるにいたって、初めて認められるようになり、後恩賜財団慶福会・県・内務省等より補助金の下付があり、更に御下賜金の拝受再三に及び、これらに力を得て拡張につとめ、特に昭和3年(1928)即位の大礼に当たっては内務大臣より表彰状および銀牌を授与された。寛善がその妻よのとともに死に水を与えた行路病者は200名を越すという。昭和9年(1934)58歳にして寛善没し、長男寛亮継承、鋭意発展に努力したが、昭和19年(1944)応召(20年戦死)するに及び現会長長谷川寛慶継承し今日に及んでいる。創立者の妻よのは昭和15年(1940)社会事業に尽した顕著な功績により、社会事業功労章を授与され、2代目会長寛亮また昭和19年に社会事業功労賞を授与された。現会長寛慶また山梨県政功労章を、更に厚生大臣表彰を受けている。
 |
因(ちなみ)に昭和45年を期して、鉄筋ブロック2階建、耐震耐火の建物を約3,000万円の予算を以て建築すべく準備を進めつつある。なお、身延山をひかえた特殊な存在であるため、収容者も全国的で遠く北海道・九州などより収容されている者もあり、山梨県出身者は僅かに5分の1に過ぎない。

