第九編 交通運輸と通信
第一章 交通と運輸
第一節 概説
本町の交通運輸のうつりかわりのあらまし
文永11年(1274)日蓮聖人が身延にご入山当時の身延町の交通運輸の姿は、日蓮聖人の身延山御書をはじめ、諸文書の中に、文飾はあったにしてもいかに困難な道中であったかが、詳細に記されている。南部氏の所領下の南部牧の興隆は、国中地方および駿河方面との物資の交流を盛んにし、当時の交通が、富士川沿いに発達したことは周知の事実である。
とくに中世にかけて、身延町を中心とした峡南地方の交通は、戦国諸大名の戦力増強と、宗教的な特異性を含めた時の権力者による、法華経の仏加護を念じての信仰参拝と、一方全国各地からの身延山参拝を目的とした交通、それに伴う物資の輸送等で殷賑(いんしん)を極めた模様である。
一方、こうした中で、穴山氏によって開かれた下山宿は、信玄時代の新宿設定の戦略的交通政策、また江戸幕府時代の本陣所在の関係や助郷の問題から、人足割当の不当性、生活環境と、経済生活におよぼした助郷の割当が、単に下山地区のみの問題にとどまらず、東西河内筋の村々との紛争を生じている。
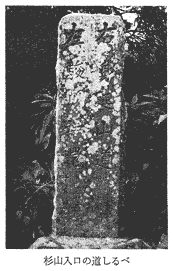 |
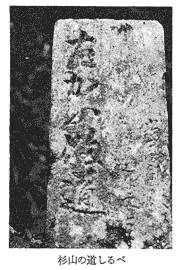 |
さらに、水運による交通運輸の面を考えて見ると、慶長12年(1607)3月、角倉了以が富士川を開さくし、高瀬舟を通ずるという、交通運輸の革命的な飛躍期に入ってからの姿は、鰍沢から岩淵や蒲原と、水運の拡(ひろ)がりは、時間的には、川丈18里(72キロメートル)を、川下げ5時間という短時間で物資運搬の面でも、量的飛躍をもって、江戸幕府への御回米輸送、海からの魚、塩の輸入、峡南地方からの木材の輸送が行なわれた。
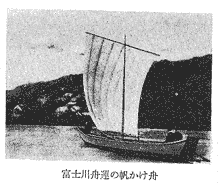 |
或るときは、河はやく石多ければ、舟破れて微塵となる」(日蓮聖人ご遺文)の内容からも考えられるように、水難にあって、命を失った船頭、乗客等の悲惨な犠牲も多く、それと同時に、貴重な物資の損失も決して尠(すくな)いものではなかった。
舟は、いわゆる高瀬舟(底の浅い、急流を通行するにむいた船)が用いられ、舟運の便益は、峡南地域をうるおした反面、遭難の歴史をも綴りながら近世から明治時代へと発展しつづけ、明治6年の船頭連名帳には、青柳19・箱原5・八日市場8・波高島10・八木沢11・帯金13・波木井9・大島4・南部3・計82人となっているが、この人数は、官許の幕府以来の船頭数で、更に員数外の人足・船頭があった。
日に上り100そう、下り100そうといわれる程の通船数で、総舟数800艘、船頭の数は、2,000人におよんだという状況であった。
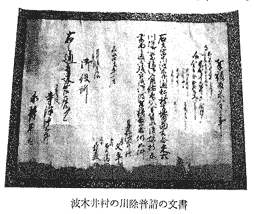 |
明治36年(1903)、中央線が開通するに至り、富士川の舟運は、俄(にわか)におとろえ、更に身延線の全通により全く富士川の舟運はとどめをさされたのである。
それ以後の舟の姿を、形だけに残したものといえば、いわゆる、横渡しと呼ばれた渡し舟に過ぎなかったが第二次世界大戦後は、東西の架橋により、舟の姿は全く消えてしまったのである。
身延線の設立が企画されたのは明治44年(1911)6月静岡県富士宮市を起点として、甲府市に至る鉄道敷設を目的として免許され、大正元年(1912)富士軌道株式会社より富士駅から富士宮市に至る敷設権を譲り受け、同年7月7日富士、富士宮間の工事が竣工した。大正4年(1915)2月富士宮芝川間完成、以来工事を続け大正9年5月18日身延まで開通、昭和3年(1928)3月30日、甲府まで完成、電車運転開始、東海道線富士駅より中央線甲府駅に至る88.1キロメートルは全通して、身延町の交通史に一つの大きな飛躍を迎えることになった。
その後、支那事変の勃発とともに、国の軍政上の観点から、昭和13年10月1日、国営移管となり昭和16年5月を期し、国鉄による買収となり名実ともに身延線の地域開発と、永年の地域住民の要望が実現したのである。
 |
当時の平常時の水量は相当あり、土地の古老が、死ぬまでに1度でよいから富士川の水底を見たいものだと語った程であり、ひとたび雨が降りつづくと富士川の増水は、身延山参拝の客を、身延の町に、または、身延駅に足どめしたのである。
こうした困難を解消するために、身延駅と対岸の大野とを結ぶ鉄橋の架設が要望され、大正12年(1923)8月、身延橋の開通となり、これにつれて、身延駅身延山間の馬車、自動車の乗り入れの時代を迎え、身延町の交通運輸に近代化への曙光が見えて来たのである。
一方甲駿往還の交通も、明治8年になり、下山横根間の新道開さくにより、陸運中馬会社規則を駅逓寮に山梨県令の具申などがあり、明治7年(1874)5月には、駿州路郵便取扱所が相又駅に設けられ、着々陸路往還の様相も道路の整備、郵便線路の開設により、今日の姿に変貌(ぼう)したのである。
 |
今日、身延山参拝者は年間100万人といわれ、宗門のメッカとしての地位を築いている折、西八代縦貫道路の整備とともに間道としての大城−安倍峠道路も林道兼観光道路として、両3年以内には完成するであろうことを想い合わせると、将来の身延町繁栄につながることであろう。

