第二節 交通運輸の変遷
一、中世の交通と運輸
日蓮聖人が、居を身延に構えるまでの身延町の交通運輸は、南部氏の所領であった関係上、南部一族の興隆とともに、急激な発展を見るに至った。鎌倉時代、文永11年(1274)5月12日、日蓮聖人は鎌倉を出発、16日に南部に1泊、17日には身延に到着した当時の模様をご遺文の中に
「十二日さかわ(酒匂)、十三日たけの下(箱根)、十四日くるまかへし、十五日ををみや、十六日なんぶ、十七日このところ(身延)」と、1日ごとの旅程を記され、又道中の困難さを表現して、波木井殿ご書の中で、
「五月十二日、鎌倉を立ちて、甲斐の国に分け入る、路次のいぶせき、峯に上れば日月をいただくが如し、谷に下れば穴に入るが如し、波たけくたて舟渡らず、大石流れて箭をつくが如し、草木茂りて、路見えず、かかる所へ尋ね入ること浅からぬ宿習なり……」と述べられている。
文の表現には、多少の誇張があったにしても、その頃の交通というものの状態が理解できるのである。
河内をめぐる交通路は、富士川沿いに発達したものであるが、山中の陸路であり、武田氏によって、戦略的に整備されるまでは、その交通運輸の姿は、難路というほかはなかったであろう。
さて、日蓮聖人の身延入山の経路を考えるに、甲州の公道は、延喜式にある国府から水市、河口、加吉とあって籠坂越えの鎌倉往還が古い道であり、13世紀の当時は鎌倉に政庁がある故に、一層の重要な公路であった筈であるのに、日蓮聖人の入山にどうして富士の南回りをとられたのであろう。
それは、一つには身延の地理的位置の問題と、甲州の政情不安にもあったのであろう。
南麓回りには、日蓮聖人の信奉者もあって、沿道何かと好都合であったのであろう。
当時の身延町は外界から閉ざされており日蓮聖人のご入山によって、世に開かれたとも考えられる、物資の不足がちの地域だけに、関係の信徒から、塩食糧をはじめ、日常生活に必要な物資が陸路によって送られて来た。
その道中のさまは、いぶせき路であり、草の生い茂った路の輸送の困難は、想像に余るものがあった。
さて、当時の富士川の渡渉地点について甲斐国志「磐橋(いわばし)」の条に
「前略、内房ハ駿河風土記ニ内富瀬ニ作ル河水ノ俯伏スル義ナルベシ此処左右ノ涯壁立数千尺岩石競イ集リテ奇絶甚シ、河水屈伏シテ其内ニ落入リテ流ル上古ハ上ナル磐連ナリテ橋トナリタルヤラン、今内房ヨリ長貫村ヘ渡ルニ縄橋トテ藤羅(ヅル)ヲ纒架ケタル危橋アリ」(以下略)
とあって、国志のなった19世紀には、藤づる橋が危なげに架してあったがここ芝川の北長貫と西岸内房の白鳥山麓の間は岩橋といって、古くは両岸の岩石が河床にせり出し徒渉に好適だったらしく、地名「いわばし」もそれによって起ったというのである。日蓮聖人の身延入山の行程も、駿河を此処で富士川を越え、万沢から南部へ進んだものであったろうし、南条氏が身延の祖師の許へ供物進上にも此処を渡ったものであろう。聖人遺文の「ふじのうえのよりみのぶの山へ」とか「富士郡上野の郷ヨリ甲州波木井郷身延山ノホラへ」との記述が此処を徒渉地点とすることにより、現実と合致し首肯し得る訳である。
そしてこれはまた、河内路が開発されるまでの身延参詣の東海道よりの交通路であったのであろう。
しかし、なんといっても、交通路が強力に整備されたのは戦国時代になってからであり、戦国大名の戦略上の要請が次第に交通政策を押し進めるようになった。
河内路については、万沢から駿河へ出る交通路は次の三筋があった。
1、万沢−宍原−興津−駿府
2、万沢−内房−由井−江尻
3、万沢−北松野−南松野−岩淵
穴山信友が居を南部から下山に移したのは戦略上からであるが、これ以後下山宿は河内地方の中心地として繁栄していったのである。
信玄が駿河攻略に出兵したのは永禄11年(1568)でその際中道往還の改修を行なったとあるのをみれば河内路は未だ開拓が充分でなく、あるいは軍略上からの理由で利用されなかったものが、その後駿河進攻が進むに従って、河内路の重要性は加わっていった。
さらに、穴山信君が江尻城主となったのは、天正3年(1575)であり、河内路が甲駿をつなぐ軍略政治上の交通路として整備を見たのは16世紀末のことであった。
かくして、河内路が甲斐府中から駿河への交通運輸の確保の必要から、船頭屋敷免許なり、伝馬法度なりの政策として現われたものであり、さらに徳川幕府となり、その安定した治安の確率を背景に近世の交通運輸へと変貌してきたのである。
二、近世の交通と運輸
慶長12年(1607)徳川家康の命により角倉了以によって富士川の開さくが行なわれ、舟を通じるようになってからの河内路は、おのずから物資の輸送と人の交通が、陸路輸送と舟運に頼ることになった。駅逓志稿に「是年更に了以に命じて駿河の富士川を浚し同国岩淵より甲州に溯って
慶長17年(1612)5月富士川の商貨漕運の制が定まった。
これによると黒印なき舟船に商貨を搭載してはいけないというもので商売の品は一駄の駕量が40貫目であり、その運賃は京銭10文とし乗掛は人馬ともに20文、富士道者も同じであった。
ただし参詣の歩行者は5文となっている。
富士川開さくの目的は、甲州の米を江戸に回送するに際し費用の多い陸路輸送よりも、低廉な富士川を利用したことが主な理由であったというよりも、物資輸送による運賃収益を目的としたものであった。
江戸への御回米については、角打市川正夫蔵の、御回米御用日記、安政2年(1855)万延元年(1860)の2冊があるがそれによれば、御回米の輸送の苦労の程が想像されるのである。
ことに蔵米収納の際の貫目不足、枡(ます)目不足などの完全な検査が終わらねば回漕の責任は終了せず、また出発についても、天候の具合と海上輸送のための船仕立も、この場合など遠州相良町から回って来た舟によっているなど、富士川船による富士川の輸送は順調に進んでも清水港、由比の浜からの仕立は順調な運行が行なわれたものでなかった。
また同氏所蔵の万延元年の御回米御用日記に(抄出)
申十月十八日より
一、四百四拾八文を□□賃
一、御役所様より御触出し江戸御回米川内領□□御用被仰付御請仕候は八朔三日十二月十七日
御役所様より御書付着十八日朝明六ツ時出立御役所様江七つ半時御届け仕罷居申候
十九日
御役所様より御書付着十八日朝明六ツ時出立御役所様江七つ半時御届け仕罷居申候
十九日
一、御役所様江上リ御前借仕并ニ御用金百両清水港迄被仰付其外御用状岩淵河岸蒲原浜清水港迄仰付られ御用相済切石村迄参り申し候
廿日
廿日
一、雨ふり切石村出立致帰村夫より江戸出立仕度致申候
廿一日
廿一日
一、天気村元出立致舟無之十嶋村名主五郎兵衛方へ泊り申候
廿二日
廿二日
一、十嶋村出立致八十沢共々八反舟にて岩淵河岸へ九ツ半時着致石和御分御出役郡中村役様江御目通り夫より蒲原浜御支配井之上亀三郎様江御目通り御用状相渡夫より由井迄参り泊り申候
廿三日
廿三日
一、天気由井宿出立致清水港江九ツ時着御出役渋谷鷲郎様御目通り金百両に御用状相渡申候郡中村役様へ御目通り三四郎方逗留罷居申候
廿四日
廿四日
一、天気清水港三四郎方逗留罷居申候
廿五日
廿五日
一、天気向嶋にて貫目升回し有之船頭受取相済御積立に相成私船中に罷有申候
とありこれから1月10日迄清水港みほが崎に逗(とう)留を余儀なくされていたが1月11日になり、「天気朝七ツ時出ばん致夫より其夜明迄に伊豆に掛り参り罷居り申し候」とやっと伊豆に出て来た。 十二日
一、天気東風吹き出しす崎港江暮九つ時参り船中逗留罷居り候
十七日
十七日
一、天気東風にてす崎港船中逗留罷居申し候
昼より西風にて相州浦賀江夜五つ時着致御届けも無之船中に罷居申候
十八日
昼より西風にて相州浦賀江夜五つ時着致御届けも無之船中に罷居申候
十八日
一、天気朝五つ時御関所より御改請罷申居候
四ツ時より東風にて相州浦賀港逗留仕申候
かくして風向きを利用して2月の4日に江戸永代橋下に着き2月9日にやっと水揚げの段取りとなったことが記されている。四ツ時より東風にて相州浦賀港逗留仕申候
ところが2月11日になり壱石弐斗五升八合の弁米し御役所へ御届け内々にて済まし方をお願いしている。
こうした苦労の結果も蔵前の役人の都合で、最後に御再見を願って精算の請取が役所でなされたのは3月2日と記されている。
いかに苦心の回漕業務であったかがわかる。
さてこの時の御回米の送り状の内容を見ると
甲州村々御回米送状之事
辰正月十日
一、壱番船 □□請負人
播磨屋三四郎
一、米七百三俵 遠州相良
本乗船頭 庄三郎
内壱俵「三斗七升入
御箱入様俵」
此石弐百五拾参石八斗
此運金拾四両壱分 永百四拾三文六分
□船主炊共四人乗
但割目中米百石に付
「渡運賃金五両弐分
船百五拾七文
甲州八代郡角打村
長百姓 上乗 平兵衛
此改
此御征米
本米弐百四拾五石弐斗四升
此運賃金拾四両 永三文七分
内金九両壱分 永八拾五文
三分一渡し
三分二江戸渡し
欠米六石八斗四升
此運賃金五分 永八拾五文七朱
湊皆渡し
右貫目升回し
拾五貫六百目 三斗七升 三貫七升五合
拾五貫四百目 三斗七升三合 三斗七升五合
拾五貫弐百目 三斗七升五合 三斗七升五合
平均 拾五貫四百目 三斗七升三合八勺三才
右者関太郎様御代官甲州村々去卯御年貢儀江戸御回米於駿州清水湊□船頭運賃相改上乗船頭為立会俵数貫目升回し等相改船にて□□□積出立□□申付候御地着岸之上御改受取可被成候 仍運状 如件
安政三辰正月十日
江戸小日向服部坂上
森田関太郎様御手代
浅井四郎助様
駿州清水湊御出役
清水孫次郎手代
中川直三郎
とあり中間検査の厳重さがおもいやられるのである。辰正月十日
一、壱番船 □□請負人
播磨屋三四郎
一、米七百三俵 遠州相良
本乗船頭 庄三郎
内壱俵「三斗七升入
御箱入様俵」
此石弐百五拾参石八斗
此運金拾四両壱分 永百四拾三文六分
□船主炊共四人乗
但割目中米百石に付
「渡運賃金五両弐分
船百五拾七文
甲州八代郡角打村
長百姓 上乗 平兵衛
此改
此御征米
本米弐百四拾五石弐斗四升
此運賃金拾四両 永三文七分
内金九両壱分 永八拾五文
三分一渡し
三分二江戸渡し
欠米六石八斗四升
此運賃金五分 永八拾五文七朱
湊皆渡し
右貫目升回し
拾五貫六百目 三斗七升 三貫七升五合
拾五貫四百目 三斗七升三合 三斗七升五合
拾五貫弐百目 三斗七升五合 三斗七升五合
平均 拾五貫四百目 三斗七升三合八勺三才
右者関太郎様御代官甲州村々去卯御年貢儀江戸御回米於駿州清水湊□船頭運賃相改上乗船頭為立会俵数貫目升回し等相改船にて□□□積出立□□申付候御地着岸之上御改受取可被成候 仍運状 如件
安政三辰正月十日
江戸小日向服部坂上
森田関太郎様御手代
浅井四郎助様
駿州清水湊御出役
清水孫次郎手代
中川直三郎
こうした上乗の者の帰国は陸路上野原を通り、市川代官所まで帰着したのであり、関係の役人から通関手形の発行があり、道中の保証をしたことは、「この者老人江戸より甲州市川陣屋迄差遣申候、其御関所相違なく御通行なさるべく候、後日ノ為仍如件」森田関太郎手代浅井豊助から小仏御関所御当番所中宛に出されている。
一方材木の筏による川下げも行なわれ、穂坂すがえ所蔵の文書に十島口留番所を通行のため通関手形の下付願がある。
乍恐書付を以て願上奉候
諸木尺〆壱万弐千本の内
一、諸木尺〆五千六百本
此筏代三百五拾枚 但壱枚付尺の杉六本分
右者巨摩郡下山村長百姓穂坂喜代平代枠仙蔵申上奉候 今般御用材八代郡上佐野村百姓持山より伐出書面ノ通十島土場にて筏に組み立富士川通駿州蒲原浜迄川下け仕度候間何卒格別のご勘弁を以て御手形仰付けられ出され度願上奉候 以上
巨摩郡下山村
長百姓穂坂喜代平 手代
長百姓見習 穂坂仙蔵
文久元酉年(一八六一)四月十八日
長百姓 市川郎
十島村長百姓 文右衛門
市川御役所
物資の富士川舟運による利用客は年とともに賑(にぎ)やかになって、楮、三椏 、塩等の物資の輸送が行なわれた。諸木尺〆壱万弐千本の内
一、諸木尺〆五千六百本
此筏代三百五拾枚 但壱枚付尺の杉六本分
右者巨摩郡下山村長百姓穂坂喜代平代枠仙蔵申上奉候 今般御用材八代郡上佐野村百姓持山より伐出書面ノ通十島土場にて筏に組み立富士川通駿州蒲原浜迄川下け仕度候間何卒格別のご勘弁を以て御手形仰付けられ出され度願上奉候 以上
巨摩郡下山村
長百姓穂坂喜代平 手代
長百姓見習 穂坂仙蔵
文久元酉年(一八六一)四月十八日
長百姓 市川郎
十島村長百姓 文右衛門
市川御役所
富士川の通船が賑やかになる一方で陸上の交通も江戸幕府の開府以来、政情安定とともに発達してきて宿制の整備、伝馬、助郷の制度が完成するとともに下山宿の宿場としての機能は増して行った。
伝馬については、既に南部宿の伝馬法度が穴山梅雪によって出されていた。
一、伝馬不勤者宿次ニ不可居住之事
一、下山江通候者至申刻者南部ニ可一宿駿河へ通候者ハ酉刻以降南部ニ可令一宿事
一、除公用伝馬ニ塩不可着之事
一、雖為御公用御印判令拝見伝馬可出之事
一、自前々立入候山林無 儀可取草木之事
儀可取草木之事
右条々相守之自今以後伝馬奉公可致之者也
仍 如件
天正五年丁丑十二月二十一日(一八七八)
仍 如件
天正五年丁丑十二月二十一日(一八七八)
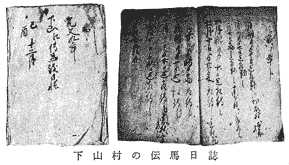 |
塩についても、この時代に駿河からの移入が盛んであり、伝馬に利用せしめないというご法度であるだけに、あるいは法度を犯して伝馬に塩をつけさせての交通が多かったことなどで、通行手形の監視は厳重なものであった模様である。
さて助郷制度については古山日記に
川内領下山宿定助粟倉
大助波木井大野清子小田舟原
門野大城相又小縄高住赤沢
大嶋雨畑拾ヶ村
南部宿 大助郷 大和塩沢成嶋本郷中
野相又中村横根
光子沢九ヶ村
享保二十年(一七三五)南部明細帳に
一、御伝馬宿 従駿州甲州信州への往還
宿継 下山江四里半 身延江三里
万沢江三里 大野江四里
右者毎日馬四疋人足四人宛当番相勤次第順番相勤申候大通之節ハ東川内領大嶋村丸滝村内船村西川内領大和村塩沢村成嶋村本郷村中野村光子沢村横根村相又村大助罷出相勤来申候
一、通船 三艘
御米川下ヶ之儀大野村より万沢村迄十六ヶ村御回米従先規当川岸諸払仕来リ申候右村々前より御米積出し申候得共御運賃金之儀ハ川丈ヶ道法平均卅弐俵積壱艘ニ付永三百四拾五文つつ被下置候
と見え南部宿の伝馬、助郷について若干の記載が見えるのである。大助波木井大野清子小田舟原
門野大城相又小縄高住赤沢
大嶋雨畑拾ヶ村
南部宿 大助郷 大和塩沢成嶋本郷中
野相又中村横根
光子沢九ヶ村
享保二十年(一七三五)南部明細帳に
一、御伝馬宿 従駿州甲州信州への往還
宿継 下山江四里半 身延江三里
万沢江三里 大野江四里
右者毎日馬四疋人足四人宛当番相勤次第順番相勤申候大通之節ハ東川内領大嶋村丸滝村内船村西川内領大和村塩沢村成嶋村本郷村中野村光子沢村横根村相又村大助罷出相勤来申候
一、通船 三艘
御米川下ヶ之儀大野村より万沢村迄十六ヶ村御回米従先規当川岸諸払仕来リ申候右村々前より御米積出し申候得共御運賃金之儀ハ川丈ヶ道法平均卅弐俵積壱艘ニ付永三百四拾五文つつ被下置候
助郷についての苦しみのほかに、鰍沢黒沢番所において、河内領への物資の搬入について抑制をしたための苦しみを受けた河内地区の住民請願書が堀内洋子蔵の文書に
乍恐以書付奉願上候
小林藤之助御代官所甲州巨摩郡八代両郡東西河内領百弐拾参ヶ村惣代手打沢与八外□□人足願上候は鰍沢村黒沢村両御番所有之候□先年は信州諏訪高遠松本其外在々より中馬付出し米穀并ニ諸物河内領迄付通し仕来り候処宝永三戌年より右中馬一切付通し為致不申候ニ付米穀類払底諸物不自由ニて目高値ニ買入東西河内領流水落込風水旱様ニ逢い候儀多分有之其上猪鹿猿発向致諸作喰荒し倍々米穀雑穀共払底ニて難儀至極仕候ニ付無是非鰍沢青柳辺より高値ニ穀物買取小前之物共一同露命無覚束歎ヶ敷奉存候、一体当国中にて数多御番所有之候得共如何の儀と奉存特に先年より産物大小豆栢荏等御年貢御上納金手当甲府表江付出し売代替候節遠路□夜分之内御番所罷通候様成行甚難渋至極仕以来之儀は河内領百姓持馬は勿論信州向より付出来り候中馬両御番所通行相成様被仰付ヒ下置度奉願上候
右願之通御聞済被成下置候て東西河内領大小の百姓相助広大之御仁恵と有難仕合ニ奉存候
小林藤之助御代官所
甲州巨摩郡八代両郡
百廿壱ヶ村惣代
手打沢村与八 内船久左衛門
西嶋太左衛門 切石新太郎
下山喜兵衛 帯金惣兵衛
中野喜重郎 瀬戸才兵衛
熊沢万兵衛 岩間市左衛門
天保九戌(一八三八)年四月
と記されていて、河内筋の生活実態が細々と表現され、御年貢上納金の代替として産物を甲府表で換金してまで納めているのに両御番所での通関の産物に無法な抑制を加えることに対する訴えが見られるのである。小林藤之助御代官所甲州巨摩郡八代両郡東西河内領百弐拾参ヶ村惣代手打沢与八外□□人足願上候は鰍沢村黒沢村両御番所有之候□先年は信州諏訪高遠松本其外在々より中馬付出し米穀并ニ諸物河内領迄付通し仕来り候処宝永三戌年より右中馬一切付通し為致不申候ニ付米穀類払底諸物不自由ニて目高値ニ買入東西河内領流水落込風水旱様ニ逢い候儀多分有之其上猪鹿猿発向致諸作喰荒し倍々米穀雑穀共払底ニて難儀至極仕候ニ付無是非鰍沢青柳辺より高値ニ穀物買取小前之物共一同露命無覚束歎ヶ敷奉存候、一体当国中にて数多御番所有之候得共如何の儀と奉存特に先年より産物大小豆栢荏等御年貢御上納金手当甲府表江付出し売代替候節遠路□夜分之内御番所罷通候様成行甚難渋至極仕以来之儀は河内領百姓持馬は勿論信州向より付出来り候中馬両御番所通行相成様被仰付ヒ下置度奉願上候
右願之通御聞済被成下置候て東西河内領大小の百姓相助広大之御仁恵と有難仕合ニ奉存候
小林藤之助御代官所
甲州巨摩郡八代両郡
百廿壱ヶ村惣代
手打沢村与八 内船久左衛門
西嶋太左衛門 切石新太郎
下山喜兵衛 帯金惣兵衛
中野喜重郎 瀬戸才兵衛
熊沢万兵衛 岩間市左衛門
天保九戌(一八三八)年四月
しかし、こうした経済生活の中で、駿州往還は、いわゆる五街道と異なって脇往還として取残されてしまったのである。つまり伝馬宿助郷について駿州街道は、脇往還のため継立場が遠く、道も嶮岨であったので割当人馬が割当数より多くかかり、しかも年々往来は頻繁となり諸物価は高騰し、ために村々はますます難渋してきたので宝永年間(1704−1710)定められたものに対して、賃銭割増方を寛政11年(1799)、天保14年(1843)、嘉永3年(1853)の3回にわたって嘆願したがきき入れられなかった。そこで嘉永4年(1854)荊沢村、鰍沢村、切石村、八日市場村、下山村、南部村、万沢村の七ヶ宿より市川役所に対し、関係資料をあげて長文の「七ヶ宿賃銭割増額」を出したのである。
更に翌5年6月市川役所より村勤高、定助郷、大助郷の勤高を書き出すよう指令があった。そこで関係村より次のような取調書を差出したのである。
御尋に付以書中奉申上候
寛政度
一、凡金弐拾弐両 下山村
嘉永度
一、凡金九拾六両
(下略)
右は御伝馬御用継立方村々凡弁金の分書付を以奉申上候 以上
(前略後略)
下山村 源兵衛
市川御役所
切石村より下山村迄道法廿三丁
人足 壱人 銭 四拾弐文
本馬 壱疋 銭 八拾四文
軽尻 壱疋 銭 五十六文
下山村より南部村迄道法四里半
人足 壱人 銭 百弐拾九文
本馬 壱疋 銭 弐百五拾八文
軽尻 壱疋 銭 百七拾壱文
後略
右は甲州道中同国粟原宿より信州往還甲州台ヶ原宿迄人馬賃銭右宿々江問合之上拾町当増減差引取調候所書面之通御座候 以上
嘉永四年亥年六月
当所御代官所
(前略)
下山宿 名主兼問屋 喜代平
南部宿 名主兼問屋 清之亟
万沢宿 名主兼問屋 重左衛門
市川御役所
そしてこの定助郷の人足賃はおよそ宝永年間(1704−1710)柳沢時代のものがそのまま踏襲されている始末であった。寛政度
一、凡金弐拾弐両 下山村
嘉永度
一、凡金九拾六両
(下略)
右は御伝馬御用継立方村々凡弁金の分書付を以奉申上候 以上
(前略後略)
下山村 源兵衛
市川御役所
切石村より下山村迄道法廿三丁
人足 壱人 銭 四拾弐文
本馬 壱疋 銭 八拾四文
軽尻 壱疋 銭 五十六文
下山村より南部村迄道法四里半
人足 壱人 銭 百弐拾九文
本馬 壱疋 銭 弐百五拾八文
軽尻 壱疋 銭 百七拾壱文
後略
右は甲州道中同国粟原宿より信州往還甲州台ヶ原宿迄人馬賃銭右宿々江問合之上拾町当増減差引取調候所書面之通御座候 以上
嘉永四年亥年六月
当所御代官所
(前略)
下山宿 名主兼問屋 喜代平
南部宿 名主兼問屋 清之亟
万沢宿 名主兼問屋 重左衛門
市川御役所
道法は韮崎−蒲原間十九里余、その間に六ヵ所の宿をもっていた。また甲府−蒲原間、二十余里余、その間五ヵ所の宿を継立所として、それぞれもっている。
しかも非常に難所が多かったから諸荷物はことごとく分け荷であり、普通の人足1人の場合は3人宛、馬1疋の時は2疋から3疋を出して継立てねばならなかった。
このような結果、宿村方では、この諸懸りを弁金してようよう間に合わせている始末であったから、寛政11年(1799)に割増賃銭を願い出たが結局五街道以外は割増不可能という下知であった。それから天保14年(1843)にまたまた願い出たが、この時も公用のみ定賃銭でやるようにという沙汰のみで終ってしまった。
そこで嘉永4年(1851)再び願い出たのが上の文書である。
この文書の中で、「一体甲州道中並甲府より信州迄之往還等者同国中に而も三十六町壱里にて継場も近く候上先年より御割増も仰付られ有之候所私共村々之儀はいづれも五十町一里之場所にて殊に継場遠く候故一度の継立に一日宛相掛り……」と繰返しているのは駿信往還の性格を非常に強く物語っているように見えるのである。
こうして、甲州街道筋の宿場へも、割増賃銭等について詳細を問い合せてその資料をそえて提出したのであった。
しかし、このようにしても、支配者側からの埒(らち)はあかず、翌年6月関係村からさらに村勤高、定助郷、大助郷の村の勤高も書き出すよう指令があった。
「其村方往還人馬継立村勤高并定助郷大助郷村々勤高とも可書出候
一、大通行之節人馬数何程迄者宿方并西助郷にて相勤其余何程迄者東大助郷江触当候と申義委細取調可書出候
右弐ヶ条帳面ニ相認来ル十七日迄心得候村役人持参可差出候
一、大野山御法会等之節紀伊殿御通行又者同家中多人数通行之砌人馬継立方旧例取調出来次第可書出候
右之通取調可差出此書付追而相返もの也
嘉永五子年六月十二日 市川御役所
これによって波木井村名主が各部落の勤高を報告している。嘉永五子年六月十二日 市川御役所
乍恐以書中奉願上候
一、高百九拾四石九斗九升 波木井村
一、高六拾三石弐斗九升三合 小田船原村
一、高拾弐石九斗六升弐合 門野村
一、高弐拾壱石七合 大城村
一、高九十石二斗五升七合 清子村
右は今般下山大助郷勤高御糺に御座候により前書の高御割合人足触当次第無差支差出来り申候依之此段御書付奉申上候 以上
嘉永五巳年七月
巨摩郡 波木井村
小田舟原村
門野村
大城村
清子村
右村総代
波木井村 名主 大兵衛
市川御役所
大助郷村方左ニ相記申上候
一、高弐拾壱石 横根村
一、高三拾六石 中村
一、高四拾八石 光子沢村
一、高百七拾三石 相又村
一、高三百五拾壱石 大嶋村
一、高六拾九石 丸滝村
一、高四百七拾弐石 内舟村
〆高千百七拾石余
こうして書出して報告はしたが市川役所から更に記録の証拠となるものを出すように指示があったものか一、高百九拾四石九斗九升 波木井村
一、高六拾三石弐斗九升三合 小田船原村
一、高拾弐石九斗六升弐合 門野村
一、高弐拾壱石七合 大城村
一、高九十石二斗五升七合 清子村
右は今般下山大助郷勤高御糺に御座候により前書の高御割合人足触当次第無差支差出来り申候依之此段御書付奉申上候 以上
嘉永五巳年七月
巨摩郡 波木井村
小田舟原村
門野村
大城村
清子村
右村総代
波木井村 名主 大兵衛
市川御役所
大助郷村方左ニ相記申上候
一、高弐拾壱石 横根村
一、高三拾六石 中村
一、高四拾八石 光子沢村
一、高百七拾三石 相又村
一、高三百五拾壱石 大嶋村
一、高六拾九石 丸滝村
一、高四百七拾弐石 内舟村
〆高千百七拾石余
乍恐以書中奉申上候
巨摩郡下山村大助郷勤高之儀従前石高を以て勤来候段先般書付奉差上候処右ニ付証拠に相成るべき書物等有之候はば取調差出べき旨被仰付承知奉畏候然る処証拠に可相成書物等見掛り不申候尤猶又得と取調証拠に相成書物有之候はば其の段奉申上候 以上
嘉永五子年七月廿四日
巨摩郡 清子村 門野村
小田舟原村 波木井村
大城村
右五ヶ村惣代
波木井村 名主 大兵衛
市川御役所
更にまた七月廿九日になって巨摩郡下山村大助郷勤高之儀従前石高を以て勤来候段先般書付奉差上候処右ニ付証拠に相成るべき書物等有之候はば取調差出べき旨被仰付承知奉畏候然る処証拠に可相成書物等見掛り不申候尤猶又得と取調証拠に相成書物有之候はば其の段奉申上候 以上
嘉永五子年七月廿四日
巨摩郡 清子村 門野村
小田舟原村 波木井村
大城村
右五ヶ村惣代
波木井村 名主 大兵衛
市川御役所
乍恐以書付奉願上候
一、巨摩郡下山村大助郷ニ勤高之儀従前石高を以て勤来り候段先般書付差上候右に付石高助郷相勤候書物等有之候はば取調可差上旨被仰聞承知奉畏候去ル寛政年中平岡彦兵衛様御支配之節大助郷勤高御取調之節之石高を以勤来り候趣以書付奉申上候猶又天保七申年御巡見様御通行之砌も前同様右高を以相勤来り候旨御巡見様御并御支配御役所様へも書付奉差上候儀相違無御座候其後東川内領拾八ヶ村と下山村大助郷一件に付弘化四未年中私共村方引合相成其節も石高を以て相勤来り候段御奉行様へ書付奉差上候処御聞済ニ相成候儀ニ御座候 依之此段奉申上候
以上
巨摩郡 波木井村 門野村
小田船原村 小縄村 赤沢 高住
清子村 大嶋村
大城村 雨畑村
右八ヶ村惣代
大嶋村 名主 八左衛門
市川御役所
乍恐以書付奉願上候
右は下山村大助郷人足差出方之儀前より石高江相掛り下山村にて宿問屋場より触当次第割合の通り無相違差出申候村方人足継方は前々仕来り家並順番ニ相勤右人足に不限外御用材用人足打込小帳相記継順ニ致付入用夫銭帳之は書類し不申候極めて山中辺びの土地にて年々稲作実法方不就成ニ付御納米ニ相立不申往古より御年貢方定金納ニ御座候
右次第ニ付奉書上候
巨摩郡 門野村
大城村
御奉行所
こうして書き出して提出した書類が証拠書の不充分ということから何度も照会を受けていることは脇往還として人足、賃銭の上で不利な立場の解決策とはならなかった。一、巨摩郡下山村大助郷ニ勤高之儀従前石高を以て勤来り候段先般書付差上候右に付石高助郷相勤候書物等有之候はば取調可差上旨被仰聞承知奉畏候去ル寛政年中平岡彦兵衛様御支配之節大助郷勤高御取調之節之石高を以勤来り候趣以書付奉申上候猶又天保七申年御巡見様御通行之砌も前同様右高を以相勤来り候旨御巡見様御并御支配御役所様へも書付奉差上候儀相違無御座候其後東川内領拾八ヶ村と下山村大助郷一件に付弘化四未年中私共村方引合相成其節も石高を以て相勤来り候段御奉行様へ書付奉差上候処御聞済ニ相成候儀ニ御座候 依之此段奉申上候
以上
巨摩郡 波木井村 門野村
小田船原村 小縄村 赤沢 高住
清子村 大嶋村
大城村 雨畑村
右八ヶ村惣代
大嶋村 名主 八左衛門
市川御役所
乍恐以書付奉願上候
右は下山村大助郷人足差出方之儀前より石高江相掛り下山村にて宿問屋場より触当次第割合の通り無相違差出申候村方人足継方は前々仕来り家並順番ニ相勤右人足に不限外御用材用人足打込小帳相記継順ニ致付入用夫銭帳之は書類し不申候極めて山中辺びの土地にて年々稲作実法方不就成ニ付御納米ニ相立不申往古より御年貢方定金納ニ御座候
右次第ニ付奉書上候
巨摩郡 門野村
大城村
御奉行所
後者に提出の文書は日付がないが関係の筋のものと考えられ実際に助郷の割当の姿まで記し報告し真実の証拠としたものであろうか。しかし当時の人足差出しの状況が判明する書類と考えられよう。助郷の地域的広さは、文久元辛酉(1861)年和宮様江戸入りの際信州沓掛に触当てされた文書があり、定助郷の触当でさえ下山村と東河内額の争がある程であるのに、信州から駿河へと広大な範囲に割当てられた助郷の歴史が、いかに土地の交通運輸に必要視されたか、また如何に村々が難渋して来たかがわかる。

