三、富士川舟運と下山宿
こうした脇往還としての不利をかこち、一方身延山への激増する交通量をさばきながら宿場としての活動をしなければならなかった下山宿は、甲駿を結ぶ河内領第一の殷邑(いんゆう)として、室町時代には下山氏、ついで武田の親族である穴山氏の城下町として長く栄え、中近世にかけて、下山千軒とまで称された所である。ことに身延山への参拝客は、南方から入る者は南部宿へ、北方から入る者は下山宿へ舟運により上陸して身延山への参拝をしたのである。
一方、下山宿は宿場としての機能のもとに、甲府勤番衆のお泊まり、身延山参拝者のための御役人衆のお泊まり、その御役人衆の扱い等に忙殺されたのである。
安永6年(1777)2月古帳改、甲府御目附様記に、
享保九辰年(一七二四)甲斐守様御所望六月御引渡し冬中御番所并御勤番様不残御引越依之甲府御目付様巳年より御出被致候
として、
享保十年 細井因幡守 廿卯年 神尾市左衛門
十一年 松井民部 元文元辰年 松平伊左衛門
十二年 片桐帯刀 二巳年 津田外記
十三年 松前隼人 三午年 稲生七郎右衛門
十四酉年 天高主馬 四未年 稲生左門
十五戌年 松野孫左衛門 五申年 牧野八太夫
十六亥年 阿部伊織 寛保元酉年 菅沼前三郎
十七子年 米倉六郎右衛門 二戌年 柘植三四郎
十八丑年 岡部主水 三亥年 細井左次右衛門
十九寅年 黒田采女 延享元子年 三淵縫之助
二丑年 奥津帯刀
三寅年 □末甚十郎 (以下略)
と毎年御目付の駐在が行なわれている。十一年 松井民部 元文元辰年 松平伊左衛門
十二年 片桐帯刀 二巳年 津田外記
十三年 松前隼人 三午年 稲生七郎右衛門
十四酉年 天高主馬 四未年 稲生左門
十五戌年 松野孫左衛門 五申年 牧野八太夫
十六亥年 阿部伊織 寛保元酉年 菅沼前三郎
十七子年 米倉六郎右衛門 二戌年 柘植三四郎
十八丑年 岡部主水 三亥年 細井左次右衛門
十九寅年 黒田采女 延享元子年 三淵縫之助
二丑年 奥津帯刀
三寅年 □末甚十郎 (以下略)
ことに寛政四子年に「奥津内記様、九月十一日当宿御泊りに成られ(中略)大助郷一統にて南部宿まで御継立、同四年、大久保八郎右衛門、身延山御泊り七面山巡見、大野山門前宅小休のみに御座候」とあり
「文化七年九月十一日 戸川大次郎様
御同勢四拾五人
秋田源左衛門殿
木村庄太夫 殿
例年御乗船にて鰍沢より当宿御泊り、夫より身延山大野山御巡見にて御乗船に遊ばされ候得共御船差つかいにて陸路御通行遊され大野より渡船にて和田村へ御越に相成候大嶋にて中野村へ御越遊され夫より南部村御弁当ニ御座候間当宿之義は大キに相助リ申候」とあり、以下弘化二年九月十二日
「彦坂三太夫様
御用人武田米蔵
御同勢二十六人」
との記録が残っている。御目付役は常に、御用人2人ないし3人と、同勢多い時は51人を引連れて下山宿に駐在したのである。従って前記の、文化7年の記事中、「当宿の儀は大きに相助り申候」という表現は、真に安堵の表情がでている記録である。こうした際には、同時に村方人足の割当が行なわれ、その処理に難渋(じゅう)したであろう文書がある。御同勢四拾五人
秋田源左衛門殿
木村庄太夫 殿
例年御乗船にて鰍沢より当宿御泊り、夫より身延山大野山御巡見にて御乗船に遊ばされ候得共御船差つかいにて陸路御通行遊され大野より渡船にて和田村へ御越に相成候大嶋にて中野村へ御越遊され夫より南部村御弁当ニ御座候間当宿之義は大キに相助リ申候」とあり、以下弘化二年九月十二日
「彦坂三太夫様
御用人武田米蔵
御同勢二十六人」
宿場の特殊的立場にありながら、一面下山大工の数多い出稼ぎによる人手不足は、定助郷の課役にも支障があって、人足を揃えることすらも困難だった。「富士川水運史」によると回米惣代を主な仕事として河内領の下山村八右衛門こと佐野喜兵衛が任命された最初の郡中惣代である。又「御米拵方以下川岸出等の儀も等閑無之様」として組合村々を巡回して米扱俵装を指導督励し、また代官よりの通達事項を末端へ徹底する責任を持っていたとあり、助郷割当人足の差出しに如何に苦労したかの実状をつぶさに訴えて、天保4年(1833)から安政2年(1855)の22年間に亘る下山宿と、東河内領の根子、瀬戸、北川、市之瀬、杉山、岩見、大炊平、清沢、常葉、湯ノ奥、下部、上の平、波高嶋(以上下部町)、上八木沢、下八木沢、帯金、角打、和田、樋の上の、拾九ヶ村との紛争する市川家の文書によると宿場としての下山の苦労のあり方、止むに止まれぬ人足触当の行為が判明するのである。
乍恐以書内済御吟味下奉願上候
当代官所甲州巨摩郡下山村名主喜代平外弐人より相手同国八代郡根子村外拾八ヶ村へ相掛難渋出入
の事件こそ宿場としての宿命と、近在の村々の迷惑、紛争の原因の歴史である。当代官所甲州巨摩郡下山村名主喜代平外弐人より相手同国八代郡根子村外拾八ヶ村へ相掛難渋出入
前略、駿府御目付様年々西河内領江御通行被為在(あらせられ)御荷物継立方之儀下山村並定助郷粟倉初鹿嶋同郡大助郷波木井門野大城大野小田舟原清子小縄高住赤沢雨畑大嶋都合拾壱ヶ村並訴証方共々拾弐ヶ村高千七百五拾石余家数凡千百五拾軒余有之右村々ニ而従前之御荷物継立来然ル処天保四巳年(一八三三)九月より私共組合
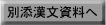
として、天保10年(1839)年訴え出で14年(1843)4月に示談内済の模様は 下山村並定助郷人足六十五人内馬掛人足二十八人残三十七人其余之分は御触に応じ壱人三人を遣し之積を以東西大助郷村々江触当陸路御通行之節は君支差無之様右人足差出且又東西大助郷村々により隔年人足拾五人づつ下山村江相詰可申候。尤東河内領の儀は正人足差出候積を以拾五人丈賃銀□□之分共□度相□勿論風雨等にて差掛御荷物船積難相成節は波高嶋村上八木沢帯金村触当正人足無差支様差出し若し川支之等にて船越不相成節は雇揚人足を以触当根子村外拾八ヶ村高割を以賃銀相払可申候云々」
という条件で御奉行所へ御伺中であったが、駿府より、五街道取締役人の通行に伴い、触当人足の割合に不相当の趣があるという風聞があったので 和田村長百姓重郎左衛門上八木沢村同利兵衛
波高嶋村同丈右衛門市之瀬村名主重郎右衛門右四人下山村罷越御先触並人足割合帳面見届候処如案訴訟方にて可相勤馬掛人足其外不相当之人足為差出置候ニ付篤と及掛合候処問屋喜代平並村役人一同申候は割違いいたし候間相違之分追而割戻し以来は御伺御下知之通取計不正之人足触当致す間敷候間此度之儀は了簡致し呉る様
と下山方からの挨拶により、訴訟して、命令をいただいている示談の際の内容のような人足触当のつもりで居たところ、天保14年(1843)9月中、波高嶋村同丈右衛門市之瀬村名主重郎右衛門右四人下山村罷越御先触並人足割合帳面見届候処如案訴訟方にて可相勤馬掛人足其外不相当之人足為差出置候ニ付篤と及掛合候処問屋喜代平並村役人一同申候は割違いいたし候間相違之分追而割戻し以来は御伺御下知之通取計不正之人足触当致す間敷候間此度之儀は了簡致し呉る様
御目附様御通行□□□触人足五十二人御上様御真筆御用物人足弐人夜に入候節は 灯持人足六人且又駿府御代官様池田□之亟様御荷物継立人足拾弐人都合人足七弐人江弐人掛或は三人掛積立右之内にて訴訟方並定助郷人足三十七人相勤候ては三ト一拾弐人三ト三リ相成、天保度済□証文之趣ニては相手方御先触人足之内三十七人は勿論拾五人都合正人足五拾弐人訴訟方にて相勤残御触人足壱人三人掛之積を以東西大助郷村々之触当御荷物継立差支無様取計可致之処右様御触人足江一図に弐人掛或は三人掛積立内三拾七人相勤候ては全く訴訟方勤メ人足不足いたし□□□□□□□拾五人分不遣立石は訴訟方並定助郷人足三拾七人其余之分と差別有之依ては添人足之儀訴訟□人足は勝手次第為差添大助郷は大助郷より壱人弐人添之の処私欲になじみ不相当之人足相手方村村江百弐拾九人触当候につき村役人壱人つゝ下山村江罷越問屋喜代平外役人共江及掛合候処素より謀意相巧ミ候もの□□何□□□□□□御出役様江右の段申上御聞済相成候得共
灯持人足六人且又駿府御代官様池田□之亟様御荷物継立人足拾弐人都合人足七弐人江弐人掛或は三人掛積立右之内にて訴訟方並定助郷人足三十七人相勤候ては三ト一拾弐人三ト三リ相成、天保度済□証文之趣ニては相手方御先触人足之内三十七人は勿論拾五人都合正人足五拾弐人訴訟方にて相勤残御触人足壱人三人掛之積を以東西大助郷村々之触当御荷物継立差支無様取計可致之処右様御触人足江一図に弐人掛或は三人掛積立内三拾七人相勤候ては全く訴訟方勤メ人足不足いたし□□□□□□□拾五人分不遣立石は訴訟方並定助郷人足三拾七人其余之分と差別有之依ては添人足之儀訴訟□人足は勝手次第為差添大助郷は大助郷より壱人弐人添之の処私欲になじみ不相当之人足相手方村村江百弐拾九人触当候につき村役人壱人つゝ下山村江罷越問屋喜代平外役人共江及掛合候処素より謀意相巧ミ候もの□□何□□□□□□御出役様江右の段申上御聞済相成候得共
と下山方へ割当てられた人足の残余の分を東西大助郷へ割り振るべきものを、御触当人足そのままへ弐人掛、三人掛した人足を割当てることの不当性を追求し、出役人にも申上げたが、下山町の役人どもの聞き入れることにはならなかった。なお訴え出ても下山方はその書類提出を故意に引き延ばし、仲に立つ人を介しても、当方の触当方法は、既に訴訟上「御載件同様と相心得」として、「我意不当之儀申張る」状態であった。この間、毎月のように御奉行所へ訴え出たが「兎角邪□不当之心底にて」押し切られてしまったので「辰巳二ヶ年(天保十五、十六年)他村役人江買揚人足世話方被仰付候分訴訟方並定助郷人足不足之分共勿論西川内領大助郷村々より差出べき分有之全ク相手方村々より可差出人足には嘗て無之」とまで当方に責任のない事を開陳しているが、下山方は、継場山坂難所がありといろいろの理由を申し立てている。一方相手村々より見れば以前から諸候の通行している道であり、手入れが行き届いて難所はない筈であり、道作り出仕による役引き高も頂いているのであるから、「下山村ニ限り勝手触不致様」仰せられたいと訴えている。然しあまり即決の行なわれない実情は「兎角年月を経、相手方村々難渋に陥り候様相工(タクラ)ミ誠に歎げかわしき次第」であり、相手方村々の模様は、「洞間に挟まれ猪鹿多分発向いたし諸作物喰荒し候に付男女の隔も無之農時は田畑に相詰猿鹿相防候程之土地柄ニ付仲々御年貢米之分定金納被仰付候」村々であり「平生木材炭焼又は薪等を伐出し米雑穀都て買入れ誠に難儀至極」の状況であるのに天保十亥年(1839)より「引続数年及出入諸入用相嵩み難儀仕り」という実情であるので「前条之通示談内済仕候儀」「相手方村々小前末々之者共迄安心罷在処間もなく御下知証文相破り勝手儘之儀申立重年難渋相掛け」という始末である。「畢竟、下山村之儀は身延山麓にて旅人止宿は勿論右山会式之節は莫大之金銀落込茶屋小屋等に至る迄潤益筋の村方にて諸入用等不厭困窮之相手方村々押掠、剰へ御上様を不恐大胆不当之心底」である。経済的に恵まれた地域と困窮の地との争は限界に来ているので、「天保十四年に御伺い済口証文の通り下山村並定助郷人足六拾五人之内馬掛り人足弐拾八人引残る三拾七人有之候ニ付御触当三拾七人迄は下山村並定助郷弐ヶ村にて相勤其余御触有之節は東西大助郷村々江触当候之共聊無差支罷出御用大切に」相勤めるにやぶさかでないとして拾壱ヶ年の下山村対下部町一円と大河内村一円との紛争は、複雑な迂余曲節を経て解決を見たのであるが、本陣を構えた下山村の幕政下の人足充足と運行の確保をしなければならない責任と、一方下山大工の出稼による村の人的資源不足との不均衡をどうして合理化するのか苦衷の深いものがにじみ出た結果であった。四、身延詣から見た甲駿街道
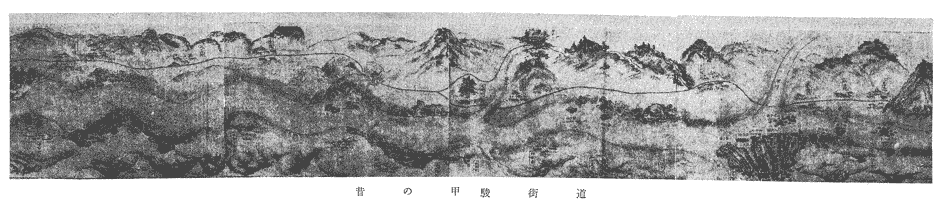 |
更に永禄2年11月、身延山十五世日叙上人に宛てて、当国中の身延末寺の計らいにつき書を送り、更に日叙上人の悪名を流布する輩の如きは、寺中追放すべしとまでいって、身延山を保護している。身延参詣の庶民の通行を容易にするために、秀吉も「当時会式参詣の輩、国中役等令免除之事」として御会式参拝者の便をはかり、家康は「会式関免許之事付当国中身延山諸末寺中寺役免除之事」天正十七年正月とあり、番所通所の保証を与えてその添状と思われるものの中に、御会式に番所を通過するに際して、「一、今月十日より十三日まで身延参詣之男女路物木綿布は五端六端米は五升六升糸は十つれ十五つれを限り役儀改有間敷者也」と、当時こうした現物を持って路銀の代りとしたり、また身延山へ奉納する貢物を認めたりする考えから、一定量のものは関銭徴集なしで通行できたものであろう。この布令は鰍沢と万沢の番所宛に出されたのであった。こうした会式参詣の保護規定も、16世紀末から18世紀初めごろまでの身延参詣者に対しては、会式の際であっても通関規定が厳重だったようで、甲州万沢村口留番所取計方伺書によっても、「一、国中より他国におもむく女有之は、是又其所支配の代官証文にて可通事」とあり、
(前略)万沢十嶋の儀は、其国許旦那寺の手形を以出候仕来に御座候、右は毎年十月久遠寺法会中、関御免の札相建候段々泥み候か、又は、一体入女の儀は御定書に無之候て右の通取計来候哉左候ては久遠寺役僧の手形を以出候儀も、不相当に奉存候(中略)平生は甲府勤番支配甲州御代官証文にて相通り候積り御定書認め直し張置なし申すべく候哉」
との伺書が寛政五丑年(1793)2月に御勘定所へ出されている。ところが、同年12月に、身延山久遠寺から市川御役所へ「身延山参詣の女万沢御関所通候儀に付問合一件−身延山久遠寺口上書−先月廿二日御切紙を以御尋の趣承知仕候、則御答左の通り身延山参詣の女、御代官所御証文にて通行致候様に相成候ては、住吉よりの振合と手重に相成、おのつから参詣甚薄く大寺の身延山石高寺領等は頂戴不仕、只諸国参詣の志のみ伽藍修復万事相続仕居候得共近年は相続も届兼候の仕合罷成候、其上に参詣女人通行手重に相成逐年身延山難立行躰と可相成段顕然にて甚迷惑仕候段、御賢察なされ下され度奉願候
と身延山としての事情を訴えて
「女人通行の儀は権現様より御免の御朱印頂戴仕り罷在候、従つて御代々様御朱印の表、右の趣被成下有難存し奉候、即権現様御朱印写別紙差上候」
との請願に対し「甲州万沢口留番所女通行の儀身延山参詣の女に限り候ては仕来の通差置、右参詣の外紛れざる様いたし、日蓮遠忌の節の参詣人は、是又仕来りの通久遠寺より寺社奉行江相願候積りに候間其意を得らるべく候」
寛政6年12月29日の文書により、一般婦人の参詣が普段の場合も檀那寺発行の手形で通行が認められるようになった。身延山への参詣は、前節の中でも記したように武家、公家の参拝が繁くあったことだし殊に大野山が徳川家の菩提寺となった関係から武家の身延山への参詣は毎年のように行なわれた。「慶安元子年紀伊大納言頼宣郷身延山大野へ御参詣同二丑年御参詣被遊候」とあって「御符水道中」といわれて、本遠寺庭内に井戸がありこの水を「御符水」といい紀州家江戸屋敷では例年御水汲みの者を遣わして、この水を屋敷の屋上に散水することがあり、この御水取りを「御符水道中」と呼び、運搬の水は肩から肩に運び決して地上に置かなかったといい、或は御符水は七面山の御池の水を汲み本遠寺内七面堂で37、21日の間祈祷したもので、徳川一門簾中の安産と産児育成の祈念の行事でもあったという。天保6年(1835)から7年にかけて、紀州家の分家である西条少将の身延山参拝についての道中見分と、通行日程の記事を記した文書には、天保6年(1835)7月に紀州家から2人を差し向けて沿道の道路状況、宿泊施設、御休止処の状況など詳細に調べ家屋の間取り、広さなども調査している。その後9月、11月、12月と見分が行なわれ、12月の見分の際には「往来の道幅凡弐間余に道造りいたし、山坂有之ところ右に准じ可成道幅広く仕り、川瀬有之場所は橋等人馬無差支罷通ル様丈夫には仕立、往還中に出張大石竹木等取除き、木枝伐払い御道筋差障り無之様可仕旨(以下略)」の請書を出させているのである。
なお別に、「継立人足の触当と、御小休被仰付、焚出し等御請仕りとあり、御通行ご同勢の儀は被仰渡候は八百人と有之、人足共は千人以上の御通行に御座候」と記しているところを見ると、当時の街道通行のものものしさがうかがえるのである。
この参詣の日程は、枚方(大阪府)11日伏見12日とあり、奥津24日、万沢25日、身延26日着で大阪から15日の行程で身延山に到着している。
さて、これに劣らないと思われる程の参詣が武田信玄において行なわれている。
身延鑑、身延と信玄の項に元亀3年(1572)9月10日、有名な川中島の戦いが行なわれた。そして謙信自らの斬込みに、信玄は危機一髪のところで命拾いしたことは有名である。信玄はこれこそ身延山のご祈祷の賜物であると感激言うところを知らなかった。
そしてその年の4月、勝頼が戦わずして謙信の軍を退けた時、感状を使者に持たせ礼物を添えてねんごろに奉謝した。今その感状が身延に蔵されている。特有の漢文体なので、書きおろすと下のようである。
翁(信玄自身)こもごも感ずる所ありて、書を身延山貫主(日叙上人)閣下に呈す。
今年元亀三壬申(一五七二)四月、北越輝虎の一万余騎、信州川中嶋に出陣の砌、勝頼、一千騎を率いて発向せしむる処、干戈を動かさずして敵軍速やかに退去す。是れ神仏の加護によらずんば、いかでか能く勝つことを得んや。
此の月乃ち佩ぶる所の紺地金泥の 経は先貫主(第十四代日鏡上人)の自ら書きて贈れるものなり。加えて、一山の僧侶、法華一万部を読誦する此の巧徳に因って、高祖日蓮大法将、七面大明神威神の力を合せて怨敵退散せしむるや必せり。然れば即ち久遠寺は当家擁護の霊場、万世遷移せざるの仏跡なり。
経は先貫主(第十四代日鏡上人)の自ら書きて贈れるものなり。加えて、一山の僧侶、法華一万部を読誦する此の巧徳に因って、高祖日蓮大法将、七面大明神威神の力を合せて怨敵退散せしむるや必せり。然れば即ち久遠寺は当家擁護の霊場、万世遷移せざるの仏跡なり。
伏して望むらくは一山の僧従日夜信心を凝らし肝胆を摧いて当家武運長久の旨宜しく祈誓あるべし書不尽 謹言
大僧正法性院 信玄判
とあり、わが子勝頼のために加護をこうむった感激に、礼を厚くしての身延山参詣であり、ことに、当家の霊場とまで頼り切っている心情からして、その参詣の道中も簡単なものでなかったであろうことが想像される。今年元亀三壬申(一五七二)四月、北越輝虎の一万余騎、信州川中嶋に出陣の砌、勝頼、一千騎を率いて発向せしむる処、干戈を動かさずして敵軍速やかに退去す。是れ神仏の加護によらずんば、いかでか能く勝つことを得んや。
此の月乃ち佩ぶる所の紺地金泥の
伏して望むらくは一山の僧従日夜信心を凝らし肝胆を摧いて当家武運長久の旨宜しく祈誓あるべし書不尽 謹言
大僧正法性院 信玄判
同じ身延鑑に(前略)
「裏の門を出れば金剛谷、東谷の内なり、これには武井坊甲斐の武田信玄の建立とかや(中略)紅葉峠とて甲府への道なり、町もありかきざわ村(今の清住町か)民家百軒におよべり」の記事があり、中世の頃の身延道の姿の一端がうかがわれ、かきざわ村民家百軒という表現は、今の清往町ばかりでなく、杉山辺の民家までを含めているものと思われる。
万治2年(1659)京都からは、深草の元政上人は、母の80歳になる妙種と共に身延山参拝を終えて江戸へ向かっている。身延道の記に
二十四日雨やまず川も水もまさらんといへば猶ほとどまる。二十五日万沢を出でて坂あり(中略)南部という村にてやすみて午のさがり(一時ごろ)そこをいづ村をはなるればはや身延の高根も見ゆ、いま三里なんあるという。申のさかり(四時ごろ)身延につく、その山のさま、たとえば比叡の山を東坂本より登る心地すべし(中略)清水房というにつきてまづたき火させて(後略)二十七日奥の院へまいる
この頃の道中は、番所通過の面倒なものはなかったにしても、道の状況も整備途上であり、80歳の母との道中は決して楽なものではなかったであろう。南部宿を出て、見延山の見えるところまで来て「いま三里なんある」という文の中には、さすがにほっとしたものと同時に、未だ3里あるのかとの詠嘆の意が見られるのである。甲駿道中記、文政13年(1830)3月の項に、
二十六日花輪出立天気晴て暖和なり、浅原東南湖大椚青柳等村々過て鰍沢の駅に至る昼餉す繁昌の地なり、関所有、小柳川飛川など云急流あり不二川へ落る水なりと、楠甫手打沢切石八日市場飯富下山なと言村過て日は山の端に入かかる、是より身延山領に入る。兼々聞しに身延山は繁昌の地と聞くままよきやどりを求めんといそぎて、山坂道を登り、下りて行とも行とも身延に出でず、日は暮て闇さはくらし大樹の生繁りたる深山路にて此処の岩の根かしこの木の根につまづきて行なやみ、やうやうと初夜(午後八時)の鐘つくころ身延の町に出てやどりを求めんとすれども旅泊なしいかんせんと気力もたゆみ、岩が根腰打かけてやすらい居る処へ一人の老翁来りつけるまま宿や尋ねければ、常陸衆の(茨城県)の坊は是より七八町山を廻り行て有と言うまま外に泊屋は有ましきやと聞ければ、参詣の人にてなくば商人の宿ありとて案内し呉けるまま地獄とやらに仏に逢し心地にて、いとうれしく一丁計て伊セ屋其の家に宿る。元より宿やにてはなく商人泊る計りと見えて表の方にて小間物荒物あきなう様子なり、奥深き処にやすむ、風呂なとなし。ようよう隣に立ちし湯などわひてもらい、そこそこに入って食事す魚類なし、菜に油あげ玉味噌の汁にも入らず、こごとたらたら打臥ぬ。
同廿七日天気好、つとめて起き出んと思えども昨夜の山路に足をいためようよう辰の半(今の九時)に宿を出立す、是迄来りし事なれば身延山を一覧せんと足を曳き曳き石段三百余も登りて(以下略)山を下りて一里余、大野村に出、此処より富士川下り船に乗る、乗合人も多きまま、しばらく待合せて艫綱をときて船出す。名にしおう富士川の急流矢の如し、水源は信州八ヶ嶽より出て、甲斐の国中の水此川へ流れ出る由、舟の長さ四間余にて板薄く幅四五尺なり、板は杉にあらず、松にもあらぬねばき木なり、この節天気続きければ水もかれ、折々、岩根に舟そこ板あたりてむねにひびきて気味悪し、下り行に右左ともに岩石峨々として滝などの落る処もあり、桃桜其外異樹多し、長松色を増し言語に絶す実に仙境の如し、清子光子沢中野村の河岸をすぎて、南部の河岸に船を付て休む(以下略)
同廿七日天気好、つとめて起き出んと思えども昨夜の山路に足をいためようよう辰の半(今の九時)に宿を出立す、是迄来りし事なれば身延山を一覧せんと足を曳き曳き石段三百余も登りて(以下略)山を下りて一里余、大野村に出、此処より富士川下り船に乗る、乗合人も多きまま、しばらく待合せて艫綱をときて船出す。名にしおう富士川の急流矢の如し、水源は信州八ヶ嶽より出て、甲斐の国中の水此川へ流れ出る由、舟の長さ四間余にて板薄く幅四五尺なり、板は杉にあらず、松にもあらぬねばき木なり、この節天気続きければ水もかれ、折々、岩根に舟そこ板あたりてむねにひびきて気味悪し、下り行に右左ともに岩石峨々として滝などの落る処もあり、桃桜其外異樹多し、長松色を増し言語に絶す実に仙境の如し、清子光子沢中野村の河岸をすぎて、南部の河岸に船を付て休む(以下略)
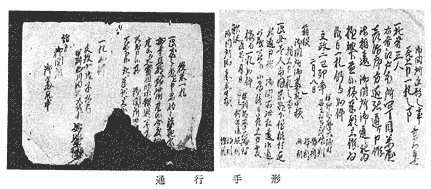 |
然しながら、公儀の巡見となる又と、自ら異なった姿が見え、天保9年(1838)の従甲府駿府迄道中巡見
九月十四日
一、今暁、六ッ時半、下山宿御本陣芦沢九左衛門方出立夫より山道通り罷越候処町外久遠寺僧侶出迎居致案内裏門にて下乗」して身延山へ初穂金五十疋を納め「夫より惣門外身延町通り町外之往還より大野へ寄道凡壱里程行」大野山へ参拝「右門前にて下乗役僧案内にて」と記され、固苦しい道中の姿も見えるのである。
然し、御会式の賑わいは、御会式に限って口留番所通行に女の出入が自由に認められる関係で、その賑わいもなかなかのものであったと思われるのは甲斐の手振に「鰍沢宿一州の廻米悉く此湊にかかり(中略)されば当国第一の都会、就中、十月身延山会式の節は、酒色店等土地ばかりにては足らず、甲府又は市川辺より男女料理人、酒肴等まで仕入れ、事夥しく数十町の間、往来陸続すと」あり、ここから舟により下山宿にて下船、近い時代になって、波木井河岸に上陸参拝をすませた行程もあった。このことは、松亭身延記行に「ここに早川の落口といへるあり(中略)かくて程なく、身延の山下に着く、ここより人々河原に上り、往くこと数丁ならずして大門に至る、開会関という額を架たり」によって、波木井の河原に着いたことがわかる。
並山日記、安政3年(1856)9月の項に「廿二日、下山という、うまやを過ぎて身延の山の坂路にかかるに、さのみはげしき道にしもあらねど、遥に遠くいたく困じたりうら門より入りて境内の山をおりつつ朝師道というにいづ(中略)此の堂前より町中に出でて熊王それがしの家に宿りぬ。廿三日かくて午の時に山をくだり狐町というより総門をいで、榧の木峠、舟山川、中野宿など三里余り過ぎて、南部のうまやにやどりぬ」
これは下山宿から杉山道を通り、参詣を済ませて陸路南部に出た道程である。
船便を利用しての当時の困難は、清水浜臣の甲斐日記4月4日の項に
てんきよし舟はやくつきて陸路はおくれたり。下山の宿の北に早河という流れあり、二瀬にわかれたり一瀬は人の肩をたのみてわたりぬ、一瀬は流れのはげしさ、たとえんにものなし、ただ白浪のたぎり落つるばかりにて、水の色を見ず、川原のこなたかなたより、水けぶりきりあびて袖をうるほす。舟の舳にふとき麻縄を二すじつつむすびつけて、川むかいに二人づつ立ちて、此縄を取り持ちつ、引きゆるむる、すなはち、舟の川下へ流るること一町ばかり中に舟人二人棹させど、浪のいきおいつよくて棹さしあえず、岸なる四人引つくるに、滝波のおとしかかるさま、おそろしともおそろし、おのれここかしこの旅ありきして、あまたの早瀬渡り見しかど、かかるばかりなるは見し事もなく、わたりし事もなし。市川のあがた司へ要のことありて行きしなりと言いしかば、わたしもりらの心のかぎり、いそしみたるだにかくこそあはれ、大かたの旅人、いかにわたりなやむらんかし。とかくして向いの岸へ引きつけぬ。うれしさいはんかたなし、舟路も此川のおちくちの水さきに、屏風岩というありて、この瀬いとおそろしとぞ、末のさかり(今の三時)身延山にいたりつきぬ
とあり、こうした難所が、身延町内の他にも、角打村地先の釜、浮き州の森(やぶがたき)今の大島の駅近所とあり、川丈18里の難所、十ヵ所を無事に舟航出来ることが、身延詣での一つの悲願でもあった。難所遭難の悲歌が鰍沢町にも、また、身延町の古老の口にも手まり歌として残されている。
富士川遭難者のための川施餓鬼供養の法要が行なわれた記録は大野山御会式会所日記、寛政三年(一七八一)辛亥三月朔日日記に、大野山本遠寺で8日までの間、日遠上人の御遠忌に当り、8日の最終日に
川施餓鬼 かじか沢村船頭より 舟弐艘出る
青柳村船頭より 舟壱艘出る
黒沢村船頭より 舟壱艘出る
〆四艘
御成り□□下馬より大野町うら□江出る
上町御高礼より東出る
貫主様御ひがさ 稚児四人、寺中万山□□より仕衆方弐拾人、外に近村之寺僧付、の行列に、前後に21人の役付きの信徒がつき「御法事はかじか沢舟に、尊前稚児御近衣、是を御座船、外舟には寺中万山諸待入るなり、御経音楽有之」と、その法要の盛大な模様が伺れるのである。この期間中の模様は、第一の法要にちご4人に大衆百八人あり、八日間を通じて、参詣同断とあるから現在の御会式からは想像を絶したものがあったし一般参詣人の宿泊状況についても「大野町方に参詣の人々一宿□□に百四・五十人づつその外、当所一宿のあまりは身延え罷越し上町に四五十人程づつ留り候由承」とあるから大野の宿に泊り切れなかったのだが、これも寺領内での博打(ばくち)が、手入れご免で行なわれるという環境からの客人もあったことが想像される。この折の催物が、芝居小屋壱軒、小芝居二ヵ所「外に見せもの数多」「あきんどは、にはより東、下馬まで弐百人余」と記し、身延参詣の特別通関の許可があったので、ことの外の賑いであったことが想像されるのである。青柳村船頭より 舟壱艘出る
黒沢村船頭より 舟壱艘出る
〆四艘
御成り□□下馬より大野町うら□江出る
上町御高礼より東出る
身延への参詣は各檀那寺の証明で通関許可になったが、当然身延から出発する者の場合も同様の措置が行なわれたが、慶応三丁卯(一八六六)十二月、相又村正慶寺発行の、往来無札ノ事、に、
此喜兵衛伜平兵衛ト申ス者代々法華宗拙寺檀那ニ紛レ御座ナク候、今般心願ニ付甲州身延山並諸国霊場参詣ニ罷出候処一返ノ御首題御受ケ下サレ度候、若行ツキ候節ハ御一宿仰付下サレ度、万一病死等仕候ハバ町御役人衆中様御所之御作法以御葬下サレ度幸使ノ砌法号御知ラセ下サルべく候、仍如件
諸国御寺院衆中様
とあり、相当の覚悟がなければ、一般庶民の旅行は容易なものではなかったことがうかがわれるのである。
諸国御寺院衆中様

