五、明治以降の交通運輸
(一)幕末から明治初期の陸運
この頃の交通運輸の状況は、幕府の権威の後退に伴い脇往還の苦難な助郷に対する反発も強くなり、一方、身延山への参詣客、大野山への参拝客、ことに大野山お会式当日には、寺領内での博奕(ばくち)などに対する取り締まりに寛大なものがあったのを幸いに、博徒や無宿者の入来などがあったので、かなりの賑わいがあったようである。まず、助郷に対する非協力の面では、古文書によれば
乍恐以書付奉歎願候
市川御支配所、西河内領五拾三ヶ村役人惣代波木井村長百姓源平大塩村同定八草塩村同東三郎一同奉申上候 今般東海道静岡外四ヵ宿去二辰五月より当午三月迄人馬余荷助郷勤□仰セ付られ然る処私共村々之儀は駿州より信州への脇往還万沢宿より切石迄五ヶ宿江の大助郷村々にて同宿より人馬触当次第罷出相勤候儀に有之ハ別て河内領の儀は山坂難所遠継場にて、御触一人は三人掛りを以御用相勤め候儀、殊には御進発以来諸家様方御通行繁々にて助郷一同難渋罷在引き続去る辰年ニ至り官軍様諸々隊御繰出しにて昼夜を不限大□通行其節宿方より願ニ付助郷村々江も日々□人足仰せ付られ御通行御差支無相勤至極難渋仕□候儀に有之、あまつさえ私共村々の儀も里方大助郷村方と違いいづれも山間谷間之村方にて極めて辺鄙(へんぴ)の土地に有之候処近年違作相続諸物価高騰当日を営み兼□□御□借奉願上漸相凌罷在候えども中には出稼ニ事寄家内引連れ離散いたし候ものも有之右宿々よりの助郷も相勤兼余儀なく右体の分は村方にて弁勤致し置き候程の義に有之、然る処今般前書静岡外四ヶ宿江勤□被仰付にては乍恐ニ重勤相成実に以テ疲弊の極難の村々立行難何とも難ヶしき次第ニ付何様にも此度之儀御免除仰付られ、幽にも相続出来候様仕度段村々挙て相歎候に付木顧恐此段奉願上候何卒格別之御仁恤を以て前件之次第御憐察の上今般静岡外四ヶ宿江の助郷勤□之儀御宥免なされ下され置度御歎願申上奉候 以上
巨摩郡
早川村(中略)波木井村 大野村 梅平村
小田舟原村 門野村 大城村 相又村 清子村
光子沢村 横根村(後略)
右村々役人惣代
大塩村 長百姓 定八
波木井村 長百姓 源平
草塩村 長百姓 東三郎
明治三年九月
甲府御役所
とあり、助郷への協力を拒否しており、陸上交通の混乱を生ずる一時期を迎えたのである。市川御支配所、西河内領五拾三ヶ村役人惣代波木井村長百姓源平大塩村同定八草塩村同東三郎一同奉申上候 今般東海道静岡外四ヵ宿去二辰五月より当午三月迄人馬余荷助郷勤□仰セ付られ然る処私共村々之儀は駿州より信州への脇往還万沢宿より切石迄五ヶ宿江の大助郷村々にて同宿より人馬触当次第罷出相勤候儀に有之ハ別て河内領の儀は山坂難所遠継場にて、御触一人は三人掛りを以御用相勤め候儀、殊には御進発以来諸家様方御通行繁々にて助郷一同難渋罷在引き続去る辰年ニ至り官軍様諸々隊御繰出しにて昼夜を不限大□通行其節宿方より願ニ付助郷村々江も日々□人足仰せ付られ御通行御差支無相勤至極難渋仕□候儀に有之、あまつさえ私共村々の儀も里方大助郷村方と違いいづれも山間谷間之村方にて極めて辺鄙(へんぴ)の土地に有之候処近年違作相続諸物価高騰当日を営み兼□□御□借奉願上漸相凌罷在候えども中には出稼ニ事寄家内引連れ離散いたし候ものも有之右宿々よりの助郷も相勤兼余儀なく右体の分は村方にて弁勤致し置き候程の義に有之、然る処今般前書静岡外四ヶ宿江勤□被仰付にては乍恐ニ重勤相成実に以テ疲弊の極難の村々立行難何とも難ヶしき次第ニ付何様にも此度之儀御免除仰付られ、幽にも相続出来候様仕度段村々挙て相歎候に付木顧恐此段奉願上候何卒格別之御仁恤を以て前件之次第御憐察の上今般静岡外四ヶ宿江の助郷勤□之儀御宥免なされ下され置度御歎願申上奉候 以上
巨摩郡
早川村(中略)波木井村 大野村 梅平村
小田舟原村 門野村 大城村 相又村 清子村
光子沢村 横根村(後略)
右村々役人惣代
大塩村 長百姓 定八
波木井村 長百姓 源平
草塩村 長百姓 東三郎
明治三年九月
甲府御役所
こうした陸上交通の今日に至る黎(れい)明期を経て、相又駅の開設がなされ、「内国通運継立所」の看板がかかげられたのが明治5年(1872)8月である。陸運会社定書之事の中で、
一、会社の儀は当名主附廻し会社にて取計い申すべきこと給料之儀は規則之通請取申可之事
一、歩人足之儀は金弐分は社入株代として出銀致すべき事、金壱分は年々積金之事
一、車馬之儀は金壱両は社入株代として出銀可致事
一、宿之儀は金壱両は株代として出銀可致事
一、木銭宿之儀は金壱分株代として出銀可致事
一、人馬差之儀は駅内仲間中にて両□国桝壱升つゝ相渡すべき事、金三両は支着代として年々相渡可申事
一、札代之儀は駿州迄銭四百文ツツ請取申すべき事
一、人足の儀昼夜六人宛会社ニ詰合御用売用共差支無之様大切に継立可申事
但し歩行者数多之儀は触当に家順に継立可申且途中荷物継立の儀は規則之通り堅く相守申可事
但し歩行者数多之儀は触当に家順に継立可申且途中荷物継立の儀は規則之通り堅く相守申可事
一、馬之儀は五疋宛前定書の通りそ略無之様相勤可申候事
一、人馬差之儀は昼夜会社に詰合右役人申付候御用御荷物触当は勿論売荷に至る
迄差支無之様人馬触当堅ク相勤可申事
但し大酒呑むべからす事
会社役人申付を相背申間敷事
として、一同申し合わせて発足し、人足、馬、宿屋等の収入の一部は、会社の株金として納めていたのである。なお、人足の勤務日には、大酒を呑むべからず、喧嘩口論など之無よう御用大切に勤め、火の用心大切に守り、ともし火くわえきせる堅くすべからずと、行儀作法の取り定めがなされている。これに従事した者は、宿屋が武田栄六外12人、人足として万右衛門外24名、馬壱匹の差出しは千頭和元右衛門外29名があり、恐らく相又村全域をあげての陸運業務であったろう。迄差支無之様人馬触当堅ク相勤可申事
但し大酒呑むべからす事
会社役人申付を相背申間敷事
明治5年(1872)8月、駿州往還相又駅陸運会社総代遠藤栄左衛門、望月小左衛門、市川九兵衛、武田常一郎の4名により発足した人馬賃銭表によると
駿州往還下山駅江里程弐里三十町
人足壱人賃銭 銅貨九銭九厘
宿駕籠壱挺賃銭 銅貨弐拾四銭
垂駕籠壱挺賃銭 銅貨三拾四銭壱厘
引戸駕籠壱挺賃銭 銅貨三拾九銭四厘
長棒駕籠壱挺賃銭 銅貨四拾九銭壱厘
長壱疋賃銭 銅貨弐拾四銭
駿州往還南部駅江弐里七丁余
人足壱人賃銭 銅貨七銭六厘
宿駕籠壱挺賃銭 銅貨拾八銭五厘
垂かご壱挺賃銭 銅貨弐拾六銭四厘
引戸かご壱挺賃銭 銅貨三拾銭四厘
長棒かご壱挺賃銭 銅貨三拾七銭九厘
長壱疋賃銭 銅貨拾八銭九厘
人足壱人賃銭 銅貨九銭九厘
宿駕籠壱挺賃銭 銅貨弐拾四銭
垂駕籠壱挺賃銭 銅貨三拾四銭壱厘
引戸駕籠壱挺賃銭 銅貨三拾九銭四厘
長棒駕籠壱挺賃銭 銅貨四拾九銭壱厘
長壱疋賃銭 銅貨弐拾四銭
駿州往還南部駅江弐里七丁余
人足壱人賃銭 銅貨七銭六厘
宿駕籠壱挺賃銭 銅貨拾八銭五厘
垂かご壱挺賃銭 銅貨弐拾六銭四厘
引戸かご壱挺賃銭 銅貨三拾銭四厘
長棒かご壱挺賃銭 銅貨三拾七銭九厘
長壱疋賃銭 銅貨拾八銭九厘
 |
「会社の雑費ならびニ肝煎以下ノ給料積立金等ノ本資ハスベテ賃銭ノ内一割五分刎銭(ふんせん)致シ諸事取賄ベク割賦左ノ通
刎銭壱割五分ノ内
七分五厘 肝煎其ノ他ノ給料トス
二分 筆墨紙炭油蝋燭其ノ他小入用
壱分五厘 営繕入費
壱分五厘 宿駕籠破損其ノ他損物繕
壱分五厘 会社積銭
刎銭壱割五分ノ内
七分五厘 肝煎其ノ他ノ給料トス
二分 筆墨紙炭油蝋燭其ノ他小入用
壱分五厘 営繕入費
壱分五厘 宿駕籠破損其ノ他損物繕
壱分五厘 会社積銭
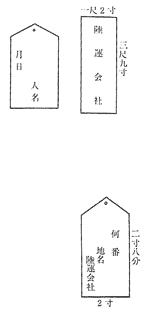 |
従事の者の鑑札は会社個人とも制定され、上の札を持たせた。
また旅人への細部を取り定めた規則書を掲出した文を下に記して当時の取扱の模様を見ると
一、陸運会社ノ儀ハ一切御旅行御便宜相成候儀ヲ旨トシ取結ビ候儀ニ付御身分ノ貴賤ヲ論ゼズ当会社ニ御申入ナサレ候ハバ何時ニ限ラズスベテ定式賃銭ニテ人馬ノ継立御世話申スベキコト
一、継立ノ儀ハ総テ御申入御着順ニ随ヒ早追ノ外ハ高貴ノ御方ニテモ別格ノ継立ハ堅ク御断リ申候事
一、早追或ハ昼夜兼行御急ギノ他多分ノ継立申入レナサレ候御方ハ前以テ案内状御差出シ可被成事
但シ右案内状継送リノ賃銭本道ノ分ハ請ケ申サズ候ヘドモ脇道等エ継送リ候分ハ相当ノ賃銭御払ナサルベキ事。
但シ右案内状継送リノ賃銭本道ノ分ハ請ケ申サズ候ヘドモ脇道等エ継送リ候分ハ相当ノ賃銭御払ナサルベキ事。
一、諸荷物目方七貫目迄ヲ人足一人、四拾貫目迄ヲ馬一疋ノ度ト定メ是ヨリ相増候分、左ノ割合ヲ以テ歩増賃銭請取候事。
人足 七百目迄ヲ壱分七百目以上壱貫
四百目迄ヲ弐分ソノ他是ニ準ズ
馬 四貫目迄ヲ壱分四貫目以上八貫目迄ヲ弐分ソノ他是ニ準ズ
人足 七百目迄ヲ壱分七百目以上壱貫
四百目迄ヲ弐分ソノ他是ニ準ズ
馬 四貫目迄ヲ壱分四貫目以上八貫目迄ヲ弐分ソノ他是ニ準ズ
一、早追ハ定賃銭ノ七割五分但酉ノ上刻(八時半ごろ)ヨリ丑ノ下刻(午後一時半ころ)迄五時間ハ一倍五割ノ賃銭御払ナサルベキコト
一、平常ノ人馬夜継ノ分酉ノ上刻ヨリ丑ノ下刻迄ハ五割増ノ賃銭御払ノ事
一、御旅行ノ都合ニ寄前後ニ三駅ツツ継越シ申スベク尤賃銭ハ表面ノ割合ニテ請申スベキ事
一、人足ノ強壮寄リ弐人或ハ三人払ノ荷物ヲモ壱人ニテ運送致スベキ事
一、会社ノ都合ソノ時ノ模様ニ従イ駄荷ヲ車力ニテ継立候儀モ有之ベク尤賃銭ハ荷駄ノ定ヲ以テ請取申スベキ事
但山川険路等車力相用難場所ニテ馬遣払候節ハ相当ノ人足賃銭御払下サルベク候事。
但山川険路等車力相用難場所ニテ馬遣払候節ハ相当ノ人足賃銭御払下サルベク候事。
一、会社ノ人馬ハ総テ左ノ雛形ノ通鑑札相渡シ置候間万一不礼不法ノ所行有之節ハ其ノ者所持ノ鑑札番号御見留置前宿会社エ御申聞下サルベク会社ノ法ヲ以テ吃度糺明致シ御迷惑相成ラザル様精々取扱申スベキ事
一、途中ニテ替荷之儀申出候ハバ会社鑑札ノ有無御取糺シ有之度無鑑札ノ者旅客相対稼替荷等可為厳禁会社ノ規則ニ御座候事
一、宿駕籠御借入ノ方ハ壱挺ニ付壱里迄ハ銅貨壱銭壱里以上ハ壱里ニ付同三厘壱毛宛ノ割合ヲ以テ損料御払可被成事
これと同様な約定による下山駅の業務も開始されたのであるが、明治7年(1874)になり、陸運会社を解散させて同類業連合となり、公私人馬継立運賃表を作製し、通運会社と改称して一定数の人馬を約定しておき通運の業に当たった。下山駅の場合は| 一、馬 三疋 | ||
| 一、人足拾人 | ||
| 一、馬壱疋賃銭 | 壱里ニ付南ノ方拾壱銭弐厘五毛 壱里ニ付北ノ方同断 |
|
| 一、人足壱人賃銭 | 壱里ニ付南方四銭五厘 壱里ニ付北方同断 |
右ノ通約定候也
当御管下巨摩郡第三十四区下山駅
継立引受人 望月万右衛門
同様の約定書が相又駅継立引受人市川三右衛門から出されている。当御管下巨摩郡第三十四区下山駅
継立引受人 望月万右衛門
明治九年(一八七六)丙子年一月付の公私諸荷物継立規則(内国通運会社引受人市川庸三の文書・市川喜洋蔵)には相又駅から各地域への里程、賃金が詳細に書かれているので下に記して当時の状況を見ると
○当駅より福居(下山)睦合両駅マテ里程
二里十八丁三拾間
二里十八丁三拾間
| 一、 | 人足壱人 | 但七貫目持 | |||
| 此賃銭 | 拾壱銭弐厘弐毛 | ||||
| 内 | 七厘九毛 | 人当料 | |||
| 外ニ | 金壱銭壱厘三毛 | 手数料 | |||
| 合金 | 拾弐銭三厘五毛 | ||||
| 一、 | 宿駕籠 | 壱挺 | |||
| 此賃銭 | 弐拾八銭三厘 | ||||
| 内 | 金壱銭 | 蒲団賃 | |||
| 金壱銭三厘 | 人当料 | ||||
| 外ニ | 弐銭八厘三毛 | 手数料 | |||
| 合計 | 三拾壱銭壱厘三毛 | ||||
| 一、 | 馬 | 壱疋 但四拾貫目持 | |||
| 此賃銭 | 金弐拾八銭三厘 | ||||
| 内 | 金壱銭三厘 | 人当料 | |||
| 外ニ | 金壱銭八厘三毛 | 手数料 | |||
| 合金 | 三拾壱銭壱厘三毛 | ||||
| 一、 | 馬 | 壱疋 但三拾貫目持 | |||
| 此賃銭 | 弐拾壱銭弐厘弐毛 | ||||
| 内金 | 壱銭弐厘弐毛 | 人当料 | |||
| 外ニ | 弐銭壱厘弐毛 | 手数料 | |||
| 合金 | 弐拾三銭三厘四毛 | ||||
| 一、 | 乗馬 | 壱疋 | |||
| 此賃銭 | 弐拾壱銭弐厘弐毛 | ||||
| 内 | 金壱銭 | 蒲団賃 | |||
| 金壱銭弐厘弐毛 | 人当料 | ||||
| 外ニ | 金弐銭八厘三毛 | 手数料 | |||
| 合金 | 弐拾四銭五毛 |
○当駅より身延町大城組両所まで里程一里四丁
| 一、 | 人足 | 壱人 | 但七貫目持 | ||
| 此賃銭 | 金五銭 | ||||
| 内 | 金五厘 | 人当料 | |||
| 外ニ | 金五厘 | 手数料 | |||
| 合金 | 五銭五厘 | ||||
| 一、 | 宿駕籠 | 壱挺 | |||
| 此賃銭 | 金拾弐銭五厘弐毛 | ||||
| 内 | 金壱銭 | 蒲団料 | |||
| 金壱銭 | 人当料 | ||||
| 外ニ | 金壱銭弐厘五毛 | ||||
| 合金 | 拾三銭七厘七毛 | ||||
| 一、 | 馬 | 壱疋 但四拾貫目持 | |||
| 合金 | 拾三銭七厘七毛 | ||||
| 一、 | 乗馬 | 壱疋 拾銭三厘四毛 |
明治17年(1884)1月、公私諸荷物継立賃銭が人足持貫目7貫目まで1人1里6銭と変更され宿駕籠は弐人五分と賃金の改正がなされこの年の9月になり新道の工事が終了したため、「今回通運廻漕陸漕ノ三社当村清子組へ転居致諸貨物御取扱ナサレ候ニ付」と清子組の43名連印で請負い、更に相又組の者もこの輸送に5名があたっている。
かくして、新道の開さくに応じ交通の便を町内に与えていたが明治37年(1904)の洪水の際栄久橋の落下にあい、43年の架橋替えを行なって交通の便を支(ささ)え、大正の馬車、馬力による輸送から、昭和の自動車による陸上輸送の飛躍的発展へと変革の途(みち)をたどったのである。
(二)明治以後の富士川舟運
明治8年5月、富士川通船規則が定められ「危険ノ川筋、至重ノ人命ニ関係致シ物資の損害モ不少、実ニ以テ容易ナラザル儀ニ付」との趣旨で、「改船所ヲ設ケ、且川筋危険ノ場所漸次川浚掘割等着手後来通船ノ安穏ヲ保全スベキタメ右入費トシテ賦金申付」ている。(山梨県史)富士川通船規則に定められいてるもののうち、乗組人員、積込荷物の定額は「下り船一般人員拾五人、荷物廿四個、」但し船頭の外の人員として、荷物壱個の重さは「壱個拾五貫メニシテ三百六拾貫目」であり、上り船壱艘、食塩四拾八俵、但小俵六貫目、荷物廿四個但壱個拾弐貫目ニシテ弐百八拾八貫目」としていた。乗客は会社または問屋問屋で、生国住所姓名を聞糺(ただ)し乗客名簿に記入し、何月何日、何某の舟に乗ったとして、身延町の河岸としては、波木井河岸、帯金河岸があり、そこで乗船証券の受け渡しをしていた。
船頭の「定員は四人以上タルベシ、何様強壮ノ船頭タリトモ四人ノ内ヲ減スベカラズ」であり、危険防止の措置として、賦金として通船に積荷の有無にかかわらず「上り船壱艘ニ付賦銭六銭、下り船同賦金壱銭三厘」を納めさせていた。おって12月になり、富士川運輸会社分社規則が作られたがこの目的は「甲駿両国ノ便益ヲ計ルガタメ蒲原新水道ヲ開さくし」その経費を支出した本社の経費の責任分担として扱荷物の手数料の10分の1を差出させて富士川筋に22の分社を設けて町内には、波木井分社佐野多兵衛代・井上治郎兵衛・大島分社片田庄兵衛門の2名が届出している。かくして富士川の通船は、鰍沢を基点として発達して行ったが町内においても、明治14年(1881)12月に発足した鰍沢の拡達会社の付属船として営業を始めた同盟仲間の盟約書(鈴木武重蔵)に「生魚又ハ至急ヲ要スル諸貨物会社ヨリ増運賃ヲ以テ二円曳或ハ二円半曳ノ指命アル時ハ水子ヲ増シ必スソノ時ヲ誤ラス河岸着ハ勿論不通ノ三円曳等ト雖モ荷主補フテ商法ノ時機ヲ誤ラセス弁利ヲ主トシテ我業務ノ拡張スル事ヲ永遠ニ計ルベシ」と、当時の舟運業務に競争が激しかった模様がうかがわれる。また、「乗船一番船ノ儀ハソノ日午後三時ヲ限リ着船居合ノモノニテクジ取リヲナシ翌日ノ出船ヲ確定スヘシ。但シ身延会式ソノ他ニテ乗船ノ多キ見込アル時ハ、クジ取りノ時間ヲ短長スル事アルベシ」数多い舟の発船順序がくじ引きで行なわれたが、身延会式の乗客の多い場合はそのくじ引き順番も間に合わなかったのであろうか、その時間をくり上げ、くり下げしたものらしい。さて仲間の運営経費の模様は、
当社附属船仲間エ総代七名ヲ置キ壱人ヲ常置トナシ其月給四円ト定メ、外六名ハ二ヶ月宛月番ヲ以テ各地へ出張又ハ常置ノ補欠ヲ補イ其月給金壱円ト定メ候事
一、当社船方仲間ノ経費トシテ置銭ノ儀一ヶ年度(正月ヨリ正月迄)予算金壱円ト定メソノ壱円ヲ一度上下金拾銭ノ宛ニ拾度ニ皆済シ其遣払ハ翌年正月総会ニ於テ報告スルモノトス
一、難破ノ諸掛リハ其最寄組合ニ於テ出金シ仮令(タトエ)バ黒沢ハ黒沢限リ別紙組合調書ノ通リタルベシ。但シ難破船ニ係リ船艇ヲ失イタルモノアル時ハ附属同盟仲間壱艘ニ付金五銭宛ニ見舞シテ会社エ出金シ本人ヲ正業ニ就カシムルコト
一、川堀補助費割合ノ儀明治十九年十二月迄ノ船持エ割合ノ事
一、通船賦金減額ノ請願ヲナシ其入費日当出金ノ儀ハ差当リ川堀補助費ノ御下ケ金ヲ以テ壱艘当テ金拾五銭ヲコレニ当テ不足ノ分ハ臨時ニ徴収スヘシ
一、乗船人ニ必要ノ器具賦金ノ内ヲ以テ購求ノ事。払達会社附船西八代郡黒沢村総代
外西八代郡各村の総代の連名があり、町内では大河内村八木沢芦沢祖市郎、久保勝兵衛外二名、帯金鈴木吉蔵、角打総代望月卯三郎となっている。一ヵ年の予算額の壱円が拾銭ずつの月割納付とされ、難破船の経費はその組限りで補助し合い、難船で失船の場合に同盟仲間の壱艘につき5銭の拠出をもってしたことは一面船数の多さを推定できる。こうした舟運の中にあって、舟行の便は、増水ならびに増水後の川瀬の変動によって手を加えねばならなかったものである。明治18年4月7日、富士川船路川堀各村請場によると、この工事を川堀瀬浚(ざら)いと呼び
| 一、伊沼前より屏風岩迄 | 伊沼村 飯富村 | |
| 一、屏風岩より波高嶋渡船迄 | 波高嶋村 | |
| 一、波高嶋渡船より上八木沢境迄 | 上八木沢村 | |
| 一、上八木沢境より宮ノ花迄 | 下八木沢村 | |
| 一、宮ノ花より波木井渡船迄 | 箱原村 | |
| 一、波木井渡船より丸滝渡船迄 | 帯金村 | |
| 一、大野小屋前より平渡し場迄 | 清子村 波木井村 | |
| 一、平小屋よりヤブガタキ迄 | 鴨狩村 田原村 宮木村 | |
| 一、ヤブガタキより大島渡船迄 | 丸滝村 角打村 | |
| 一、大嶋渡船より戸栗川下迄 | 和田村 大嶋村 | |
| 一、獅子山瀬 | 楠甫村 | |
| 一、獅子山瀬下より福士休場迄 | 南部村 西行村 内船村 |
富士川の通船に際しての難船の始末は、所在の問屋に届けたもので、前記のヤブガタキは富士川の難所の一つでもあり、
文化八年(一八一一)未正月、着出申手形之事。
一、塩
一、藍玉弐個
右は和田村分内板取之滝ト申ス所ニテ引縄三筋共ニ一同切表振出候ニ付破舟仕在荷物不残相見エ申サズ候、右ノ趣届ケ候ニ付私立合見届ケテ候処書面ノ通リ相違無御座候
文化八年未正月
和田村名主 七郎右衛門
御問屋中様
板取の滝がヤブガタキと同一のものであるかどうかは判然としないが和田から大島までの間の難所であるところからあるいは同一の場所とも思われる。一、塩
一、藍玉弐個
右は和田村分内板取之滝ト申ス所ニテ引縄三筋共ニ一同切表振出候ニ付破舟仕在荷物不残相見エ申サズ候、右ノ趣届ケ候ニ付私立合見届ケテ候処書面ノ通リ相違無御座候
文化八年未正月
和田村名主 七郎右衛門
御問屋中様
明治初年頃の権令藤村紫朗に宛てた文書に次のように見えている。
鰍沢青柳黒沢三河岸より駿州岩淵河岸迄富士川通船村々運賃表(片田為丸蔵)
| 一、人壱人ニ付金四銭五厘二毛 | 波高嶋、上下八木沢、下山駅、凡五里 | |
| 一、荷物拾貫目ニ付金壱銭六厘九毛 | 右村方へ | |
| 一、人壱人ニ付金五銭二厘壱毛 | 帯金村、波木井村 | |
| 一、荷物拾貫目ニ付金壱銭九厘四毛 | 凡六里 | |
| 一、人一人ニ付金五銭五厘五毛 | 大野村、丸滝村、角打村 | |
| 一、荷物拾貫目ニ付金弐銭六毛 | 和田村、凡六里半 | |
| 一、人壱人ニ付金五銭九厘 | 光子沢村、大嶋村 | |
| 一、荷物拾貫付金弐銭壱厘八毛 | 清子村、凡七厘 |
大正5年1月、大野区内の通船切符交付権をめぐって、同区と波木井の有力者との間に紛争が生じたことが記録されているが、これによると大野区は明治23年以来26年間、運輸会社より取締所設置に対する権利金を徴収していることが説明されており、その額は明治25年の契約書によると年額金6円とされており、当時の物価から考えても、船着場としての権利と収益は決して小さいものではなかったことがわかる。
なお、通船業者は数社あったといわれ、各社とこのような契約を結んでいたとも思われる。

