第三節 道路・橋梁
一、道路
身延町の道路の姿を歴史的に眺めると、下山村の場合、大正8年(1919)の町村取調書によると、「古来村の南端より山腹に沿って一里松に出て、身延・豊岡を経て南部に通ぜしが、明治九年本村より南部に至る富士川岸に県道開さく成るも、古道は身延参詣者のために年々修理を加へ保有す。北方は渡舟により飯富に通ぜしが、明治三十五年早川に沿い約十八丁西に入り釣橋(注・早川橋)を架す」とあり、豊岡村の状況については、「僻陬(へきすう)の地交通不便、県道大野界より遊亀橋に至る一里十丁。身延街道(旧県道)・遊亀橋より横根中区栢木(かやのき)峠相又区小田舟原区身延山総門に終る一里三十四丁。横根道・光子沢天神社より坂路横根に至り身延街道に合す十丁。光子沢道、光月橋より登り奥を経て栢木峠に出で身延街道に合す(十二丁)、大久保道・清子道・中山道・針山道・大城道・安倍道」とある。大河内村の状況は、「水路は富士川の便あり、陸路狭隘の坂路多くして人力車の通ずる道路なし、帯金区より下八木沢区に越ゆるに引核(さね)峠あり。角打区より和田区に越ゆるに和田峠あり、又帯金区より下山へ、丸滝より身延へ、大嶋より中野へ渡る三ヵ所富士川横渡し」と町内各地域の道路状況を説明している。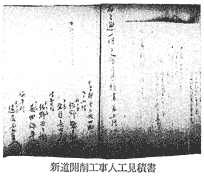 |
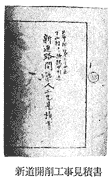 |
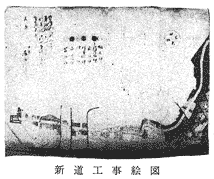 |
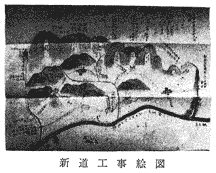 |
巨摩郡第三十四区下山村より横根中村まで、新道路開築人工凡そ見積書、明治
八年申戊年十月
字トビイ沢より深沢迄
一、長千八十七間半
人足七千九百七十二人
杣、四十八人、大工、四十五人
内訳
トビイ沢より三十沢迄
一、長四十六間半
人足 百八十六人、但一間四人
また、清子区の工事請負模様について八年申戊年十月
字トビイ沢より深沢迄
一、長千八十七間半
人足七千九百七十二人
杣、四十八人、大工、四十五人
内訳
トビイ沢より三十沢迄
一、長四十六間半
人足 百八十六人、但一間四人
道路切開請負書(明治九年三月十二日)
清子村第八十七号より第九十一号迄
光子沢村第一号より第十二号迄
一、長三百四十間 但し横二間
五分法(の)り
此請負金三百五十円四十銭
人足二千九百人
一人につき日当十二銭
区長と新道世話掛り御中
として出されている。清子村第八十七号より第九十一号迄
光子沢村第一号より第十二号迄
一、長三百四十間 但し横二間
五分法(の)り
此請負金三百五十円四十銭
人足二千九百人
一人につき日当十二銭
区長と新道世話掛り御中
この工事の完了は、結局明治11年11月となったが、この間「田作り仕付中、去る七月十日迄休暇中、同十一日より着手致すべき旨先般書面差上罷在然る処近年稀なる大旱魃に付田方用水手配方」昼夜つとめたので着手が延引したこと、陸路は完成したが橋梁用材難のため工事ははかばかしくなく「先達て御下木願書差上置候旧大野村本遠寺領上地官林の外用材になるべき木品区内に無之」と訴え、他より探索して架し候節は落成の目途立ち難し」と工事のやりくりの苦しさを、下山・波木井・大野・横根・清子の各区長、副区長連署で山梨県令に差し出している。
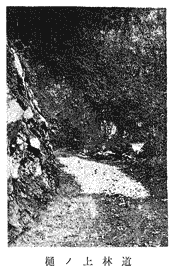 |
この県道とは別に身延村には波木井宮の花から殿前をとおり、総門に通ずる道路があって、この道路も昭和3年5月、身延村村会議録に、村費3,000円寄付し豊岡村大字小田舟原字大嶋(総門前)より身延村大字波木井字宮ノ花に至る現在道路を全部6尺に拡張し完全なる橋梁を架設の上波木井川沿いに林道を布設することとすると決議され改修されたが、この林道は、大城中嶋部落を起点として湯平・門野・横尾・小田舟原までの林道の延長の必要から開さくされたもので昭和初年ごろまでこの林道は恩賜林の搬出に利用されたのである。次に町内の主な林道一覧表(表1)を掲げる。
(表1)林道一覧表 (昭和43年11月調べ)
| 路線名 | 主要経過地 | 延長 | 着工年月 | 竣工年月 | 所属 | 備考 | |
| 長野林道 | 大島馬込部落上−長野 581番 |
26年度 540m 27年度 226m |
昭和26年6月 | 昭和27年 | 身延町 | 昭和26年民間開設 昭和27年県単開設 |
|
| 豊岡林道 | 大城部落−大城部落下 土場−古谷城−安倍峠 下−安倍峠 |
28年度〜43年度 5,463m |
昭和26年6月 |
未定
|
山梨県 | 昭和44年度分 1,044m 未着工分 6,507m 総延長 11,324m |
|
| 大島林道 | 大島部落水上−大島部 落大日向大日向6,211 番地 |
28年度 568m 29年度 292m |
昭和28年8月 | 昭和29年 | 身延町 | 昭和28年臨時救農土木事業 昭和29年県単開設 |
|
| 樋之上林道 | 樋之上−針原−垈 | 42年度 1,431m 43年度 920m |
昭和42年9月 | 昭和44年3月 | 身延町 | 林業構造改善事業 | |
| 大垈林道 | 椿草里−大垈 | 43年度より 5,045m |
昭和43年9月 |
昭和45年3月
(予定) |
身延町 | 林業構造改善事業 | |
| (身延町役場 建設課) | |
| (注) | 豊岡林道の静岡県分は梅ヶ島温泉まで、総延長8,105m中、43年度までに2,725mが完了し、残り5,380mは林野庁において施行の予定。 |
道路の拡幅整備とともに、戦後の交通革命ともいうべき自動車の発達は、当然従来の道路状況をもってしては道路としての使命が完全に果たされなくなり、県道は昭和31年11月22日ニ級国道に編入されて、清水上田線と呼ばれ昭和37年5月1日に一級国道となり、のち一般国道となる。交通量の激増に伴い6.5メートルに拡幅舗装されて面目一新したのである。現在町道も逐年拡幅改修また、一部は逐次舗装され、一方県道舗装も進みその舗装率は24.4パーセントの完成を示して地域の経済文化の向上に役立っている。なお、町道の舗装率は2,327メートルで1.2パーセントである。
町では毎年春秋2回、道路愛護の日を設けて町内全域の国・県・町道および農道等の改修整備作業を行なっており、文字どおり町民総出動で道づくりに協力している。
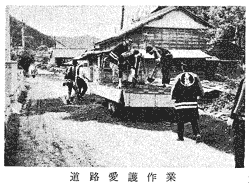 |
 |
(一)辺地道路の開発
町では合併以来町内の格差解消を目標として辺地への道路開発と整備に力を入れ、「どんな山の中の部落へも車が行けるように」をスローガンにしているが、合併以来今日までの辺地開発道路工事の主なものを掲げると次のとおりである。 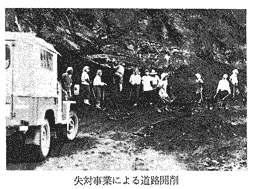 |
 |
| 実施年度 | 路線名 | 区間 | 事業区分 | 事業費(千円) | ||||
| 30 | 上粟倉線 | 粟倉旧分校−上粟倉 | 失対事業 | 600 | ||||
| 30 | 光子沢横尾線 | 星久保−戸坂 | 失対事業 | 367 | ||||
| 30−31 | 大野清子線 | 本遠寺−清子分校 | 失対事業 | 2,067 | ||||
| 31 | 杉山線 | 下山口−身延口 | 失対事業 | 554 | ||||
| 31−33 | 大垈線 | 名元橋−人家入口 | 失対事業 | 2,141 | ||||
| 31 | 大崩線 | 桑柄沢橋−水谷 | 失対事業 | 1,853 | ||||
| 33 | 北清子線 | 二ッ橋−人家入口 | 失対事業 | 1,105 | ||||
| 34 | 樋之上線 | 時雨沢−樋之上 | 失対事業 | 565 | ||||
| 34−25 | 塩之沢椿線 | 林前−宮の前 | 失対事業 | 4,345 | ||||
| 36−37 | 清子光子沢線 | 旧横光分校−谷津 | 失対事業 | 3,535 | ||||
| 38 | 樋之上線 | 樋之上−針原 | 失対事業 | 4,583 | ||||
| 39−40 | 清子光子沢線 | 古宿橋−谷津 | 失対事業 | 10,479 | ||||
| 40 | 大野清子線 | 本遠寺−清子分校 | 国辺地債事業 | 7,103 | ||||
| 40 | 小田船原大城線 | 奥川橋永久化工事 | 県辺地債事業 | 3,774 | ||||
| 42 | 相又坂本清子線 | 坂本橋永久化工事 | 県辺地債事業 | 2,400 | ||||
| 42−43 | 大崩線 | 大曲−人家入口 | 県辺地債事業 | 7,013 | ||||
| 42−43 | 樋之上線 | 針原−垈 | 林業構造改善事業 | 23,053 | ||||
| 43 | 小田船原大城線 | 湯沢橋 | 県辺地債事業 | 2,147 | ||||
| 43 | 光子沢横尾線 | 星久保−戸坂 | 失対事業 | 6,164 | ||||
| 43 | 光子沢横尾線 | 亀久保−立屋橋 | 国辺地債事業 | 5,162 | ||||
| 43−44 | 大垈線 | 一号橋上−人家入口 | 林業構造改善事業 | 37,298 |
(二)失対事業の沿革とその終末
(合併以前各地区の状況)昭和20年、わが国は太平洋戦争に手ひどい惨敗を招いた結果、国内の産業は全くマヒし、復員、引揚げ、軍需産業からの徴用解除等による尨大な失業者の発生をみた。
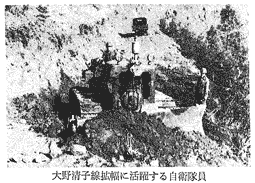 |
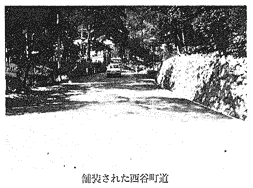 |
 |
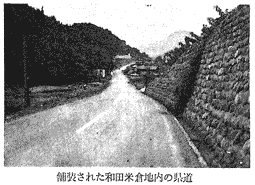 |
かくして昭和25年旧身延町、次いで翌26年旧大河内村、さらに1年遅れて26年に旧下山村と旧豊岡村がそれぞれ失対事業を実施することが認可された。
この失対事業は、各地区とも開発の遅れた未整備の道路の改修と新設にあたったので、各部落の好評を得、その要望が多くなった。これがため1地区年間4路線の道路工事をすることもあり、地区によっては財政面の都合もかねて労力費や資材費の一部を地元受益者に負担させたところもあった。
 |
 |
(合併後の主なあゆみ)
昭和30年、四ヵ町村が合併して新身延町の誕生をみたが、各町村ともこの失対事業は重要な政策としてそのまま新町に引きついだ。
新町の発足より、失対事業を廃止した昭和43年度まで14年間の事業の実施経過は、別表「町村合併後における失対事業の年度別推移」において概略示したとおりである。
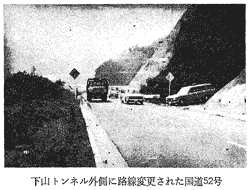 |
(事業の終末)
かくして本町における失対事業は、町村合併前の旧町村時代からかぞえて29年、新町発足以来14年の歴史を記録し、この間失業者救済という社会政策の役割りを果たすとともに、町内道路の整備という土木行政推進にも大きな貢献をしてきた。
その実施した路線数48本、道路延長32.49キロメートル、就労人員延べ10万5,607人、事業額は実に7,738万2,000円に達しており、本町道路史におけるその功績はさんとして輝くものといえる。
特にこの失対事業によって開発された道路は辺地部落が多く、中でも幹線道より遠く離れた一里松・豆畝・光子沢・戸坂・大崩・椿・樋之上などの部落は、この工事によって初めて車が出入りすることができるようになったことは特筆される。
(表2)身延町内県道
| 路線名 | 実延長 (m) |
舗装道 (m) |
砂利道 (m) |
舗装率(%) |
| 市川大門下部身 延線 |
7,285.0 | 1,953.0 | 5,350.0 | 26.5 |
| 身延本栖線 | 5,269.0 | 681.0 | 4,588.0 | 12.9 |
| 身延線 | 1,173.0 | 1,173.0 | 0 | 10.0 |
| 万沢身延線 | 6,044.0 | 921.0 | 5,123.0 | 15.2 |
| 野呂川・波高島 (停)線 |
3,237.0 | 920.0 | 2,317.0 | 28.4 |
| 全体 | 23,008.0 | 5,630.0 | 17,378.0 | 24.40 |
現在の町内を通じている道路を図示すると図1のごとくである。
町内の交通量と交通安全施設について
町村合併後における失対事業の年度別推移
(内)補助金
| 年度 | 吸収人員(人) | 道路工事実施状況 | 事業費 (千円) |
|||
| 1日平均 | 年間 | 延長(m) | 路 線 数 と 場 所 | |||
| 昭和30年度 | 61 | 18,155 | 8,000 | 12 | 山額、本町、上粟倉 大野、西塩沢 門野、光子沢、清子 大島、和田角打、塩之沢帯金 八木沢大垈 |
7,050 (3,600) |
| 31 | 17,518 | 7,050 | 8 | 粟倉富山橋、杉山 西川、豆畝、相又、二ツ橋清子 大垈、大崩 |
6, 555 (3,423) |
|
| 32 | 10,482 | 3,003 | 5 | 大工町、横根、大垈 和田、平、角打 |
5,351 (2,656) |
|
| 33 | 13,050 | 3,875 | 6 | 下山、身延、北清子、東谷 大崩、大垈、帯金 |
6,050 (3,000) |
|
| 34 | 10,111 | 3,440 | 5 | 西平、大久保、樋之上 水上、椿草里 |
5,532 (2,177) |
|
| 35 | 5,674 | 360 | 2 | 大庭、粟倉、椿草里 | 4,026 (1,482) |
|
| 36 | 5,074 | 986 | 2 | 竹下、大庭、光子沢 | 4,014 (1,534) |
|
| 37 | 4,238 | 1,200 | 2 | 大庭、光子沢 | 3,576 (1,379) |
|
| 38 | 4,598 | 1,160 | 1 | 樋之上 | 4,583 (1,956) |
|
| 39 | 4,449 | 995 | 1 | 清子、光子沢 | 5,461 (2,395) |
|
| 40 | 3,576 | 460 | 1 | 清子、光子沢 | 5,018 (2,063) |
|
| 41 | 3,272 | 520 | 1 | 北沢(下山) | 8,263 (2,107) |
|
| 42 | 3,278 | 520 | 1 | 西塩沢 | 5739 (1,929) |
|
| 43 | 2,137 | 580 | 1 | 戸沢 | 6,164 (2,448) |
|
| 計 | 105,607 | 32,149 | 48 | 77,382 | ||
町内、特に国道52号線の交通量は近年道路状況の改良にともない、マイカー族、観光バスの増加、一方砂利採取のダンプカーの激増等、急カーブで上昇している。観光シーズン等のピーク時の交通量についての正確な資料はないが、現況の一端を示す資料として、43年3月の秋季交通量調査の記録を表3に掲げる。
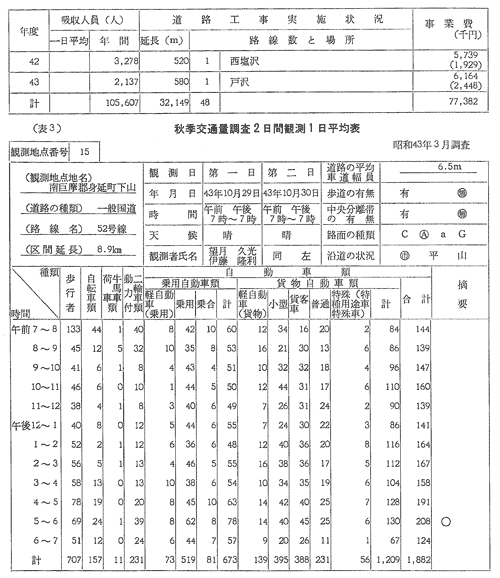 |
この交通事情激化に対応して、各種の交通安全対策が行なわれているが、下山地内の国道拡幅にともない両側歩道が設置されたのをはじめ、42年から43年度にかけて梅平の身延高校前通り、身延小中学校前通り、豊岡小中学校前通りにそれぞれ歩道が設置された。また昭和43年度には身延小学校前に、44年度には下山小学校前にそれぞれ横断歩道橋が設置され、大いに効果を挙げている。今後ともに各種の安全施設の充実が望まれている。

|
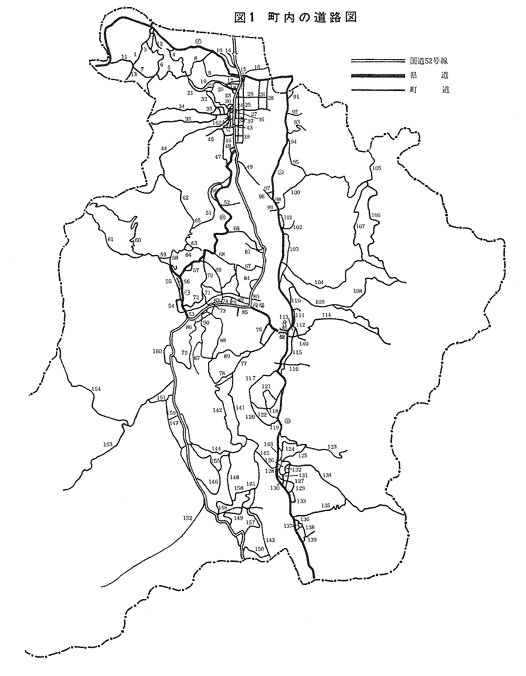 |
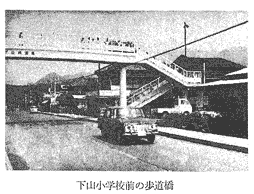 |
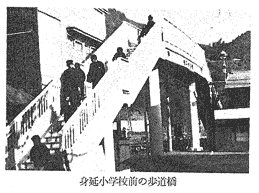 |

