第五節 消防近代化への胎動
昭和44年4月を期して消防団員への定数削減が実施されることに伴い、町議会においても「消防近代化研究特別委員会」が設置され、消防の近代化への諸問題について鋭意調査研究を進め、昭和44年3月28日年度末議会において「消防近代化についての意見書」を満場一致議決するに至った。次にその全文を掲げる。
消防近代化についての意見書
進行する過疎現象、流出する若い労働力、兼業化の増大等々、社会的条件の大きな変動は本町にとっても例外ではなく、好むと好まざるにかかわらず、長い歴史と伝統を持つ自治体消防のあり方について再検討が迫られていることは、衆目の認める所である。
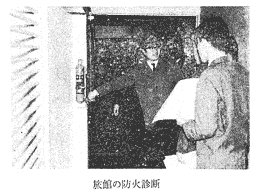 |
全国的にも非常勤消防の体質の改善と近代化、広域化、精鋭化が叫ばれ、減員に伴う装備面、組織面での改革や、半常設的乃至常設的消防態勢への前進、団員処遇の改善、生活環境の変化に対応する消防力の科学化、機動化も促進され、法的措置もなされつつある。
本町においても、かねてよりこの問題に関心が高まり。昭和41年には町独自の消防賞じゅつ金条例の制定が全国にさきがけて行なわれ、42年度には消防団員を907名より618名に削減し、少数精鋭化をはかったのである。しかし、消防近代化は単に消防団員の減員によって目的が達せられるものではなく、現在我々が置かれている社会的条件に適応した強力にして有効な消防の組織、機構、装備、運営を実現し、かつ今後長期に亘る見通しの上に立ってその在り方が研究され、実践されねばならないのである。
町議会はこのような観点より、町消防の現状を考え、先進町村の事例や成果も取り入れつつ、当面必要な対策及び町の長期建設計画の中に生かして行くべき諸問題について、次のとおり意見を提出し、町当局の一層の努力を要望するものである。
(一) 本部機動隊の設置について
この件については、前議会において中間報告として当局に要望したが、改めて述べる。既に昭和三十六年の消防庁通達により、人口五千以上の密集地帯においては常備的消防を設けるよう方針が打ち出されており、多数の町村が従来の非常勤消防にのみ依存するあり方から一歩前進して、常備的消防力の育成に踏み切りつゝある現状である。
本町においても冒頭に述べたような社会的条件により非常勤消防団は弱体化しつゝあり、昼間において特にその現象は著しいものがある。過疎化の半面町中心部には小規模ながら都市化ともいうべき集中現象が進みつゝあり、貴重な宗教的文化財としての身延本山をも守護していかねばならぬ本町の立場を思うとき、当然自治体の任務として消防法第六条にも規定された責任を果たすためには、専門化された常備的消防力設置の時期がきていることは明らかである。
勿論、地域の固有の条件から考え、風水害、山林火災等にも有効に対処できる非常勤的自主防衛力の存在は不可欠であり、これが充実の必要性はいうまでもないが、今後の在るべき姿としては、両者の相互協力運営によって初めて実情に即した、住民に信頼される消防力が確保できるのではなかろうか。
(1)昭和四十四年度より、消防団長直属の本部機動隊を設置し、所要の条例、団規則改正、予算化をなすべきである。
本町においても、かねてよりこの問題に関心が高まり。昭和41年には町独自の消防賞じゅつ金条例の制定が全国にさきがけて行なわれ、42年度には消防団員を907名より618名に削減し、少数精鋭化をはかったのである。しかし、消防近代化は単に消防団員の減員によって目的が達せられるものではなく、現在我々が置かれている社会的条件に適応した強力にして有効な消防の組織、機構、装備、運営を実現し、かつ今後長期に亘る見通しの上に立ってその在り方が研究され、実践されねばならないのである。
町議会はこのような観点より、町消防の現状を考え、先進町村の事例や成果も取り入れつつ、当面必要な対策及び町の長期建設計画の中に生かして行くべき諸問題について、次のとおり意見を提出し、町当局の一層の努力を要望するものである。
(一) 本部機動隊の設置について
この件については、前議会において中間報告として当局に要望したが、改めて述べる。既に昭和三十六年の消防庁通達により、人口五千以上の密集地帯においては常備的消防を設けるよう方針が打ち出されており、多数の町村が従来の非常勤消防にのみ依存するあり方から一歩前進して、常備的消防力の育成に踏み切りつゝある現状である。
本町においても冒頭に述べたような社会的条件により非常勤消防団は弱体化しつゝあり、昼間において特にその現象は著しいものがある。過疎化の半面町中心部には小規模ながら都市化ともいうべき集中現象が進みつゝあり、貴重な宗教的文化財としての身延本山をも守護していかねばならぬ本町の立場を思うとき、当然自治体の任務として消防法第六条にも規定された責任を果たすためには、専門化された常備的消防力設置の時期がきていることは明らかである。
勿論、地域の固有の条件から考え、風水害、山林火災等にも有効に対処できる非常勤的自主防衛力の存在は不可欠であり、これが充実の必要性はいうまでもないが、今後の在るべき姿としては、両者の相互協力運営によって初めて実情に即した、住民に信頼される消防力が確保できるのではなかろうか。
(1)昭和四十四年度より、消防団長直属の本部機動隊を設置し、所要の条例、団規則改正、予算化をなすべきである。
ア、本部機動隊は隊長のほか、町職員中より三十五歳以下、普通以上の運転免許所有者である適任者二十一名を以て組織し、昼間(在庁時間)は七名づつ三班編成とし交代勤務により出勤態勢をとる。夜間は二十一名が一名づつ宿直し、有事の際は、役場周辺在住の隊員八名を夜間搭乗要員として指名しておき、通報により九名をもって出動する。
その他の隊員は現場で合流する。夜間出動の際の指揮は当直者が、昼間の際は班長がとり、隊長に引きつぐものとする。
その他の隊員は現場で合流する。夜間出動の際の指揮は当直者が、昼間の際は班長がとり、隊長に引きつぐものとする。
イ、隊員の宿直については手当を支給し、出動については一般団員同様とする。
ウ、隊員は所属部より離籍し、機動隊に専属するものとする。
エ、機動隊には科学消火装置を備えたポンプ自動車を備え、強力な現場司令用拡声機投光装置、着色した予備ホース等の器材を搭載する。
オ、車庫、宿直室等を建設する。
カ、右の実施にあたっては、町職員の充分な理解と協力を得て行なうべきである。
(二)今後の消防近代化について
常備部設置と共に町建設計画の一環として計画的、段階的に推進すべき方策は非常に多いが、主なものを列挙する。
(1)定数、原則として出動可能な実数をもって定数とし、いわゆる出初め団員は整理する。
常備部設置と共に町建設計画の一環として計画的、段階的に推進すべき方策は非常に多いが、主なものを列挙する。
(1)定数、原則として出動可能な実数をもって定数とし、いわゆる出初め団員は整理する。
ア、当面、機動隊発足に伴い、定数は五百名程度に減員されるべきである。
イ、退団年限は今後三十五歳まで引下げるべきだが、地区の実状によっては例外も認める場合が考えられる。
ウ、将来、常備部の強化に伴い、更に妥当な線まで減員し、質的向上、精鋭化をはかるべきである。
(2)機構
ア、部の統廃合を実情に即して行ない、広域化、能率化をはかるべきである。
イ、本団、分団の機構改革を行ない、役員の減員、機構の簡素化をはかるべきである。将来、分団は廃止され、本部直結の形をとるべきである。
ウ、役員の選任方法についても人材本位とし、地区持ち回りのような慣例は改めたい。
エ、顧問は現在条例にも規則にも何等規定がなく、慣例的にくり上げ補充され無任期、無定員の観がある。又、一部には現場において指導命令系統に影響を与える事例も見られ、現役幹部より批判も出ている。
この際、顧問制度を批判的に再検討し、もし必要性があるならば法的にもその位置づけを明確にし、任期一年程度として、あくまで経験を生かした助言的役割を果たすよう改めるべきである。
オ、今後、政令改正により消防署設置基準の緩和、観光地に対する特例等が実現し、国の補助等の条件が整った場合には、積極的に消防署設置をはかるべきである。
(3)装備について
ア、今後の装備充実の重点を水利の強化におき、辺地部落に至るまで四〇立方メートル程度の貯水池を完備し、消火栓の充実をはかることが必要である。
イ、このため、現在実質四割以上地元負担となっている実情を軽減し、国、県補助を除く額の少なくとも七割程度を町が負担すべきであろう。
ウ、現在以上部の自動車ポンプの増設は行なわず、部落においては可搬式ポンプによる自衛を主眼とする。
エ、本部より各地域へ又現場における連絡を完全にすすめるための無線機、トランシーバー等の連絡器材を充実し、火災はもちろんあらゆる天災地変、混乱に対処できるようにすべきである。
(4)消防予算について
常設部充実に伴う一時的増加は当然のことであるが、団員の減少、機構の合理化による予算の節減を期するが、一方団員処遇の改善、住民の負担軽減、装備の近代化等の増額要因も考え合わせると、おおむね平年度一般財源の三%乃至最高五%の範囲で運営することがのぞましい。
(5)町独自の退職報償金制度を設けること
年限の切り下げ、整理等により十五年に達しない者の救済措置として、町独自の退職報償金制度を設け、円滑な処理を期すべきである。四十二年度の団員削減にあたって議会から強く要望されたにもかかわらず、一名二百円の退職報償金の増額がなされていないことは、まことに遺憾である。この点反省と善処を要望する。
(6)災害救恤金の増額について
現在最高額一〇〇万円と規定されているが、三〇〇万円に増額すべきである。
(7)団員の処遇の改善について
団長の私費支出が多い弊風を改めると共に少くとも年額三万円程度に報酬を引上げるべきである。(その他の役員についてもこれに準じて改正)団員についても最低年額一千円の本人支給及び出動手当の支給を行なうこと。
(8)出動基準の制定
出火時の出動規定を設け、連絡態勢の完備と相俟って無駄な出動等をなくし、効率化をはかるべきである。
(9)日常的予防活動の徹底
「火消し」から一歩進んで「火災を出さない」活動を強化することが消防の第一義的任務である。そのためには、消防法その他の法令基準に定められた日常的、定期的かつ巌正な査察、指導助言或は必要に応じた改善命令等を行なうべきであり、本団、分団、各部の段階毎に効果的に実施すること、火災期には月一回程度は必要である。特に旅館、宿坊、文化財、公共施設等を重視し、又、プロパン、油類等の取扱い、木造危険家屋等の指導に意を注ぐべきであろう。お座なりに堕している「カマド検査」の現状は実効がないと考えられるので、先ず末端より改めて行くべきであろう。
又、家庭における初期消火の器材、技術、知識の普及と指導(消火器の備え付け、防火用水、非常用蛇口、ホースなど考えられる)も重要である。
(10)団員の研修と訓練の徹底
新入団者に対し法規、技術等の研修を施し、消防要員としての実力を涵養することが必要であり入団時の宣誓さえ規則にありながら行なわれていない現状は改められるべきである。
幹部、団員とも日常的訓練と研修、専門研修機関への派遣等を通じてその資質を向上するとともに、住民に奉仕、自らの郷土を守る精神面における研修向上もはかることが大切である。
(11)服装について
当面ヘルメットの全員着用をはかるよう措置すべきである。今後なるべく早急に活動に便利な甲種制服の採用が望ましい。
(12)現場活動について
消防法二八条に基づく交通規制を徹底するため、本部、分団、各部に交通専門係を設け、安協の協力も得て現場における混乱を防ぎ、防火活動の万全を期すべきである。
ホースの夜間識別方法(蛍光剤等)水源と筒先の連絡方法等、科学的に改善をはかりたい。
機動隊車には予備ホース、中継槽等の器材を積載しておき、現場で必要に応じ貸与できるようにする。
命令系統の厳守と一本化は特に重要で伝達方法の改善とあわせ徹底をはかる。
(13)住民負担の軽減について
消防は自治体の責任であるとのたてまえから、住民の負担に大きく依存している現状を改めて行くべきである。
常設部充実に伴う一時的増加は当然のことであるが、団員の減少、機構の合理化による予算の節減を期するが、一方団員処遇の改善、住民の負担軽減、装備の近代化等の増額要因も考え合わせると、おおむね平年度一般財源の三%乃至最高五%の範囲で運営することがのぞましい。
(5)町独自の退職報償金制度を設けること
年限の切り下げ、整理等により十五年に達しない者の救済措置として、町独自の退職報償金制度を設け、円滑な処理を期すべきである。四十二年度の団員削減にあたって議会から強く要望されたにもかかわらず、一名二百円の退職報償金の増額がなされていないことは、まことに遺憾である。この点反省と善処を要望する。
(6)災害救恤金の増額について
現在最高額一〇〇万円と規定されているが、三〇〇万円に増額すべきである。
(7)団員の処遇の改善について
団長の私費支出が多い弊風を改めると共に少くとも年額三万円程度に報酬を引上げるべきである。(その他の役員についてもこれに準じて改正)団員についても最低年額一千円の本人支給及び出動手当の支給を行なうこと。
(8)出動基準の制定
出火時の出動規定を設け、連絡態勢の完備と相俟って無駄な出動等をなくし、効率化をはかるべきである。
(9)日常的予防活動の徹底
「火消し」から一歩進んで「火災を出さない」活動を強化することが消防の第一義的任務である。そのためには、消防法その他の法令基準に定められた日常的、定期的かつ巌正な査察、指導助言或は必要に応じた改善命令等を行なうべきであり、本団、分団、各部の段階毎に効果的に実施すること、火災期には月一回程度は必要である。特に旅館、宿坊、文化財、公共施設等を重視し、又、プロパン、油類等の取扱い、木造危険家屋等の指導に意を注ぐべきであろう。お座なりに堕している「カマド検査」の現状は実効がないと考えられるので、先ず末端より改めて行くべきであろう。
又、家庭における初期消火の器材、技術、知識の普及と指導(消火器の備え付け、防火用水、非常用蛇口、ホースなど考えられる)も重要である。
(10)団員の研修と訓練の徹底
新入団者に対し法規、技術等の研修を施し、消防要員としての実力を涵養することが必要であり入団時の宣誓さえ規則にありながら行なわれていない現状は改められるべきである。
幹部、団員とも日常的訓練と研修、専門研修機関への派遣等を通じてその資質を向上するとともに、住民に奉仕、自らの郷土を守る精神面における研修向上もはかることが大切である。
(11)服装について
当面ヘルメットの全員着用をはかるよう措置すべきである。今後なるべく早急に活動に便利な甲種制服の採用が望ましい。
(12)現場活動について
消防法二八条に基づく交通規制を徹底するため、本部、分団、各部に交通専門係を設け、安協の協力も得て現場における混乱を防ぎ、防火活動の万全を期すべきである。
ホースの夜間識別方法(蛍光剤等)水源と筒先の連絡方法等、科学的に改善をはかりたい。
機動隊車には予備ホース、中継槽等の器材を積載しておき、現場で必要に応じ貸与できるようにする。
命令系統の厳守と一本化は特に重要で伝達方法の改善とあわせ徹底をはかる。
(13)住民負担の軽減について
消防は自治体の責任であるとのたてまえから、住民の負担に大きく依存している現状を改めて行くべきである。
ア、器材、施設等の住民負担
イ、夜警などの労力奉仕
ウ、出火時の過大な地元負担
イ、夜警などの労力奉仕
ウ、出火時の過大な地元負担
これらはいずれも逐時軽減、廃止の方向に向うべきである。
(14)町ぐるみの消防(防災)協力組織について
防火防災は消防のしごとという考え方を改め、住民の日常生活の中に常に防火、防災の知識や技術をうえつけ、いつでも消防に協力して防災の実を挙げられるような地域ぐるみの消防協力自治組織が今後の消防態勢の大きな支えとなろう。
(14)町ぐるみの消防(防災)協力組織について
防火防災は消防のしごとという考え方を改め、住民の日常生活の中に常に防火、防災の知識や技術をうえつけ、いつでも消防に協力して防災の実を挙げられるような地域ぐるみの消防協力自治組織が今後の消防態勢の大きな支えとなろう。
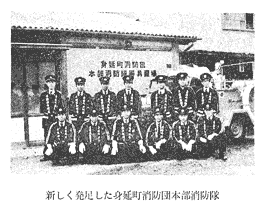 |
将来、消防署設置等により消防力が都市なみに専門化され、非常勤消防が補助的役割にかわり、更にこのような自治的組織に吸収されて行くかもしれないが、いずれにしても防火、防災は少数の専門機関のみに依存することはできないのであって、このような住民組織の重要性は時代の進行と共に増大すると思われる。
現在の婦人消防後援隊にも少なからず問題があり、今後地域ぐるみの消防協力組織の中に発展的解消することが望ましい。
(15)出初式は昔ながらの消防の象徴として式典中心に行なわれているが、若い世代の感情にそぐわず、形式にのみ流れているうらみもある。運営方法に再検討をのぞみたい。
現在の婦人消防後援隊にも少なからず問題があり、今後地域ぐるみの消防協力組織の中に発展的解消することが望ましい。
(15)出初式は昔ながらの消防の象徴として式典中心に行なわれているが、若い世代の感情にそぐわず、形式にのみ流れているうらみもある。運営方法に再検討をのぞみたい。
ア、来賓祝辞は、代表一名位とし紹介にとどめる。
イ、表彰はプリントして配付し、代表により一括授賞する。
ウ、実技発表、機械点検、講習訓練等により重点をおく。
また出初式は廃止し年一回の総合的訓練又は演習に改めることも研究すべきではなかろうか。
以上集約すれば専門的常備消防の育成強化による消防力の強化を軸に、それを補う非常勤消防の古い体質を大胆に改革し、その近代化と精鋭化をはかり、町財政負担と住民負担の軽減をはかりつつ、新しい時代にふさわしい自治体消防のビジョンを追求することが、本意見書の目的であり、町当局はこのような考え方に立って具体的な施策を積極的に講ずるよう要望する。
本町消防団も議会のこの動きに即応しながら、団員定数の削減、役員改選期の変更等つねに消防近代化への脱皮を図りつつあり、昭和44年9月議会では、町役場職員14名で構成する本部消防隊の新設が決定され、本部用の消防車の配置その他器材の整備と相まっていよいよ常設消防への第一歩がふみ出されたことはまことにたのもしい限りである。以上集約すれば専門的常備消防の育成強化による消防力の強化を軸に、それを補う非常勤消防の古い体質を大胆に改革し、その近代化と精鋭化をはかり、町財政負担と住民負担の軽減をはかりつつ、新しい時代にふさわしい自治体消防のビジョンを追求することが、本意見書の目的であり、町当局はこのような考え方に立って具体的な施策を積極的に講ずるよう要望する。

