第二節 各種の信仰形態
一 馬頭観世音 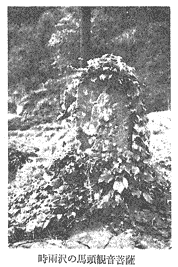 |
昔は盛大にお祭りを行ったが、馬を飼わなくなった今はあまりこの行事はみられない。部落の一隅に馬頭観世音と刻んだ石碑が昔をしのんで、大庭区、大工町区、大石野、波木井1区、城山、塩沢峯、元町殿前、梅平丈山、横まくり、梅平2区、梅平堰、大野荒久山、舟原志麻の沢、門野区、大久保堂平、清子舟越、古宿、下水久保、上八木沢、大崩、角打入、和田時雨沢、上大島などにさびしく立っている姿が見られる。
二 地神
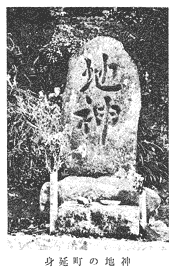 |
波木井1区八幡社境内、 西塩沢、元町岩の鼻、梅平宮原、上町区、相又上妙久寺上、大野。
三 産児神
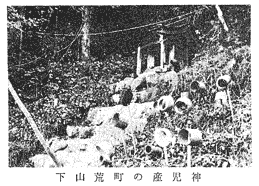 |
祭典に団子を供えて安産を祈る観音さま、妊婦が安産を願ってヒシャクに穴をあけて供える産児神等いろいろと変った習わしが今でも行われている。
四 秋葉神社
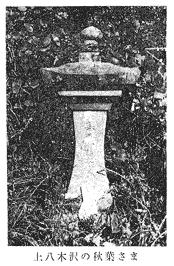 |
五 甲子講
梅平堰端の甲子講、椿草里の甲子講は、甲子の日に当番の家に集まって一日楽しく過ごす行事で今も行なわれている。
六 ほうそう神
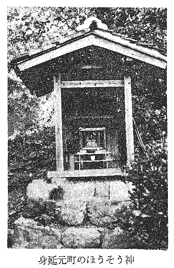 |
七 不動様
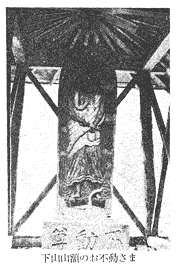 |
八 観世音堂
 |
帯金焼野の観音様は、牛馬等の転落死した霊を祀るとともに事故防止を祈念する。
河内三十三観音の一つである清子古宿観音堂は10月17日に祭典を行なっている。
九 清正公様
 |
祭典は8月24日に行なっている。
十 子の神
大石野子の神、丸滝子の神については詳しい資料がない。
大石野では正月17日に子供たちが弓をつくって納める習わしが残っている。
十一 聖徳太子堂
中谷二王門境内にあり、聖徳太子をお祀りし、門内の大工さんたちによる太子講々員が特に信仰厚く、正月2日の仕事始め、正月8日には例大祭を行ない1年を無事に仕事ができるよう祈念する。なお村々にもあったが今は行なわれていない。
十二 鬼子母神堂(別に十如坊ともいう)
創立明応3年(1494年)11世日朝代。
身延山上の山にあり、鬼子母神さまをお祀りしている。伝説によればお厨子は古い時代本山の宗祖尊像奉安の厨子で、その外4本の柱は宗祖御在世時代の御草庵の柱であったと伝えられ、明応3年の日朝上人の棟札の写と、永享6年の日学上人の板本尊が保存されている。毎月8日は命日、9月20日に上町区3組で盛大な祭典が行なわれている。
十三 その他
この外信仰の対象としてお祀りしてあるいくつかの神々の中に、説明のできないものもあるので、簡略に列記して紹介することにする。
| ○ | 粟倉大石野にある大日如来は、昔早川町差越の大屋の女中オセンが非業の死をとげたので、オセンの霊を供養するため祠を立て、お祀りしたといわれている。 |
| ○ | 波木井1区の恵比寿は商売繁昌の神として、各職人が毎年1月に恵比寿講を行なっている。 |
| ○ | 大野区においては昭和39年より区内にお祀りしてある9神社の祭典日を統一して、10月17日に行なっている。妙法神、熊谷稲荷八幡社、諏訪神社、加茂神社、大野部落に田用水を引くために大野堰を開さくした、日寛上人謝恩の祭典等もこの日に合わせ行なっている。 |
| ○ | 小原島一円寺境内にある大黒天は、お祀りしてあるが行事は行なっていない。 |
| ○ | 下山本町二十三夜講、門野の二十三夜講は月の23日、本町二十三夜講は隔月23日に組ごとにお題目を唱えて各戸を回る。門野にはこの外二十日講、二十八日講があり、当番の家に集まってお題目を唱えている。 |
| ○ | 大城区では2月1日区内の各神社に五穀豊穣を祈願し獅子舞を奉納する。 |
| ○ | 帯金上小路の薬師堂には木喰上人作の木像があり毎年9月8日に祭典を行なっている。帯金静仙院境内の虚空蔵様のお祭りは旧8月15日に五穀豊穣を祈願して行なわれる。 |
| ○ | 秋祭りとして10月16日、17日甘酒等を振舞って祭典を行なう和田原の金山神社、米倉の権現様は春祭りとして6月16日、17日の2日間甘酒を振舞って祭典を行なう。 |
| ○ | 下山竹下区の御八朔は季節の変りで夜業始めの行事として、8月31日八朔祭りの祭典を行なっている。竹下区の風祭りは町境内に〆縄を張り、御神酒、鈴など供えて嵐を除け、作物の豊作を祈願する祭が、毎年9月1日に行なわれている。 |
| ○ | 下山地区一円に行なう秋祭、秋の稔りを神に報告し町内安全を祈願する。 祭典は10月15日に行なわれている。 |
| ○ | 塩之沢金竜寺山南山々頂の妙法大明神は火伏せの神として、弘化4年7月勧請金竜寺檀家中で毎年8月17日に祭典を行なう。 |
| ○ | 花火で有名な下山新町愛宕堂の祭典は戦前は毎年23日であったが若者の帰郷期間が短くなったので現在は8月16日に行なわれる。200、300年前より無火災、家門繁栄、町内安全を祈願している。当日は近在近郷から参詣の人で賑わい、祭典は盛大に行なわれる。 |
| ○ | 波木井西平思沢のお天白様は毎月17日がお逮夜で部落中でお詣りする。11月17日 の祭典には近在からの参詣者もある。 |
| ○ | 西塩沢の日興様、神明大明神、梅平宮原の「めようとう様」堰端の新羅明神、芦沢の三光天神、舟原の妙法神、光子沢下組の塚、横根間々下の東照宮、上八木沢向山の天王神社、下八木沢の金比羅さま、椿草里の沢の神、大崩の三石大明神、熊野権現、上大島の金刀比羅さま、金山さま、五輪の碑、下山本町の願満講、清子矢口の神明社、丸山の諏訪社、舟越の妙見堂、芝原の妙法神、塩之沢林前組の御崎大明神、波木井坂下の浜松明神、相又坂本裏山の妙法神、丸滝の流水宮、妙見様等それぞれ心願満足を祈念してお祀りし、部落によって祭典日を定めて行事を行なっている。 |
| ○ | 本国寺の日朝さん。 祭典は8月24日夜行なわれている。眼病守護の仏である。 なお「甲斐路」(昭和41年12月号80頁)において、清雲俊元が「身延山の守護神」の項に、 「身延山には多くの守護神が見られる。その一に考えられることは日蓮聖人が、文永十一年身延草庵に入るにあたり、土地の神祗(ぎ)信仰を積極的に導入して、習会思想を盛んにしたことにある。」とし、その研究を記されているが、確かにそうした点も考えられる。 |

