第十節 鰍沢林務事務所身延営林区
1 所在地 身延町角打1,087番地2 沿革 明治44年3月11日
明治40年、明治43年と重なる山梨全県下大水害救恤の御心より明治天皇ご下賜の恩賜県有財産実測面積約18万6千ヘクタールはその後、在御料林および民有地等を買い受けた反面、不要在地林野として町村に売払ったものおよび水道水源林として東京都をはじめ神奈川県横浜市および甲府市等へ売払ったもの、演習地として旧日本陸軍へ移管したもの自作農創設特別措置法による政府売払い等があり、現在の県有林面積は156,885ヘクタールと山梨県森林面積340,386ヘクタールの46パーセントを占めている。
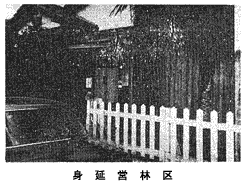 |
昭和13年12月、機構改革が行なわれ出張所を林務署と改称し県下に甲府、塩山、韮崎、鰍沢、大月、吉田、栄と7林務署を設置すると同時に現地担当として分担区を47ヵ所に設置した。
昭和25年8月、時代の推移と県有林経営のみを専門的に行なう必要から5営林事務所(韮崎、鰍沢、塩山、大月、吉田)を設置し現地担当の営林区を25ヵ所設置し管理経営業務に当たってきている。
昭和28年、再び民有林行政および森林土木(治山、林道)業務を含めた総合林務行政を行なう林務事務所を甲府市を加えた6ヵ所に設置し担当営林区として35ヵ所配置し現在にいたる。
3 管轄区域
身延営林区は県の最南端温暖多雨の気候に恵まれ、数々の杉檜の有名林業地をもつ富沢町に面積644ヘクタール南部町に785ヘクタールをもつ南部営林区と身延町内2,182ヘクタールの県有林をもつ身延営林区計3,611ヘクタールを管理する。その地勢は最南端富沢町の標高400メートル付近から身延町サワラ森の2,000メートル付近に至る急しゅんな山岳地でその地質は泥板岩、砂岩、堆積礫岩から成る三倉統群で占められ軟弱な山地を形作っている。資源としては昭和40年度調査によると針葉樹29,000立方メートル、広葉樹192,000立方メートルの計221,000立方メートルとなっており針広の混淆歩合は針葉樹13パーセント、広葉樹87パーセントとなっている。
4 業務内容処理件数等について
県有林3,611ヘクタールの管理を主業とし、主産物調査(立木関係)に関する業務一切、造林関係(測量、地ごしらえ、植付、下刈)の監督指導一切並びに山葵(わさび)田貸付地外植栽貸付地等関係一切の外に境界の維持管理並びに部分林関係等管内に生ずる全部の問題について所長の命によりその任に当たっている。次に年間の業務内容は次の通りである。
主産物収穫業務 6,000ヘクタール 継続貸付地調査 10件
造林面積 約80ヘクタール 部分林関係調査 500ヘクタール(300立方メートル)
5 現況とその動向管内面積3,611ヘクタールのうち昭和43年度までの植栽面積は約800ヘクタールであるが人工造林の始めは昭和7、8年頃より南部町上佐野地区及び身延町鷹取山等比較的人家に近いところより始められたがその面積はわずかなものであった。第二次世界大戦終了の昭和20年までには約60ヘクタールの造林面積であったがその後木材の需要が増すにつれて奥地林の伐採が進行し、跡地更新の必要から人工造林面積も増加の一途をたどり、昭和30年までには約140ヘクタールを植栽、次の昭和40年までの10年間に340ヘクタールの植栽を完了した。しかし本地方は県の最南端に位置し気象並びに地理的条件に恵まれ、杉檜の優良林地を造成できる可能性の高いこの林地に広葉樹を繁茂させておくことは得策でないとの見地から、残存する広葉樹の粗悪林分の優良樹種への林種転換を計画したところ、たまたま今まで顧みられなかった広葉樹の利用価値が高まったことと、搬出施設の改善が進んだことと相まって伐採計画が順調に進行したために昭和41年度より43年度までに260ヘクタールの人工造林が終了しているがまだ全体面積の約22パーセントに過ぎず、今後も人工による更新が可能な地にはでき得る限り植栽を行ない、将来全体面積の50〜60パーセントまでに人工造林地をもってゆく計画である。

