第三節 地質
一、地質分布概観
身延町の地質で特記すべきは何といっても、フォッサマグナ(大地溝帯)と糸魚川−静岡構造線であるがまず富士川の東側には毛無山系の五宗山・三石山などの1,000メートル以上の山なみがつづき、一段低く700〜800メートルの山地が地塊的に分立し、さらに高度をさげ富士川に没している。この地域一帯のほとんどは静川層群といわれほぼ南北の方向に延び、礫(れき)岩を主体とし砂岩・泥(でい)岩などから構成されている。礫岩は硬質であるので富士川に急斜面をむけ特異な急しゅんな地形をつくっている。御持川(椿川)の源流地、五宗山付近は閃(せん)緑岩、石英閃緑岩が貫入しており南部町方面にも分布している。大部分は礫岩からなるが、貫入岩のため熱変成をうけ、岩質もかたく急崖を呈している。それらの地塊を横断して御持川、桑柄沢をはじめ、多くの河川が東西の方向に流路をとり、富士川に合流している。
東部山地と対称的に西側に
身延山の東部から清住町を経て相又川にそい榧の木トンネル、横根、南部町北原を結ぶ断層を北部では富士見山断層、南部を榧の木断層とよんでいる。この断層線より東部を静川層、西部を
身延山の西側は、いわゆる糸魚川−静岡構造線と称する一大断層線によって西方の七面山、安倍峠、その他1,000メートル以上の山なみを構成している山地を、中生層と呼んでいる。この構造線にそって早川や支流の春木川が流れ角瀬付近で流向を東に転じ飯富付近で富士川に合流している。春木川は断層谷で、白糸滝付近は
二、大地溝(こう)帯と糸魚川−静岡構造線
糸魚川−静岡構造線は日本列島をほとんど中央部において横断し、日本列島を東北日本と西南日本の2つに区分するもので、日本の地質図を大観すると、だれでもその存在に気がつくことができる。構造線とは断層線の1つでその断層を境として両側の地質構造がまったく異なる場合に構造線といわれている。
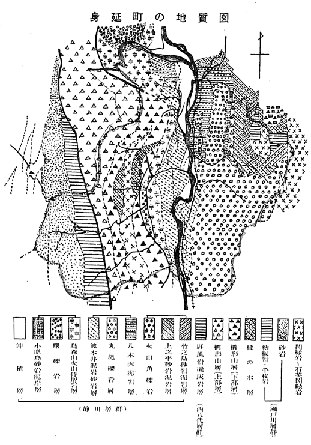 |
フォッサマグナの西縁をなす糸魚川−静岡構造線は北より、新潟県の糸魚川、長野県の大町、松本盆地、塩尻、諏訪盆地、本県に入り韮崎、甲府盆地の西部から南巨摩郡の西部をとおり、静岡市におよぶ線である。本地域における糸魚川−静岡構造線は早川谷を南下し春木川を経て大城川の大城−古谷城間を通過し、相又川上流から戸栗川上流、折付−音下間を通過し、剣抜の南方から富沢町を経て静岡に達している。井尻博士は大城−古谷城間において西方の古期砂岩頁(けつ)岩層が、東方の橄欖(かんらん)石玄武岩と逆断層(走高北10度西、傾斜80度西)で接触する露頭を観察している。また南部町戸栗川上流の折付−音下間において大体同様な岩相の関係において断層面(走高北30度西、傾斜65度北西)を認めている。その大城川を横ぎる場所は、大城川の上流、赤岩橋の上流300メートル位の地点の左岸にみとめられた。赤岩橋付近は、
三、各地層の詳説
(一)瀬戸川層群
南北方向に流れる春木川を通る糸魚川−静岡構造線の西側にある地層を瀬戸川層群とよんでいる。身延町の飛地である七面山を構成する地層を、瀬戸川層の角瀬砂岩層とよんでいる。ア、角瀬砂岩層
この層は七面山の東と西の斜面に広く分布している。特に角瀬付近に露出する岩石を、代表して角瀬砂岩質と名づけられ、七面山塊を構成するのはほとんどこの砂岩である。おもに淡灰色の硬質塊状の砂岩からなり、ところどころに粘板岩の〃はさみ〃をもっている。七面山の裏参道角瀬付近の礫はこの岩石である。山頂付近は粘板岩・千枚岩・砂岩などの互層からなり、走向はほぼ南北方向で春木川を境に東側の
大城川上流、赤岩橋付近より西側は走向北10度西、傾斜西80度〜90度で砂岩、頁岩の互層からなり、古谷城下方の大城川岸ではよくこの状況が観察される。古谷城の上方では粘板岩の露出がみられ、節理が著しく発達し、千枚岩化し、地質はきわめて脆(ぜい)弱となっている。
相又川上流の瀬戸川層中には、多数貫入岩床として玄武岩がみられることは注目すべきことである。このことは、糸魚川−静岡構造線は現在の小断層の存在にかかわらず、かって火成岩(玄武岩)の貫入関係にあったことを明らかに示すものである。以上のほかこの玄武岩中に相当広範囲に瀬戸川層の捕獲岩が存在している。大きな岩塊の一部は頁岩で一部は玄武岩であることがしばしば観察される。
(二)新第三紀層群
ア、桃の木層(中山層)および桃の木層は中巨摩郡桃の木鉱泉付近を中心に南北に分布し、おもに砂岩・頁岩・礫岩よりなる地層に命名されたものであり、
久遠寺付近に分布している頁岩は層位上から桃の木層に属するものと考えられる。
久遠寺黒色頁岩(桃の木層)
久遠寺の河床に露出しているものに代表されるもので、女坂付近にも露頭がみられる。南方へ分布し、小田船原西方の大倉沢に広く露出している。黒色緻(ち)密のやや珪質の頁岩であるが石英閃緑岩〜閃緑
イ、
中富町富士見山嶺および身延山、鷹取山一帯に分布している。身延町内では、身延山東山腹で烏森山火山砕屑岩層と逆断層で接している。身延町元町付近から身延川に沿って露出する安山岩、角閃
高座石付近では閃(せん)緑
高座石付近から願満堂、願満大社を経て追分に通ずる参道にそって、角閃
ウ、
春木川東部に帯状に広く分布している。ことに早川横谷部から南方の追分にかけて著しい。おもに層理に乏しい黒色凝灰角礫岩よりなり、その他、黒色凝灰岩・黒色火山礫凝灰岩も多く、ところどころに黒色頁岩のレンズをはさんでいる。
追分付近を西に進むと石英閃緑岩の脈岩が変質され着色された露頭がみられるが、それをすぎると十万部の西に砂岩・頁岩の互層するところに断層線が落差1メートル内外で数か所にみられる。
(三)静川層群
中富町静川一帯に分布する地層を代表して静川層群とよんでいる。ア、八木沢泥岩層
波高島から富士川沿岸ぞいに南に分布する。八木沢付近の富士川河崖に露出する地層から八木沢泥岩層、または鰍原泥岩層ともよんでいる。北部では東−西性走向をもち、南へいくにしたがって北−南性走向になっていき、しだいに層の厚さも減じ椿草里西方では50メートル位になっている。この層はおもに暗灰色の泥岩からなり、南方にいくほど砂岩や細礫岩がはさまれてくる。また、この地層から小型有孔虫の化石や植物の化石も発見されている。下八木沢−帯金間の身延線トンネル上には、この八木沢泥岩層の上部層にあたる淡褐色凝灰質泥岩がはさまれている。また、上八木沢にはこの部層中に幅2メートルの粗粘玄武岩の岩床があり、周囲の泥岩に変質され硬質緻密なホルンフェルス状の岩石もみられる。下山の北沢・大沢にはこの部層の上部に分級度の低い礫岩などがみられる。さらに、この地点の北部に上の平砂岩泥岩層が分布し、走向東−西性で厚さ5センチメートル内外の灰色砂岩と黒色泥岩との規則正しく美しい互層が早川河底にみられる。
イ、丸滝礫岩層
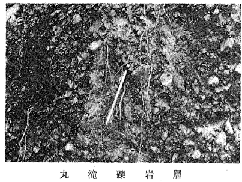
|
しかし、下八木沢−塩之沢間の礫岩は丸滝礫岩層とはいちじるしく異なり、層理に乏しく、軟弱で礫も淘汰(とうた)悪く雑然としている。また、礫種は上記のもの以外に、丸滝礫岩のものと思われる礫や、八木沢泥岩層のものと思われる泥岩などの円礫を含んでいる。さらに、塩之沢北方1キロメートル地点では、この礫岩中に上記泥岩円礫のほかに花崗岩礫も混じり、八木沢泥岩に不整合で接している。この軟弱な礫岩層は丸滝礫岩層の上位層と考えられ、中富町曙一帯に分布する曙礫岩層に相当するものではないかといわれている。
丸滝礫岩層は、椿草里部落では追跡できないが、大崩部落の東部山嶺地域では石英閃緑岩の影響をうけて、ホルンフェルス化している。この地域の石英閃緑岩は、南部方面に分布している。
ウ、波木井泥岩層
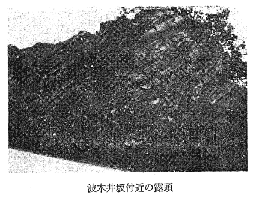
|
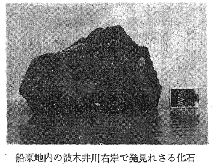
|
総門付近より東側にかけて、灰色〜黄褐色の層理の明瞭な砂岩が、波木井川河岸にほぼ南北の走向で、傾斜垂直に近い地層が分布している。
塩沢付近に入ると、砂岩と泥岩の互層で泥岩がちの地層である。この泥岩は青灰色を帯び風化して細かく割れる。化石を含み部分的には浮石質になっている所もある。波木井坂の西で、この層の上部に厚さ5メートルの海緑岩砂岩がみられるが、あまり連続していないようである。
その東側、波木井橋付近までは波木井坂南の沢沿いの露頭で代表する地層であり、砂岩と泥岩との互層で境ははっきりしており、波木井橋付近では約30メートルの礫岩質砂岩をはさんでいる。
エ、烏森山火山砕屑礫岩層
中富町早川橋から観音橋に至る道路沿いの露頭に命名された地質で岩相変化に富み、おもに複輝石安山岩質の火山角礫岩・凝灰角礫岩・凝灰岩・凝灰質砂岩および泥岩などからなり、特に凝灰質砂岩や泥岩は古屋敷付近から南にしだいに厚くなる。身延地区元町付近に角礫安山岩・輝石安山岩・溶岩などの火成岩を角礫にもつ暗灰色〜暗褐色の凝灰角礫岩の露頭がみられ、さらに南にのび梅平付近の山地・北清子・大久保付近の山地を構成している。古屋敷の沢には淡緑色軽石質(石英安山岩質)凝灰岩がはさまれており、杉山の北の当子沢には沸石、方解石の杏仁粒(きょうにんりゅう)を含む玄武岩の火山角礫岩が露出している。
オ、小原島砂岩泥岩層(静川砂岩層)
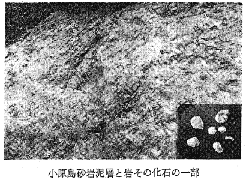
|
カ、曙礫岩層
相又川の小田船原付近や大城口・豊岡の学校南・さらに南部町城山付近などに細く曙礫岩層の小露出がみうけられる。曙礫岩層は中富町曙一帯の標準露出に命名された礫岩層で砂岩の薄層をはさんでいる。礫は径20センチメートル以下の円礫で、礫種は硬砂岩・頁岩・粘板岩・それらのホルンフェルスで、その他に、御坂層起源のものと思われる閃雲花崗岩、石英閃緑岩、
四、第四紀層
(一)洪積層
ア、段丘堆積物段丘堆積物は富士川・早川・波木井川などの諸河川およびその支流の河岸付近に大小数多く点在している。構成物は礫および砂よりなり粘土を表土としており、農耕地や住居として多くの住民の生活の基盤となっている。

|
中位段丘−現河床から7〜8メートル以上の高所にやや明瞭に形態を残して存在する。
低位段丘−現河床から2メートル以上の高所にほぼその現形を残している。
この高、中、低の三段丘にあたる地域例をあげれば、波木井古屋敷などは高位段丘であり、大城、湯平、波木井坂などは中位段丘としてあげられ、低位段丘は下山、波木井、梅平、帯金など数多くあげられる。
特に梅平、鏡円坊付近の段丘は三段階のようすがよく残っており段丘の典型的なものである。
(二)沖積層
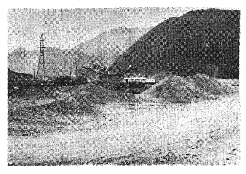 下山地区の砂利採集場 |
五、鉱物資源
(一)硅藻土
七面山頂の池は東西にせまく敬慎院の平坦地にあり、通常一の池と呼んでいる。背後(西方)に200〜300メートルの急斜面をもって山稜がつづいている。池には灰白色土状物質が化石状に堆積した珪藻(そう)土があり、現在も無数の珪藻が生息浮遊してさかんに堆積土をつくりつつある。池底には1メートル内外の堆積土をつくり、その上層部では半化石の珪藻類、水中に生活する珪藻類が順序よくみられる。珪藻類の種類をあげてみると、フラシラリヤ・ジャトマ・ナビィキラ・メラシラ・エセセミヤ・シネドラなどがあげられる。この珪藻土を乾燥させたものが「お土」である。
(二)沸石
大城付近の凝灰岩中にはいちじるしく杏仁状沸石、または沸石の薄い脈がところどころ横ぎっているのがみられる。奥川橋付近にすばらしい露頭がみられる。この成因については、凝灰岩結成のさい、輝緑岩や武岩質の火成岩の迸入にあい変質のさい、さかんにガスを放出し岩石に多くの気孔を生じ、一方には方解石の沸石化作用をおこし、この現象を呈したものといわれる。相又川流域にもみられ、(三)銅鉱床
榧の木トンネルの南の県道わきに銅鉱床があり採鉱されたが、現在は廃坑になっている。この鉱石は黒−灰色の輝銅鉱と緑色の孔雀石で、輝銅鉱は鉱物としては非常に珍しく美しい結晶面をもっている。大久保部落にも鉱床があり、現在採鉱している。湯平には金鉱を掘ったといわれる廃坑がみられるが、おそらく段丘地形の中における砂金の採鉱跡であろう。

