第二章 気象
第一節 気象の概況
本県の南端に位する身延町は、本県における温暖多雨区の南部町に次ぎ温暖で雨量も多い。いま気温と降水量について、県下各地と比較してみると表1のようになる。表1 各地の平均気温と降水量 (明治34〜昭和25年) 山梨県気象年報
| 月 観測所 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
全年
|
|
|
身 延
|
℃
|
3.5
|
3.4
|
7.9
|
13.0
|
17.4
|
21.8
|
25.9
|
26.6
|
23.1
|
16.7
|
11.3
|
5.7
|
14.7
|
|
㎜
|
58
|
63
|
106
|
158
|
124
|
275
|
170
|
244
|
236
|
307
|
138
|
65
|
1,944
|
|
|
南 部
|
℃
|
3.7
|
4.5
|
8.0
|
13.4
|
17.6
|
21.5
|
25.4
|
26.0
|
22.9
|
16.9
|
11.4
|
6.0
|
14.8
|
|
㎜
|
78
|
98
|
106
|
212
|
196
|
218
|
278
|
329
|
397
|
263
|
129
|
92
|
2,519
|
|
|
鰍 沢
|
℃
|
2.0
|
3.2
|
7.3
|
13.3
|
17.5
|
21.7
|
25.8
|
26.5
|
22.6
|
16.1
|
9.8
|
4.3
|
14.2
|
|
㎜
|
45
|
68
|
102
|
114
|
113
|
163
|
170
|
199
|
234
|
177
|
88
|
57
|
1,530
|
|
|
甲 府
|
℃
|
2.0
|
3.2
|
7.2
|
13.2
|
17.4
|
21.8
|
26.1
|
26.6
|
22.7
|
16.0
|
10.2
|
4.5
|
14.2
|
|
㎜
|
37
|
51
|
77
|
83
|
92
|
136
|
137
|
175
|
198
|
138
|
69
|
46
|
1,239
|
|
|
韮 崎
|
℃
|
1.7
|
2.8
|
6.6
|
12.8
|
17.0
|
21.1
|
25.4
|
26.1
|
22.0
|
15.8
|
9.5
|
4.1
|
13.7
|
|
㎜
|
39
|
53
|
77
|
95
|
98
|
146
|
145
|
155
|
195
|
142
|
66
|
46
|
1,257
|
|
|
小淵沢
|
℃
|
-0.7
|
-0.4
|
3.4
|
9.1
|
14.1
|
17.9
|
22.2
|
22.6
|
18.8
|
12.5
|
7.4
|
1.7
|
10.7
|
|
㎜
|
39
|
50
|
77
|
99
|
107
|
174
|
146
|
133
|
187
|
134
|
69
|
43
|
1,258
|
|
|
日下部
|
℃
|
1.8
|
2.8
|
6.8
|
12.9
|
17.1
|
21.5
|
25.5
|
25.8
|
22.2
|
15.6
|
9.6
|
4.2
|
13.8
|
|
㎜
|
34
|
48
|
69
|
80
|
91
|
140
|
151
|
171
|
185
|
133
|
64
|
42
|
1,208
|
|
|
大 月
|
℃
|
2.4
|
3.3
|
5.3
|
12.3
|
16.5
|
20.0
|
24.7
|
25.3
|
21.9
|
15.0
|
9.7
|
5.0
|
13.5
|
|
㎜
|
30
|
57
|
56
|
91
|
105
|
236
|
203
|
216
|
203
|
255
|
91
|
54
|
1,597
|
|
|
山 中
|
℃
|
-2.7
|
-2.5
|
1.6
|
7.6
|
11.8
|
16.1
|
20.0
|
20.3
|
17.1
|
11.3
|
5.9
|
0.4
|
8.9
|
|
㎜
|
68
|
107
|
164
|
191
|
181
|
273
|
254
|
326
|
368
|
308
|
156
|
89
|
2,485
|
|
まず、年平均気温についてみると、山中より5.8度高く、小淵沢よりも4.0度高いが、甲府と比較してみると意外にも0.5度高いだけである。これは大陸性気候のため夏期に盆地の気温が急上昇し、峡南地区よりもかえって高温となるためであり、身延町の年平均14.7度という数字は、主として冬期の温暖によるところが大きい。
次に、降水量についてみると、年間1,944ミリを記録し、山中、南部に次いで3位となっている。表2のクライモグラフは身延と甲府の気候を対比したものであるが、甲府が内陸性の特色をもつ、いわゆる中央高地式の型であるのに対して、身延は海岸気候にやや近い特色を示している。
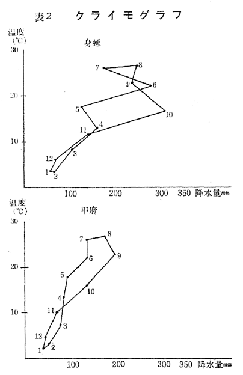
|
| 1、 | 温暖多雨区−年平均気温14度以上で年間の降水量は2,000ミリをこえて、湿度が高く、気候温和で積雪は、年数回、海岸的気候に近い地区。 |
| 2、 | 温暖中雨区−年平均気温12度〜14度で、降水年量1,400〜2,000ミリで多分に内陸的気候の地区。 |
| 3、 | 温暖小雨区−年平均気温12度〜14度で気温較差が大きく、降水年量は1,400ミリ以下で、非常に乾燥し内陸性気候の典型的地区。 |
| 4、 | 寒冷多雨区−年平均気温11度以下で、1月2月の平均気温は零度以下となり、降水年量2,000ミリを突破する地区。 |
| 5、 | 寒冷中雨区−年平均気温12度以下で、年降水量1,400〜2,000ミリの地区。 |
| 6、 | 寒冷小雨区−年平均気温12度以下で、1月2月の平均気温は、いずれも零度以下となり、年降水量は1,300ミリ前後で非常に乾燥する地区。 |
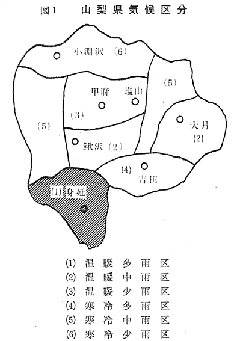
|

