第二節 気象要素
一、気温
(一)気温の変化
一般にいわれる春暖、夏暑、秋涼、冬冷の現象を年間の気温の変化の上からみて、どこで区切るかについては、いろいろ考え方があると思うが、ここでは、山梨県気象年報における次の区分の方法に従って、身延町の四季を区分し、甲府と比較しながら、その季の特長等について述べてみる。身延町の年間の気温の変化については、1951年から1960年までの十年間、身延高等学校で観測したものである。
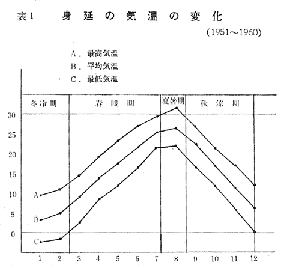
|
春暖期−気温が0度以上、30度以下の範囲内で変化する期間。
夏暑期−最高気温が連日30度を必ず越える期間。秋涼期−春暖期と同様。
冬冷期−最低気温が必ず氷点下に下がる期間。
ア 春暖期、この期をさらに次の三期に区分できる。
(ア)交代期 気温は零下を脱して強く上昇しはじめ、日中の最高気温は20度近くなることも珍らしくないが、天気は動揺しやすく、暖湿で南風の快晴があるかと思えば北風の寒冷な日もある。
(イ)晩霜期 高気圧性の快晴が多く、日中の最高気温は20度を越え、初夏を思わせるが、夜間は急に気温が低下して時に降霜をみる。
(ウ)梅雨期 6月中旬より7月上旬までの陰湿な曇天、雨天の続くこの期は、気温がやや低めとなり、日照時間は極めて少なくなる。身延町においては、春暖期は約4ヵ月で、この期の前後を通じ約1ヵ月間甲府よりも長くなっている。
イ 夏暑期 この期は、梅雨前線の北上通過により、陰気な天気から解放されて本格的の夏となる。最高気温は連日30度を必ず突破し、平均気温は25度以上、最低気温は20度以下にはならない。本町の夏暑期は短く約1ヵ月である。
ウ 秋涼期 春暖期同様気温は0度より30度の間で変化し、本町では9月上旬より12月下旬までの約4ヵ月 である。この期の前半は多湿な台風期であり、後半は静穏な多照期である。
である。この期の前半は多湿な台風期であり、後半は静穏な多照期である。
エ 冬冷期 氷点上のみで変動することのまったくない期間で、夜間は必ず氷点下に下がる。12月の下旬より2月の中旬までの約2ヵ月間である。なお最も寒いのは、1月の中旬より2月の初旬までであるが、甲府に比較すればやや暖かい。
(二)最高最低気温
南部観測所開設以来六十年間の記録をみると、南部町における最高の極は、昭和6年(1931)8月28日の40度であり、最低の極は昭和11年(1936)2月2日の氷点下11.6度である。次に、1951年から1960年までの身延・甲府・南部・鰍沢の最高、最低気温を示すと表2の通りである。最高気温の平均をみると、身延南部と甲府鰍沢とはわずか0.2−0.3度、最低気温では身延と甲府の差は0.7度である。これを内容的にみると、身延南部が年間を通じ徐々に気温が上下しているのに対して、甲府鰍沢は盆地特有の夏と冬の気温の変化のいちじるしさがはっきり出ている。これに対し、身延南部は海岸的気候にやや近い気候といえる。
1951−1960年までの天気現象日数は表3の通りである。
表2 最高・最低気温身延と甲府、南部、鰍沢との比較 (1951〜1960)
|
項目
|
月 地名 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
全年
|
|
最
高 |
身 延
|
9.3
|
10.8
|
14.6
|
19.5
|
23.6
|
27.2
|
29.4
|
31.1
|
27.0
|
21.9
|
17.0
|
12.2
|
20.2
|
|
南 部
|
9.7
|
11.2
|
14.4
|
19.4
|
23.5
|
25.9
|
28.9
|
30.8
|
26.9
|
22.1
|
17.3
|
12.9
|
20.3
|
|
|
鰍 沢
|
8.2
|
10.0
|
14.0
|
19.5
|
23.4
|
26.3
|
29.7
|
31.4
|
26.6
|
21.6
|
16.4
|
11.4
|
20.0
|
|
|
甲 府
|
8.3
|
10.1
|
14.2
|
19.6
|
23.3
|
26.4
|
30.0
|
31.4
|
26.9
|
21.6
|
16.6
|
11.5
|
20.0
|
|
|
最
低 |
身 延
|
-2.4
|
-1.1
|
2.5
|
8.1
|
11.8
|
16.5
|
21.2
|
21.8
|
18.5
|
12.2
|
6.0
|
0.1
|
9.6
|
|
南 部
|
-1.4
|
-0.4
|
2.8
|
8.3
|
12.3
|
16.9
|
21.1
|
22.2
|
18.8
|
12.8
|
6.9
|
1.2
|
10.2
|
|
|
鰍 沢
|
-2.9
|
-1.7
|
2.1
|
7.3
|
11.2
|
16.4
|
21.0
|
21.7
|
18.2
|
11.3
|
5.0
|
-0.6
|
9.1
|
|
|
甲 府
|
-3.5
|
-2.1
|
1.8
|
7.0
|
11.1
|
16.6
|
21.4
|
21.9
|
18.2
|
11.2
|
4.6
|
-1.1
|
8.9
|
表3 天気現象日数 (1951〜1960)
|
月
|
雨
|
雪
|
霰
|
雹
|
霧
|
濃煙霧
|
雷電
|
霜
|
霜柱
|
結氷
|
快晴
|
曇天
|
|
|
1
|
累計
|
57
|
19
|
5
|
0
|
5
|
0
|
0
|
192
|
551/7
|
224
|
148
|
99
|
|
平均
|
5.7
|
1.9
|
0.5
|
0
|
0.5
|
0
|
0
|
19.2
|
7.9
|
22.4
|
14.8
|
9.9
|
|
|
2
|
累計
|
58
|
20
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
130
|
541/8
|
177
|
118
|
113
|
|
平均
|
5.8
|
2.0
|
0.1
|
0
|
0.1
|
0
|
0
|
13.0
|
6.8
|
17.7
|
11.8
|
11.3
|
|
|
3
|
累計
|
102
|
6
|
1
|
0
|
3
|
0
|
3
|
74
|
71/7
|
70
|
94
|
145
|
|
平均
|
10.2
|
0.6
|
0.1
|
0
|
0.3
|
0
|
0.3
|
7.4
|
1
|
7.0
|
9.4
|
14.5
|
|
|
4
|
累計
|
114
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
1
|
13
|
0
|
1
|
76
|
157
|
|
平均
|
11.4
|
0
|
0
|
0
|
0.5
|
0
|
0.1
|
1.3
|
0
|
0.1
|
7.6
|
15.7
|
|
|
5
|
累計
|
121
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
491/8
|
1311/8
|
|
平均
|
12.1
|
0
|
0
|
0
|
0.3
|
0.1
|
0.5
|
0
|
0
|
0
|
6.1
|
16.4
|
|
|
6
|
累計
|
133
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
30
|
206
|
|
平均
|
13.3
|
0
|
0
|
0
|
0.2
|
0
|
0.5
|
0
|
0
|
0
|
3.0
|
20.6
|
|
|
7
|
累計
|
135
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
12
|
0
|
0
|
0
|
39
|
177
|
|
平均
|
13.5
|
0
|
0
|
0
|
0.4
|
0
|
1.2
|
0
|
0
|
0
|
3.9
|
17.7
|
|
|
8
|
累計
|
126
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
11
|
0
|
0
|
0
|
59
|
148
|
|
平均
|
12.6
|
0
|
0
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
1.1
|
0
|
0
|
0
|
5.9
|
14.8
|
|
|
9
|
累計
|
148
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
0
|
0
|
0
|
48
|
179
|
|
平均
|
14.8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.6
|
0
|
0
|
0
|
4.8
|
17.9
|
|
|
10
|
累計
|
124
|
0
|
0
|
0
|
8
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
74
|
163
|
|
平均
|
12.4
|
0
|
0
|
0
|
0.8
|
0
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
7.4
|
16.3
|
|
|
11
|
累計
|
85
|
0
|
1
|
0
|
8
|
0
|
1
|
53
|
4
|
13
|
128
|
100
|
|
平均
|
8.5
|
0
|
0.1
|
0
|
0.8
|
0
|
0.1
|
5.3
|
0.4
|
1.3
|
12.8
|
10.0
|
|
|
12
|
累計
|
58
|
2
|
0
|
0
|
4
|
0
|
1
|
195
|
511/9
|
157
|
167
|
85
|
|
平均
|
5.8
|
2.0
|
0
|
0
|
0.4
|
0
|
0.1
|
19.5
|
5.7
|
15.7
|
16.7
|
8.5
|
|
|
全年
|
累計
|
1,261
|
47
|
8
|
1
|
44
|
3
|
46
|
657
|
34.2
|
642
|
1,026
|
1,703
|
|
平均
|
126.1
|
4.7
|
0.8
|
0.1
|
4.4
|
0.3
|
4.6
|
65.7
|
3.4
|
64.2
|
102.6
|
170.3
|
|
二、風
(一)風向
自然に起る風を大きくわけると、まず冷たい所から、暖かい所へ向かって吹きこんで起る海陸風、山谷風、季節風がある。次に空気の渦巻によって起る低気圧や、台風、たつ巻などがある。海陸風 日中は太陽に照りつけられて、海も陸も温度が上るが、陸地の方が海面よりも温度が高くなる。それで陸上の空気は上昇し、その後へ海より空気が流れて来て起る。夜になると、海面よりも陸地の方がよけいに冷えるので、陸から海に向かって空気が流れ出して起る。
山谷風 この風は、山間部に起る風で、日中は谷間から山頂へ向って吹き上げ、夜間は平地に向って吹きおろす風である。
季節風 これは海陸風を大型にしたもので、日本付近について述べてみると、夏は太平洋から大陸へ向かっておもに南東の風が吹き、冬は反対に大陸から太平洋に向って北西の風が吹くことが多い。
身延町の風向をみると、富士川筋では日中は南風が多く、夜は北風が吹くことが多い。しかし山間地においては、谷にそって吹く山風や谷風が多い。梅平を例にとってみると、富士川筋では南風が吹いているのに、梅平では、おもに東風が吹くことが表4でわかる。この表は身延高校で、1962〜1966年までの5年間の午前9時現在の風向を、月別に表わしたものであり、東風が最も多く623回、次に北東の風が254回となっている。南風は意外に少なく6回しかない。このように風向は観測地の地形に大きく左右される。
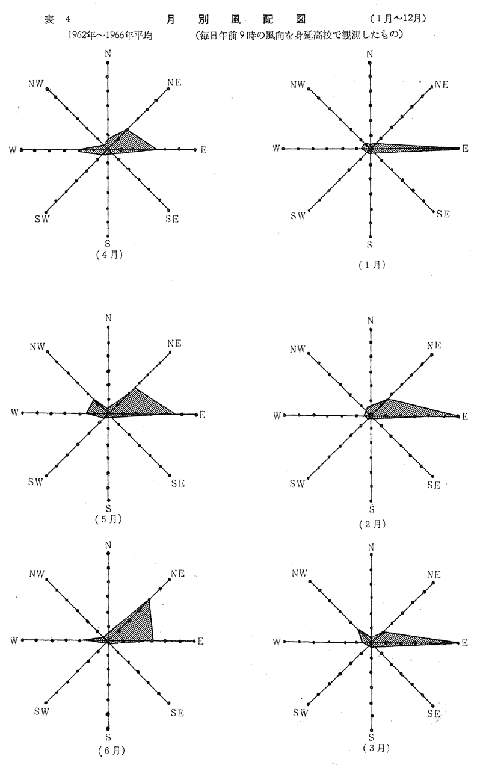
|
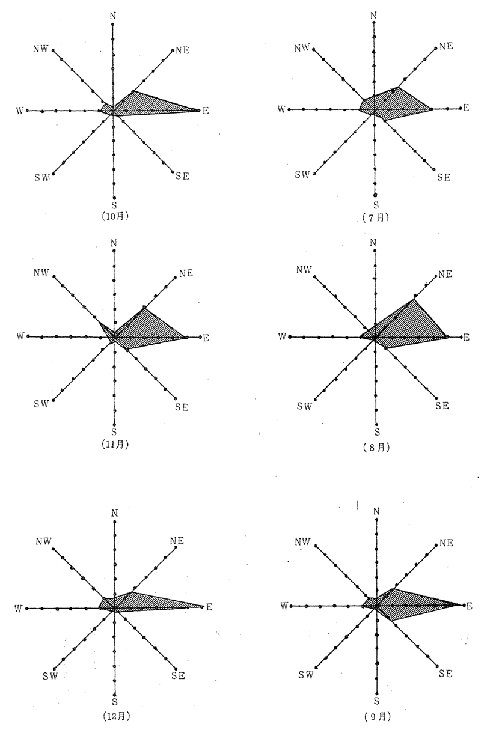
|
(二)風の強さ
風の強さは表5の通り秒間に空気が何メートル動いたかできめる。 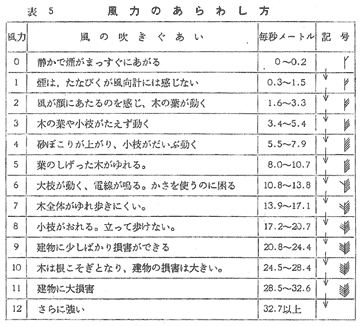
|

