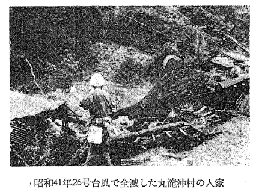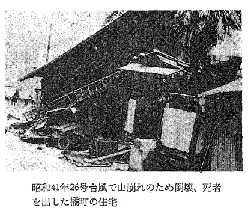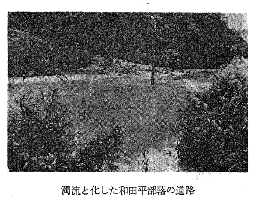第三節 気象と災害
一、風水害
災害には、地震、暴風、冷害、凍害、早魃(かんばつ)などがある。地震や火山噴火によるものは過去、関東大地震(1923、9、1)や北伊豆地震(1930)の時には、本県にも相当被害があり、富士山だけでも有史以来27回の噴火の記録が残されている。しかし、本町の特殊性として最も注意しなければならないのは風水害である。風水害の大部分は、台風によるものである。特に台風が多く来るわけではないが、地形の関係で洪水が起りやすく、昔から人々を苦しめてきた。本県の大水害の記録は、平安時代初期の歴史に残っているが、大小の水害は数えきれず、明治以後の暴風雨および豪雨の主なものは表1、2からみてもいかに多かったかということがわかる。表1 豪雨水害時の降水量
| 昭41.9 (26号) |
36.6 (新潟) |
34.9 (15号) |
34.8 (7号) |
33.7 |
29.9 |
22.9 |
20.10 |
11.9 |
3.9 |
明43.8 |
明40.8 |
| (5日間) |
(7日間) |
(4日間) |
(2日間) |
(8日間) |
(3日間) |
(3日間) |
(4日間) |
(2日間) |
(2日間) |
(6日間) |
(5日間) |
| 13—20.3 |
2—15.5 |
26—299.5 |
15—180.8 |
5—1.4 |
|
||||||
| 14—190.5 |
3—33.0 |
27—168.3 |
16—129.5 |
6— 41.0 |
|
||||||
| 15—110.7 |
4—35.2 |
|
|
7— 42.0 |
|
||||||
| |
6—60.6 |
|
|
8—131.0 |
|
||||||
| |
|
|
|
9—252.0 |
|
||||||
| |
|
|
|
10—187.0 |
|
||||||
| 観測場所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (身 延) |
(南 部) |
(身 延) |
(南 部) |
(南 部) |
(南 部) |
(身 延) |
(身 延) |
(身 延) |
(身 延) |
(南 部) |
(南 部) |
| 計 376㎜ |
676.4 |
206.4 |
389.3 |
446.9 |
472.1 |
321.5 |
460.5 |
467.8 |
310.3 |
461.8 |
469.3 |
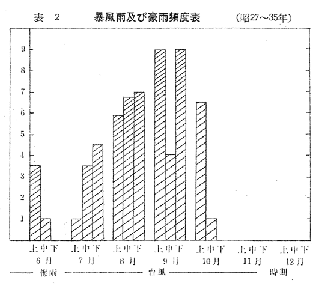
|
また、極めてまれな例であるが、明治33年9月の台風では、北西の風が甲府で32.3メートル、県下の倒壊家屋が千余戸であったが、水害はなかった。
次に表3で戦後における本県関係の主な台風を年代順にあげてみよう。
表3 戦後の本県に関する主な台風
|
年 月 日
|
名 称
|
被害地域
|
死 者
|
行方不明
|
傷 者
|
全壊家屋
|
|
昭19.9.18
|
枕崎台風
|
全国
|
2,084
|
1,046
|
2,295
|
23,945
|
|
20.10.10
|
阿久根台風
|
全国
|
351
|
70
|
184
|
288
|
|
22.9.15
|
カスリーン
|
関東・東北
|
1,077
|
853
|
1,547
|
5,301
|
|
23.9.16
|
アイオン
|
〃
|
512
|
1,956
|
326
|
45,077
|
|
24.8.31
|
キテイ
|
〃
|
135
|
479
|
25
|
3,027
|
|
25.8.3
|
11号・12号
|
〃
|
40
|
59
|
764
|
31
|
|
25.9.3
|
ジェーン
|
全国
|
398
|
141
|
36,062
|
17,062
|
|
26.10.14
|
ルース
|
〃
|
572
|
371
|
2,644
|
21,527
|
|
27.6.23
|
ダイナ
|
関東・東北
|
65
|
70
|
28
|
52
|
|
28.9.25
|
テス
|
近畿・東海
|
393
|
85
|
2,559
|
5,989
|
|
29.8.18
|
グレイス
|
全国
|
30
|
33
|
77
|
331
|
|
29.9.13
|
ジューン
|
〃
|
107
|
37
|
31
|
1,648
|
|
29.9.18
|
ローナ
|
四国以東
|
36
|
24
|
59
|
52
|
|
29.9.25
|
洞爺丸
|
全国
|
1,361
|
400
|
1,601
|
8,005
|
|
31.8.16
|
パブス
|
〃
|
33
|
3
|
213
|
1,864
|
|
31.9.27
|
ハリエット
|
〃
|
20
|
11
|
41
|
489
|
|
33.7.23
|
アリス
|
関東
|
26
|
14
|
64
|
106
|
|
33.8.25
|
フロシイ
|
四国・関東
|
15
|
30
|
39
|
86
|
|
33.9.27
|
狩野川
|
関東
|
888
|
381
|
1,138
|
1,289
|
|
34.8.14
|
ジョージア
(7号) |
東日本
|
147
|
47
|
1,503
|
3,297
|
|
34.9.26
|
伊勢湾(15号)
|
中国以東
|
4,997
|
402
|
38,921
|
36,134
|
|
36.9.16
|
第二室戸
|
全国
|
186
|
15
|
3,877
|
13,294
|
|
39.9.24
|
20号
|
〃
|
49
|
3
|
540
|
3,256
|
|
40.9.10
|
23号
|
〃
|
62
|
—
|
61
|
1,096
|
|
40.9.17
|
24、25号
|
〃
|
111
|
—
|
565
|
140
|
|
41.9.26
|
26号
|
関東
|
318
|
—
|
796
|
2,493
|
昭和34年8月13、14日の台風は、過去における最大の水害と、最大の風害を同時に起こし、家屋、人命、農産物、山林等に甚大な被害を与えた、本県の水害のはげしいのは地形、地質によるところが多いが、
①河川の傾斜が急で、豪雨時の水流が強勢で破壊力が大きい。
②地質の関係で地盤がもろく、山崩れが起きやすい。
③多くの河川は天井川で、河床が年々高くなり、堤防がその役を果たしにくくなる。
④水系は富士川に集中し、短時間で広はんな地域の水を集め水害を招く結果になりやすい。
最近の被害の大きかった昭和34年8月の7号台風は、その中心が富士川河口付近(図1)に上陸し、そのまま富士川にそって北上し、猛烈な暴風雨を伴って本県を縦断した台風で、本町での被害は表4のようであり、なお、同年9月、15号台風が、これまた例もみないほどの超大型台風で、主として暴風による被害が大きかった。本町でも表6でしめすように、ことの外被害が大きく、同じ年に県下を2度襲ったのは前例のないことである。
続いて41年9月の26号台風は、県下に死者、行方不明175人、家屋被害18,400世帯、被害総額275億円にのぼる大きなつめ跡を残し、特に人命被害は県史上空前の数字を記録した。(表9)
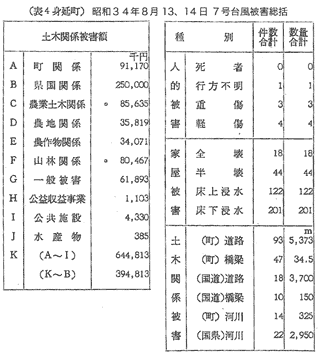 |
| 表5 昭和34年台風15号全県被害
|
表6
表7 河川の水位(26号台風)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表8 26号台風雨量および風力・気圧 (その1)
2.最大雨量は25日0時30分ら午前1時30分ごろ 3.風力階級 5=風速8.0〜10.7m 7=13.9〜17.1m 8= 〃 17.2〜20.7m 10=24.5〜28.4m (その2)
|
表9 台風26号 県下の被害 (10.31現在)
|
台風26号の気象概況
昭和41年9月23日、硫黄島の南東約80キロメートル付近に発生した台風26号は、しだいに速度を早めながら西進、のち北西に進み、24日6時には硫黄島西方約300キロメートルに達して、毎時40キロメートルの速度で北上をはじめた。
その後勢力を増しながら北上を続け(小型から中型となり速度も60キロメートルとあがる)発生からわずか2日の24日23時頃から静岡県御前崎付近に上陸した。
上陸後も台風の勢力は衰えず(速度70キロメートルとあがる)25日1時頃から県南部に入り、西北ぞいに西湖−塩山−三富付近を通り埼玉県北部に抜けた。このため、24日23時頃から県下全域にわたって風雨が強まり、25日1時過ぎには暴風雨となった。(注甲府・船津とも1時40分頃最低気圧を観測)甲府気象台は台風接近に伴い24日21時30分暴風洪水警報を発令し翌3時45分暴風警報を解除した。
台風が県内に猛威をふるったのは約2時間、被害地が実際に暴風雨圏内にあったのは、わずか1時間ぐらいであった。
二、地震
甲府気象台の記録によると、昭和38年から41年までの無感、有感の年平均回数は、人体に感ずるもの22.5回、人体に感じないもの511.8回となっている。甲府気象台が地震観測開始以来記録したもっとも強い地震は、大正12年(1923)9月1日の関東大震災および翌13年1月15日の丹沢山地震で、ともに震度は烈震であり県内に被害を生じた。次は、明治42年(1909)8月14日の近江姉川の地震で震度は強震であった。気象50年報によると、身体に相当強く感ずる地震は年1回程度である。
三、その他の災害
(一)雪害
大雪の害は本町は海岸的気候のため、ほとんどないが昭和44年には春の重い大雪が2度にわたり降ったため、近年稀にみる被害があり、特に7−8年生から15年生の杉、檜に被害が多かった。地区別被害状況は次ぎの通りである。
|
地区名
|
樹種
|
人・天別
|
林齢
|
被害面積
|
被害本数
|
被害材積
|
被害金額
|
被害名
|
|
下 山
|
杉檜
|
人工
|
5—20
|
72.10ha
|
1,560本
|
15.60m3
|
224,640円
|
雪折
|
|
身 延
|
〃
|
〃
|
〃
|
42.00
|
5,189
|
51.89
|
747,216
|
〃
|
|
大河内
|
〃
|
〃
|
〃
|
260.00
|
119,206
|
1,192.06
|
17,165,664
|
〃
|
|
豊 岡
|
〃
|
〃
|
〃
|
72.00
|
14,270
|
142.70
|
2,054,880
|
〃
|
|
計
|
446.10
|
140,225
|
1,402.25
|
20,192,400
|