(七)各地区の植物
ア、下山の植物上沢寺と本国寺には、ともに国の天然記念物指定のオハツキイチョウがある。これは葉に実のつく変ったイチョウで、全国的に有名である。くわしくは別の項で述べる。下山地区には、暖地性の植物は数が少ない。
ナンテン、アカメガシワ、ネムノキは、随処に見られる暖地性植物である。
下山で特に注目すべきは、一の宮賀茂神社のヒサカキの群落とサカキの自生である。サカキの自生は本町ではここより外は見当らない貴重な存在である。その他の暖地性植物では、ヤブツバキ、ネムノキ、ダンコウバイ、テイカズラ、アラカシ、シラカシなどがある。
イ、下山から杉山を経て身延山までの植物
裏参道の代表的な植物をあげると、クサギ、バッコヤナギ、ハナイカダ、ナンテン、ヤブサンザシ、センニソウ、ハンショウヅル、ボタンヅル、コボタンヅル、ミズキ、ガマヅミ、コマツナギ、フサザクラ、ニワトコ、ミツマタ、イロハカエデ、ケンポナシ、テイカズラ、ヒトリシズカ、フデリンドウ、イカリソウ、ヤブラン、シュンラン、ギンラン、ゲンノショウコ、カワラナデシコ、シモツケ、ホシダ、クマワラビ、ゲシゲシシダ、タチシノブ、オオバイ、モトソウ、ウラジロ、ウスヒメワラビ、クマワラビなどである。
ウ、寺平付近の植物
ここにはタブノキ(クスノキ科)目通り幹囲4.60メートルの巨木があったが、昭和41年9月の台風26号による土砂崩れで流出してしまった。寺平の南に面した地域には、ヤブツバキ、アオキ、シラカシ、ニガキ、ムクノキ、ツルグミ、ヤブソテツなどの暖地性植物が混生している。
エ、身延山の植物
身延山は中腹から下は暖帯で上は温帯に属している。その境は650メートルぐらいである。天然固有の林相の場合は、下方は暖帯の代表であるカシ類のシラカシ、アラカシ、ウラジロガシを主とする常緑広葉樹林で、上方はブナ、イヌブナ、シデ類、カエデ類の落葉広葉樹林この両者は接しているのが普通であるが、スギ、ヒノキなどの植林のため天然の林相が失われている。スギは本山の南から西へとさらに裏山から奥の院へかけてうっそうとして茂っている。総門や三門裏の杉並木は実に見事な大木で、霊山身延の尊厳をつくり出している。この中には目通り幹囲6.50メートルの巨樹もある。身延山杉林中最も代表的なものは千本杉である。本数は約260本、材積石高の多いことで東洋一の美林といわれ、県指定の天然記念物となっている。
身延山は斜面を南に向けた日だまりなので、暖地性植物が多く分布している。三門裏にはヤブミョウガの小群落が目につき、シダ類ではハカタシダ、ベニシダ、ウスヒメワラビ、ナンカイタチシダがあり、シャガは大群落をつくっている。オオバイノモトソウ、オオツヅラフジ、キッコウハグマ、ナキリスゲなどが生育している。西谷側にはハゼノキ、サネカズラ、ヤブミョウガ、ケンポナシなどが少々目につく。また栽植されたイトザクラ(シダレザクラ)が数多くあって、何れも見事なもので花の季節はまことに美しい。また随処にカラスウリが生育している。三門裏、男坂、本山裏などのスギ林下や西谷の諸処に暖地性のタブの木が見られる。
本山周辺は、アオキ、ナンテン、アラカシ、シラカシ、タブノキ、ヤブツバキなどの常緑広葉樹がある。クスノキやフクノキの大樹もある。栽植されているものには、シキザクラ、オオバボダイジュ、西谷には、コウヨウザン、シナアブラギリ、イトザクラなどがあげられる。
オ、久遠寺から三光堂を経て奥の院までの植物
タブノキ、ムラサキシキブ、アオキ、エノキ、ヤブミョウガ、アラカシ、コクサギ、コバノガマズミ、ヤブコウジ(群落)、シャガ(大群落)、タマアジサイ、ベニバナボロギク、イロハカエデ、シキミ、モウソウチク、ウリノキ、ガガイモ、ウバユリ、キヌタソウ、ムカゴイラクサ、アブラザサ、キイチゴ、ミネカエデ、クマシデ、チョウジタデ、ツルマキ、ミツデカエデ、リョウブ、ヒメシヤラ、キヌタソウ、ブナ、サンカイズル、センナリホホヅキ、ヒメジョオンなどが頂上近くにある。
カ、西谷から願満堂追分を経て奥の院までの植物
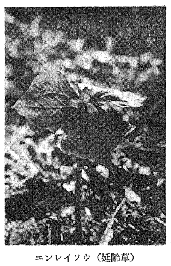
|
奥の院への道の南側はスギ、ヒノキの人工林となっているが北側は落葉広葉樹林である。アブラチャン、ウリハダカエデ、ミツカエデ、エンコウカエデ、オオモミジ、カジカエデ、フサザクラ、エゴノキ、ケハリギリ、ヤシャブシ、サワシバ、クマシデ、ホオノキ、コバノトリネコ、カマツカヤマハンノキなどがあり、ブナが多く純林となっているところもある。山頂のスギ、ヒノキ林の下にはスズタケ、ミヤマザサが茂っている。思親閣付近には日蓮聖人手植えの巨樹が4本あるが、うち1本は枯れ、他の2本も枝の一部が枯れている。思親閣の前にボダイジュ2本が植えてある。
キ、大城川流域と安倍峠の植物
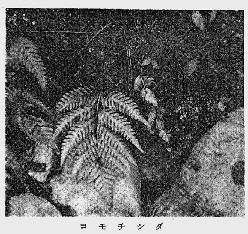
|

|
古谷城上方には本県唯一の自生と思われるオオクジャクシダや、南部町の戸栗川上流に見られる葉の表と裏とが同じような緑色をしているリョウメンシダなどがある。
安倍峠の上部は自然林が残されているが、下部一帯はスギ、ヒノキの植林地となっている。沢筋には自然が残されていて落葉広葉樹が多い。沢筋から中腹へかけての植物をあげると、木本では、ハゼノキ、タラノキ、ヤマウルシ、コウゾ、アセビ、ウラジロノキ、マルバアオダモ、シラカシ、ウリノキ、ホオノキ、アワブキ、アカシデ、エゴノキ、コンテリギ、イヌツゲ、ウワミズザクラ、コアジサイ、クロモジ、ハクウンボク、クリ、コミネカエデ、メグスリノキ、トチノキ、ヒメシヤラ、オニグルミ、サワグルミ、カツラ、ミヤマキ、ハダ、ケウツギ、フジウツギ、エンコウカエデ、ミツカエデ、チドリノキ、ウリノキ、カマツカ、コバノトリネコ、オオカメノキ、モミ、サルトルイバラ、バライチゴ、モミジイチゴなどで草本ではムカゴイラクサ、フジアザミ、アキノキリンソウ、コメナモミ、アメリカセンダングサ、エゴマ、ヘビノネゴザ、リュウノウギク、ノコンギク、フジテンニンソウ、アカネ、ヨツバヒヨドリ、ゲンノショウコ、ホソエノアザミ、ツルニンジン、オトコヘシ、カンスゲ、キンミヅヒキ、オオバユキザサ、ヌカビキ、フクオウソウ、ヤマハハコなどで、珍しいものには岩壁に生えているイワナンテン、イワユキノシタ、カイイワカガミ、湿岩に生えているものではイワタバコ、特に貴重なシラヒゲソウがある。つる木(ぼく)ではアケビ、ミツバアケビ、フジ、テイカズラ、サルナシ、ミヤママタタビなどでシダ類では、イヌワラビ、フユノハナワラビ、イワガネゼンマイ、リョウメンシダ、キョタキシダ、ハリガネワラビ、ミヤマイタチシダ、ヤマイヌワラビ、岩壁に着生するエヒラシダは稀なものである。安倍峠の中腹から頂上へかけては標高1,000メートルあたりからイヌブナ、ブナの混生林に入りヒメシヤラの相当太い木が目につく、落葉広葉樹林では、オオカメノキ、ミズナラ、コバノトリネコ、ナンキンナナカマド、ウリハダカエデ、アオハダ、キハダ、コミネカエデ、ハウチワカエデ、アヅキナシ、コシアブラ、ミヤマシグレ、アセビ、ヤマアジサイ、リョウブ、タンナサワフタギ、ホオノキ、ノリウツギ、ミヤマアオダモ、ヒトツバカエデ、ヒカゲツツジ、トウゴクミツバツツジ、チチブドウダン、ゴヨウツツジ、ホツツジ、ウスギヨウラクなどのツツジ類も多い。頂上近くにはブナを主とした林であるが、ツガ、ウラジロモミなどが混生している。林下にはスズダケ、ミヤコザサ、トウゲシバなどが生えている。草本では、オオバユキササ、キンレイカ、ヤマイワカガミ、テバコモミジガサ、ヤブレガサ、シラネセンキュウ、マイヅルソウ、ヂガバチソウ、シシガシラ、シラネワラビがある。
ク、大島、和田、樋之上周辺の植物
この地域には暖地性の植物が多い。ヒサカキ、アオキ、イヌツゲなど多く小群落をつくっている。特に注目すべきウラジロの群落やマンリョウの群落がある。目につく植物をあげると、アカメガシワ、クリ、ハナイカダ、エゴノキ、クサアジサイ、モチツツジ、イヌシデ、アカシデ、ヤブレガサ、ゼンマイ、コゴメウツギ、メダケ、ヤダケ、カンアオイ、カギガタアオイなどがある。垈には県指定天然記念物のヤマボウシとタカオモミジ(イロハカエデ)の大樹がある。
ケ、角打から大崩を経て椿草里までの植物
アラカシ、シラカシが沢に沿って大崩まで達している。途中の坂道の上下には常緑広葉樹が多い。ツバキ、ヒサカキ、アラカシ、シラカシにまじってダンコウバイ、ネムノキ、アブラチャン、コナラ、キブシ、バイカウツギ、タマアジサイ、岩壁に暖地性のマメヅタが着生している。草本ではウバユリ、アカネ、ヒヨドリバナ、ミヅタマソウ、タケニグサ、センニンソウ、オミナエシ、ヒヨドリジョウゴ、シオデ、ノブドウ、ルリソウ、ソバナ、キキョウ、ガンクビソウ、コウヤボウキ、タイアザミ、リュウノウギク、ホウチャクソウ、ヤブカンゾウ、ヤマユリ、ヤブラン、ホトトギスなどで沢の岩間にセキショウが生育している。峠付近では樹皮のなめらかなリョウブが目につく。イヌシデ、カゴノキ、クロモヂ、サンショウ、イヌザンショウ、マルバウツギ、アカマツ、イヌツゲ、ウリカエデ、タラノキ、ミヅキ、ハナイカダ、モチツツジ、コバノガマズミ、ガマズミ、アケビ、ヤマザクラなどであまり大木はない。
椿草里にはツバキの大きい木が8株1列に栽植されてあり、また栽植と思われるシキミとエドヒガンザクラの大樹がある。小枝の先に長さ約10センチメートル総状の花序をつける。ウワミズザクラが路傍にある。渓谷の対岸にナンジャモンジャノキといわれているムクノキの大木がある。このあたりにはアラカシ、シラガシ、アカマツ、イヌシデ、アカシデが多い。
(八)帰化植物
外国から渡来して、その分布を拡大し、一時的もしくは、永続的に野生化した植物で、本町においても数多く帰化植物が見られる。これらの植物は低地に多く分布しているが近年急に山麓や亜高山帯にまで見られるようになった。最近見られるようになったアフリカ原産のベニバナボロギクが、本町では大城から大城川に沿って安倍峠の中腹まで見られ、また本山西谷上部から三光堂下まで及んでいる。大河内地区、下山地区ではまだ見られないが、まもなく本町全域に見られよう。帰化植物は路傍や荒地などに多く見られ越年性のキク科植物が多い。オニノゲシ(キク科)ヨーロッパ原産、ノボロギク(キク科)ヨーロッパ原産、明治初年、ベニバナボロギク(キク科)アフリカ原産、ヒメジョオン(キク科)北アメリカ原産、明治初年、ヒメムカシヨモギ(キク科)北アメリカ原産、明治初年、アレチノギク(キク科)北アメリカ原産、オオアレチノギク(キク科)ブラジル原産、オオイヌノフグリ(ゴマノハグサ科)ヨーロッパ原産、タチイヌノフグリ(ゴマノハグサ科)ヨーロッパ原産、センナリホオヅキ(ナス科)アメリカ原産、エゴマ(シソ科)中国原産、マツヨイグサ(アカバナ科)チリー原産、オオマツヨイグサ(アカバナ科)北アメリカ原産、アレチマツヨイグサ(アカバナ科)アメリカ原産、シロツメグサ(マメ科)ヨーロッパ原産、江戸時代、ムラサキツメグサ(マメ科)ヨーロッパ原産、明治初年、マメグンバイナヅナ(アブラナ科)北アメリカ原産、アカザ(アカザ科)中国原産、ソハカズラ(タデ科)ヨーロッパ原産、アメリカセンザングサ(キク科)北アメリカ原産

