二、北限の植物
富士川に沿って北上した暖地性植物がわが身延町に数多く分布している。これは身延町が温暖な地であることを物語っている。次に本町に自生する南方系暖地植物は、タブノキ、シラカシ、アラカシ、ウロジロガシ、シキミ、サカキ、ヒサカキ、ヤビツバキ、ヒイラギ、アカメガシワ、ハゼノキ、マンリョウ、ツルグミ、サネカズラ、テイカズラ、ツヅラフジ、ナンナン、フュザンショウ、クサアジサイ、モチツツジ、シャガ、カギガタアオイ、ササユリ、ヤブミョウガ、カニクサ、イワガネソウ、オオイタチシダ、ナンカイイタチシダ、ハカタシダ、ウラジロ、ベニシダ、マメヅタ、ウスヒメワラビ、ヒメワラビ、オオバノイノモトソウ、ホシダ、サジラン、ラシダ、テバコモミジガサ、キッコウハグマ、イワナンナンなどがあげられる。これらの暖地性植物の中には、身延がその北限になっているものと、シラカシ、アラカシ、テイカカズラ、ヒメワラビ、ホシダなどのようになお北上して甲府の北まで達している寒さに強い植物もある。
(一)本町を北限とする植物
タブノキ(クスノキ科)常緑広葉の高木でタモともいわれている木である。6月頃黄緑色の花が咲き、7月末頃黒紫色に実が熟す。生長は早く大木となる。太平洋岸などの暖地に多く、本町では、波木井神之平八幡神社境内に見事な大樹がある。また、本山の周辺と三光堂に若木がある。タブノキの最北限のものとして貴重である。
シキミ(モクレン科)
常緑の小高木で4月下旬淡黄色の花をつける。漢字で
アオキ(ミズキ科)
暖地性常緑広葉の低木、観賞用に庭に多く栽植されている。自生地は大島・樋之上・和田・角打・丸滝・身延山三門裏などである。
ヒイラギ(モクセイ科)
暖地性の常緑小高木、本州関東以西、四国、九州に分布し、観賞用によく栽植されている。老壮樹はよく葉のとげがなくなり、尖卵形の葉となって別の植物のように見える。本町では、自生をあまり見かけないが、追分感井坊の下あたりにわずかに見られるだけである。
サネカヅラ(モクレン科)
つる性の暖地性植物で雌雄異株、8月頃淡黄色の花をつける。液果は紅熟して美しい。時に観賞用として栽植される。自生はわずかに西谷に見ることができる。
ハゼ(ウルシ科)
暖地性の落葉高木、葉の付き方もウルシのように奇数羽状複葉である。秋に美しく紅葉しヤマハゼによく似ている。ハゼノキは全株無毛である。男坂と西谷で見られる。
ササユリ(ユリ科)
ユリ科の多年草で本州中部以西、四国、九州の暖地の林中に生ずる。高さ70センチメートルぐらいで、葉は無毛でなめらか、わずかに白い粉がある。7月頃淡紅色のテッポウユリ型の花が3個くらい横向に咲く。本町最南端の横根あたりが北限であろう。
ヤブミョウガ(ツユクサ科)
暖地性の多年生の草本、高さ50−60センチメートル円錐花序に小花をつける。果実は藍色の小球形をしている。陰湿な樹下に多く群落をつくる。三門裏、本師堂西側の杉の下に小群落をつくっている。
コモチシダ(シシガシラ科)
暖地性の大型常緑シダ、時に葉の表面に芽がでるのでこの名がある。本町では大城入口と身延南谷で発見されているのみで貴重である。
ベニシダ(オシダ科)
暖地性の常緑シダ、全国的に少ないもので珍品である。三門裏に少しある。
サジラン(ウラボシ科)
名前だけでは、ラン科と間違えられるがやはり暖地性の常緑のシダである。主として山林中の岩や樹幹に着生する。湯平で見かけたがおそらく北限であろう。
ヘラシダ(ウラボシ科)
サジランに似た暖地性のシダ、山林中の湿地や陰湿な斜面に生ずる。湯平に若干ある。
イワガネソウ(イノモトソウ科)
常緑羽状の暖地性のシダ、イワガネゼンマイに似ているが側脈が結合している。暖地山林中に生育する。本町では三門裏に少しある。
(二)分布の北限に近いもの
ヒサカキ(ツバキ科)妙石坊、下山一之宮。マンリョウ(ヤブコウジ科)和田接心庵。ウラジロ(ウラジロ科)大島・西谷・杉山。オオイタチシダ(オシダ科)身延山男坂。マメヅタ(ウラボシ科)波木井・大崩道(三)身延を越えて北上しているもの
ムクノキ(ユリ科)甘露門下、椿草里、下山。アカメガシワ(トウダイソウ科)下山上粟倉。ツヅラフジ(ツヅラフジ科)甘露門下。カキカタアオイ(ウマノススクサ科)垈。ナンテン(メギ科)身延町全域。ウスヒメワラビ(オシダ科)感井坊下。イワヒメワラビ(イノモトソウ科)西谷(四)分布上注目すべきもの
ヒメシヤラ(ツバキ科)七面山、奥之院、安倍峠に多く分布している。樹皮が淡赤褐色でなめらかである。七面山から箱根を結ぶ線がその北限であるので、身延山はその北限である。ミヤマウコギ(ウコギ科)追分感井坊下のミヤマウコギはおそらくその北限であろう。
三、群生植物とその分布状況
生育条件の同じ状態を好む植物が、同一の個所にむらがってはえることを群落という。(一)シャガ
シャガはアヤメ科の植物で、林下陰湿地に群生する常緑多年草である。高さは50−60センチメートルで、根茎は浅く横走し細長い匐枝(ふくし)を出して繁殖する。葉は袴状に2列互生の剣状、尖頭、革質、鮮緑色で光沢がある。5月頃葉間に1茎を出して総状互生に分枝し、各枝に白紫碧色の花を2−3花開く、花の直径は5−6センチメートルである。花のない季節でも葉が美しい。身延山三門裏より男坂にかけて一面に大群落を形成し、また、本山裏から三光堂までの杉の下草として広大な地域に及んでいる。(二)ヤブコウジ
ヤブコウジはヤブコウジ科の常緑の小灌木で時に観賞用としても庭園に栽培される。冬季の赤熟した果実が美しい。高さは10−20センチメートルで葉は短柄互生で長楕円形、緑で鋸歯があり普通梢に1−2層をなして集り輪葉のように見える。地下茎を引き繁殖するので群落をつくる。小群落は随処にあるが、三光堂下の参道のわきの群落は見事である。(三)ヤマブキ
イバラ科の落葉灌木、広く庭園に栽培されヤエヤマブキ、シロヤマブキ、キクザキヤマブキなど変種がある。幹は高さ2メートル位で叢生(そうせい)し、枝は細くわん曲する。晩春初夏の頃黄色五瓣(べん)花を多数つける。「七重八重花は咲けどもやまぶきの実の一つだになきぞかなしき」と歌に詠まれているが、果実は数箇宿存萼(がく)内に座している。総門山之坊の上方山中に群落がある。(四)ウラジロ
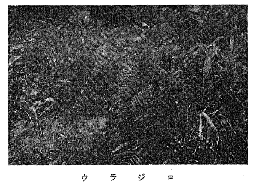
|
(五)ヤブミョウガ
ツユクサ科に属しているが、暖地の陰地に生ずる多年草みょうがに似ているが同じ科ではない。三門裏と本師堂西側の杉林の下に小群落がある。四、特記すべき植物
オハツキイチョウ(イチョウ科)葉に実のつく珍しいイチョウである。イチョウは雌雄異株で上沢寺、本国寺のイチョウは雌株で八木沢のは雄株である。上沢寺のオハツキイチョウの葉上結実は正常種子7に対して3である。葉上結実の事実が明治24年白井光太郎博士によって学会に発表され、同年藤井健次郎博士によって木の形態的意義が明らかになったもので、3株とも国の天然記念物の指定をうけている。上沢寺のオハツキイチョウは樹高27メートル目通り幹囲6.3メートル、八木沢のは葉上葯(葉の上に花粉を貯えておく袋)がある。
タブノキ(クスノキ科)
暖地性の常緑の大高木で、本州、四国、九州の主として海岸に多く、5、6月黄緑色の花を開き黒紫色に熟し、果柄は赤色をおびている。別名をイヌグス、タマグスともいい、本地方では方言でタマまたはタモとも呼んでいる。タブノキは富士川に沿って北上し、富沢町、南部町に多く、標高400メートルまでの地に分布している。身延町におけるタブノキの分布を見ると、久遠寺三門裏に幹囲1.4メートルのものが1本あり、本山の杉林の中に小木が点在している。西谷の坊の境内にも諸処に見られ、三光堂、妙石坊にも小木がある。波木井神之平八幡社境内のタブノキは目通り幹囲2.7メートル、樹高約72メートルの樹勢旺盛な大木で自然の樹形を呈し、分布北限としてきわめて貴重である。
カシ類(ブナ科)
暖地性の常緑高木でシラカシ、アラカシ、ウラジロガシ、ツクバネガシが分布しているがツクバネガシはわずかである。シラカシ、アラカシは耐寒性が強いため町全域の山腹まで分布している。ウロジロガシは下山地区には少ない。身延山では妙石坊から願満堂までの間にとくに多く、上部まで達している。
ヒサカキ(ツバキ科)
常緑の小高木で暖帯各地に見られるサカキに似た植物である。多数の枝、葉を生じ、枝葉ともに毛がない。葉は有柄、互生、楕円形で先がとがっている。雌雄異株で3、4月頃淡黄色の小花をつける。果実は球形、黒紫色である。大島・樋之上・角打に多く自生している。とくに下山一ノ宮境内の小群落は分布上珍らしい。
ムクノキ(ニレ科)
暖性地の落葉高木で、エノキに似ている。葉の上面がざらつく、葉は幅広い卵状の楕円形で鋭い鋸歯がある。果実は球形に熟し甘味がある。ムクドリが好んでこれを食するのでこの名がある。甘露門傍、椿草里渓谷に大樹がある。
ヤマボウシ(ミズキ科)
落葉小高木、葉は楕円形か卵状円形で先がとがっている。葉のへりは波をうっている。6、7月頃短枝の先に白い苞が4枚開き、花のようであるが、花はこの中心に20−30が頭状につく。果実は球形・集合果・肉質で熟すと赤くなる。径は10−20ミリメートルでイチゴの実に似ている。垈のヤマボウシは県指定の天然記念物として有名である。
シキザクラ(バラ科)
コヒガンザクラの1種で四季咲性の強いものである。返り咲き現象ではなく四季花をつける。久遠寺本堂前の池の両端にあるのがこれである。
コウヨウザン(スギ科)
中国原産の常緑針葉樹で広葉杉と書く。スギよりカヤに似た葉をしている。総門前の石垣にあるのは相当大樹でこの外、信行道場の西と竜雲寺の境内にそれぞれ1本ずつある。
シナアブラギリ(トウダイグザ科)
中国原産の落葉高木で、実から桐油をとるため栽培されたもので信行道場、西方に植えてある。
アカメカシワ(トウダイグサ科)
暖帯より温帯南部にわたって分布する落葉高木で若芽も葉柄が赤色で美しい。雌雄異株で果実はブドウ状につき黒熟する。本町では平地全域で見られる。とくに上粟倉の高地にあることは珍しい。
クロツリバナ(ニシキギ科)
ムラサキツリバナともいう。落葉低木で、葉は長円形または卵形で質は薄く、しわが一面に出ている。鋸歯は細く浅い。葉の前後がとがり対生している。花は細柄の先につりさがるのはツリバナと同様である。花の色が暗紫色なのでこの名がある。七面山頂上付近でみかける。
ダケカンバ(カバノキ科)
ソウシカンバともいう。シラカンバに似た落葉高木で、樹皮はシラカンバのような白さではなく灰白色か淡褐色である。葉は三角状卵形あるいは広卵形、基部は通常円形で表は緑でつやがあり、裏の色は表より淡い、ヘリに歯がある。七面山頂で多く見られる。
ヨグソミネバリ(カバノキ科)
落葉高木、葉はややシラカンバに似ている。樹皮は灰褐色で枝の皮をはげば独特の臭気をはなつ。名とは違うサロメチールのようなさわやかな匂(におい)がある。ブナと混生林をつくっている。
ブナ(ブナ科)
落葉高木、幹は直立で高さ30メートルにもなり、樹径は約1.5メートル以上の大樹となる。樹皮は灰色でなめらかである。よく枝分かれしてしげる。身延山・安倍峠・七面山に相当の大木がある。
カツラ(カツラ科)
落葉大高木、高さ27メートル径1.3メートルに達し時に数幹に分岐し枝には短枝が多い。葉は細長柄、対生、広卵形またはハート形、やや鈍頭で鋸歯がある。雌雄異株で5月頃葉より早く苞に包まれた花を葉液に単生する。安倍峠中腹の沢筋には多い。身延町役場と大野トンネルの中間の道路傍に1株ある。
タンナサワフタギ(ハイノキ科)
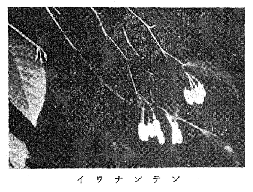
|
イワナンテン(ツツジ科)
ツツジの仲間であるが葉がナンテンに似ている。本州関東以西の山地に分布している。早川町以南の岩場で見られる。七面山の表参道、古谷城上方の岩壁にある。
イワユキノシタ(ユキノシタ科)
常緑多年生の小草木、東海地方や四国の深山にまれに産する珍品、古谷城上方の道南の岩壁、大城川の岩壁に生えている。
シラヒゲソウ(ユキノシタ科)
本州の中部・西部・四国・九州の暖地に生えているが、極めて稀な珍らしい植物で、県下でも数少ないものである。
コバイケイソウ(ユリ科)
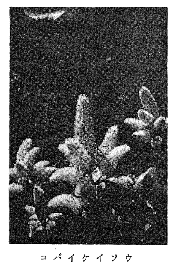
|
ツバメオモト(ユリ科)
全体の形がオモトに似ている。ツバメが飛来する頃花をつけるので、この名があると思われる。葉は根ぎわから5−7枚の鮮緑色の厚味のあるものをつけ、花は柄の上に2−8個まばらにつける。七面山で見かける。
ヤマトリカブト(キンポウゲ科)
花の形が烏帽子(えぼし)のようであるのでこの名がつけられたと思う。花は紫色で美しいが、猛毒である。七面山には処々に生えているが、お池のほとりに群落がある。
その他注目すべき植物としては身延山・和田樋之上周辺・大城川上流に見られる暖地性植物があるが、これは北限の植物の項にゆずる。
本町教育委員会指定の植物園(下部町地内望月栄別荘の庭園)には200数十種の植物がある。(七編五章九節六ノ(三)参照)

