第九節 図書館、博物館
一、社会教育施設としての図書館、博物館
社会教育法第3条に、「国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設、及び運営、集会の開催、資料の作成、頒布その他の方法により、すべて国民が、あらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する、文化的教養を高め得るような、環境を醸成するように、努めなければならない」と規定されている。この趣旨を、具体的に展開したものが、公民館をはじめとして図書館であり、博物館であり、成人の利用をねらったもので、重要な社会教育施設である。二、町立図書館、その他
(一) 町立図書館設置条例
沿革 昭和三十二年三月三十日条例第四号公布町立身延図書館設置条例
(設置の目的)
第一条 図書、記録その他必要な資料(以下「図書資料」という)を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、町立身延図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(設置の場所)
第二条 図書館は、身延町教育委員会事務局内に置く。
第三条 図書館の活動を十分にするため、必要があるときは、図書館分館を置くことができる。
(業務内容)
第四条 図書館は、第一条の目的を達するため、左の各号に掲げる事務を行なう。
一 図書館資料の収集、整理、保存および利用に関する業務
二 読書会、研究会、鑑賞会、映画会、資料展示会等の主催および奨励
三 時事に関する情報、参考資料の紹介および提供
四 郷土研究に関する助成、及び資料の紹介、並びに提供
五 その他必要な業務
(職員)
第五条 図書館に以下の職員を置く。
一、館長 一名
二、書記 一名
(経費)
第六条 図書館の経費は、町費・補助金・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。
第七条 本条例に定めるものを除く外、必要な事項は規則でこれを定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
第一条 図書、記録その他必要な資料(以下「図書資料」という)を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、町立身延図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(設置の場所)
第二条 図書館は、身延町教育委員会事務局内に置く。
第三条 図書館の活動を十分にするため、必要があるときは、図書館分館を置くことができる。
(業務内容)
第四条 図書館は、第一条の目的を達するため、左の各号に掲げる事務を行なう。
一 図書館資料の収集、整理、保存および利用に関する業務
二 読書会、研究会、鑑賞会、映画会、資料展示会等の主催および奨励
三 時事に関する情報、参考資料の紹介および提供
四 郷土研究に関する助成、及び資料の紹介、並びに提供
五 その他必要な業務
(職員)
第五条 図書館に以下の職員を置く。
一、館長 一名
二、書記 一名
(経費)
第六条 図書館の経費は、町費・補助金・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。
第七条 本条例に定めるものを除く外、必要な事項は規則でこれを定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
(二) 身延町立図書館
沿革昭和32年3月、身延小学校内にあった身延町教育委員会事務局内に、町立図書館設置条例にしたがって設置した。昭和35年、教育委員会事務局とともに、身延町役場内に移った。昭和41年9月、台風26号来襲に際し、浸水のため蔵書の大半を失った。昭和42年4月、身延公民館内に移った。
現況(昭和44年度)
館長 遠藤誠
書記 田中隆
蔵書 1,192冊
図書費 74,000円
現在地は、付近に小・中・高の学校があり、また町民の出入にも便利のため、利用者は以前より増加している。
(三) 町内公民館の図書と利用状況
下山公民館蔵書 500冊豊岡公民館蔵書 150冊
大河内公民館蔵書 1,700冊
各公民館とも、蔵書冊数が貧弱な上に、古い本が多くあまり利用されていない。社会教育の重要施設としての図書館は、蔵書冊数を増加するとともに、設置条例にもあげてある業務内容を整備し、従来ややもすると、書庫的な感があった静的図書館から脱皮して、近代的性格を持って活動する、動的図書館に成長しなければならない。
(四) 明星文庫
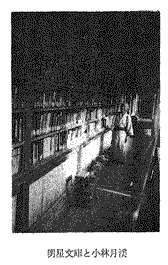 |
| 設置場所 | 身延町和田1662番地 | |
| 設置者 | 小林月渓 | |
| 設置年月 | 昭和23年9月29日 | |
| 蔵書冊数 | 約3,000冊 |
| 目的 | 戦後の青少年育成のためと、檀家利用のため | |
| 開館 | 毎日曜日 | |
| 図書分類 | 宗教哲学教育・文学語学・歴史地理・政治法制・社会・婦人風俗・経済商業・理学工学医学・商業・美術諸芸・運動娯楽 |
山梨県指令第五七号
西八代郡大河内村和田一六六二番地
小林月渓
昭和二十三年五月二十一日付願出の図書館設立のことは下記条件を付しこれを認可する
昭和二十三年九月二十九日
山梨県知事 吉江勝保
一、以下に掲げる事項に該当するときはその設置を取り消すものとす。
西八代郡大河内村和田一六六二番地
小林月渓
昭和二十三年五月二十一日付願出の図書館設立のことは下記条件を付しこれを認可する
昭和二十三年九月二十九日
山梨県知事 吉江勝保
一、以下に掲げる事項に該当するときはその設置を取り消すものとす。
| (一) | 著しく設置基準に遠ざかり図書館の機能を発揮し得ない時又は発揮し得る見込のないとき |
| (二) | 正当の理由がなくて六ヵ月以上公開しないとき |
| (三) | その他公衆に対する奉仕が不充分でその存置の意義のないと認められるとき |
三、学校図書館
(一) 学校図書館の設置
(小学校)校別 蔵書 |
下山 | 身延 | 豊岡 | 清子分 | 帯金 | 大和 | 合計 | 1校平均 | 児童 1人当り |
文部省基準 1人当り |
基準との比較 |
| 冊数 | 1,200 | 1,462 | 1,875 | 700 | 1,276 | 1,249 | 7,762 | 1,293.6 | 5.7 | 5冊以上 | 基準以上 |
(中学校)
| 校別 蔵書 |
下山 | 身延 | 豊岡 | 大河内 | 合計 | 1校平均 | 生徒 1人当り |
文部省基準 1人当り |
基準との比較 |
| 冊数 | 1,200 | 2,069 | 1,170 | 2,487 | 6,926 | 1,731.5 | 8.7 | 5冊以上 | 基準以上 |
昭和21年3月、来日した第一次アメリカ教育使節団の報告書の中に「学校図書館」を設置する必要が説かれ、文部省でも改めてこのことに気づき、「学校図書館の手引き」の編集に着手して、23年にこれを完成した。耳新しい「学校図書館」という用語が、教育界に広く用いられるようになった。しかし、多くの学校では、戦争のいたでがまだ生々しく、青空教室も解消しない頃であったから、学校図書建設のしごとは容易なことではなかった。本県における学校図書館建設への動きは、全国的にみて早い方で、すでに昭和24年度にはいくつか見るべき学校図書館が生まれた。学校図書館に続いて、各地の公民館図書館、公立図書館も着々整えられて来たので、これらを含めて昭和26年「山梨県図書館協会」が誕生した。学校図書館の初期はいわば「読みもの図書館」時代といえよう。小中学校図書館では、まず「楽しく足を図書館へ運ばせるために」という考えから、物語を書架にならべることからはじめた。「読みもの図書館」から脱皮して、「教育課程図書館」期にはいったのは、昭和28年ころからであった。昭和29年4月1日から「学校図書館法」が施行され、待望の法的裏付けがなされて、学校図書館活動は急激に進展をみせた。昭和32年からは、山梨県図書館研究大会が開かれ、昭和36年11月には、甲府市で関東地区学校図書館研究大会が開かれた。こうした一連の動きの中において、本町内の小中学校の図書館も、次第に発展して今日に至っている。学校図書館は新教育においては学校の中心であり、教育課程をゆたかに活気づけるための必要不可欠の施策であるとされている。
(二) 町内小中学校図書保有状況
町内小中学校はいずれも図書館又は図書室を施設してある。(三) 山梨県立身延高等学校図書館
所在地 県立身延高等学校内(身延町梅平)建設 昭和28年12月28日
施設 独立建物(総坪数 105.6平方メートル)
設備 閲覧室(105.6平方メートル)
蔵書数 6,099冊
図書以外の資料・各種新聞雑誌その他
開館毎日 (休祭日以外)
閲覧方式 接架式
(四) 身延山短期大学図書館
身延山短期大学内にあり、昭和42年に完成し、館長室1、書庫4、閲覧室1がある。館内には目下整理中の、日蓮宗関係書・一般仏教関係書・天台宗関係書・哲学書・一般文学書・その他雑書等にわたり、新古多数の書籍を蔵している。
館長 林是幹
司書 長谷川義浩
係員 猪俣日康
四、みどり号来町とその利用状況
 |

