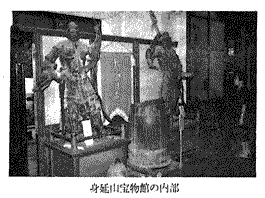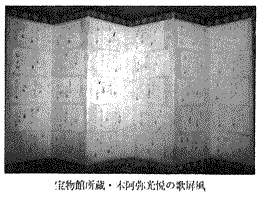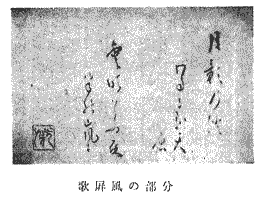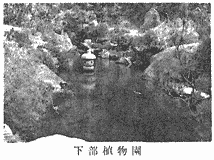六、博物館
博物館とは、博物館法第2条に、この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学に関する資料を収集し、保管(育成を含む以下同じ)、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行ない、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法による図書館を除く)のうち、地方公共団体、民法第34条の法人宗教法人または政令で定めるその他の法人が設置するもので、第1章の規定による登録を受けたものをいう。またこの法律において「公立博物館」とは、地方公共団体の設置する博物館をいい、「私立博物館」とは、民法第34条の法人、宗教法人または前項の政令で定める法人の設置する博物館をいう。なおこの法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、または展示する資料というと規定している。同法では、博物館の事業について次のように規定している。博物館はその目的を達成するため、おおむね次の事業を行なう。実物、標本、模写、模型、文献、図表、フイルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、展示すること。一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導を行なう。博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書を作成し、および頒布すること。
当該博物館の所在地または、その周辺にある文化財保護法の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
博物館は、事業を行なうに当っては、土地の事情を考慮し、国民の実生活を向上し、学校教育を援助し得るように留意せねばならぬ。
(一) 身延山宝物館
| 名称 |
|
私立身延山宝物館 |
| 所在地 |
|
山梨県南巨摩郡身延町久遠寺境内 |
| 設立 |
|
大正15年4月 |
| 指定 |
|
昭和30年博物館相当施設指定 |
| 代表者 |
|
林 是幹 |
| 開館 |
|
午前8時から午後5時まで |
| 休館 |
|
無休 |
| 入場料 |
|
大人30円、小人15円 |
| 収蔵品 |
|
1,200点 美術、工芸 |
| 特徴 |
|
収蔵品は久遠寺所蔵の書籍、筆跡、絵画、仏具、工芸品等であるが中に県の文化財に指定されているものがある。 |
| 施設 |
|
敷地、建物、陳列室440平方メートル |
| 沿革 |
|
久遠寺所蔵の寺室を収蔵展示するため、大正15年4月工費7万円を投じて設立したものである。 |
| 備考 |
|
国宝や国の重要文化財は宝蔵庫に保管されている。 |
| (注) |
|
昭和54年5月久遠寺本堂建立に伴い解体され、現在は、本堂の地階に移設展覧されている。 |
陳列品(昭和44年1月13日現在)
| 品目 |
|
実数 |
| 今上天皇御用度品 御衣 |
|
5 |
| 明治天皇御用度品 御茶碗、他 |
|
6 |
| 昭憲皇太后御遺品 香炉 |
|
1 |
| 子爵小笠原長生書寿量品 |
|
1 |
| 浪越君川大島徳書・竜、虎 |
|
2 |
| 広瀬和育書 |
|
1 |
| 源応挙筆幽霊図絹本 |
|
1 |
| 閻魔大王お裁きの図 |
|
3 |
| 身延山七十四世日鑑上人賛天台大師画像 |
|
1 |
| 日蓮聖人御肖像画(厨子入) |
|
1 |
| 撫順炭の彫刻鶴の置物 |
|
1 |
| 毘沙門天王(等身大木像) |
|
1 |
| 持国天(等身大木像) |
|
1 |
| 日蓮聖人合掌立像 日石子実之作(石膏) |
|
1 |
| 日蓮聖人御涅槃像(厨子入) |
|
1 |
| ビルマ渡来仏像 |
|
1 |
| 日蓮上人辻説法立像(石膏) |
|
1 |
| ビルマ伝来釈迦尊像(青銅) |
|
1 |
| ビルマ渡来涅槃の釈迦(大理石) |
|
1 |
| 本阿弥光悦月づくしの歌屏風(六枚折) |
|
2 |
| 舞楽の図屏風(四枚折) |
|
1 |
| 水野淡路守重央着用の甲胄敷皮付 |
|
1 |
| 天海版仏書大蔵経 |
|
1部 |
| 弘安6年鋳造梵鐘(県文化財) |
|
1 |
| 朝鮮渡来の半鐘(県文化財) |
|
1 |
| 古布袋の置物 |
|
1 |
| 推未七重塔(500年前中国作) |
|
1 |
| 身延山舞楽用の古面 |
|
7 |
| 充填化石(外国伝来木材の化石) |
|
黒1白1 |
| 東京久月作深要日円猊下人形 |
|
1 |
| 欅の古木祖廟奉仕殿建設現場より発掘 |
|
1 |
| 名古屋光明会奉納大数珠珠径10センチメートル |
|
1 |
| 紀州産身延山形石 |
|
1 |
| 古鏡 |
|
3 |
| 七面山御来迎の写真 |
|
1 |
| 慶長年間の町中掟 縦1メートル 横2メートル |
|
1 |
| 花器(焼物) |
|
1 |
| 千利休作竹製花指 |
|
1 |
| 書籍 |
|
6 |
| 白犬供養の塔婆 |
|
1 |
日蓮聖人等身立像
特別陳列日蓮聖人御供画(植中直斉作)
| 番号 画題 |
|
番号 画題 |
| 1 扉絵 |
|
15 帰郷 |
| 2 古郷 |
|
16 清澄帰山 |
| 3 聖誕 |
|
17 叡山遊学 |
| 4 疑念 |
|
18 大遊学の旅 江の島 芦の湖 |
| 567 入山1、2、3 |
|
19 大遊学の旅 富士の急激 瀬田 |
| 8 涕涙石 |
|
20 大遊学の旅 俊範対面 叡山光風 |
| 9 虚空像祈願 |
|
21 大論議 |
| 10 凡血文笹観学 |
|
22 京五条 浄本宅 |
| 11 鎌倉遊学 袂別 惟子辻 |
|
23 日蓮木 泉誦寺 |
| 12 八幡宮 大阿訪問 |
|
24 三井寺 道元禅寺 |
| 13 大阿死葬 |
|
25 冷泉家、東寺 |
| 14 八幡宮経蔵 禅堂 |
|
以上25面以下目下製作進行中 |
(二) 下部植物園
| 名称 |
|
身延町教育委員会指定私立下部植物園 |
| 所在地 |
|
下部町下部1132番地の3 |
| 経営者 |
|
身延町下山265の1番地 望月 栄 |
| 面積 |
|
55アール |
| 樹種 |
|
224種ほかに未整理のもの15種 |
| 沿革 |
|
昭和24年造園着手、昭和43年7月10日身延町教育委員会より下部植物園として指定され、同日開園式挙行、町長ほか来賓多数列席。 |
| 備考 |
|
同園は個人経営のものとしては県下有数の植物園であり、雨河内川に臨み園内に池あり巨石あり景観もすぐれている。また園内はキャンプに好適で、年々児童生徒その他が多数利用している。 |
(注)昭和55年3月 指定解除
|
|