第十節 社会体育
一、社会体育とは
社会体育を「複雑高度化する現代社会の物的、心理的に望ましくない環境から市民を解放して、その健康生活の増進をはかろうとして、地域職域の全年齢層を対象として編成される体育」と考えたい。昭和36年スポーツ振興法が制定されて以来、わが国の社会体育は画期的に発展をみせている。それは、国民の生活水準の向上、国民の自由時間の増大と楽しみへの積極的志向、オリンピックを契機とする国民のスポーツに対する深い関心、スポーツ施設の整備並びに体育指導員の制度化などによっているとみてよいが、社会体育は体育的身体活動や、スポーツが国民の日常生活に定着するまでには、なお多くの障害のあることを認めないわけにはいかない現状である。
一方、技術革新による作業態様や、生活全般にわたる機械化はますます促進され、人間の健康保持に必要な身体活動も次第に少なくなり、特に都市生活者には運動不足を訴えるものが多くなりつつあり、近年運動不足による疾病は決して少なくない実情にある。
また、文部省の調査によれば、次代をになう青少年の体力や運動能力は、身長や体重の増加に伴わず、細長型となり、欧米諸国の青少年と比較するとその能力においてかなり遜色が認められる。このときにあたり、国においてはこれが原因の究明と対策にせまられている。
本県においては、田辺知事が「健康山梨」を県の施策の一つとしていることは、県民周知の事実であり、また大いに共感を得ているところである。山梨県スポーツ振興会を通じ、県民の健康・体力の増進、スポーツの水準の向上等について努めている。県民七つの体操や、体育主事の増員等はその具体的なあらわれの一端である。
本町においても体育指導員の指導、体育協会の自主活動、スポーツ少年団の結成、各種施設の設置等により漸次盛んになりつつあり、近年特に10月10日の国民の祝日「体育の日」には各公民館主催で体育行事が盛大に催されていることが目立っている。
いまや体育は大衆のものである。1人1人の体位の向上と体力の強化を図り、人生の幸福の基盤である健康の保持増進につとめなければならない。
二、社会体育の変遷
(一) 戦前
戦前の地区の社会体育については、大正11年(1922)9月県立身延中学校(現身延高校)の設置の頃にさかのぼってみたい。身延中学校は、設置とともに広大な運動場をはじめ、各種の施設設備も順次整備され、当時すでに小規模ながらプールまであった。
正課としての柔剣道をはじめ、庭球・野球・陸上競技等は、地方の体育を刺激して、その普及発達にあずかって力があった。
整備された施設設備は、地方の体育行事に利用され、峡南オリンピックと呼ばれた峡南陸上競技大会も始められた。
昭和初年から、身延線開通を記念して、山静両県の中等学校の体育大会山静大会が行なわれたのも、また身延中学校だった。
山静両県の親睦と学徒スポーツの向上に、大きな意義があったが、その後都合により、昭和29年立ち消えになったが、その中止は各方面から惜しまれている。
(二) 戦時中
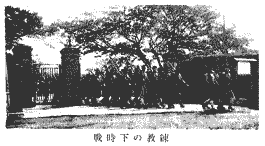 |
種々行なわれていた体育行事は、大方中止され体力章検定・武道章検定・滑空・海洋・通信等の諸訓練・教練・柔道・剣道・薙刀等の鍛錬で、練成体錬に終始した。
国民学校や中等学校でも、時代を反映して集団走、土嚢(のう)運び等その他国防色濃厚なものが盛んになり、建国体操もはじめられた。
一方運動用語も、従来使用されていた外国語は改められ、不都合な日本語があてはめられた。当時身延地区には疎開者が多く、中には武道について練達の士があり、地元有志とともに練習に励んだ。
(三) 戦後
戦後は、新たな観点に立って民主的平和的理念のもとに、画一的訓練をさけ、人格の尊重と自発能動による個性を完成する、平等にして自由な、科学的合理的体育として、全く面目を一新するに至った。そこで老若男女があらゆる機会に、あらゆる場所で、体育スポーツに親しむことのできる体育思想の普及こそ、国民体位の向上に貢献し、明朗濶(かつ)達の気風を振興し、民主的にして、明るい社会を実現する根本となるものとして、その実現を図るべく次の諸点に重きが置かれた。
すなわちレクリエーション思想の普及、スポーツマンシップの涵(かん)養、スポーツの生活化、女子体育の振興、学校体育と社会体育の一連化、地域職域の体育団体の結成推進、施設の整備、体育指導者の資質向上等であった。
 |
これらを大同団結して、全く民主的な純然たる民間スポーツ団体として、山梨県体育協会が発足し県民みな体育を目標に、昭和23年秋第1回体育祭を実施し、今日におよんでいる。なおこの趣旨を生かす上から各郡市に郡市体育協会が逐次結成されるに至った。
一方町内においても、体育協会・野球連盟・柔剣道連盟等が相次いで結成され、社会体育は年を追って盛大になっている。
また屋内運動場やプール等の体育施設も、順次整備されつつあり、組織の活用、施設の利用等により、練習の結果、県郡等その他各種大会に出場し、好成績を得ている。
しかし何といっても、社会体育の目的とするところは、地域住民の体育の振興にある。
これについても、次第に理解が深まり、公民館主催の体育祭、球技、レクリエーション等の大会も持たれ、参加者が年々増加して、老若男女が嬉嬉(きき)として親しんでいる様を見るようになって来た。
戦後特筆すべきことの一つとして、婦人のレクリエーション活動が盛況になったことで、戦後の婦人の地位の向上や、考え方の進歩等から、地域・職場・団体等で球技、舞踊・旅行等が自発的に計画実施されている。
またスポーツ少年団をはじめ、青少年間には、登山・ハイキング・キャンプ等の野外活動が盛んになってきた。
三、社会体育の活動の数々
(一) 敗戦における身延町の柔剣道
昭和24年、旧身延町に青少年の健全育成と柔道の振興を図る目的で、柔道愛好者の会が設立された。26年、終戦後占領軍により禁止されていた学校柔道が、スポーツ柔道として復活するや、身延中学校では柔道クラブを創設した。同年第1回県下中学校柔道大会で優勝、続いて4年連続優勝、その後優勝6回、準優勝4回、その他輝かしい成績を残している。
27年には、旧下山村には土橋隆四郎を会長として柔剣道連盟が設立され、翌年には旧身延町にも柔剣道連盟が設立された。
29年には、予算80万円をもって、身延中学校に215平方メートルの武道場を建設し、その武道場開きには、我が国柔道界の最高段者三船10段を招いて、盛大に挙行した。
武道場建設により、町内の柔剣道は、一層盛況を呈するようになった。
30年町村合併により、各地区柔剣道連盟は発展的に解消し、身延町柔剣道連盟が誕生し、今日に至っている。
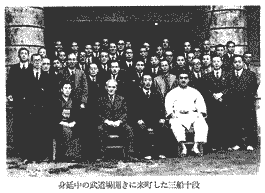 |
剣道有段者
| 教士7段 | 鮎川省三 | |
| 教士6段 | 小沢常敏 | |
| 教士6段 | 松田寛次 | |
| 教士6段 | 藤田富士弥 | |
| 教士5段 | 市川良政 | |
| 錬士5段 | 土橋隆四郎 | |
| 錬士5段 | 渡辺直材 | |
| 5段 | 池上正 | |
| 4段 | 北川惣七 | |
| 4段 | 望月忠常 | |
| 4段 | 鮎川栄一 | |
| 4段 | 望月等 | |
| 3段 | 望月栄 | |
| 3段 | 萩原武雄 |
| 講道館6段 | 松木幹之甫 | |
| 講道館6段 | 松本学昭 | |
| 講道館5段 | 笠原健二郎 | |
| 講道館4段 | 雨宮正 | |
| 講道館4段 | 市川光宣 | |
| 講道館4段 | 佐野正行 | |
| 講道館4段 | 一宮嘉孝 | |
| 講道館3段 | 川口久広 | |
| 講道館3段 | 松田虎男 | |
| 講道館3段 | 高橋正人 | |
| 講道館3段 | 深沢永寿 | |
| 講道館3段 | 望月民雄 | |
| 講道館3段 | 鴨狩幾夫 | |
| 講道館3段 | 池上義雄 | |
| 講道館3段 | 笠井正涌 | |
| 講道館3段 | 佐野始 | |
| 講道館3段 | 近藤茂 |
(二) 南巨摩縦断駅伝
| 主催 | 南巨摩郡体育協会 | |
| 後援 | 山梨時事新聞社 | |
| 区間 | 万沢村県界から増穂中学校庭まで | |
| 距離 | 52.5キロメートル | |
| 第1回 | 昭和28年12月6日 優勝豊岡村チーム(記録不明) |
|
| 第2回 | 昭和29年11月3日 参加13チーム 優勝豊岡村チーム 記録3時間33分33秒 メンバー、小泉、望月(哲)、秋山、遠藤、鴨狩、望月、粟冠(文)、松田、粟冠(庄) 2位 五開以下睦合、富河、鰍沢の順 |
|
| この回より中学校も参加、区間身延増穂間、参加18チーム優勝五箇中チーム | ||
| 第3回 | 昭和30年11月3日 一般参加チーム、18 優勝身延町チーム 記録3時間22分40秒 メンバー、松田、遠藤、佐野、秋山、鴨狩、小泉、粟冠、千須和、望月 2位 富沢以下南部、増穂、都川の順 中学校参加チーム 11 優勝 増穂中チーム 1時間49分 交通事情により第3回まで実施以後中止 |
|
 |
 |
|
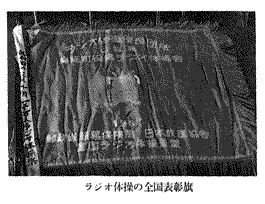 |
(三) 身延町役場ラジオ体操会
身延町役場では、昭和34年11月現町長佐野為雄が助役就任以来、毎朝実施して今日に至っている。この努力と実績が認められて、昭和41年には郵政省簡易保険局長、日本放送協会長関東ラジオ体操連盟会長の三者連名による表彰状と、表彰旗ならびに記念品をうけている。
更に昭和42年には、下記の表彰状と表彰旗ならびに記念品をうけている。
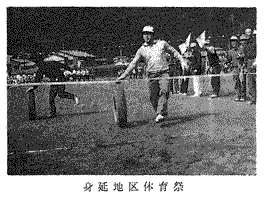 |
 |
|
 |
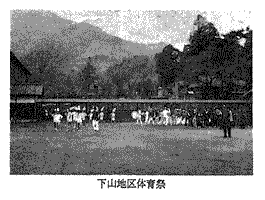 |
表彰状
身延町役場ラジオ体操会殿
平素ラジオ体操の普及発達に積極的に協力し国民の体位向上に寄与せられその功きわめて大きいものと認めます
ここに記念品を贈呈してこれを表彰します
昭和四十二年十月四日
郵政大臣 小林武治
日本放送協会長 前田義徳
全国ラジオ体操連盟会長 迫水久常
なお昭和40年8月には、NHKアナウンサー柳川英麿が実地指導のため出張し身延小学校庭からその実況が全国に中継放送された。身延町役場ラジオ体操会殿
平素ラジオ体操の普及発達に積極的に協力し国民の体位向上に寄与せられその功きわめて大きいものと認めます
ここに記念品を贈呈してこれを表彰します
昭和四十二年十月四日
郵政大臣 小林武治
日本放送協会長 前田義徳
全国ラジオ体操連盟会長 迫水久常
(四) 各地区公民館主催体育祭
ア 下山地区体育祭イ 身延地区体育祭
昭和39年青年団主催で、一般社会体育振興の目的をもって開始した。
昭和43年からは公民館と共催で、門内上、門内下、梅平、波木井、大野清住町塩沢の5地区にわけ、地区対抗で実施している。
種目としては、野球、ソフトボール、バレーボール、卓球の四つである。
44年からは地区公民館主催の「町民体育祭」となり、多彩な競技種目をプログラムに組んで地区をあげての体育まつりとなった。
ウ 豊岡地区体育祭
豊岡地区では、昭和40年小中学校の屋内運動場建設を機会に、秋祭りを利用して、球技大会を実施してきたが、たまたま昭和42年に、国民の祝日として体育の日が制定されたので、球技のほかの種目も増加し、地区体育祭を開催することにした。
チームの編成は部落を合せて次の5チームとする。
小田船原、門野湯平大城、相又上下、清子、光子沢大久保横根(横光)
種目は、男ソフトボール・女バレーボール・民謡おどり・フォークダンス・競争遊戯等である。
昭和42年度優勝 小田船原チーム昭和43年度優勝 横光チーム
エ 大河内地区体育祭
大河内公民館では、球技大会、水泳大会などをとおして、地区の社会体育の振興に努力してきたが、昭和43年から、大河内地区各種団体の協賛により、多年の懸案であった、誰でもよろこんで参加できる地区体育祭を実施することになった。
 |
 |
|
 |
八木沢大垈・帯金・塩之沢椿草里・丸滝大崩・角打・和田・大島
種 目
球技(ソフトボール・バレーボール)踊り、競争遊戯等
12月1日(日)に第1回地区体育祭を実施したが、計画よろしきを得て、良好の成績を納め終了した。
(五) 育成会ソフトボール大会
昭和38年から、青少年育成親子ソフトボール大会として、郡主催で企画実施されてきた。昭和39年には、身延町代表角打チームは郡大会で優勝している。種々の理由により、昭和40年からは、町村独自で年々実施されている。
昭和43年からは、男女にわけ、女子の種目はバレーとなった。
地区予選の上それぞれ2チームが、地区の名誉にかけて年々奮闘している。
優勝チーム
ソフトボール
昭和40年度 波木井三区チーム
昭和41年度 角打チーム
昭和42年度 大野チーム
昭和43年度 清子チーム
昭和44年度 大島チーム
バレーボール
昭和43年度 大島チーム
昭和44年度 大島チーム
(六) 西八代縦貫駅伝
昭和25年にはじまり、年々実施され、すでに20回に及んでいる。上九一色村から、下部温泉までを5区にわけて、互に健脚を競っている。
わが身延町チームは、第1回から参加し、数回優勝している。
20回目にあたり、年々参加していることを、新聞紙上でも称えられている。
(七) 山の実会
柿島良行をリーダーとする、ハイキングの会である。身延郵便局員、身延町役場職員、その他また町外の参加者をも加えて、二十数名で組織されている。
すでに七面山・八紘嶺・甘利山・瑞牆(みずがき)山・鳳凰山等その他を踏破している。
毎月第1土曜を定例日として、種々話し合いをしている。会費は月200円である。
(八) 身延町野球連盟の活躍
昭和38年6月1日結成した身延町野球連盟は、年々春秋二季町長杯争奪野球大会をトーナメント方式で実施している。また山梨日日新聞社主催の、県下町市対抗野球大会には、連続出場し、すでに20回を数え、準決勝に進んだこともあった。
なお昭和42年度には、郡体育祭並びに県体育祭に出場し、ともに優勝している。
(九) その他
昭和22年、初冬大一製材赤塚社長が勧進元で、東京大相撲所属出羽海部屋大関汐の海、関脇千代の山一行の1日興行があった。昭和27年陽春にも、身延山で前記出羽海部屋横綱千代の山一行の1日興行があった。
古くから下山・波木井・元町・梅平・大城・清子・和田などで、草相撲があって、各地から力士が集って盛況だったが、今の下山をのこし殆んど廃(すた)れてしまった。
また和田・大島・相又などでは大弓を引いたというが、これも昔語りとなってしまった。
かくして時代とともに、レクリエーションの変遷ということを感じさせられる。
昭和32年8月7日、七面山登山競争が実施されたが、記録は一切不明である。
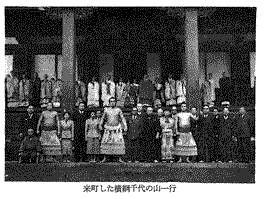 |
四、社会体育施設として利用できるもの
(一) 屋内運動場
名称 設置年月身延小・中屋内運動場 昭和36年12月
豊岡小・中屋内運動場 昭和40年9月
下山中屋内運動場 昭和42年2月
大河内中屋内運動場 昭和44年3月
(二) プール
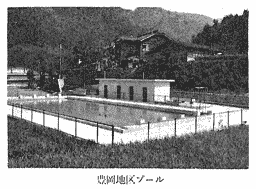 |
身延小プール 昭和30年2月
身延中プール 昭和30年7月
下山中プール 昭和36年7月
帯金小プール 昭和38年11月
大河内中プール 昭和39年8月
豊岡地区プール 昭和44年6月
五、身延町体育指導委員について
主として、町内の社会体育の振興を図るため、体育指導員を置いてある。指導委員は、次の規則にしたがって、職務に専念している。
身延町体育指導委員に関する規則(抜萃)
(職務)
第二条 体育指導員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行なう。
一、住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行なうこと。
二、住民のスポーツ活動促進のため組織の育成を図ること。
三、学校、公民館等の教育機関、その他行政機関の行なうスポーツ行事、または事業に関し、求めに応じ協力すること。
四、スポーツ団体、その他の団体の行なうスポーツに関する行事、または事業に関し、求めに応じ協力すること。
五、住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
六、前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言を行なうこと。
2、前項の規定により、体育指導委員が分担する地域、又は事項は教育長が定める。
(定数)
(定数)
第三条 体育指導委員の定数は五名とする。
(任期)
(任期)
第四条 体育指導委員の任期は二年とする。
(服務)
(服務)
第五条 体育指導委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2、体育指導委員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例ならびに教育委員会の定める規則、及び規程に従わなければならない。
3、体育指導委員は、その職の信用を傷つけ、またはその職全体の、不名誉となるような行為をしてはならない。(以下略)
体育指導委員(昭和44年4月現在) 委員氏名
吉野孝
小沢常敏
秋山実
山本寛
熊谷明治
吉野孝
小沢常敏
秋山実
山本寛
熊谷明治

