第二章 縄文時代・弥生時代
第一節 縄文時代
わが身延町にも数千年の昔、人々が住んでいた遺跡が確認されている。前章に述べたように、日本に人類が住みついたのは、数万年前からであり、県下においても1万年前にさかのぼることができるが、本町はさらに時代が下り、3,500年から5,000年以前の一時期であろうと推定されるのである。
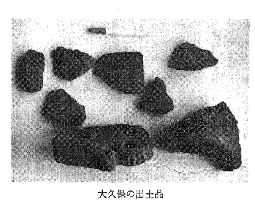
|
では、本町の遺物について、上野晴朗、山本寿々雄等の調査した結果や、その後発見された事実をもとにして、以下順に述べよう。
本町の遺跡として先ず大久保遺跡をあげることができる。大久保遺跡は地域的には身延町の最南端であって、遺物の豊富な南部町原間台地遺跡群と一連のものである。標高350メートル、富士川河岸段丘上にあって現在十数戸の農家がある。背後は標高約450メートルの榧の木峠をひかえている。遺物は唯勝寺裏の台地上(面積数アール)の墓地周辺である。たまたま数年前の豪雨の際、寺の背後の東組一帯から石器や、土器片多数が露出した。これを分類すると、縄文中期の加曽利E式・勝坂式・阿玉台式の系統が中心で中期初頭の頃の五領台式もわずかに認められた。石器も土器片に比べ数が多い。すべてが打製で石斧・石鍾・石鏃・皮
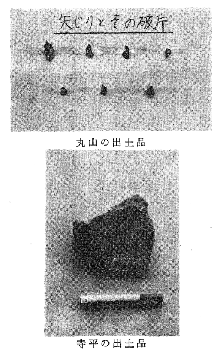
|
また、寺平にも遺物が発見された。その地域は波木井川の北岸の山腹にあって、標高407メートルのお塔林と呼ばれる旧寺院跡を南西にやや下った標高約360メートル付近のところで、そこに遺物の散布が見られたが、土器片は中期加曽利E式のものが認められた程度で大久保ほど種類が多くない。石器は大久保や丸山と同様、打製石斧、皮はぎが多い。(甲斐路No.14参照)
つぎに桜井もこの時代の遺跡地として認められる。桜井は塩之沢の南、標高約300メートル前後でやはり富士川岸の段丘上にある。南西に傾き平坦な段丘である。ここの神社西側の畑地から黒曜石の石核数個が発見されている。またその付近の畑地からも少量ではあるが、中期のものと思われる土器片や石器が発見された。(昭和43年度調査)
なお、その他和田、帯金、波木井一区にもこの期の遺跡と推定される条件をそなえているところがあるが、確実な遺物が発見されていない。
現在まで確認された本町の遺跡・遺物は以上の通りであるが、しかし、これを広く日本および県下の状況と比較検討して見なければ、当時の本当のようすは理解しにくいので、つぎにわが国および県下の概況を眺めてみよう。
わが国縄文文化の遺跡数は先土器文化に比べ一躍その数を増し、数千ヵ所におよんでいる。県下においても約400ヵ所の多きに達し、ほとんど遍く全県下に分布している。さきの先土器文化に比較していかにその文化が盛んであったかが推察できる。これら遺跡を時代区分の上から見ても早期のものはいたって少ないが前期になると一段と数を増し、中期にはその最盛期となり出土品の大半を占めている。後期、晩期は再び減少の傾向を示しやがて次の弥生期へと移行する。
更に遺跡分布を地勢の上から概観すると、最も濃密なところは笛吹川南側の曽根丘陵、御坂山地一帯である。これについで八ヶ岳山麓の高原地帯、郡内地区桂川流域の段丘上である。やや稀薄なところが盆地の北側と西側の山岳地帯縁辺の段丘であり、最も少ないのがこの本町の属する峡南地帯である。(「山梨県の考古学」参照)
では、一体この峡南の地方一帯の稀薄性は何に起因するのであろうか。縄文時代の人々は先土器人と同様、狩猟採集等の収集経済に立脚していた。したがって彼等の生活環境はそのための条件を備えていなければならない。彼等は、南面傾斜の日当りがよく、獲物や飲料水が得やすく、また竪穴住居であるため、水はけのよい台地や段丘上を選ばなければならなかった。ところがこの峡南の地は背後は峻嶮(しゅんけん)な山岳が間近に迫り、前面は急流の河川で渓谷は深く、わずかに河岸上は猫額大の段丘が点在しているというありさまなので、そうした条件に適合した土地が少なかったためではなかろうか。更にはまた、静岡に盛行した平地性文化圏と本県国中周辺の台地上に発達した文化圏のかけ橋の役目を担い飛石的に生まれた遺跡ではなかろうか。
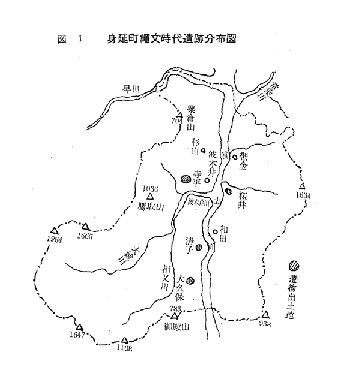
|
| 表1 南巨摩縄文遺跡主要地名表 「山梨県の考古学」の巻末の表より
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
彼等の住居は竪穴住居といい、排水のよい段丘上に3〜6メートルくらいのやや長方形で、深さ0.5〜0.9メートルくらいの竪穴を掘り、数本の柱を組み、屋根は草などを用い地面に接してふきおろした。生産手段としての農業生産の方法は全く知らず、生活の基盤を収集経済の上においた。だから彼等は毎日、付近の山野に獲物を追う狩猟に、河川に群がる魚を求める魚撈に、実りの秋には果実や草の実を、また四季折々の山菜を採集することに奔走したことであろう。各遺跡から発見された石鏃や石錘がこれをもの語っている。またこうして得た獲物は土器によって蒸され、焼かれて食膳に供せられたのである。なお土器はこのような炊事用ばかりでなく入れ物用ともし、あるいは信仰の対象ともされたといわれている。このように土器は彼等の生活と切り離すことのできない極めて重要な道具であったため、その製作に当たっては精魂を傾け、極めて芸術性豊かなものを作製した。大久保から出土した土器の中にも、こうした美しい文様のあるものが発見されている。こうして彼等は豊かな資源と、のどかな陽光の下で一家団らんの平和な毎日を送ったことであろう。
ところが、このように平和に暮していた中期縄文人は、どうしたことか縄文後期以降全くその消息を断ち切り、歴史時代にはいるまでの約2,000年の間考古学上全く空白期間となってしまった。このような中期の盛行した文化が以後とだえたのは、本町ばかりでなく中部山岳地帯に見られる一般的特徴である。このことについて甲州風土記に八幡一郎の説として「盛行した縄文中期の文化が長く痕(あと)をひいたため」とし、また、同書に藤森栄一の説として「気象の寒冷化による生活環境の変化」であろうと述べられている。

