二、南部氏と奥州
南部氏累代が甲州波木井郷に居館を持ち、陸奥国司北畠顕家卿について義良親王を奉じて活躍し、名を後代に遺したことは既に周知の事実であるが、爾来800年陸奥において綿々その家系を持して来たことや、いかにして陸奥の地で縁が結ばれたかを考察してみる。平泉藤原氏は
天児屋根命−8代略−鎌足−○−房前(北家藤原氏)−5代略−秀郷−5代略−清衡−基衡−秀衡−泰衡で、奥州藤原氏は清衡−基衡−秀衡−泰衡の父祖4代が相継いで奥州6郡を領知し、権勢を陸奥・出羽両国に張ったが、文治5年(1189)秋、源頼朝に征せられて約100年にして滅亡した。
頼朝が藤原氏を討伐したのは、弟義経を庇護したことを表面の理由にしているが、実は奥州藤原氏の強大な勢力を覆滅して鎌倉の源氏政権を強固にするのが目的であった。源平2氏が各地で合戦をし、死闘を繰り返しているとき、平泉藤原氏は富を擁し強大しかも奥羽17万騎の頭領と仰がれながらも、源平いずれにも組せず軍事行動を起こさなかった。頼朝はこの強大な経済力と軍事力とをそのまま放任しておけば、奥羽一円が鎌倉幕府に無縁の地方豪族として存在するの脅威を感じ、これを討滅し覇業を樹立するために追討の軍を出したのである。
文治5年7月19日、頼朝鎌倉を発向の時随従するもの1,000騎、鎌倉より供するもの数100騎、その中に南部一族信濃守遠光・加賀美次郎長清・加賀美太郎長綱・南部次郎光行の名が連ねてある。
頼朝が藤原氏を滅ぼし奥羽を平定すると、その功臣に奥羽地方に所領を与えたがその中に、南部光行に糠部五郡(二戸・三戸・九戸・七戸・北)を与えられその功を賞せられている。南部光行は、甲斐源氏の一族加賀美次郎遠光の三男として加賀美館に誕生、成長して南巨摩郡南部郷に入り、地名を姓として南部三郎と称した。
光行は領土糠部に建久2年(1191)10月に由比浜より乗船、12月28日進駐している。このことについて八戸家系に
とあるのは味わうべきことである。
越えて建久3年春、光行は三戸郡平良ヶ崎(南部村)に、築城したが管理行政責任者を残して鎌倉に帰った。
しかし南部氏が腰を据えて糠部郡を開拓したのは、承久の乱(1221)が終って北条氏が幕府の実権を握ってからである。
その頃北条氏は、安藤氏を蝦夷代官に住じ、津軽内陸を幕府の直轄地とし、また曽我氏に兵糧米収納の事務をとらせた。
南部氏の奥州下向は、これと時を同じくしているところを見ると、南部氏は甲斐の南部牧、波木井の牧監であったので、貞応元年(1222)に示された、鎌倉幕府の奥羽の牧場独占事業政策の用人に登用されたと思われる。
三、南部氏歴代の勤皇
南朝正統論の根拠は、人皇88代後嵯峨天皇の遺詔に端を発している。梅松論に 一の御子後深草院(持明院−後の北朝)御即位あるべし。下居の後は長講堂領百八十二箇所を御領として御子孫永く在位の望を止めらるべし。次に二の御子亀山院(大覚寺統−後の南朝)御即位ありて御治世は累代敢えて断統あるべからす。
と、そもそも我が日本は、肇国(ちょうこく)以来万世一系の天皇を載いていることを唯一の誇りとして来たのであるが、この皇位継承には、必ず祖宗伝来の三種の神器がこれに随うものであり、またこの継承は天皇の意志のみによって決定され、人民の容喙(ようかい)を許さないのが鉄則とされている。しかるに南北両朝に分れ長い間、国をあげて戦闘を続けて来たのは、後嵯峨(ごさが)天皇の遺詔を無視して、北条氏が権力をたてに皇位の継承に容喙し、元弘元年(1331)後醍醐天皇在位中にもかかわらず、三種の神器の伴わない光厳天皇を立て、更に延元3年(1338)足利尊氏が、後醍醐天皇にそむき、あまつさえ逆賊の汚名を免れるためにこれまた、三種の神器の伴わない光明天皇を立て、大覚寺統の子孫の滅亡をはかったのである。ここにこの暴虐(ぼうぎゃく)に対し、国家護持のため、大義明文のため、幾多の誠忠の士の尊い血潮が全国到る所に流された。この時代程麗しい国民性が発揮された時代はなく、これがすなわち南朝57年史である。
後醍醐、後村上、長慶、後亀山の4代にわたる戦闘の結果は、足利氏の勢力益々増大するに反し、南朝方の将卒相ついでたおれ、国民また永年の戦乱によって疲弊困憊(こんぱい)その極に達したので、元中9年(1392)後亀山天皇は不本意ながら、北朝との講和に応じた。しかしその最大要件は両統迭立ということであった。
その後、北朝ならびに足利氏は、聖約を履行せず、後亀山天皇の皇子小倉宮広成親王が皇位に即くべきを、応永18年(1411)11月、北朝後小松天皇の皇子躬仁親王を皇太子に立てた。この方が翌19年8月29日即位の称光天皇である。これがため南朝方は事あるごとに、皇位を要求して一歩も譲らなかった。
近年近衛家の秘庫から発見された資料で、明徳3年(1392)11月13日付の足利義満が河内前内大臣実為にあてた書状に
御合体の事、連々以兼熙卿申合候之処、入眼の条、珍重候、三種神器可有御帰坐之上者可為御譲国之旨、得其意候 自今以後両朝御統相代々御譲位 令治定候畢 就中諸国々衙 悉皆可為御計候 長講堂領者 諸国分一図可為持明院殿御進上候 以此等趣 吉田右府禅門相共可有執奏候 可得其意候哉 恐々謹言
明徳 三年十一月十三日
とありこれは原本ではないが、足利末期に写したものである。この義満の書状を意訳すれば明徳 三年十一月十三日
義 満
河野前内大臣殿 1、神器は譲位の儀式を以て後小松天皇に授け給うこと
2、自後の両統は代々迭立であるべきこと
3、国衙領は大覚寺統の御領たるべきこと
4、長講堂領は持明院統の支配たるべきこと
となる。この4ヵ条の条件のもとに後亀山天皇は吉野の行宮を出でて入洛し、50数年の両統の争は平静に帰したのであるが、しかし前述のように足利義満は聖約を履行しなかったので、南朝遺臣は義憤に燃え、遂に再び挙兵するにいたった。2、自後の両統は代々迭立であるべきこと
3、国衙領は大覚寺統の御領たるべきこと
4、長講堂領は持明院統の支配たるべきこと
南北朝時代に於ける国内勢力分布と甲斐の国
南朝系は伊勢を拠点として、大和・摂津・幡磨・備前・讃岐・遠江・越後・越中・信濃・駿河・河内・武蔵・甲斐・上野・美濃・尾張・三河等の神社・門跡・寺院等の莫大な領地と強大な武力を基盤として立ち、北朝系は幕府の武家の応援を得て対峙したのである。伊勢を拠点としたのは、
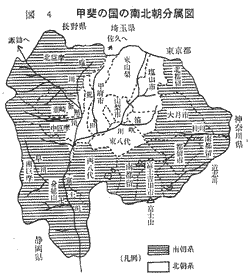
|
1、吉野朝の柱石北畠親房の南朝復興の拠点が伊勢の国にあったこと
2、吉野を中心として河内の楠木氏、南紀の熊野衆と連絡に便利であったこと
3、大湊は、東は関東から奥羽の官軍に、西は四国・九州の宮方に連絡が便利であり、古来造船業が発達し南朝唯一の軍港であること
4、南勢一帯は地味肥沃で、物質頗る豊かで、経済的支援が出来ること
5、皇祖太神の鎮産地に根拠を置くという、所謂帝王神権説の思想的・精神的・信仰的の理由によること
などの軍事的・地理的理由からである。そこで甲斐国の南北朝の分属はどうであるか、武田氏は信武・信成・信春の時代であるが、いずれも足利氏の部将となって各地に転戦して殊勲を顕わし、尊氏の寵遇を蒙り一族各地に栄え、甲府盆地中央いわゆる国中に勢力を張り、信濃の足利党小笠原氏と互に気脈を通じていた。
また都留郡富士谷(富士山の北麓をめぐる山中湖から南都留郡桂川上流の諸村)には、南朝宮方南部信光の私領があり、それに足利氏を仇敵とする北条の残党、この地に拠って南部一族と相通じ侮り難い勢力であった。
建武4年(延元2年)(1337)7月、武田陸奥守信春の勝沼大善寺に出した文書に「御敵初雁五郎当時炎上云々」とあり、
また本町相又区武田家所蔵「武田文元軍忠状」正平7年(1342)正月付に、
「甲州凶徒武田上野介以下等於七覚寺退治之間馳向致忠節訖」とあって上野介石和貞政が、東八代郡右左口村七覚山丹楽寺に拠って、信濃の武家方小笠原政長の部将武田文元と戦ったことを記してあるなどは、甲斐における南北朝の対立をうかがう有力の資料である。
なお、後村上天皇より南部氏に賜わった綸旨に
| 甲斐国神郷半分 | 大和 守跡 |
可令知行者天気如此悉之以状 |
(信光)
南部薩摩守館
| 甲斐国倉見山三分一 | 中野 入道跡 |
可令知行者天気如此悉之以状 |
(政持)
南部左馬助館
富士谷勤王の士には
朕末期の願也 足利将軍之一類の計策、繋りて無念骨髄に染む 朕が髑髏(どくろ)朽チ 晒シテ腐ル共一念魂魄(こんぱく)此世に止ルベシ而シテ日本男子忠臣之汝等国賊足柄一類退治を望むこと此の如し、仍て院宣執達件の如し。
甲辰年四月五日(応永廿三年)
外勤王忠臣之義士中
の後亀山院末期の院宣が下ったので、南部氏をはじめ南朝勤王の各地の代表は、明応7年(1498)8月15日に富士谷に集まり、大評定をしたことを考えると甲州富士谷が南朝勤王の重要な拠点となったことと思う。甲辰年四月五日(応永廿三年)
密院使
日野右少辨邦氏
富士谷大統領 三浦越中守道次外勤王忠臣之義士中
以下南部累代の勤王についてしるす。
二 代 実 継
南部実継は甲斐南部氏の祖、実長の嗣子である。南部家文書に、実継出生の奇瑞として、
就其梅平之鎮守 梅花一枝之夢想を実長公之室被為蒙、彦次郎実継御出生、童名梅平(うめひら)ト申候キ等之儀モ、弥初其御書附ヲ以存候、珍長之事々、亥年被下候御書附共ニ一冊之書ニ悉記認并其御本紙共ニ添此西文庫ニ什物と共ニ可収置候云々
梅花一枝之夢想を実長公之室被為蒙、彦次郎実継御出生、童名梅平(うめひら)ト申候キ等之儀モ、弥初其御書附ヲ以存候、珍長之事々、亥年被下候御書附共ニ一冊之書ニ悉記認并其御本紙共ニ添此西文庫ニ什物と共ニ可収置候云々
上の文書は身延山第34世見竜院日裕上人が、八戸若狭守(南部家26代信有)病気平癒祈願の為め、七面明神に御刀(備前忠光)一腰、本阿弥の添状をつけて奉納のため代参した宇夫方平太夫に対する、口上書の一節である。日蓮聖人身延入山後、波木井郷蓑生を身延と改めてから門内身延の地発展し、やがて身延が波木井郷の中心となるに至り、波木井郷(九村南部家旧記)が身延村と変り、かつて波木井郷の中心であり、波木井館の所在地を実継の幼名をとって梅平とし、旧波切(昔は富士川舟運の舟着き場であったためか、波切、または破切ともいわれた)の地区を波木井としたものであろう。
実継は甲州波木井郷に生まれ、幼名を梅平(うめひら)と呼び、長じて彦次郎と称した。
南部実継の事績については、日蓮聖人身延山御書中、弘安4年11月25日、鎌倉出仕中の南部六郎殿に送った書状の中に、
次郎殿等の御公達、親の仰せと申し我心に入れて御座しますことなれば、われな地を引き柱を立て、藤兵衛、右馬の入道、三良兵衛ノ尉等、己下の人々一人も疎略の義なし云々
とあり、また波木井公御書に 畏こみ申し候道の程別の事候はで池上まで着きて候、みちの間、山と申し、河と申し、そこばく大事にて候けるを、公達に守護せられ参らせ候て難もなく是まで着きて候云々 弘安五年九月十九日
これを小川泰堂居士の「日蓮聖人」伝には 波木井入道は、次男彦次郎実継をお伴にさしそへ・・・難処多かる此程の旅、彦次郎実継厚く介胞し給ひ云々
と述べて日蓮聖人池上御出立の御供したことが記されているだけで、他のことは知られなかったが、千葉県藻原町藻原寺所蔵、金綱集裏文書に(和漢並列体)
然りと雖も明春は、必定して急速に参上いたすべし。
一、二品親王尊良親王、元弘二年(一三三二)元弘の変により、北条氏のために土佐に流され、延元二年(一三三七)(金崎城で自殺)御遠流定めて披露せられ候歟、御供奉召籠めらるるの処、日記先度進め参らせ候間、備に御覧候ぬらん、此人々今月十三日六条河原に於て切られ候言語同断の事、令見物、凡哀れは何れも大方の事に候、中に南部次郎殿 初に切られ候こそ、都て目あてられず、なにしにいでて、まのあたりうき作法見聞仕候哉と覚て候けれ、はら殿御心中察申候九日より京中以外に騒動に候、阿賀川に朝敵充満し、山崎よりせめいり候間、宇津宮、赤松入道打手を賜い、早速追返し候了んぬ、仍ち仁定寺(忍頂か)に城廓を構へ、引籠り候を、宇津宮ついて責候、即ち昨十五日打落頸其多数持参せしめ候、是大塔宮御所為に候也其外京中処々にて、日々召し取られし人数言語及び難く候、禅僧二人押寄せて、在々処々御供の雑談息延さこそ思い出され候はヾ、いよいよ徒然もまさり、心もうかれ候はんと案ぜられ候、此の如く巨細状捧じ候条尾籠無申計候、自然の至りに候、御免有るべく候、千日殿、秋山殿内裏門前にして対面の時伯耆律師御□□、鎮西より御上りて候、是に御座候と申候しはよも存じなきの間遂に面謁に及ばず候
初に切られ候こそ、都て目あてられず、なにしにいでて、まのあたりうき作法見聞仕候哉と覚て候けれ、はら殿御心中察申候九日より京中以外に騒動に候、阿賀川に朝敵充満し、山崎よりせめいり候間、宇津宮、赤松入道打手を賜い、早速追返し候了んぬ、仍ち仁定寺(忍頂か)に城廓を構へ、引籠り候を、宇津宮ついて責候、即ち昨十五日打落頸其多数持参せしめ候、是大塔宮御所為に候也其外京中処々にて、日々召し取られし人数言語及び難く候、禅僧二人押寄せて、在々処々御供の雑談息延さこそ思い出され候はヾ、いよいよ徒然もまさり、心もうかれ候はんと案ぜられ候、此の如く巨細状捧じ候条尾籠無申計候、自然の至りに候、御免有るべく候、千日殿、秋山殿内裏門前にして対面の時伯耆律師御□□、鎮西より御上りて候、是に御座候と申候しはよも存じなきの間遂に面謁に及ばず候
一、下山の南方関所に治定候て或は壁書にをし、或は恩賞のそみ申人々多候事、随分歎き申して罷り過候、かく存候とは此方此方はよも思食候はす候、自然事も候はヾ謗法之地と成候はん事悲しく覚え候 一人も誘はれ候て、闕所たるまじき由をも申し開き、安堵をもなと申されず候やと存候、愚身等が一族の中にも申者多き中に、縁者こそ多候へ共、みな謗法者にて候間、下山の方々におも口かへ存候、所存なく候、此段は御在京の時も、大方令申し候と存候、但随世習に候へば、愚身が名字ばかりは御隠密に預かるべく候か、但又訴訟何もさうなく達候はん事も又ありかたく候、人々申候事は如此候、恐々謹言
(元弘二年)十二月十六日 僧日静(花押)
一、二品親王尊良親王、元弘二年(一三三二)元弘の変により、北条氏のために土佐に流され、延元二年(一三三七)(金崎城で自殺)御遠流定めて披露せられ候歟、御供奉召籠めらるるの処、日記先度進め参らせ候間、備に御覧候ぬらん、此人々今月十三日六条河原に於て切られ候言語同断の事、令見物、凡哀れは何れも大方の事に候、中に南部次郎殿
一、下山の南方関所に治定候て或は壁書にをし、或は恩賞のそみ申人々多候事、随分歎き申して罷り過候、かく存候とは此方此方はよも思食候はす候、自然事も候はヾ謗法之地と成候はん事悲しく覚え候 一人も誘はれ候て、闕所たるまじき由をも申し開き、安堵をもなと申されず候やと存候、愚身等が一族の中にも申者多き中に、縁者こそ多候へ共、みな謗法者にて候間、下山の方々におも口かへ存候、所存なく候、此段は御在京の時も、大方令申し候と存候、但随世習に候へば、愚身が名字ばかりは御隠密に預かるべく候か、但又訴訟何もさうなく達候はん事も又ありかたく候、人々申候事は如此候、恐々謹言
(元弘二年)十二月十六日 僧日静(花押)
僧日静(1298−1369)は京都本国寺第24代妙竜院と号す。駿河の人、俗姓は藤原氏、父は上杉氏、修理亮頼重、母は足利家の女である。師小字は豊寿磨と云う。幼より世相をいとい、同州池田村本覚寺日住に投じて出家する。
実継は後醍醐天皇の第一皇子尊良親王、北条高時への謀反を授けたる罪明らかとなり、六条河原に於て斬首されたのである。第2項の「下山の南方は身延を指したので、南部家文書の実継の名の見えないのは、実継の処刑によって、身延山の闕所となるを懼れたためにこれが関係文書を湮滅(いんめつ)したものと思う。また、文中に「伯耆律師鎮西より上洛す」とあるから日蓮宗の僧侶が鎮西に使したことも知ることが出来る。
また「愚身等が一族の中にも申者多き中に、縁者こそ多候へとも、みな謗法者にて候間」とあるより見て、足利氏の縁によって日蓮に帰依し出家したのではなくて、恐らく駿州加島の産であるから、本覚寺は当時の名刹であり、身延山末寺であったため、身延山と縁が深く、第5代日台上人が実長の裔孫であるという関係上、特に南部実継のことについて知らせて来たものであろう。
元弘2年3月、後醍醐天皇隠岐へ遠流となり、皇子尊良親王もまた遷流された。尊良親王はさきに天皇に従って笠置山に入り楠木正成の赤坂城にも移り、弟護良親王とともに京畿の地に奮闘したのであった。この時、尊良親王に従って軍忠を誓った諸士また幕府の兵に捕えられ、12月13日、六条河原で斬られたもの多く、その中に老齢の南部実継、先ず第一に斬られたのである。前掲日静の書状に「南部次郎殿最初に被切候こそ都目もあてられず」とあるのは、身延にあって地頭実長の子として、日蓮聖人にも親しく接していた実継が最後を、図らずも京都にあって目撃した僧日静が、身延の南部一族の日台上人に宛てた一文であろう。
かくて実継は六条河原に斬られたが、その他の史実全く湮滅(いんめつ)して何等徴すべきものもないが、南北争乱期の将士の動向として、概ね名利に専らであって大義を省みず、南朝・北朝孰れにもその時節に戦の利ある方に加担し、昨日の友は今日の敵、時々刻々帰趨(きすう)を豹変(ひょうへん)するが世の通念であった。この動乱の世相に毅然として起ち、建武中興の先駈けをしたのである。そして後に続く、長継・師行・政長・信政・信光・政光の累代に亘る甲斐南部勤王史の劈頭(へきそう)を燦然(さんぜん)たる光輝を以て飾ったのである。

