二、武田家親族衆としての穴山氏の活動
穴山信友は出生、武田信虎におくれること12年である。信虎が甲斐一国を平定、更に信州に進出しつつも性情過激にわざわいされて、娘婿今川義元のもとに追われた時信友は武田の中堅としての地位にあり、信君は2歳前後である。武田の勝利を確実にした第4回川中島の永禄4年(1561)の前年、信友は卒した。三方ヶ原合戦の元亀3年(1572)には信玄は52歳、信君は32歳でこの作戦に当たり戦場で大活躍している。
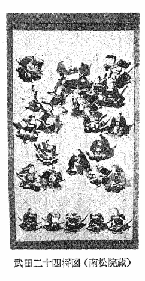
|
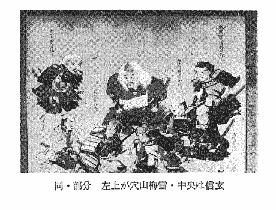
|
その死の永正10年(1513)前後は甲斐一国の支配を目指しての信虎の悪戦苦闘の時期であり信懸は常に信虎に最も信頼されてその力をつくした。
5代信綱は享禄4年(1531)に没していてこの時は信虎が石和より府中の地へ居館して12年目、甲斐国内の諸勢力を整理し国外勢力と国境内外において対抗していた時期である。
この間の信綱は国志が引いているように飯田系図に「小田原北条家ノ為ニ討死 弓法相伝 五人張大勇力荒馬乗り」とあるのをみれば信虎陣営にあってその豪勇をうたわれていた様子が偲(しの)ばれる。下山竜雲寺に信綱愛用の鐙(あぶみ)が寄進されているのも何か暗合するものを思わせる。この頃の信友の行動を語るものもまたないのだが父信綱の死の前後信虎の女、後の南松院殿を夫人に迎えていたはずであり青年武将として信虎陣営の一翼を担(にな)う重要な地位にあったわけである。
晴信の代になって後の信友、信君父子の武田親族衆としての活動は誠にめざましく、それを記録する諸文献も多数残されているのであるが郡内小立の妙法寺記(勝山記)、栗原左兵衛の高白斉記(甲陽日記)、甲陽軍鑑、その他の文書等からそれを概観してみたい。
妙法寺記天文14年(1545)の項に
更に高白斉記の天文18年9月晦日の項に
これは今川義元の家臣一宮出羽守が義元の意を伝えて来たので彼を坂木の豆州つまり伊豆守信友の所へ遣わした。だが信友は例の大酒振舞いのみで談合は調わなかった、ということでその背景には上杉、武田の争いがありその調停役を今川氏がしており、信玄は小山田、穴山をその交渉に当たらせていることを現わしていると説明している。
国志に初鹿島望月喜兵衛蔵として年不明の今川氏真より信君に送った次の書状
があるが、前出の天文24年の晴信から、竜淵斉に与えた文書に関連したもので一宮出羽守を武田、上杉の調停役としてさし向けた。
今川氏が高白斉からさしたる儀なく越軍退散との報があったので安心とは思うが其の後如何(いかが)であるか承りたいので陣中へ飛脚をおくったというのである。
信友が信州の戦線で活躍している時、子の信君も20歳から30歳の間の年ぐらいで同じく武田の戦列にあって活動していたのである。なお晴信の竜淵斉への書状の「いつもの例式で信友は大酒振舞で大切な、問題の核心にふれなかったので、」とのべているあたり信友に対する晴信の感情がかえって濃(こま)やかであることが言外にあらわされていると見るべきであろう。そしてまた信友の「例式の大酒振舞」は武田の外交を担う者としての悠(ゆう)容せまらぬ、奥深い手腕の程をうかがわせるものがあって興味深い。この文書から推して今川氏真も父義元のかげにかすんでしまっていたのではなかったことが知られる。
この今川氏真が永禄3年(1560)父義元の桶狭間戦死後は今川家を統卒(そつ)することとなるのが信君へのこの書状のころから18、9年後の永禄11年の暮には叔父である信玄自身の猛撃をうけ、駿府を占領され遠州へ落去することとなるのである。
義信が父信玄によって永禄10年(11年の説もあり)自害させられたのは氏真の生母、義元夫人が信玄の姉であり、自分の妻がその子であったことから、おそらく父信玄の今川打倒に同調できなかったことがその要因の一つではなかったかと思われる。
また2月小朔の項に
とあるがこれは天文19年正月から始まった義元の女と信玄の長子太郎義信との婚約の件についての総仕上げがなされたことを示すものであり、そのため一足早く駿府(静岡市)へ赴いていた穴山信友宿へ使者が赴(おもむ)き、ここで穴山信友は一宮出羽守、高井兵庫と相談し婚儀について義元へ披露し、3日義元の婚約の誓文を得て飛脚でそれを甲府へとどけたのである。高白斉記によると義元の女はその年の11月21日駿府を発った。
その頃に「廿一日御新造様駿府を御出、興津に御泊り廿三日うつふさせ廿四日南部 廿六日下山 廿六日西郡 廿七日乙巳酉戍の刻府中穴山宿へ御着」とある。
甲斐国志巻之百二十一に下山百姓蔵として
とあり、永禄3年(1560)義元戦死後の今川氏真に対する重要な交渉のため信友(幡竜斉)が長期にわたって駿府にあり、これに対し信玄が深い感謝と信頼をこめて送った書状で年不明であるが義元戦死後間もなくのものであろう。
永禄12年(1569)信玄は2度目の駿河侵入を行ない大宮城を攻め浅間神社の富士兵部少輔を降伏させたが信濃史料第十三巻の長野県の次の玉井文書
をみると浅間神社の富士氏を信君に従がわせ、城明け渡しをさせている。また前記同巻に
とあり、信州平定に際しての信友の役を駿河大宮では子の信君が継いでいる状況が見える。元亀3年(1572)10月3日、信玄は約2万の大軍をもって甲府を発し雪の信州路を経て遠州に出撃し12月22日夕刻三方ヶ原で家康および信長の援軍と戦って大勝したがこの信長包囲陣営の中にあって最も有力な勢力であった浅井長政は元亀4年2月21日付の書状を信君にとどけているが雄図空しく信玄が没したのはこの年の4月12日のことであった。
この長政の「武田左衛門大夫殿人々御中」とした書状は信君の長政への書状に対する返書であって、信玄の尾張、美濃への進出を待ち望み、朝倉義景と固く連繋していることをのべ、将軍義昭の書状をともに進献するとの内容のもので信君が上記信長包囲外交上の枢機に任じていたことを示すものである。(この書状は現在石和・土屋益雄蔵)
ちなみに浅井氏朝倉氏が信長に滅ぼされたのはこの年の8月のことであった。
以上の他に信玄から信君への身延山日叙上人保護を依頼した永禄初年の書状、同じく信玄から信君への年代不明の身延山の10月の会式に参集する僧俗への通行上の保護を恒例のように執行すべきことを命じた書状がある。
これらは信玄時代の穴山信友、信君の武田家における活動を示すものであるが勝頼の時代に入っての状況を次に述べる。
国志巻之百二十一に宮原村桜林保格蔵文書、
をのせているがこれは天正2年(1574)5月、遠州高天神城を勝頼が攻め落した際降伏した小笠原長忠の取り扱いについて信君におくったものである。また同巻に古府要法寺蔵として次のようにのせている。
これは高天神を落して一時勢のあがった勝頼ではあったが天正3年5月21日の長篠の戦で織田、徳川連合軍に大敗して以後はまさに落日的状態となり高天神を守っていた信君もまたこの大勢の中で徳川方と戦って敗北を喫し、そのため勝頼に御祈祷礼と蝋燭(ろうそく)との送致を願ったものである。文書は天正3年の筈である。また下山一之宮蔵文書の中に
これは山県三郎兵衛が長篠合戦で天正3年戦死しているので天正3年以前となりまた高天神が前年5月勝頼によって陥落しているので天正2年の6月のもので人事上の要件についての書状である。なお信君が江尻城主と確定したのは山県の戦死に伴ってのことであるのがわかる。また国志同巻に相又村百姓蔵とし
国志に年代は按ズルニ天正8年也とある。信玄の死、長篠の敗戦と次第に衰退の色を濃くしつつあった武田勢であったが天正8年勝頼はその前年から北条氏政と対戦していた。
氏政は家康に応援をたのみ家康は何かの条件を信君に再三申し入れたらしく、その真相を勝頼は知りたがっている。そして江尻城主信君に油断なきようはげましの言葉をおくったのであった。文面に勝頼の不安焦燥の気持ちがにじみ出ている。そしてまた信君に対する大きな期待と信頼をあらわしている。
以上諸種の文献の示すように穴山氏は武田親族衆の中でも特にその活動が際立つのであるが、その活動は信友としてもまた信君としても単に武弁として武田親族衆の中に座を占めていたのではなく武田氏の対外交渉の要路をになっていたことがわかり、信友、信君の幅広い人物像がおのずから浮かびあがってくるのである。
広大な自領を持つ穴山氏の地位と実力は郡内を領した小山田氏とともに武田家の下にあって形は小山田と似てはいるが内容は全く違う武田分国内での再支配を行なっていたのであった。このことは後述する中で明らかにしたいが穴山氏に向けて発せられた信虎、晴信の文書の性格は、小山田氏に出された監視的、警戒的文書とはその性格を異にする。
後述するように穴山氏は本宗武田と全く同型の直臣、被官をもち、各種の奉行、代官の組織を持ち自領経営に細密な手を打ちつつ終始したのであった。