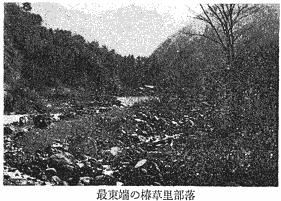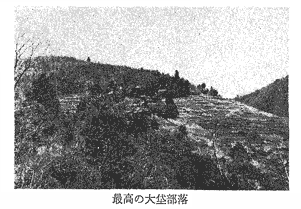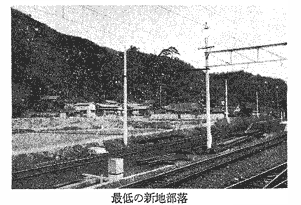第二節 集落の分布と形態
一、概説
集落の分布と形態についての分類は、いろいろなされているが概要次のように分類されている。1 人口の程度による分類
2 集落の形態による分類
3 集落の成立原因による分類
4 地域による分類
 |
(一)人口の程度による分類
人口の程度による分類は、従来内閣統計局などで人口10,000人以下を村落と見ていたがこれは便宜的な分類方法で深い根拠のあるものではないといわれている。(二)集落の形態による分類
形態による分類としては、街村・円村・散村・塊村・集村等の類型や、荘宅式村落、垣内式村落等に分類されているが、身延町には前者の類型が多い。(三)成立原因による分類
この分類では、都市分類として門前町・宿場町・城下町・港町・市場町などがあり、村落の分類として開発新田村、隠遁(とん)百姓村・寺百姓村・豪族屋敷村・多田百姓村などがある。身延町には、都市分類として門前町・宿場町・城下町の例はいくつかある。
しかし、村落の成立原因による分類としては客観的資料に乏しく、分類決定が困難で記述できなかった点は遺憾である。
(四)地域による分類
この分類では、集落が分布している地域によって郊村・農村・山村・漁村等に分類されている。郊村は、都市周辺の集落形式で、漁村は、海岸地帯に分布する集落で、ともに身延町には該当例はない。身延町における地域分類は、一部を除いて大部分が農山村である。
以上集落分布の形態についてその類型を概説したのであるが、以下個々の集落について述べることにする。
二、身延町の集落
(一)下山地区 図2・3参照
ア、小原島 図2参照小原島は、上組(8戸・31人)中組(11戸・47人)下組(10戸・41人)から成っている。身延町最北端の集落で、上沢から、西へおよそ3.6キロメートルのところにある。粟倉山(704メートル)の支峯が北に延びる麓(ふもと)で、早川が大きく蛇(だ)行している。
この蛇(だ)行によって形成された氾濫(はんらん)原を後背地として、やや街村形態をして分布している農村である。最近における早川奥地開発事業の活況と相俟(ま)ち、その人口を扼(やく)しているともいうべき位置にあって将来の発展が期待される。
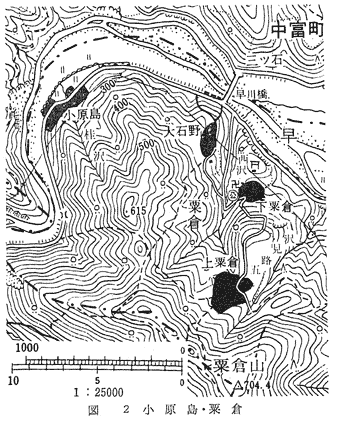 |
粟倉は、早川橋右岸(7戸・23人)下粟倉(16戸・77人)大石野(7戸・27人)上粟倉(8戸・19人)から成っている。
早川橋右岸は、中富町に通ずる県道と早川入り県道との分岐点で、山梨交通のバス発着所があり、この方面の交通上の要地である。粟倉山の麓(ふもと)が絶壁状をして県道に迫り、県道は直ちに早川の岸に境して平坦面はほとんどない。住居は護岸工事を施して定められ、食堂、雑貨商などを営んでいる。
大石野は、早川橋の東およそ200メートルにある西沢の小渓流が、深い浸蝕(しょく)谷を刻む西傾斜面に塊状に分布している農山村である。
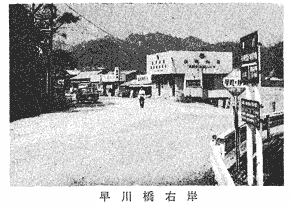
|
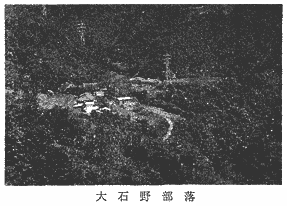
|
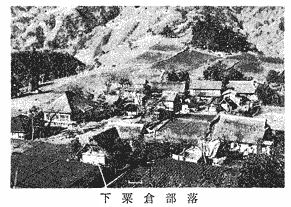 |
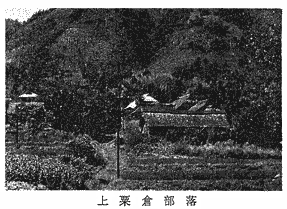
|
上粟倉は、粟倉山の中腹480メートル付近に塊状をなして分布する農山村で、人口の都市集中化の世相を反映して、青年は離村しさびしい集落となっている。
ウ、下山 図3参照
下山は、上沢(83戸・385人)大庭(45戸・166人)本町(40戸・177人)仲町(49戸・200人)竹下(17戸・90人)大工町(48戸・229人)新町(43戸・143人)山額(24戸・95人)荒町(62戸・252人)杉山(21戸・89人)の10区から成っている。
下山は、歴史の町として有名で歴史編に詳説されているように、古くは巨摩郡西河内領下山庄のあったところで、駿州路の伝馬宿であり、往時における交通の要衝(しょう)でもあった。また中世甲斐源氏の一流であった下山氏の城下町でもあり、降っては、戦国時代の武田家の門葉穴山氏の城下町でもあって、これらに係わる神社・寺院・古蹟も多く今に当時の名残りを留(とど)めている。
歴史の町下山は、地形的にも恵まれている。町の北端上沢付近から北にかけて早川の河口氾濫原が広がっている。町の東部一帯には富士川氾濫原がある。この両氾濫原は、上沢付近を接点として東西およそ500メートル南北およそ2キロメートルに及び、その大部分はよく整備された水田で文字通り下山地区の穀倉地帯をなしている。
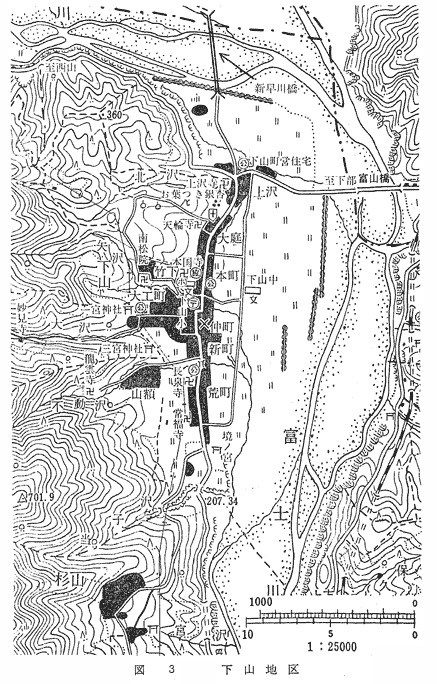 |
これら小渓流は、流域に西から東に傾斜した扇状沖積地を形成し、10メートル乃至(ないし)20メートルの較差をもって富士川氾濫原と境している。下山は国道52号線をはさんで典型的な街村形態で南北2キロメートルにわたって分布している。上沢、大庭、本町、仲町、新町、荒町の大部分は街道に面し、竹下、大工町は街村よりやや西の丘陵性をした沖積地に、一部散村的に一部集村形態で分布している。街村全体がそうであるが、特に竹下大工町のあたりは高燥地で排水もよく、西から東に適当な傾斜をしていて住居地として最も適している。大工町は、昔から下山大工の出身地として有名で腕利きの大工が多数輩出した部落で、部落名もここからでているといわれている。なお、国指定の天然記念物となっている「上沢寺の御葉付イチョウ」は上沢の上沢寺に、「本国寺の御葉付イチョウ」は本町の本国寺にある。
山額部落は街村の西およそ300メートルのところにある集落で、奥之院の東麓、海抜約500メートル付近に源を発している不動沢の渓流が、深い浸蝕(しょく)谷を刻んで平地に出る渓口に、階段的にやや塊(かい)状に近い形態で分布している。渓口は、小規模ながら扇状地を形成し、集落地理の教える典型的渓口村ともいえる。
杉山部落は、街村下山を去るおよそ2キロメートルの南にある農村で、奥之院の東麓にあって垂直分布およそ360メートルである。下山より身延山に通ずる裏参道に臨んでいる。現在この参道は、参道としてはほとんど利用されていないが、かつては北よりする身延山の参道で殷賑(いんしん)を極めたと伝えられている。この裏参道は昭和41年県道に編入され目下改修中で、完成後は、身延山と下部温泉を結ぶ自動車道ともなり観光面でも活況を呈することと思われる。既に述べた通り下山は、恵まれた地理的条件と豊富な歴史的要素とを兼ね備えた峡南における有数な集落である。
なお昭和43年10月には、上沢を起点とする新早川橋(幅員8.5メートル延長557メートル)を含む延長2,170メートルの新国道52号線が完成し、従来の早川橋を迂回して中富町方面に至る距離を約2.88キロメートル短縮し、この方面における交通は一段と便利になるとともに、上沢付近は、下部町方面、中富町甲府方面、早川入り方面に至る3分岐点として峡南地方における交通上の要地となった。

|
 |
 |
 |
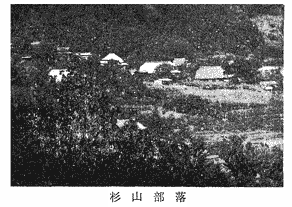 |