(二)身延地区 図4参照
イ 波木井一区波木井一区は、城山一里松(9戸・48人)古屋敷(9戸・46人)神之平(11戸・58人)から成っている。
城山一里松は、西川と深沢の小渓流が浸蝕谷を作って東に流れ、この両浸蝕谷に挟まれた海抜300メートルの丘陵の西縁380メートル付近に分布している。身延山裏参道に面し、かつて波木井六郎実長の城址のあったところといわれ、城山の名もここから出ているといわれている。
古屋敷は、丘陵の東縁が富士川に臨むところに散村形態に分布している。往時の下山邑と南部御牧との分界点でもあったといわれている。
神之平は、西川の浸蝕谷が東西に開いている緩傾斜面に、やや塊状に近い形態で分布している農村である。
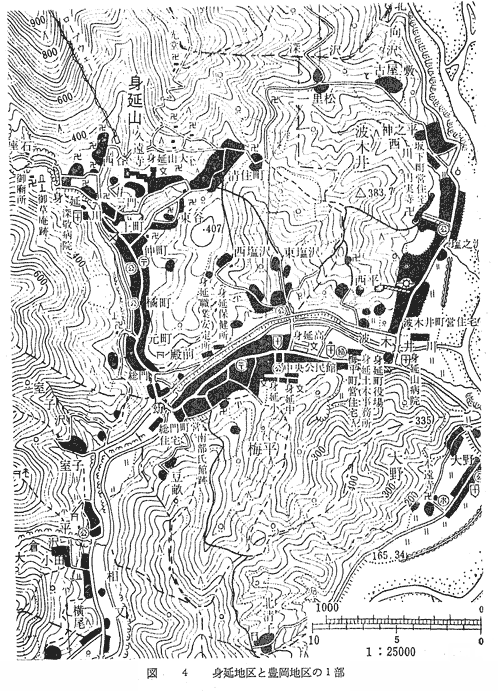 |
かつて富士川舟運が華やかであった頃の、舟つき場として有名であった波木井二区は、大原(9戸・50人)町屋向(9戸・45人)向出(7戸・28人)西村(11戸・60人)西素麺屋町(10戸・51人)東素麺屋町(9戸・42人)坂下町営住宅(20戸・75人)から成っている。
城山一里松の南に源を発している西川は、海抜200メートルから300メートルにかけて流域に沖積地を作って東南に流れ、170メートル付近で富士川氾濫原に出て東に流れ富士川に注いでいる。国道52号線は、氾濫原の西縁を南北に走り、これに沿って二区の一部は街村的に分布している。他の一部は、西川流域に集村形態で分布している。西川流域及びその氾濫原は、二区の背後地となっている。波木井六郎実長を開基とする波木井山円実寺は、海抜300メートル付近の山麓にある。
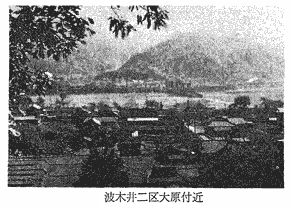
|
 |
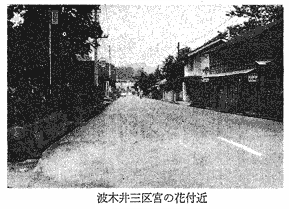 |
波木井三区は横丁(19戸・76人)日軽金社宅(12戸・50人)仲町(24戸・105人)宮の花(8戸・30人)宮の下(7戸・32人)宮の下町営住宅(15戸・59人)西平(20戸・75人)から成っている。
波木井三区は、国道52号線に沿って二区に続いて南に延びている。
仲町、宮の花は、国道に沿って街村形態に分布し、横丁及び日軽金社宅は、氾濫原が西に尽きる山麓に散村的に又塊状に分布している。
宮の下及び町営住宅は、氾濫原上の西部に集村的に分布している。
西平集落は、三区の西にあって海抜300メートルより200メートルにかけて南面する山の中腹に散村分布している。二区三区ともに国道に沿って一部商業を営む外は大部分農業を営んでいる。
エ 塩沢
塩沢は、かつては久遠寺の寺領であり八日市場という名称で呼ばれたところで、塩沢川の渓流が南に流れ波木井川に注いでいる。この小渓流の東に東塩沢(12戸・46人)があり、西に西塩沢(24戸・103人)がある。両塩沢は、ともに小起伏に富む山の中腹及び流域に散村的に分布し農業を営んでいる。
塩沢区に属する殿前の一部(24戸・94人)は、波木井川左岸の狭長な段丘及び山麓に散村的に分布している。殿前は、かつて旧身延町時代、学校や諸官衙のあったところであるが、その後逐次他に移り今僅かに身延公共職業安定所、身延保健所、県職員公舎が残っているだけである。
オ 清住町
清住町(36戸・154人)は、奥之院の麓、海抜360メートル付近に、身延山裏参道に面してやや街村の形態を分布している。往時よりここは新宿とも呼ばれたところで北よりする身延山参拝路で、いわば裏の門前町ともいうべきところであったが、現在ここを通る参拝客はほとんどなく町並は淋しくなっている。街村に近い分布形態が昔の名残を留めている。
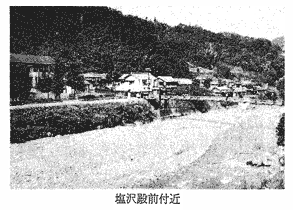 |
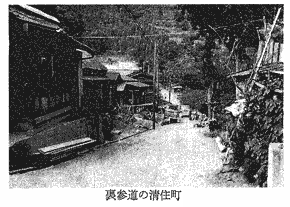 |
東谷(11戸・73人)は、身延山久遠寺の東南寺平(407メートル)と久遠寺との境を流れる片隈沢の流域一帯に分布する集落で、11戸は寺院となっている。身延鏡にある八谷の中の1つで西谷とともに1区を形成している。
キ 西谷
西谷(44戸・270人)は、鷹取山(1,036メートル)および追分に源を発している田代川2支流が海抜360メートル付近で合流し更に2キロメートル下流で樋沢川を合わせ身延川となる地域をいい、区内21の寺院は、身延川の浸蝕谷に臨む南面した傾斜面に階段状をなして分布している。域内には救癩施設として有名な深敬園や日蓮宗信行道場もあり、また日蓮聖人の御草庵跡、御廟所も近く、深山幽谷の感が深く霊地にふさわしい自然のただずまいをしている。
 |
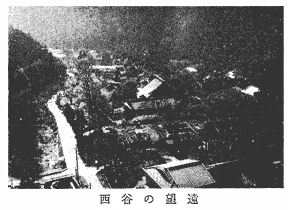 |
身延鏡に、「まづこの山は甲斐国巨摩郡波木井の郷の乾(いぬい)にあたり、蓑夫(みのぶ)の沢と申し侍りしに、元祖大聖人文永11年甲戊5月12日に鎌倉を御出でありて、同17日に此の沢に入り給う。元祖御入山ありて蓑夫を身を延ぶる山と書きあらため給うなり」とあり、また同書注に蓑夫山について、「蓑着たる農夫がうづくまれる形の山を身延山と改め給う。身も心も延び延びと延ぶる山、寿命無量の寿量品の山、延寿の山と開顕し給う」とあって身延という地名の由来を最もよく言い表わしていると思われるので、その一節をここに引用した。
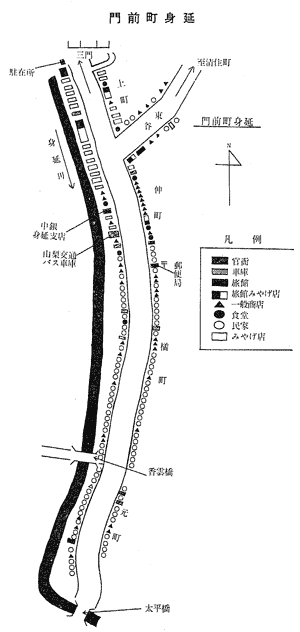
|
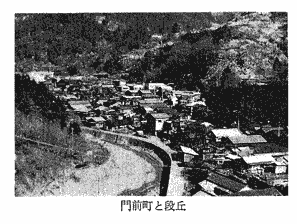 |
佐々木清治理学士は、著書の「郷土地理研究法」の中で門前町を、御陵門前町と寺院門前町とに分類し、更に寺院門前町を、奈良時代の平地仏教、中世における天台・真言の山岳仏教・近世における真宗・浄土宗・臨済宗・曹洞宗・日蓮宗等の山岳と平地を兼ねた仏教に分類し、その門前町発達の特徴を説明している。
日蓮宗は、近世における仏教の中でも庶民に最も信仰された宗教で、各本山は、或いは平地に或いは山地に、全国各地に建立されその門前町の発達を促したのである。門前町身延は日蓮宗総本山久遠寺の門前町として、日蓮聖人の庶民を吸引する力、境内の自然美、祖師堂をはじめとする堂塔の人工美、最近における交通機関の発達等と相まってますます発達したものと思うのである。
以下門前町身延の地形的位置、町の景観、段丘と門前町、参拝客等について具体的な記述をしてみたい。
(ア)門前町の位置
町の西を流れているのが身延川で、三門付近で樋沢川、上町付近で東谷からくる片隈沢を合わせ、南に流れて太平橋の下流で波木井川に注いでいる。この身延川の左岸三門付近から太平橋までのおよそ1.5キロメートルにわたって狭長な河岸段丘が発達している。
門前町身延は、この狭長な段丘上に典型的な寺院門前町の形態で分布している。
(イ)門前町の景観
略図が示しているように、太平橋を渡ったところが元町で三門から最も遠く、他の町並に比較して町が寂しく、門前町の華やかさは感じられない。家並みも普通の住宅で、職業も普通の勤め人や身延山などで木材業に従事している人が比較的多く、ただ女の人などで旅館や宿坊に手伝いに出ているものは相当に多い。
橘町に入ると、元町よりやや華やかさを増してくるが、それでも普通の田舎にある町と変りはない。職業も植木屋・建具屋・豆腐屋・数珠製造・湯葉製造・その他一般商店等でいわゆる門前町らしい雰(ふん)囲気は感じられない。
仲町にゆくとやや門前町らしい華やかさが出てくる。それも山梨交通株式会社のバスの発着所付近から上町に近いところで、その手前の仲町は一般商店街とそんなに変りはない。商店も一般雑貨商・食料品店・文房具店・薬店・写真店・洋品店等である。それでも元町・橘町に比較すると店頭などの華やかさは増してきている。
上町に入るとさすがに門前町らしく、身延山に因(ちな)んだみやげ店も多くなり、店頭は美しく装飾され出入の客も参拝人が多く活気と華やかさが感じられる。旅館も2階建、3階建となり食堂等も門前町らしい雰囲気が多分に感じられる。
(ウ)段丘と門前町
元町から上町まで町並みは何とも狭苦しいという感じで一ぱいである。狭い段丘に制約された町並みという感じが極度に目立つ、そして全体を通じて間口が非常に狭い。これは、ここがもと身延山の寺領であったが、第11代日朝上人代に平等に分け与えられて現在に及んでいて、この間栄枯の変遷はあったものの平等に与えられた狭い間口は、今にその名残を留め狭い間口を奥行で工夫し、段丘の西端崖まで極度に利用している。
なお元町から上町まで、道路は緩傾斜をしておりまた曲っている。狭い間口の上こうした自然条件の制約を受けているので、家の建築も道路と並行していない特別の作り方をしている。
(エ)参拝客
最近における参拝客は、団体バス、自家用車等を利用するものが多くなり、従って的確な数の把握は困難であるが、国鉄身延駅利用客の数はある程度正確を期することができる。
昭和42年度(自昭和42年4月 至昭和43年3月)における身延駅利用客数を調査した結果を次表で見ることにする。
年間身延駅利用客総数916,524人のうち遠距離客と団体客は全部参拝客と見なして差支えなく、その総数は292,073人である。なお近距離客の中にも参拝客があるので年間参拝客総数は、概算40万人と推定されるので貸切バス自家用車利用者50万人を加えると総計90万人の参拝客がある。なおこの参拝客の中には観光を兼ねたものもあって、月別にして5月・8月・10月が最も多く、7月・1月・3月がこれに次いでいる。このことは身延山の行事や観光シーズンとの関連が考えられるのである。これらの参拝客は、数軒の旅館や東谷西谷にある23の宿坊に宿泊するが、旅館にしても宿坊にしても宿泊者は固定しているといわれている。従って客引きということがなされない。
参拝客を地域別に見ると、やはり東京が一番多く、愛知・静岡・大阪・岡山・新潟・神奈川・北海道がこれに次ぎ、大体全国に及んでいるといわれている。
(資料は身延線管理長室営業課提供による)
|
ケ 梅平一区
梅平一区(99戸・427人)は、身延川が波木井川と合流し東流するあたりから右岸に河岸段丘が発達し、この段丘上に散村形態で分布している農村である。
段丘の西南で北に面した山の中腹に豆畝の部落がある。垂直分布およそ280メートルから300メートルで緩傾斜地を利用して農業を営んでいる。また段丘の南縁山麓に、日蓮聖人に帰依した南部六郎実長公の館址と廟がある。
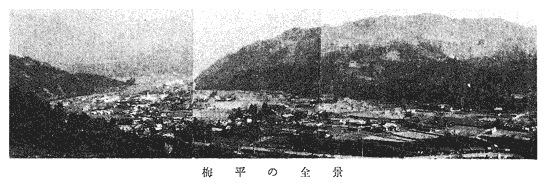 |
梅平二区は(144戸・554人)梅平河岸段丘が東に尽きるところあたりから広がる波木井川氾濫原に、一部散村的に、大部分は国道52号線を挟んで街村形態で分布している新興商店街であり、官衙学校街でもある。
かつては氾濫原を背後地とする全く寂しい散村であったが、大正12年(1923)4月、旧制県立身延中学校がここに創立されてから一躍峡南における教育文化の中心地となり、その後身延小学校、身延実科高等女学校(現身延中学校舎)も移転し、国道52号線も通じてますます発展し、今に見るような商店街となった。昭和30年2月旧下山、大河内、身延、豊岡の1町3村が合併し、新町役場庁舎が波木井橋のたもとに建設され、その後、身延山病院、身延土木事務所、東京電力身延営業所等も相次いでここに移り、更に昭和43年6月には町民待望の身延電報電話局が身延高校の西に開設され、また身延町農業協同組合の新築もあり梅平二区は名実共に政治、教育、文化の中心地となったのである。

