大野は、家の前(19戸・94人)南天畑(24戸・113人)島(20戸・76人)中沢(20戸・92人)北清子(3戸・15人)から成っている。
部落は南北およそ1キロメートルに及ぶ富士川氾濫原を背後地として県道を挟んで街村形態をして分布している農村である。
部落の西南に大野山本遠寺がある。身延山22世日遠上人の開山で、紀伊頼宣卿の母堂養珠院お万の方の廟のある由緒深い寺で、かつては門前町も繁栄を極めたとのことであるが、山梨、静岡両県を結ぶ国道52号線が梅平から相又に通ずるようになってから街道は逐年寂しくなり、参拝客も減少してきている。富士身延鉄道(現国鉄身延線)開通以前富士川舟運の華やかだった頃は峡南における舟着き場として繁栄した部落で、寂しくなった街村形態の中に栄枯の歴史がしのばれる。北清子は、街村大野の南およそ1.8キロメートル、垂直分布約300メートル、中山の東麓に分布する農村で、最近における離村傾向を反映して人口は漸減している。
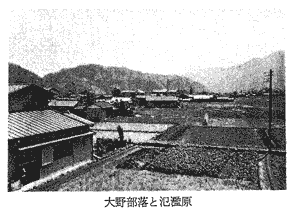
|
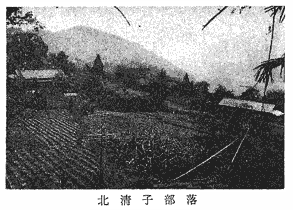 |
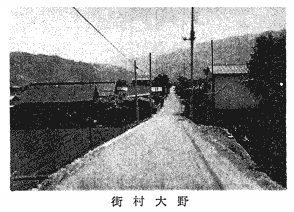 |
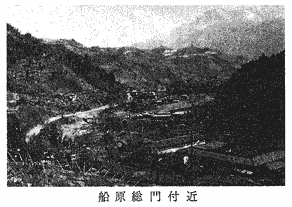 |
(三)豊岡地区 図4・5・6参照
ア 船原 図4参照船原は、身延山総門の南側から南に続く町並みで、総門組(17戸・69人)、町営住宅組(7戸・23人)、室子(もろご)組(13戸・66人)、平組(14戸・63人)から成っている。
図4からわかるように、集落としての総門組は一般商店が多く商業街を形成している。
室子部落は、室子沢の南海抜260乃至340メートル付近の山の中腹に階段状に散村形態で分布している農村である。
平部落は、大倉沢が作る浸蝕谷に臨む南傾斜面に、散村形態で分布している農村である。町営住宅は、波木井川左岸の沖積地にある。
イ 小田(おだ) 図4参照
小田は、小田(12戸・99人)、横尾(12戸・43人)、三段池(9戸・51人)から成っている。
大倉沢の渓流が波木井川に注ぐ河口付近から南へおよそ800メートルにわたって段丘が形成され、国道52号線はこの段丘に沿って南北に走り横尾を経て相又下部落に至っている。
段丘の北端、海抜260メートル付近の国道沿いから300メートル付近に散村状に分布している農村が小田部落で、横尾部落は、相又川大城川の合流点に形成された小氾濫原を背後地として散村的に分布している農村である。横尾から大城部落に通ずる県道を西に約300メートル行ったところが三段池部落で、大城川の沖積原から山の中腹にかけて散村的に分布している。
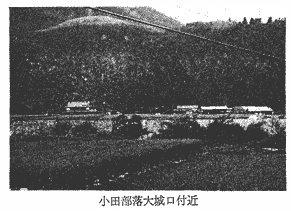 |
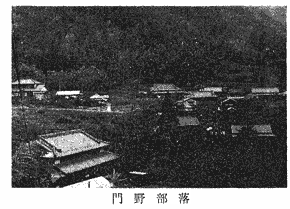 |
ウ 門野と湯平 図5参照
門野(25戸・127人)湯平(13戸・50人)は、湯沢川の渓流が大城川に注ぐ河口に分布している典型的な渓口村で、地域的分類からする農村である。
湯沢は、大城川の河岸段丘を浸蝕しそこに小規模ながら扇状地を作っている。この扇状地の土壌は粒子が大きく礫(れき)が多く、渓谷の傾斜の大きいことを物語っている。この湯沢川の渓谷に臨んで、左岸に門野部落が階段状に集村し、右岸に湯平部落が、一部は湯沢川の浸蝕谷に臨み、一部は大城川の河岸段丘面に階段状に分布している。
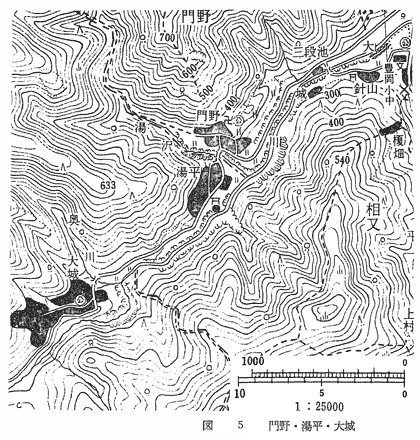
|
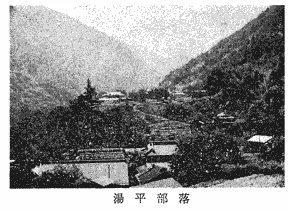 |
大城は上(14戸・81人)、中(17戸・69人)下(21戸・107人)から成っている。
奥川と宮沢の小渓流が合流するところに渓口村として発達した農村で、垂直分布は360メートルから400メートルである。門野・湯平と同様、渓谷が平地に開ける扇状地に分布している農村で、山麓から河岸段丘にかけて階段状に分布している。段丘面は礫が多く谷の浸蝕のはげしさを思わせる。
大城は、古くは駿州路への間道で、間道を守衛した遠藤伊勢守の墓が部落の西の山の手妙覚寺にある。大城という部落名も間道を守衛した城砦(さい)からきていると甲斐国志に見えている。
オ 相又下 図6参照
相又下は、針山(10戸・32人)、通り(10戸・33人)、上之段(11戸・32人)、榎畑(2戸・6人)から成っている。
通り組は、相又川と大城川が合流付近に作っている氾濫原上を南北に走っている国道52号線に沿って分布している。
針山部落は、相又川大城川の合流点からおよそ200メートル上流の大城川右岸にある段丘上に散村状に分布する農村で、段丘の東縁に豊岡小中学校がある。
榎畑部落は、針山の南海抜360メートル付近の山の中腹に分布する農村である。
上之段部落は、榎畑の東相又川右岸の河岸段丘にやや集村形態で分布している農村で、部落のほぼ中央に大石山正慶寺がある。文永11年日蓮聖人が相州鎌倉より身延へ入山の際ここに休息を取り、土地の住人・庄左右衛門夫妻が粟飯を献上し教化されたという由緒(ゆいしょ)ある寺で、聖人が座したという腰掛石も境内にある。粟飯を首(こうべ)に戴き冠りたる姥という故事からその子孫が粟冠(さつか)をもって氏とすることも甲斐国志にみえている。
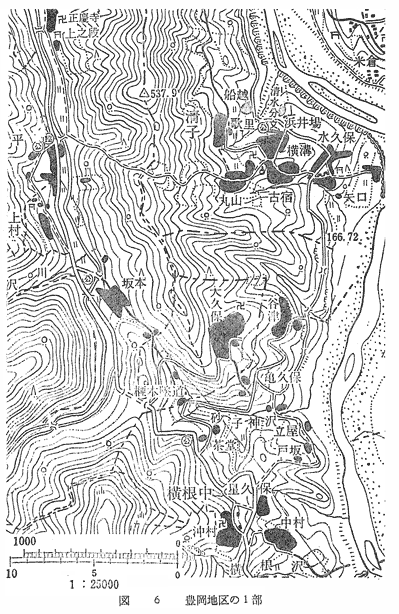
|
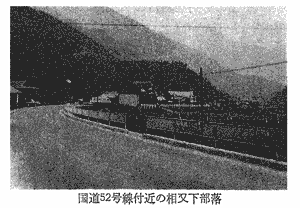 |
相又上は、漆久保・平・上村(16戸・59人)、坂本(21戸・99人)からなっている。漆久保、平、上村の各部落は、相又川左岸の河岸段丘上を南北に通ずる国道52号線に沿って一部は散村的に、一部は国道の西、海抜360メートル付近の山腹に散村的に分布している農村で、ここも人口の都市集中化の傾向を反映して戸数人口ともに漸減している。
坂本部落は、平・上村部落の南およそ500メートル、相又川右岸の河岸段丘が石仏峰(榧木(かやのき)峠)の山麓に尽きる付近に、やや集村に近い形態で分布している農村である。
キ 大久保 図6参照
国道52号線が榧木トンネルを南に出たところが大久保で、中山(537メートル)の峰が南に尽きるところに砂子神沢の渓流が深い谷を刻んでいる。砂子神沢の北およそ800メートルに大沢の小渓流が深い浸蝕谷を刻んで東に流れて富士川に注いでいる。この両浸蝕谷に挟まれた小丘陵地に、東(11戸・37人)、西(5戸・20人)、奥(5戸・22人)の部落が散村形態をもって分布し農業を営んでいる。
部落の東端に道長山唯勝寺がある。付近一帯から採集された石器や土器片が陳列されている。
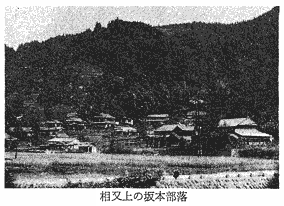 |
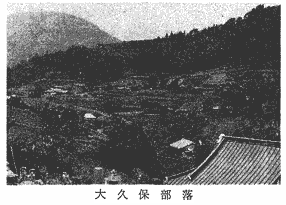 |
ク 光子沢 図6参照
大久保部落の東に隣接しているのが光子沢で、付近一帯は軟弱な土壌で鶯歌和川、砂子神沢の両渓流がここを深く浸蝕して谷を作っている。この浸蝕谷に風化が加わり小起伏に富んだ地形となっている。この小起伏の間に、谷津(5戸・22人)・長畑(8戸・34人)・下組(10戸・37人)の部落が点々と散村的に分布している。平地が少なく従って耕地に乏しく、水田は階段状に開拓されている。
ケ 横根 図6参照
横根は、中村(11戸・53人)・沖村(8戸・39人)・昇り組(8戸・36人)から成っている。
光子沢の南に隣接し、南は南部町中野に境している。また横根地内には地質の軟弱なところがあってしばしば地すべりを起している。中野区との境界を東流する横根沢が深い浸蝕谷を刻んで富士川に注ぎ、更に、北およそ500メートルにも柳沢の小渓流があり東に流れ富士川に注いでいる。これら渓谷に挟まれた山地は光子沢と同様小起伏に富み、この小起伏に富んだ山地を縫うようにして、中村が国道52号線の東に散村的に、昇り組、沖村は西にやや集村に近い形態をして分布し、養蚕業・養鶏業などを営んでいる。なお、日蓮聖人にゆかり深い桜清水の霊場は玉林山実教寺に近く、部落の西にある。
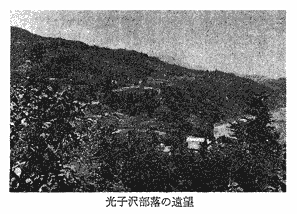 |
 |
コ 清子 図6参照
清子は、丸山(10戸・44人)、船越(5戸・22人)、歌里(9戸・40人)、浜井場(7戸・37人)、水久保(7戸・33人)、横溝(6戸・27人)、矢口(13戸・54人)、清水(6戸・18人)古宿(10戸・42人)から成っている。
中山の東麓、海抜200メートルから300メートルにかけて段丘が東西約800メートル南北約1キロメートルにわたって開けている。段丘の東縁は較差30メートルをもって富士川氾濫原に接している。西端に分布する丸山、船越両部落は垂直分布も最高で約280メートル、両部落を最高にしてこれより段丘の東縁海抜200メートルにかけて歌里・浜井場・横溝・古宿・水久保・矢口の各集落が部分的には塊状に近く、全体的には散村状に近い形態で分布している。清水部落は、一部は、氾濫原土に、一部は段丘上に散村形態で分布している。富士川氾濫原はほとんど全部が水田に開拓され、段丘上は大部分畑作地帯で段丘上を流れる二渓流の流域に一部階段状をなして水田が開けている。
清子はかつて静岡県に通ずる幹線道路に臨んでいたが、国道52号線が相又川に沿って通ずるようになって取り残され、交通不便な僻地集落に変った現在道路改修再開発の途上にある。なお丸山・横溝からは縄文中期の石器や、土器の破片が採集されている。
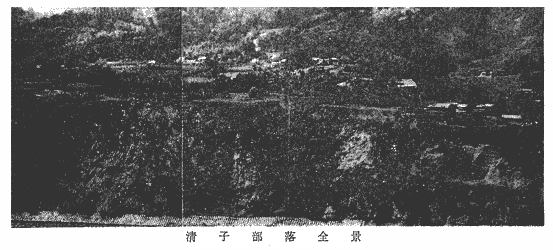 |

