(四)大河内地区 図7・8・9・10・11・12参照
ア 上八木沢 図7参照上八木沢は、鰍原(8戸・30人)、上向(12戸・51人)、下向(12戸・44人)から成っている。
鰍原は、隣接する下部町から西流する常葉川が富士川に注ぐ河口付近に形成した段丘に塊状に近い形で分布している農村である。
上向、下向両部落は、鰍原を距る南およそ500メートル、毛無山脈の支峯に源を発している松葉沢の渓流右岸の扇状沖積地から南面した山麓にかけて、集村に近い形態で分布している農村である。国指定の天然記念物である「八木沢お葉付イチョウ」は、雄株で山神社境内にある。
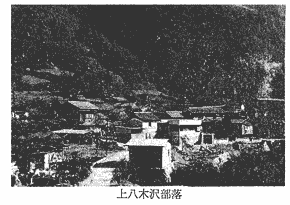 |
イ 下八木沢 図7参照
下八木沢は、石倉(5戸・21人)、上向(8戸・38人)、下向(8戸・27人)、向(8戸・25人)から成っている。
不動沢の渓流が、西に流れて富士川に注ぐ河口付近に小段丘が形成されている。また流域には狭長な沖積地が、東西およそ400メートルにわたって開けている。これら段丘と沖積地は水田に開拓されている。この沖積地右岸に散村に近い形態で分布している部落が上向で、河口段丘に散村的に分布する農村が下向で、不動沢左岸から南に散村形態で分布している部落が向である。
石倉は、不動沢に臨む海抜およそ300メートル付近の南面した山腹に、やや塊状に近い形態で階段的に分布している。
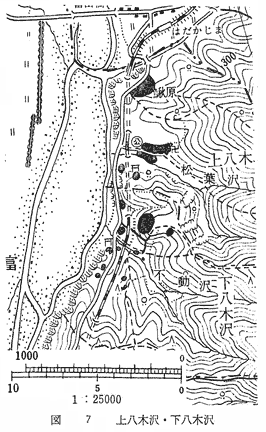 |
 |
ウ 大垈 図8参照
大垈は、部落の東を深い浸蝕谷を刻んで南に流れる大垈川を南に臨む傾斜地に、階段状に、やや塊状に近い形態で分布している農山村である。垂直分布で760メートルで身延町最高の集落である。かつては、下部町川向部落も大垈部落に所属していたが、明治22年に分村したことが、大正8年(1919)の村政報告書に見えている。現在戸数は7戸、人口は35人であるが、文化年間戸数は26戸、人口は124人と甲斐国志には見えている。戸数人口の激減はもちろん分村のためであるが、最近における離村傾向も人口減少を一層助長している。
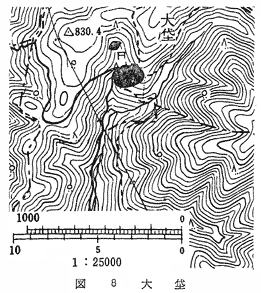 |
エ 帯金 図9参照
帯金は、上方(20戸・91人)、下北(19戸・72人)、上小路(17戸・68人)、南小路(14戸・56人)、泥之沢(23戸・75人)から成っている。
集落発生が、地形に強い制約を受けることは、しばしば述べてきたのであるが、帯金部落の分布形態と地形の関係は、集落地理の教える典型的なものと考えられる。すなわち、地形図から観察できるように、背後地として富士川氾濫原がよく発達している。上方部落より塩之沢に至るおよそ1.5キロメートルの氾濫原がそれである。そして住居決定に必要な南に面した排水佳良な高燥地として扇状沖積地がある。北から大久保沢、見付沢(上流は入沢)泥之沢、薬師沢の諸渓流が、富士川氾濫に出るところに作っている沖積扇がそれである。
上方部落は、大部分が大久保沢の作る扇状沖積地にやや集村に近い形態で分布し、一部は湧泉を求めて東の山麓に集村形態で分布している。下北・上小路・南小路の各部落は、見付沢の作る扇状沖積地に集村に近い形態で、泥之沢部落は、泥之沢及び薬師沢が作る扇状沖積地に散村に近い形態で、それぞれ分布している。
集落地理の一般形態をしている帯金は、また歴史の集落でもある。上小路の東、入沢が平地に出るところが地頭帯金刑部の居館址で、維新当時まであったといわれる判行(はんぎょう)の跡も上小路下小路の十字路に残っている。また上小路南小路の町並みも京都平安京に擬して作られたといわれている。
刑部一族にゆかり深い上方部落にある若宮八幡神社は、帯金刑部信継が相州鎌倉の鶴岡八幡を勧請したものと伝えられている。甲斐国志に、「本村地沃ヘ民多シ、東河内一二ノ寛邑ニシテ、今ニ属村拾貳頗ル旧矩ヲ存シタリ」とあって当時の繁栄を物語っている。
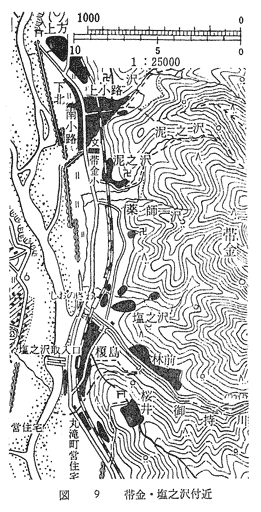 |
 |
オ 塩之沢 図9参照
塩之沢は、塩之沢(30戸・132人)、林前(12戸・63人)、榎島(20戸・77人)、日軽金社宅(6戸・17人)から成っている。
帯金上方付近から南に延びる富士川氾濫原は、御持川及び塩之沢渓流が河口に作る扇状沖積地と、国鉄塩之沢停留場付近で接している。塩之沢部落は、大部分塩之沢渓流の左岸に発達している。小規模の段丘上に、やや集村に近い形態で分布している一部と、御持川の扇状地に散村的に分布している一部とからなっている。
林前部落は、御持川の河口の上流およそ500メートルの御持川右岸に形成する段丘上に散村形態で分布している農村である。
榎島部落は、御持川扇状地の左岸に、旧街道を挟んで小規模の街村形態をして分布している。段丘及び扇状地は大部分水田に開拓され、塩之沢の背後地をなしている。
日軽金社宅は、塩之沢取入口の富士川左岸の段丘上に県道に沿って分布している。
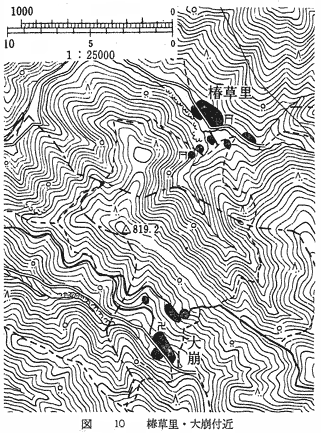
|
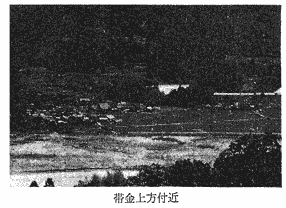 |
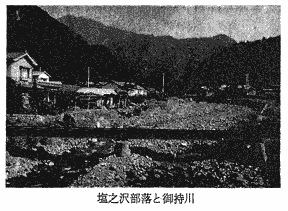 |
カ 椿 草 里 図10参照
椿草里(10戸・43人)は、身延町最東端の集落で、国鉄塩之沢停留場から御持川に沿って約4キロメートルの上流にあって、垂直分布約460メートルである。五宗山(1,634メートル)に源を発している椿川(下流は御持川)の上流は三支流に分れている。この三支流は合流点に小さい扇状地を作っている。椿草里はこの扇状地に散村に近い形態で分布している農山村である。部落の下流凡そ1キロメートル付近は、浸蝕谷の谷壁が垂直に近い状態で谷底に臨んでいて、下刻の激しさを示している。この浸蝕谷の下刻から部落のある扇状地は、かつては漏斗状盆地であったものと推測される。
部落では、椿川の渓流を利用して近代的養鱒業が営まれている。椿草里の部落について「按ツルニ椿草里ハ山茶アル所ニ焼畑ヲ開墾セル故ヲ以テ村名トナレルカ」と甲斐国志村里部に見えている。
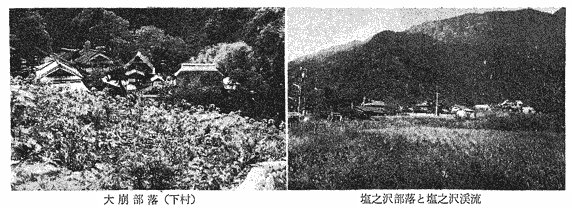 |
|
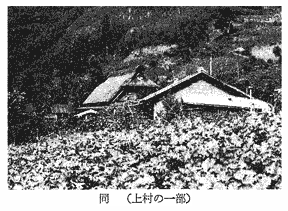 |
|
キ 大 崩 図10参照
大崩(10戸・40人)は、国鉄身延駅より桑柄沢の渓流に沿っって東およそ4キロメートルの上流にある。垂直分布下村およそ500メートル、上村およそ600メートルで大垈に次いで高い。
下村は、桑柄沢に臨む南面した傾斜面にやや塊状に近い形態で階段状に分布している。
上村は、それよりおよそ100メートル高くやや散村的に分布している。ともに農山村で、しいたけやわさびを栽培している。
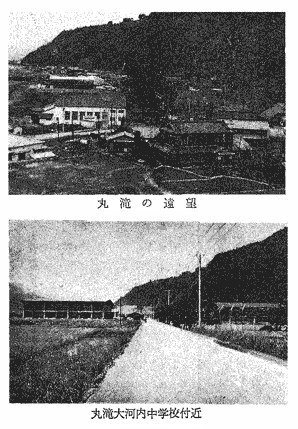 |
ク 丸 滝 図11参照
丸滝は、丸滝(46戸・202人)、沖村(22戸・103人)、桜井(10戸・51人)、町営住宅(20戸・73人)から成っている。
丸滝は、三つ石山(1,173メートル)の麓に源を発している桑柄沢が、富士川に注ぐ河口付近に作っている扇状沖積地の北部に、集村に近い形態で分布している農村である。丸滝部落の南は角打区に属し、扇状沖積地は、この角打区に属する国鉄身延駅の裏通りから身延駅本町通りまで及んでいる。丸滝が集村分布している扇状地は、南に高く北に低い地形で住居地としては不適であるが、排水佳良であり、高燥地で水利もよいので集落の発達を見たのである。
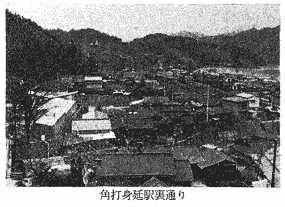 |
沖村付近一帯は、富士川氾濫原で、丸滝の水田地帯であったが、明治43年(1910)および大正7年(1918)の水害で荒野と化した。しかし、その後護岸工事も完成し、日本軽金属株式会社による塩之沢のダム設置と相俟(ま)ち、水害の危険も少なくなり、ここに大一製材所の設立を見、更に昭和26年7月大河内中学校が設置されて、沖村付近は丸滝の中心地の観を呈するようになった。
丸滝町営住宅は、沖村の北およそ700メートル、富士川左岸段丘上に県道沿いにある。
桜井部落は、丸滝山の北麓、海抜およそ300メートルにやや集村的に分布している農村で、先史の遺物の発掘を見る考古学研究の対象地でもある。
丸滝山の麓には、懸流20メートルの不動滝があり、かつて大野山開山の日遠上人がここに遊んだという古蹟ともなっている。滝の落ち口近くに芭蕉句碑が立っている。丸滝という地名も滝に因んだものと甲斐国志に見えている。
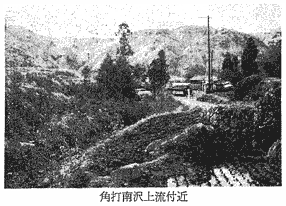 |
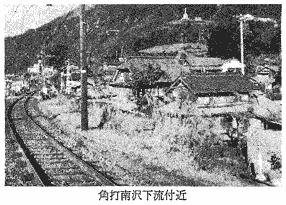 |
身延橋のたもと(袂)から南1キロメートル余の南沢の渓流に至るまでの広い地域に分布している集落が角打で、中央部に国鉄身延駅がある。角打は町行政区では最大のもので、現在、旧村(46戸・221人)、身延駅前(44戸・225人)、身延駅本町(40戸・196人)、身延駅裏(44戸・171人)、国鉄官舎(17戸・60人)美登見町営住宅(17戸・67人)、町営住宅市路団地(16戸・44人)となっている。
旧村は、南沢北沢の両渓流が、富士川に注ぐ河口に作る扇状地と流域の段丘に集村に近い形態で分布している。
町営住宅市路団地は、南沢の流域に分布している。
身延駅前通りは、富士川河岸段丘上に駅前繁華街を形成している。
身延駅本町は、駅前繁華街に続き、富士川左岸の河岸段丘上及び桑柄沢の扇状地にかけて商店街を作り身延橋のたもとまで及んでいる。
身延駅裏通りは、桑柄沢の扇状沖積地から宮沢扇状地にかけて山麓に沿って南北に長く集村している。
国鉄官舎は駅裏にあって一隣組を形成している。
美登見町営住宅は、駅裏集落の東に続き桑柄沢左岸の段丘上に分布している。
国鉄身延駅は、前身である私鉄富士身延鉄道の時代に設置されたもので、大正9年(1920)5月の完成である。ついで昭和3年(1928)3月身延甲府間が開通し、東海道線中央線を結びいわゆる表日本裏日本の連絡路となっている。更に昭和13年(1938)10月国営移管となって現在に至っている。
身延駅が誕生して50年になる。50年の歴史の中に身延駅は、名実ともに身延山の玄関として発展を続けてきている。
身延駅付近一帯は、かつては一面の水田で民家は1軒もなく、建物としては子神社があるだけで文字通り狐狸の出没する寂しい地域であった。
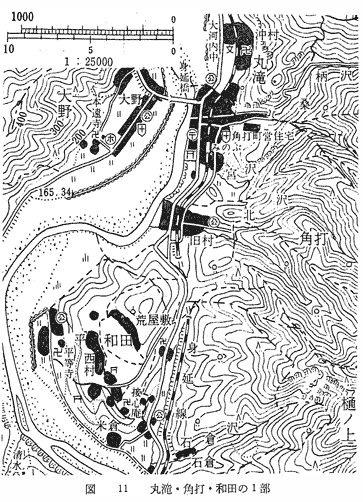
|
コ 和 田 図11参照
和田は、荒屋敷(7戸・40人)、西村(24戸・100人)、平(16戸・76人)、米倉(30戸・129人)、樋之上(8戸・39人)垈・針原(7戸・37人)から成っている。
 |
平部落は、台地の麓で富士川が大きくメァンダーを作る左岸の氾濫原に集村的に分布している農村である。
米倉部落は、田之沢・石倉沢の二つの渓流が、富士川に注ぐ河口に作る扇状地と富士川氾濫原との複合地帯の北部山麓に、集村分布をしている農村である。
東坂は、米倉の一部で、田之沢渓流に面した東傾斜面に散村状に分布している。
時雨沢も米倉の一部で、石倉沢の扇状地に散村状に分布している農村で、紀伊頼宣郷の母堂養珠院の方が訪ねた古蹟のあるところである。
新手は、渡々沢渓流が富士川に注ぐ河口の河岸段丘に散村に近い状態で分布している農村である。
樋之上は、図12に示されているように、新手の東、海抜およそ200メートル付近、渡々沢渓流の深い浸蝕谷に臨む段丘上に、散村形態で分布している農村である。
針原は、樋之上の東およそ2キロメートル、垂直分布約340メートルにある農山村で、垈は、針原から上ること東約1.5キロメートル、垂直分布540メートルにあり、針原とともに、しいたけ栽培で名高い。
 |
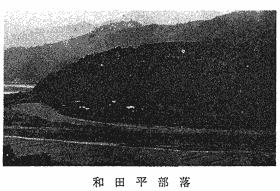 |
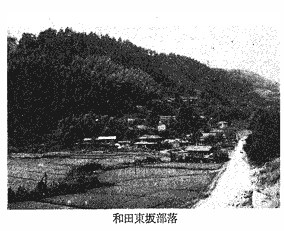 |
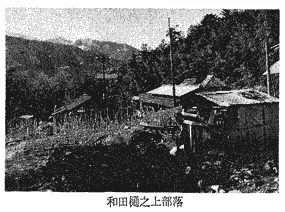 |
サ 上 大 島 図12参照
上大島は、東(22戸・88人)、中(22戸・103人)、西(18戸・91人)から成っている。
地形図に示されているように、富士川は、上大島付近からメァンダーを作り湯別当の南に至るまで大きく弧を描いている。弧の東は富士川氾濫原で小室沢付近まで発達している。この氾濫原は、上下大島の背後地として、水田地帯、畑作地帯になっている。
氾濫原の北部は、長戸川渓流が作る扇状地に接している。扇状地は、東西およそ500メートル、南北およそ600メートルに亘っており、東北に高く西南に低い緩傾斜をして、排水佳良で高燥地であるため住居地としてまさに適地といえる。
上大島部落は、この長戸川扇状地一帯に、山手から東、中、西の各集落が、粗密の差はあるが、集村に近い形態で農村分布をしている。部落の東は、三つ石山系の峯が南に延びて、山林資源にも恵まれ、産業資源に乏しい峡南地方としては、先ず地理的条件の比較的整った集落といえる。また、富士川護岸堤防の安全性、国鉄身延線の甲斐大島駅も近く、西八代縦断道路も域内はほとんど完成し、その人文条件も整った集落といえる。
なお上大島は古戦場でもある。大永元年(1521)遠州今川氏の将福島兵庫頭正成が甲斐に進軍し、9月6日武田信虎の甲州勢とここで激戦、武田勢は敗れて飯田河原に退き、越えて11月25日上条河原において甲州勢のため福島一類は大敗し、1,000余人討死、残党は翌年正月身命を乞うて帰国している。この大島合戦で戦死したつわものの霊を慰めるため、ゆかりの人が建てたと思われる五輪塔が、長戸川扇状沖積地が富士川氾濫原に尽きるあたりの桑畑の中にある。年を経て刻まれた文字も読むに堪えず、弔う人もないまま今寂しく残っている。
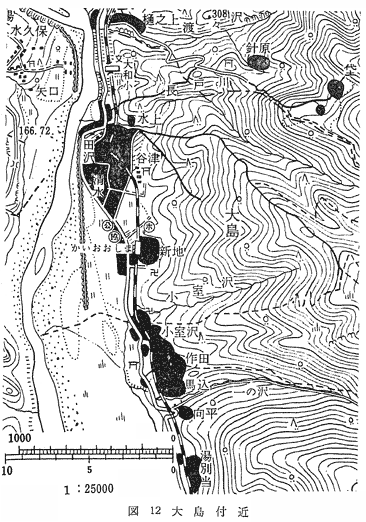 |
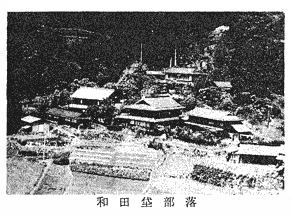 |
シ 下 大 島 図12参照
下大島は、新地(28戸・113人)、作之田・小室沢(24戸・114人)、馬込、向平、湯別当(21戸・109人)から成っている。
新地部落は、富士川氾濫原が東の山麓に尽きる山手に、一部集村的に分布し、一部は国鉄甲斐大島駅前に商店街を作っている。
小室沢、作之田集落は、新地の南、小室沢下流の段丘上にやや集村に近い形態で分布している。
馬込部落は、作之田の南に延びる小起伏に富んだ段丘上に、散村に近い形態で分布している。
向平部落は、馬込の南を西流する一之沢の小渓流の流域に、集村に近い形で分布している小集落である。
湯別当部落は、向平の南およそ400メートル、富士川に臨む傾斜面に3戸の小集落を形成し身延町最南端の位置を占めている。下大島は、新地から湯別当までおよそ1.6キロメートルにわたる広い地域に分布している農村で農耕地にも恵まれ山林資源も豊富で美しく植林された山は、部落繁栄の象徴ともいうべきものである。
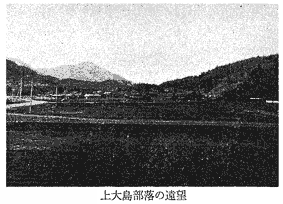 |
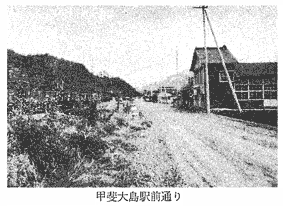 |
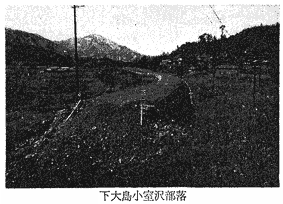 |

