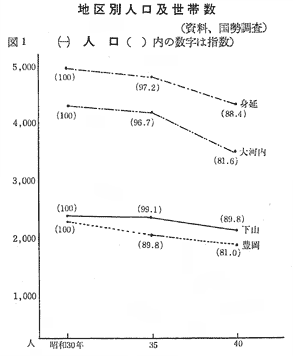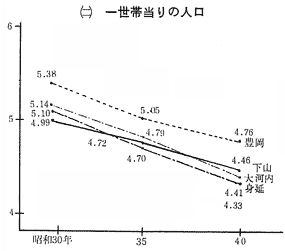第四章 人口概観
第一節 人口動態
人口の問題はすべての社会事象の根底をなし、その動態は、地域の地理的・社会的および経済的諸条件を背景としてその発生が見られる。身延町における最近の人口動態は、近年の我が国の人口問題の中に流動する二つの大きな現象の中にあると見ることができる。すなわち、昭和20年の敗戦を境として、それまでの多産多死の傾向から次第に脱却して、少産少死の方向へと急速に移行しつつある。
また、これと同時に、人口の地域的流動の激しさを表わしていることである。この流動による人口の社会的増減は、農山村から都会へと極端な過密地域を現出して、大きな国家的問題となっており、今後もこの傾向は更に強まるものと考えられる。
本町においても最近10数年の人口の動きの中に、これらの現象がはっきり見られる。
一、総人口とその推移
昭和30年以後10ヵ年間の本町の総人口の推移を、県および国全体と比較したものが表1である。この表により、昭和40年10月現在の身延町の人口は12,250人で、山梨県総人口の1.6パーセントを占め、市部を除いては、県下57町村のうち、本郡の増穂町についで7番目の大きさである。昭和30年の総人口に対する10年後の割合は県下郡部のいずれよりも低く、実数で2,108人減少している。全国四六都道府県の人口推移からみると、山梨県は平均減少率を上回っている状態である。この点からも、本町の人口減少の割合は極めて大きく、過疎の状態が急速に進んでいるとみられる。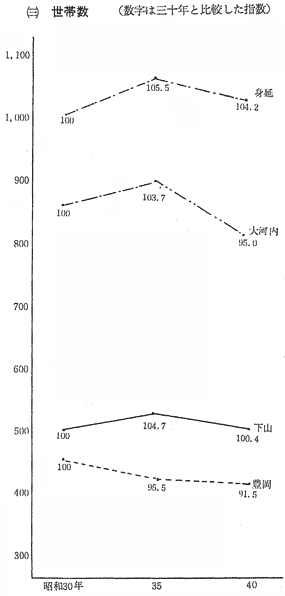 |
更にこの状態を町内四地区別に表わしたものが表2である。これによると4地区とも一様に減少の一途をたどり、中でも豊岡地区はこの10年間の減少の割合は4地区内で最も高いことを示している。これは豊岡地区が地理的条件により、労働人口の収容力に欠けていることが主要な原因とも思われるが、零細農家の多い本町においては、豊岡地区だけでなく、町全体の姿でもある。また世帯数についてみると、昭和35年は豊岡地区を除いた他の3地区とも、5年前の30年に比べて3.7パーセントから3.5パーセント多くなっている。更に昭和40年には身延地区以外はすべて減少しているが、その制合は、人口の減少率よりかなり少ない状態である。これは最近一般的にみられる世帯規模の縮少の傾向が年々強まっていることの現われである。
表1 総人口の推移と比較 (国勢調査統計)
| 年次 区分 |
昭和30年
|
昭和35年
|
昭和40年
|
|||||||
|
総人口
|
増加指数
|
総人口
|
増加指数
|
総人口
|
増加指数
|
|||||
|
身延町
|
14,359
|
人
|
100.0
|
13,805
|
人
|
96.1
|
12,250
|
人
|
85.3
|
|
|
南巨摩郡
|
74,558
|
人
|
100.0
|
71,942
|
人
|
96.5
|
62,570
|
人
|
83.9
|
|
|
山
梨 |
総数
|
807,044
|
人
|
100.0
|
782,062
|
人
|
96.9
|
763,194
|
人
|
94.6
|
|
市部
|
358,733
|
人
|
100.0
|
363,243
|
人
|
101.3
|
371,429
|
人
|
103.5
|
|
|
郡部
|
448,311
|
人
|
100.0
|
418,819
|
人
|
93.4
|
391,765
|
人
|
87.4
|
|
|
全
国 |
総数
|
8,928
|
万人
|
100.0
|
9,342
|
万人
|
104.6
|
9,827
|
万人
|
110.1
|
|
市部
|
5,426
|
万人
|
100.0
|
5,933
|
万人
|
106.3
|
6,693
|
万人
|
123.2
|
|
|
郡部
|
3,502
|
万人
|
100.0
|
3,409
|
万人
|
97.3
|
3,134
|
万人
|
89.5
|
|
また、人口密度の点については、昭和40年の国勢調査の結果によると、本町の面積は、130.47平方キロメートルで、この中に分布する人口は12,250人である。従って人口密度は一平方キロメートル当り93.9人なり、郡平均の73.1人をやや上回っている。また、山梨全体としては171人、全国では265.8人であり、この面からも田舎(いなか)町としての本町の姿が見られる。
表2 地区別人口および世帯数 (国勢調査統計)
| 年次 区分 |
昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 年次 区分 |
昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 一世帯当りの人口 | |||||||||||||
| 人 口 |
実 数 |
総数 | 14,359 | 人 | 13,805 | 人 | 12,250 | 人 | 世 帯 数 |
実 数 |
総数 | 2,795 | 戸 | 2,885 | 戸 | 2,764 | 戸 | ||||
| 下山 | 2,448 | 人 | 2,426 | 人 | 2,199 | 人 | 下山 | 491 | 戸 | 514 | 戸 | 498 | 戸 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | |||||
| 身延 | 5,076 | 人 | 4,935 | 人 | 4,489 | 人 | 身延 | 995 | 戸 | 1,050 | 戸 | 1,038 | 戸 | 下山 | 4.99 | 4.72 | 4.46 | ||||
| 豊岡 | 2,393 | 人 | 2,148 | 人 | 1,938 | 人 | 豊岡 | 445 | 戸 | 425 | 戸 | 407 | 戸 | 身延 | 5.10 | 47.00 | 4.33 | ||||
| 大河内 | 4,442 | 人 | 4,296 | 人 | 3,624 | 人 | 大河内 | 864 | 戸 | 896 | 戸 | 821 | 戸 | 豊岡 | 5.38 | 5.05 | 4.76 | ||||
| 指 数 |
総数 | 100.0 | 96.1 | 85.3 | 指 数 |
総数 | 100.0 | 103.2 | 98.9 | 大河内 | 5.14 | 4.79 | 4.41 | ||||||||
| 下山 | 100.0 | 99.1 | 89.8 | 下山 | 100.0 | 104.7 | 100.4 | 身延町 | 5.14 | 4.79 | 4.44 | ||||||||||
| 身延 | 100.0 | 97.2 | 88.4 | 身延 | 100.0 | 105.5 | 104.2 | 全国 | 4.05 | ||||||||||||
| 豊岡 | 100.0 | 89.8 | 81.0 | 豊岡 | 100.0 | 95.5 | 91.5 | 山梨 | 5.19 | 4.77 | 4.34 | ||||||||||
| 大河内 | 100.0 | 96.7 | 81.6 | 大河内 | 100.0 | 103.7 | 95.0 | 南巨摩 | 5.25 | 4.90 | 4.47 | ||||||||||
二、自然動態
我が国の出生率は、敗戦直後の昭和22年の34.3パーセントをピークに高率が続いていたが、25年以後次第に低下しはじめ、35年にはピーク時の半分で17.2パーセントにまで低下した。その後また年々わずかずつ上昇して、昭和40年には18.5パーセントを示している。この間死亡率も同じように減少しているが、その低下率は出生率ほど大きくなかったので結果としては自然増加の現象を招き現在に至っている。本町においても全国と同じような傾向をたどっている。最近の本町の自然動態については、表3を図表化した。図2によりその推移が見られる。出生率については昭和35年以降年々低下して、17.4パーセントから42年には9.1パーセントにまで下っている。これに対して死亡率はほとんど横ばいの状態にあるため、自然増加率はいきおい激減して、35年の7.5パーセントから42年の1.6パーセントまでに急落している。更にこの状態を全国及び山梨全体と比較してみると、表4により出生率は全国の上向きの中にあって、本町の場合は年々減少傾向にあり、35年を除いた各年次とも全国や山梨のいずれよりも低い率となっている。
これは最近特に多く見られる青年層の都会への流出も大きな原因と思われる。また死亡率についても本町の横ばいの状態は、全国や山梨のそれと同様な傾向を示している。したがって自然増加率は極めて低く、昭和40年には全国の11.4パーセントよりはるかに下回り1.9パーセントという増加率でしかない状態である。
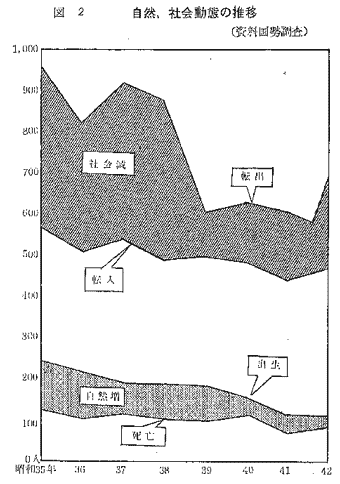 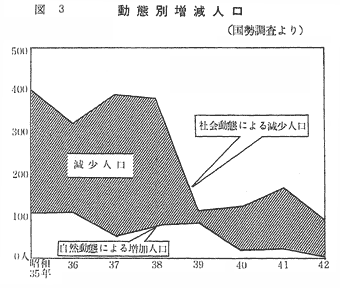 |
三、社会動態
社会動態は特に地域の経済的諸条件に左右されるところが大きいが、身延町における人口の減少は、主としてこの社会動態による転出超過に起因するものである。一般的に商工業が高度に発達した大都市、及びその周辺地域から離れた地方の町村にとっては一つの宿命的な現象である。最近数年間の本町の社会動態について、図2によりその傾向がみられる。総人口に対する転入者の割合はほとんど横ばいの状態を続けており、これに対して転出率は39年に急激に低下して、その後同様の状態にあるが、いずれも転入率より高いため、結果としては転出超過となり、しかもその超過分は各年次とも自然増加率を上回っており、人口減少の要因をなしていることを判然と示している。これらは本町の経済力などその背景の要素が、人口収容力に欠けていることの現われでもある。表3 人口動態
|
年次別
|
総人口
|
自然的人口動態
|
社会的人口動態
|
(A)+(B)
|
||||||
|
出生
|
死亡
|
(A)自然増加
|
転入
|
転出
|
(B)差引増減
|
実数
|
||||
|
実数
|
比率
|
実数
|
比率
|
|||||||
|
昭和35年
|
13,805
|
240
|
136
|
104
|
7.9
|
559
|
958
|
△399
|
△2.90
|
△295
|
|
昭和36年
|
13,569
|
215
|
108
|
107
|
7.8
|
507
|
829
|
△322
|
△2.40
|
△215
|
|
昭和37年
|
13,230
|
198
|
135
|
63
|
4.8
|
551
|
935
|
△388
|
△2.90
|
△325
|
|
昭和38年
|
12,914
|
197
|
119
|
78
|
6.0
|
497
|
881
|
△384
|
△3.00
|
△306
|
|
昭和39年
|
12,882
|
188
|
103
|
85
|
6.6
|
502
|
606
|
△104
|
△0.80
|
△19
|
|
昭和40年
|
12,250
|
148
|
125
|
23
|
1.9
|
495
|
634
|
△139
|
△1.10
|
△116
|
|
昭和41年
|
12,129
|
118
|
86
|
32
|
2.6
|
446
|
611
|
△165
|
△1.40
|
△133
|
|
昭和42年
|
12,062
|
110
|
91
|
19
|
1.6
|
481
|
571
|
△90
|
△0.28
|
△71
|
表4 出生率、死亡率、増加率の推移と比較
|
区分
|
昭和35年
|
昭和36年
|
昭和37年
|
昭和38年
|
昭和39年
|
昭和40年
|
|
|
出
生 率 |
身延
|
17.4
|
15.8
|
15.0
|
15.3
|
14.6
|
12.1
|
|
山梨
|
16.3
|
16.5
|
15.6
|
16.2
|
15.9
|
17.6
|
|
|
全国
|
17.2
|
16.9
|
17.0
|
17.3
|
17.7
|
18.5
|
|
|
死
亡 率 |
身延
|
9.9
|
8.0
|
10.2
|
9.2
|
8.0
|
10.2
|
|
山梨
|
8.3
|
7.9
|
8.3
|
7.6
|
7.9
|
8.3
|
|
|
全国
|
7.6
|
7.4
|
7.5
|
7.0
|
6.9
|
7.1
|
|
|
増
加 率 |
身延
|
7.5
|
7.8
|
4.8
|
6.1
|
6.6
|
1.9
|
|
山梨
|
8.1
|
8.6
|
7.3
|
8.7
|
8.0
|
9.3
|
|
|
全国
|
9.6
|
9.5
|
9.5
|
10.3
|
10.7
|
2.4
|
|