第二節 人口構成
一、年齢別、性別構成
人口構成の要素をなす年齢別、及び性別人口の最近数年間の推移は、表1をグラフにした図1からその形態をみることができる。先ず昭和25年から40年に至る推移の中で25年及び30年においては、大体ピラミッド型の構成を示し、人口が着実に増加してきたことを表わしている。35年から40年になるに従って、軍艦型構成に変わり、人口減少の傾向をはっきり現わしている。これは現在の日本全体の傾向とほとんど同様である。本町の特徴としてみられるところは、昭和40年の構成の場合20歳から34歳の生産年齢人口の中の中堅層が男女とも減少している点である。これは、この層が多く都会地に流出していることを現わしているものである。
なお戦後20年の今日に至っても、戦争のきずあとがはっきりこのグラフにみられる。即(すなわ)ち25年の構成をみると、30歳から40歳が非常に少なく、これは戦死、あるいは未復員の結果であろうが、更に以後15年たった40年において45歳から54歳までの層が少ない結果となってあらわれている。次に最近10ヵ年の増加率においては、高齢者になるに従って増加が目立ち、平均寿命の延びを如実に物語っている。その他も増加している層はいずれも中高年齢層であるが、これにひきかえ次代をになう青年層や幼年層はともに著しく減少している状態である。
性別構成においては、いずれも女性がやや多く40年には身延町で3.2パーセント、県では3.5パーセント、国で1.8パーセント女性が上回った構成比を示し、数年間同様な傾向をたどっている。
更に年齢を大きく3区分して、14歳までの幼年人口、15歳から65歳までの生産年齢人口、及び65歳以上の老齢人口の階層別にその構成をみると、最近10ヵ年の傾向は幼年人口の割合は年ごとに減少し、逆に生産年齢人口や老齢人口の割合はともに増加の傾向にあり、この点からも身延町の人口構成は老齢化をたどっている状態がみられる。
表1 年齢別人口構成 (5歳階級別人口の推移)
|
区分
|
昭和25年
|
昭和30年
|
昭和40年
|
|||||||||
|
山梨
|
身延町
|
山梨
|
身延町
|
山梨
|
身延町
|
|||||||
|
男
|
女
|
計
|
男
|
女
|
計
|
男
|
女
|
計
|
||||
|
0〜4
|
102,933
|
788
|
866
|
1,654
|
84,930
|
823
|
773
|
1,596
|
61,233
|
494
|
463
|
957
|
|
5〜9
|
98,594
|
884
|
907
|
1,791
|
98,229
|
926
|
790
|
1,716
|
66,380
|
595
|
583
|
1,178
|
|
10〜14
|
96,982
|
883
|
899
|
1,782
|
94,819
|
855
|
865
|
1,720
|
82,168
|
769
|
715
|
1,484
|
|
15〜19
|
84,367
|
796
|
682
|
1,478
|
78,500
|
667
|
632
|
1,299
|
80,103
|
680
|
592
|
1,272
|
|
20〜24
|
70,613
|
624
|
558
|
1,182
|
68,200
|
507
|
532
|
1,039
|
54,395
|
263
|
327
|
590
|
|
25〜29
|
55,529
|
458
|
526
|
984
|
62,183
|
532
|
582
|
1,114
|
51,302
|
298
|
324
|
622
|
|
30〜34
|
47,739
|
348
|
455
|
803
|
51,519
|
420
|
467
|
887
|
55,442
|
375
|
378
|
753
|
|
35〜39
|
46,272
|
332
|
425
|
757
|
45,190
|
335
|
436
|
771
|
56,569
|
453
|
490
|
943
|
|
40〜44
|
42,474
|
388
|
398
|
786
|
43,540
|
326
|
400
|
726
|
48,246
|
391
|
423
|
814
|
|
45〜49
|
38,485
|
347
|
408
|
755
|
40,249
|
361
|
379
|
740
|
42,041
|
288
|
392
|
680
|
|
50〜54
|
31,577
|
335
|
320
|
655
|
36,073
|
329
|
381
|
710
|
39,589
|
264
|
340
|
604
|
|
55〜59
|
26,764
|
234
|
232
|
466
|
29,205
|
305
|
276
|
581
|
35,718
|
310
|
322
|
632
|
|
60〜64
|
24,908
|
217
|
250
|
467
|
24,000
|
217
|
238
|
455
|
30,461
|
260
|
336
|
596
|
|
65〜69
|
19,067
|
172
|
225
|
397
|
20,985
|
181
|
219
|
400
|
22,798
|
226
|
227
|
453
|
|
70〜74
|
13,884
|
112
|
140
|
252
|
14,767
|
142
|
177
|
319
|
16,584
|
146
|
166
|
312
|
|
75〜79
|
7,072
|
62
|
100
|
162
|
9,345
|
62
|
110
|
172
|
11,543
|
72
|
130
|
202
|
|
80〜84
|
2,838
|
19
|
44
|
63
|
3,867
|
35
|
53
|
88
|
5,874
|
40
|
79
|
119
|
|
85以上
|
1,036
|
|
|
|
1,436
|
9
|
17
|
26
|
2,768
|
17
|
32
|
49
|
|
総計
|
811,134
|
6,999
|
7,435
|
14,434
|
807,037
|
7,032
|
7,327
|
14,359
|
763,214
|
5,932
|
6,318
|
12,250
|
|
就業人口
|
|
3,232
|
2,751
|
5,983
|
3,571
|
2,604
|
6,175
|
|
3,143
|
2,221
|
5,364
|
|
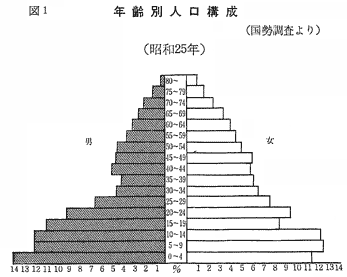 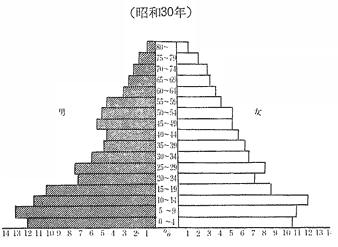 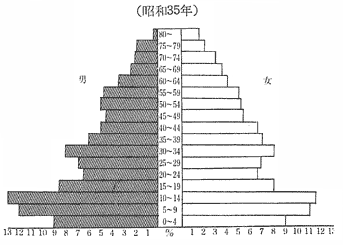 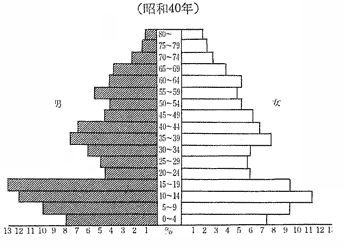
|
二、労働力人口構成
労働力人口は15歳以上のいわゆる生産年齢人口の中の就業者と失業者を包括した人口であるが、本町のこれらの人口は、表2によりその構成をみることができる。本町の総人口が、前述のごとく年々減少しているのに対して、生産年齢人口の占める割合は逆な傾向を示している。表によると昭和30年には総人口の中の生産年齢人口の割合は65パーセントであったものが、10年後には70.5パーセントとなり、5パーセント増加している。しかしこのように増加の傾向にある生産年齢人口が、そのまま労働人口の増加につらなるものではない。どちらかといえば逆に非労働力率が上昇しており、30年の22.6パーセントが、40年には37.4パーセントとなっており、労働力人口は減少している。このような状態は、最近特に目立ってきた進学者の増加、生活の安定、社会保障の充実などの理由によるところも大きく、これは、更に全国的に傾向として今後も続くものと思われる。表2 労働人口の推移
|
区分
|
昭和30年
|
昭和35年
|
昭和40年
|
|||||
|
実数(人)
|
割合(%)
|
実数(人)
|
割合(%)
|
実数(人)
|
割合(%)
|
|||
|
生産年齢人口
|
総数
|
9,327
|
100.0
|
9,307
|
100.0
|
8,631
|
100.0
|
|
|
男
|
4,428
|
47.5
|
4,537
|
48.7
|
4,074
|
47.2
|
||
|
女
|
4,899
|
52.5
|
4,772
|
51.3
|
4,557
|
52.8
|
||
|
労働人口
|
総数
|
6,288
|
67.4
|
6,369
|
68.4
|
5,404
|
62.6
|
|
|
就業人口
|
計
|
6,175
|
66.2
|
6,347
|
68.2
|
5,366
|
62.2
|
|
|
男
|
3,571
|
38.3
|
3,737
|
40.1
|
3,144
|
36.4
|
||
|
女
|
2,604
|
27.9
|
2,610
|
28.1
|
2,222
|
25.8
|
||
|
失業者
|
計
|
113
|
1.2
|
22
|
0.2
|
38
|
0.4
|
|
|
男
|
87
|
0.9
|
11
|
0.1
|
22
|
0.3
|
||
|
女
|
26
|
0.3
|
2
|
0.1
|
16
|
0.1
|
||
|
非労働力人口
|
総数
|
3,039
|
32.6
|
2,940
|
31.6
|
3,227
|
37.4
|
|
|
男
|
770
|
8.3
|
789
|
8.5
|
908
|
10.5
|
||
|
女
|
2,269
|
24.3
|
2,151
|
23.1
|
2,319
|
26.9
|
||
三、職業別人口構成
職業別及び産業別就業者の構成を国勢調査結果からまとめたものが表3表4である。これを図表化した図2からみられることは、昭和30年から10年後にはその構成比が大きく変っていることである。特に本町では農業を主としている人が多く、30年には約半分の割合を占めていたものが次第に減少して40年には約3割にまで下っている。これは最近農業の兼業化が年ごとに多くなっているためであり、国全体の傾向でもある。更に本町の農業における女性就業の割合は各年次とも男性を上回っている。これは現在の農業の低所得性からくる問題で、特に本町のような農業規模の極めて零細な地方においては、この問題はいよいよ深刻である。従って農業従事者の男子は他に収入を求めなければならないため、現在農業の大半が婦人や老人によってになわれている状態である。
そして農業をはなれた人たちは、第二次、第三次産業へと移行し中でも建設業、サービス業が増加の傾向を示している。さらに以上のような本町の構成状態を全国のそれと比較してみるに、図3により最近のわが国における生業別就業構成比は、昭和40年において第一次産業が24.7パーセント、第二次産業が32.3パーセント、第三次産業が43.0パーセントと順に高く、いわゆる先進的形態をなしている。これに対して本町の場合は、第三次が43.8パーセントでもっとも大きく、ついで第一次の34.2パーセント、第二次の22.0パーセントの順であり、第三次産業だけは全国平均とほぼ同一の数値を示している。これは身延山を中心とした「仏都観光の町」としての本町の姿でもあると思われる。また、各産業のうちでも生産性の高い第二次産業の就業構成比が極めて低いことは本町における第二次産業の立ち遅れを現わしているものとみることができる。
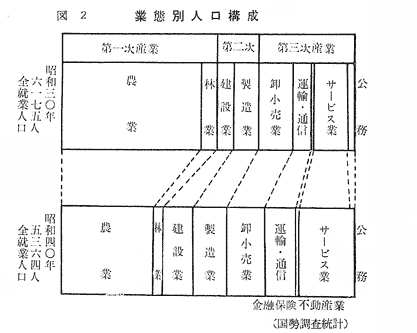 |
表3 職業別人口及び人口指数
|
区分
|
昭和25年
|
昭和30年
|
昭和40年
|
人口指数
|
|||||||
|
男
|
女
|
計
|
男
|
女
|
計
|
男
|
女
|
計
|
25年
|
40年
|
|
|
専門的技術的職業従事者
|
324
|
119
|
443
|
287
|
29
|
316
|
260
|
124
|
384
|
100
|
86
|
|
管理的職業従事者
|
100
|
4
|
104
|
83
|
0
|
83
|
64
|
3
|
67
|
100
|
64
|
|
事務従事者
|
267
|
121
|
388
|
246
|
105
|
351
|
295
|
145
|
440
|
100
|
113
|
|
販売従事者
|
223
|
205
|
428
|
289
|
277
|
566
|
244
|
319
|
563
|
100
|
132
|
|
農林漁業従事者及類似従
事者 |
1,720
|
1,967
|
3,687
|
1,573
|
1,684
|
3,257
|
787
|
1,069
|
1,856
|
100
|
50
|
|
採鉱採石従事者
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
4
|
2
|
0
|
2
|
100
|
0
|
|
運輸通信従事者
|
88
|
0
|
88
|
79
|
14
|
93
|
234
|
46
|
280
|
100
|
319
|
|
特殊技能工、生産工程従
事者単純労働者 |
932
|
201
|
1,134
|
917
|
202
|
1,119
|
1,139
|
250
|
1,389
|
100
|
122
|
|
サービス職業従事者
|
74
|
138
|
212
|
93
|
203
|
296
|
118
|
265
|
383
|
100
|
184
|
|
分類不能職業
|
3
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
100
|
67
|
|
計
|
3,732
|
2,755
|
6,487
|
3,571
|
2,514
|
6,085
|
3,144
|
2,222
|
5,366
|
100
|
83
|
表4 業態別人口および世帯数
|
区分
|
昭和30年
|
昭和40年
|
|||||||||
|
世帯数
|
人口
|
上のうち就業人口
|
世帯数
|
人口
|
上のうち就業人口
|
||||||
|
男
|
女
|
計
|
男
|
女
|
計
|
||||||
|
第一次産業
|
農業
|
1,048
|
5,756
|
1,290
|
1,647
|
2,937
|
615
|
2,901
|
625
|
1,048
|
1,673
|
|
林業及狩猟業
|
154
|
715
|
248
|
46
|
294
|
115
|
522
|
138
|
23
|
161
|
|
|
漁業及水産業
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
計
|
1,202
|
6,471
|
1,539
|
1,693
|
3,232
|
730
|
2,423
|
763
|
1,071
|
1,834
|
|
|
第二次産業
|
鉱業
|
1
|
3
|
2
|
0
|
2
|
30
|
121
|
53
|
5
|
58
|
|
建設業
|
179
|
973
|
337
|
8
|
345
|
349
|
1,635
|
487
|
72
|
559
|
|
|
製造業
|
263
|
1,312
|
453
|
100
|
553
|
309
|
1,423
|
419
|
147
|
566
|
|
|
計
|
443
|
2,288
|
792
|
108
|
900
|
688
|
3,179
|
959
|
224
|
1,183
|
|
|
第三次産業
|
卸売業小売業
|
277
|
1,405
|
353
|
332
|
685
|
301
|
1,333
|
329
|
388
|
717
|
|
運輸通信公益事業
|
56
|
797
|
292
|
52
|
344
|
253
|
1,182
|
421
|
69
|
490
|
|
|
金融保険不動産業
|
8
|
38
|
14
|
6
|
20
|
16
|
64
|
32
|
20
|
52
|
|
|
サービス業
|
301
|
1,558
|
452
|
356
|
808
|
385
|
1,617
|
542
|
431
|
973
|
|
|
公務
|
103
|
444
|
129
|
57
|
186
|
65
|
312
|
97
|
18
|
115
|
|
|
分類不能産業
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
計
|
745
|
4,240
|
1,240
|
803
|
2,043
|
1,020
|
4,508
|
1,421
|
926
|
2,347
|
|
|
その他
|
完全失業者
|
31
|
139
|
7
|
26
|
||||||
|
非労働者
|
214
|
845
|
196
|
652
|
|||||||
|
総計
|
2,635
|
13,983
|
3,571
|
2,606
|
6,175
|
2,649
|
10,788
|
3,143
|
2,221
|
5,364
|
|
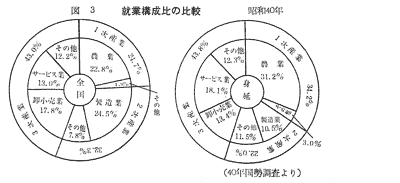 |

