第二章 町政の沿革
第一節 旧下山村
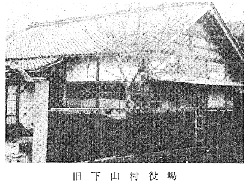 |
明治5年(1872)行政区設置により、巨摩郡第34区となり、後18区所属となる。明治8年(1875)1月19日、下山村と粟倉村とが合併し、村名を福居村と名づけた。明治25年(1892)8月二十五日の大火災により、役場および村の過半数が焼失、続いて翌年は仮役場をはじめ山額部落の全焼、災害はなお疫病の流行等重なり合い、経済は極めて疲弊困窮したために民心の一新を願って、明治29年(1896)3月7日福居村の名称をもとの下山村に再改称した。
次に明治21年福居村予算の概要を掲げる。
明治21年度福居村予算より
| 1、 | 戸長役場費 | 454円 | 24銭5厘 | |
| 2、 | 会議費 | 3円 | 25銭 | |
| 3、 | 土木費 | 284円 | 48銭2厘 | |
| 4、 | 教育補助費 | 180円 | 25銭 | |
| 5、 | 衛生費 | 27円 | 20銭 | |
| 6、 | 救助費 | 20円 | ||
| 7、 | 災害予防費 | 150円 | ||
| 8、 | 勧業費 | 25円 | ||
| 合計額 | 1,134円 | 42銭7厘 |
明治22年(1889)町村制公布され、従来の戸長は村長と改名され、初代の村長は同年9月5日戸長職にあった遠藤文五郎が就任した。助役は遠藤富貞、収入役は遠藤政太郎がそれぞれ就任した。
明治25年8月25日役場火災、続いて翌年仮役場(常福寺)焼失にともない小学校舎2階に仮役場を設置し、3年後ようやく役場移転新築の運びとなる。その間の消息資料として村長の村会に対する諮問案事由書を掲げる。
役場移転諮問案事由
| 明治二十五年役場祝融の災に罹り爾来校舎ノ階上ヲ仮用スル事殆ンド三年今ヤ就学生徒日一日ニ増加シ目下通学生徒弐百名ニ及バントシ最早入ルヘキ教室ナキニ至ル曩日新調セシ高机廿ノ配置ニ窮シ松木校長ヨリ懇談アリタリ抑モ児童ノ教育ハ一日モ忽諸に付スベカラザルハ言ヲ復ザルナリ然ルニ充塞ニ足ルヘキ教室ヲ役場ニ仮用シ為ニ生徒ノ入学ニ躊躇ヲ興ヘ教育発達ノ機ヲ遅延ナラシムルハ遺憾ノ至ニ付役場ヲ他ニ移転センカ適切ノ家屋ナキニ苦シム進ンデ新築センカ民費多端ノ際ニ窮ス然レドモ長ク校舎ヲ使用セントスレバ教育上不便ヲ来タスベシ故ニ前者ノ一ニ出ザルベカラズ蹙首復案別紙費途支出方法ヲ以テ進ンデ新築セントシ諮問案ヲ提出ス幸ニ賛同セラレン事ヲ但設計其ノ他ノ方法は村会ノ議ニ委ス | |
| 明治二十八年九月十六日 | |
| 福居村村長 深沢金太郎 |
役場新築費支出方法
一金 300円也
(内訳)
(内訳)
| 金 | 120円 | 早川渡船収益 | ||||
| 金 | 50円 | 会社其の他共有収益 | ||||
| 金 | 20円 | 役場吏員一同ヨリ献金 | ||||
| 金 | 20円 | 村会議員一同ヨリ献金 | ||||
| 金 | 5円 | 教員一同ヨリ献金 | ||||
| 金 | 8円 | 50銭 | 地価100円以上ヲ有スル85人ヨリ | |||
| 金 | 5円 | 75銭 | 地価200円以上ヲ有スル33人ヨリ | |||
| 金 | 2円 | 40銭 | 地価300円以上ヲ有スル6人ヨリ | |||
| 金 | 3円 | 60銭 | 地価400円以上ヲ有スル6人ヨリ | |||
| 金 | 3円 | 20銭 | 地価500円以上ヲ有スル4人ヨリ | |||
| 金 | 5円 | 地価600円以上ヲ有スル5人ヨル | ||||
| 金 | 4円 | 地価700円以上ヲ有スル2人ヨリ | ||||
| 金 | 10円 | 地価1,200円以上ヲ有スル1人ヨリ | ||||
| 金 | 10円 | 他村入作人ヨリ | ||||
| 金 | 6円 | 50銭 | 特志者ヨリ | |||
| 金 | 22円 | 粟倉区ヨリ(下山共有金割合ニテ55戸分) | ||||
| 計 | 300円也 |
明治29年新築工事はめでたく落成したが工費は金548円49銭9厘と記録されている。
明治40年(1907)より累年の大水害は流失家屋30数戸、富士川沿いの美田の大半を失い、被災した人々は北海道・甲府・横浜等へ転出していった。維新以後村の力で行なった大きな事業としては、63町歩にわたる仙王外五山恩賜林の経営に全村民をあげて植樹、下刈作業等に尽力し美林に育成した事業や、堤防の築構により、早川河原の開田、昭和開墾田等往時の姿に復興した事業等である。
昭和22年地方自治法発布により、公選第1回の村長として望月嘉作が無投票により選出され、助役望月静夫、収入役松木四郎がそれぞれ就任した。自治法初の村会議員には次の16名が当選した。
議長網野茂八、副議長有泉不二隆、議員望月正作、望月竹重、遠藤半弥、遠藤治、松木新六、松木芳秋、望月耀、望月彦平、近藤保、石川好一、深沢雅治、佐藤理、佐野正陽、大原正朔
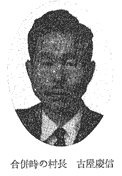 |
下山村には古くから自治制度の方便として、各部落に「若者」「若衆」「中老」等という制度組織があって、部落及び村全体の祭や行事に参画し運営に当り、時には、争いごとの仲裁もしたりして自治の一助をになってきた。現在もなおこの制度は受けつがれている。
(記録に残る戸長名)
| 粟倉村戸長 | 望月新右衛門 | 明治6年 | ||
| 下山村戸長 | 穂坂喜兵衛 | 明治5年〜明治7年 | ||
| 望月喜右衛門 | 明治7年〜明治8年 | |||
| 福居村戸長 | 初代 | 佐野貞往(惣兵衛) | 明治8年〜明治10年 | |
| 福居村戸長 | 2代 | 望月常三郎 | 明治11年〜明治12年 | |
| 福居村戸長 | 3代 | 遠藤富貞 | 明治13年 | |
| 福居村戸長 | (以下代数不明) | 網野重助 | ||
| 福居村戸長 | 佐野貞往 | |||
| 福居村戸長 | 遠藤富貞 | 明治20年 | ||
| 福居村戸長 | 望月潔 | 明治20年 | ||
| 福居村戸長 | 遠藤文五郎 | 明治21年〜明治22年 |
| (歴代村長) | ||||||
| 遠藤文五郎 | 明治22、9、5 | 明治25、12、24 | ||||
| 望月潔 | 明治26、1、10 | 明治26、6、10 | ||||
| 稲葉希遊 | 明治26、6、12 | 明治26、10、20 | ||||
| 遠藤富貞 | 明治26、10、24 | 明治28、4、20 | ||||
| 深沢金太郎 | 明治28、7、29 | 明治31、3、1 | ||||
| 村長臨時代理 | ||||||
| 長沢義一 | 明治31、3、7 | 明治32、2、1 | ||||
| 石坂順武 | 明治32、2、1 | 明治32、3、2 | ||||
| 望月退蔵 | 明治32、3、21 | 明治34、8、18 | ||||
| 石川伴作 | 明治34、9、3 | 明治35、11、30 | ||||
| 佐野慶蔵 | 明治36、4、28 | 明治40、4、27 | ||||
| 佐野慶蔵 | 明治40、5、9 | 明治43、2、8 | ||||
| 土橋守吉 | 明治43、3、17 | 大正3、3、16 | ||||
| 望月退蔵 | 大正3、3、19 | 大正3、8、31 | ||||
| 望月亀次郎 | 大正3、9、9 | 大正6、5、11 | ||||
| 佐野寛 | 大正6、7、31 | 大正7、3、4 | ||||
| 石川伴作 | 大正7、4、9 | 大正11、4、8 | ||||
| 松木喬 | 大正11、4、28 | 大正11、10、13 | ||||
| 遠藤伴弥 | 大正12、5、12 | 昭和2、5、11 | ||||
| 遠藤伴弥 | 昭和2、5、13 | 昭和6、5、12 | ||||
| 村長臨時代理 | ||||||
| 石原芳雄 |
昭和6、10、20 |
昭和7、4、29 | ||||
| 望月� | 昭和7、4、29 | 昭和7、11、20 | ||||
| 佐野寛 | 昭和8、4、20 | 昭和10、11、16 | ||||
| 石川伴作 | 昭和10、12、11 | 昭和14、12、10 | ||||
| 佐野慶蔵 | 昭和14、12、1 | 昭和16、10、19 | ||||
| 竹下幸内 | 昭和16、11、8 | 昭和20、11、7 | ||||
| 山内椿房 | 昭和20、11、8 | 昭和22、4、6 | ||||
| 望月嘉作 | 昭和22、4、7 | 昭和23、12、25 | ||||
| 網野茂八 | 昭和23、12、27 | 昭和24、12、25 | ||||
| 望月栄 | 昭和25、2、1 | 昭和27、2、1 | ||||
| 古屋慶信 | 昭和27、2、11 | 昭和30、2、10 | ||||
| (歴代助役) | ||||||
| 遠藤富貞 | 明治22、9、10 | 明治24、8、20 | ||||
| 遠藤政太郎 | 明治24、9、20 | 明治26、1、2 | ||||
| 遠藤文五郎 | 明治26、1、17 | 明治26、4、20 | ||||
| 穂坂睦三郎 | 明治26、5、9 | 明治26、5、20 | ||||
| 遠藤政太郎 | 明治26、5、29 | 明治27、4、20 | ||||
| 稲葉台作 | 明治27、7、26 | 明治28、8、15 | ||||
| 土橋守吉 | 明治28、8、24 | 明治30、12、20 | ||||
| 穂坂睦三郎 | 明治30、12、27 | 明治31、3、1 | ||||
| 望月退蔵 | 明治32、2、1 | 明治32、3、20 | ||||
| 山内道蔵 | 明治32、3、22 | 明治33、3、9 | ||||
| 石川伴作 | 明治33、3、27 | 明治34、8、30 | ||||
| 佐野慶蔵 | 明治34、9、13 | 明治36、5、1 | ||||
| 望月米吉 | 明治36、5、14 | 明治38、4、30 | ||||
| 遠藤源太郎 | 明治38、5、9 | 明治42、5、8 | ||||
| 望月亀次郎 | 明治42、7、5 | 大正2、7、4 | ||||
| 松木猪之吉 | 大正2、7、14 | 大正3、7、11 | ||||
| 渡辺信吉 | 大正3、7、29 | 大正7、7、28 | ||||
| 稲葉関太郎 | 大正7、8、10 | 大正8、6、28 | ||||
| 深沢昌三 | 大正8、9、12 | 大正9、12、20 | ||||
| 遠藤半弥 | 大正10、1、17 | 大正12、5、11 | ||||
| 望月直蔵 | 大正12、7、10 | 大正13、3、31 | ||||
| 松村佐十郎 | 大正13、5、23 | 昭和3、5、22 | ||||
| 井上角太郎 | 昭和3、6、7 | 昭和6、5、5 | ||||
| 松村英実 | 昭和6、5、13 | 昭和6、10、20 | ||||
| 遠藤静 | 昭和7、10、23 | 昭和8、12、30 | ||||
| 望月嘉作 | 昭和9、2、1 | 昭和13、1、31 | ||||
| 深沢英雄 | 昭和13、2、11 | 昭和13、3、31 | ||||
| 網野茂八 | 昭和13、5、29 | 昭和13、11、30 | ||||
| 遠藤忠治 | 昭和13、12、15 | 昭和14、8、21 | ||||
| 稲葉政之 | 昭和14、8、29 | 昭和16、4、10 | ||||
| 望月栄 | 昭和16、9、30 | 昭和17、6、30 | ||||
| 遠藤弥禄 | 昭和17、7、16 | 昭和24、2、28 | ||||
| 松木四郎 | 昭和24、3、21 | 昭和27、1、10 | ||||
| 網野正一 | 昭和27、2、16 | 昭和30、2、10 | ||||
| (歴代収入役) | ||||||
| 遠藤政太郎 | 明治22、9、25 | 明治26、3、30 | ||||
| 古屋保右衛門 | 明治26、4、1 | 明治26、5、4 | ||||
| 松木市右衛門 | 明治26、5、5 | 明治26、11、1 | ||||
| 山内巻耳 | 明治26、11、13 | 明治27、5、2 | ||||
| 深沢金太郎 | 明治27、7、19 | 明治28、7、28 | ||||
| 佐野慶蔵 | 明治28、8、26 | 明治30、4、1 | ||||
| 遠藤源太郎 | 明治30、4、13 | 明治34、4 | ||||
| 遠藤源太郎 | 明治34、4、5 | 明治42、5、8 | ||||
| 渡辺信吉 | 明治42、6、12 | 大正2、6、11 | ||||
| 渡辺信吉 | 大正2、6、13 | 大正6、8、2 | ||||
| 深沢昌三 | 大正6、8、12 | 大正9、11、1 | ||||
| 松村佐十郎 | 大正9、12、28 | 大正13、12、27 | ||||
| 遠藤滋三 | 大正14、2、25 | 大正4、2、24 | ||||
| 遠藤弥禄 | 昭和4、4、7 | 昭和5、8、31 | ||||
| 遠藤静 | 昭和5、9、6 | 昭和7、10、23 | ||||
| 望月嘉作 | 昭和7、10、28 | 昭和9、1、31 | ||||
| 服部泰 | 昭和9、3、1 | 昭和11、2、26 | ||||
| 佐野為雄 | 昭和11、3、8 | 昭和13、3、11 | ||||
| 遠藤英次 | 昭和13、4、15 | 昭和17、4、14 | ||||
| 遠藤英次 | 昭和17、6、13 | 昭和20、3、15 | ||||
| 松木四郎 | 昭和20、3、16 | 昭和24、3、15 | ||||
| 杉田昌二 | 昭和24、3、20 | 昭和28、3、19 | ||||
| 杉田昌二 | 昭和28、3、29 | 昭和29、3、31 | ||||
| 望月武雄 | 昭和29、5、1 | 昭和30、2、10 | ||||

