第二節 旧身延町
明治5年(1872)に実施された80区制当時、旧身延町の地域は巨摩郡第34区に所属し、身延山久遠寺の支配下にあって「身延町」と称していた現在の門内地域と、波木井村、大野村、梅平村(大野山本遠寺領)の4村より成っていた。明治8年11月1日、県の合村勧奨によりこの4村は合併して身延村となった。(身延村取調書による)当時の人口2,486名と山梨県市郡村誌(明治25年刊)には記されている。
翌明治9年(1876)十月には県の区制改正により第18区に所属するようになった。
合村当時の戸長、副戸長名は記録が乏しく、明らかでないが、僅かに各種資料に左の人々の名が見える。
| (合併以前の戸長、副戸長) | |||||
| 身延村戸長 | 佐野金左衛門 | (明治6年10月) | |||
| 身延村副戸長 | 藤田喜平 | (明治5年11月、明治8年3月) | |||
| 波木井村戸長 | 藤田源平 | (明治6年) | |||
| 大野村戸長 | 片田宗兵衛 | (明治6年) | |||
| 梅平村戸長 | 遠藤又右衛門 | (明治6年) | |||
| 身延村戸長 | 佐野重右衛門 | (明治6年) | |||
| 波木井村戸長 | 藤田源平 | (明治8年10月) | |||
| 波木井村副戸長 | 佐野太兵衛 |
(明治8年10月) |
|||
| 梅平村戸長 | 佐野由太郎 | (明治8年10月) | |||
| 梅平村副戸長 | 遠藤与五右衛門 | (明治8年10月) | |||
| (合併以後の戸長) | |||||
| 身延村戸長 | 藤田源平 | (明治11年2月)初代戸長と思われる | |||
| 身延村戸長 | 葉山新重郎 | (明治14年8月)最後の戸長と思われる | |||

|
明治17年(1884)には豊岡村と連合戸長役場を持ち、それまであった村役所を廃した。連合戸長には豊岡村戸長であった清水為八(横根中)が官選で任命され9月29日就任している。その後20年には星野茂三郎(身延村)が連合戸長に就任した。
明治22年8月の町村制施行にともない豊岡村との連合役場は解消され、新たに役場を大字梅平の宮本坊においた。戸長、副戸長に代る村長、助役は村会で選挙されることになった。初代村長は豊岡村長に選ばれた清水為八が兼任している。21年当時村費は僅か200円余りで、消防費が年16円という記録が残されている。
古老の談によるとこの頃の村長様の権威は絶大なもので、村内各戸回り番で村役場のお茶番に毎日出勤した村民は、村長様が羽織袴でお出ましになると土下座をしてヘーッと敬意を表するのが普通であったという。まだまだ封建時代のおもかげが残っていたのである。
役場はのちに南谷の太平橋のそばの身延山所有地に建てられた。
明治35年(1902)4月には殿前に村立身延尋常高等小学校が設立されている。時の村長は佐野寉太郎、学務委員は望月宗太郎である。
大正年代に入り、2年(1913)には近隣にさきがけて電灯が点灯され、文化の光が輝やきはじめるが、特に大正10年(1921)の日蓮聖人生誕700年祭を境として11年の大野隧道、12年の身延橋竣工、15年の身延−鰍沢間バス開通、さらに昭和3年(1928)には身延線全線が開通するなど、久遠寺を中心に信仰の町として交通・通信は急速にひらけ、宿坊、旅館も整備され、峡南地方の中心地として発展して行くわけである。
700年祭の大正10年4月には、老朽化した役場を当時の村長田中久治郎の努力により、土地有力者より5,000円余の寄付を仰いで新築工事を行ない、瓦葺木造2階建56坪(185平方メートル)の新庁舎が落成している。
上棟式は700年祭大法要のため延期して11月13日盛大に行なわれたが、昔ながらの引戸に代って蝶番片開きで真中にガラスの入った洋式のドアーがもの珍らしくもまたハイカラだったとは古老の思い出話である。
当時の役場は極めて小規模なもので、村長、助役、収入役以下書記4、5名ぐらいなもので、昭和元年(1926)の例によると、事務分掌は議事(村長)学事、会計税務、庶務、戸籍、兵事、統計勧業土木、学務衛生、社寺宗教となっている。
参考までに昭和3年に改正された身延村給与規程を抜すいしてみよう。
身延村給与規程
第一条 本村吏員ノ報酬及給料額ハ下の範囲内ニ於テ毎年度予算ノ定ムル所ニ依ル但シ書記及雇ノ給料額ハ村長ノ定ムル所ニ依ル
|
職名
|
報酬給料額 | |
|
村長
|
名誉職
|
報酬年額 200円以上500円以下 |
|
有給
|
給料月額 50円以上80円以下 | |
|
助役
|
名誉職
|
報酬年額 150円以上450円以下 |
|
有給
|
給料月額 40円以上70円以下 | |
|
区長
|
報酬年額 3円以上10円以下 | |
|
区長代理者
|
報酬年額 2円以上5円以下 | |
|
委員
|
報酬年額 2円以上20円以下 | |
|
収入役
|
給料月額 35円以上70円以下 | |
|
書記
|
給料月額 25円以上60円以下 | |
|
雇
|
給料月額 15円以上40円以下 | |
附則
本規程ハ昭和三年度分ヨリ之ヲ適用ス
大正15年(1926)には地域の発展を期するため、鰍沢にあった土木出張所を役場横に移転誘致、ついで昭和9年(1934)には殿前にあった旧身延小学校々舎の一部を県へ無償提供して移転している。
このほか鰍沢区裁判所身延出張所、職業紹介所の誘致など、常に官公庁の誘致、町のビジネスセンター化に努力した先人の苦心がしのばれる。
昭和2年には、明治22年からあった村の委員条例を改め、常設委員制度を町村制69条にもとづいて施行した。これは村長の補助機関として、土木委員4名、勧業委員2名、衛生委員2名(任期2年)をおくというもので、初代の常設委員には次の各氏が村長の推薦、村会の議決を経て就任している。
| (土木委員) | 望月祥 佐野佐重郎 藤田高治 小笠原三四郎 | |||
| (勧業委員) | 今村松次郎 小林豊三 | |||
| (衛生委員) | 伊東丑太郎 深沢茂十郎 |
また、学務委員もこの時設置され、初代委員として次の3名が就任している。
| (学務委員) | 藤田佐一郎 望月善長 望月九房 |
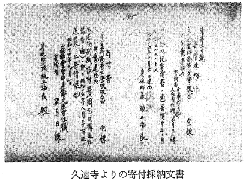
|
このように、旧身延町の町財政の中で、身延山久遠寺からの寄付援助の比重は非常に大きく、年々5,000円程度の普通寄付のほかに、道路橋梁、学校建築、備品整備その他の事業のための指定寄付も常に行なわれていることが特徴である。
身延山を中心とする門前町として町行政と寺との結びつきが強かったことと、身延町出身の望月日謙上人が法主の座にあり、町の発展にも熱意を注がれたことが大きな理由であった。
町制施行
昭和5年6月13日、時の村長藤田佐一郎は町会に「村ヲ町ト為ス件」を提案、満場一致の議決を経て昭和6年1月1日町制を施行し、ここに「身延町」が誕生新発足したのである。当時の戸数800余戸、人口は約4,100人である。
町制施行議案の理由書および議事録は次のとおりである。
議第八号
村ヲ町ト為ス件
身延村ヲ身延町ト為スモノトス
昭和五年六月十三日提出
身延村長 藤田佐一郎
理由
本案議決ヲ要ス其ノ理由ハ身延村ハ名僧日蓮大聖人ノ霊場タル身延山久遠寺ノ所在地ニシテ今ヤ世界ノ身延山トシテ年々十数万人ノ参詣者往来シ依テ近年著シク発達シ鰍沢区裁判所身延出張所、県立身延中学校、県土木出張所ヲ始メトシ実科高等女学校、身延祖山学院其ノ他多数ノ官公署ヲ有シ南部警察署ノ移転モ県下ノ与論トハナレリ、交通モ遺憾ナク整ヒ電信電話等モ完備シ全ク町トシテ差支ヘナキ程度ニ至リ峡南文化ノ中心地トナレリ殊ニ明六年八月日蓮大聖人御入滅六百五十年遠忌執行ニ付参詣者百万人ヲ予想セラレ諸準備ニ努力シツツアリ此ノ年ヲ永遠ニ記念スル為昭和六年一月一日ヨリ前記ノ通改称セントスルニアリ
会議録
議第八号 村ヲ町ト為ス件
議長 本案ヲ議題トスル事ヲ宣ス
議長 書記ヲシテ議案ヲ朗読セシム
村長 議案ニ対シ詳細説明ヲナス
第九番議員第八番議員原案賛成続イテ全員原案ニ賛成ス
議長ハ本件ハ議案ノ通確定セラレタル事ヲ宣告ス
(注・八番議員 望月九房 九番議員 深沢豊治)

