第三節 旧豊岡村
明治8年(1895)2月、県の合村勧奨により、小田船原・門野・大城・相又・清子・光子沢・横根中の七ヵ村が合併し豊岡村と称した。所属は巨摩郡第34区である。
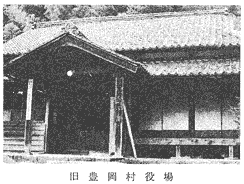
|
しかし、合村が認可になる直前と思われる明治8年2月10日の「合村議掟書」にも、認可直後と思われる2月17日の「合村確掟御指令願」にも、明確に「豊岡村」と記されているところを見るとこの説も疑問である。
おそらくは、合併前に新村名を協議立案する課程で、そのようないきさつがあったのではなかろうか。
合併新発足した豊岡村の戸長には横根中村の戸長をしていた清水為八が就任、副戸長はもと光子沢村戸長の長畑平四郎、もと大城村副戸長の望月作右衛門、もと小田船原村戸長の松田儀兵衛、もと相又村副戸長の武田栄六、それに門野村の鴨狩与一右衛門の五人が就任したのである。
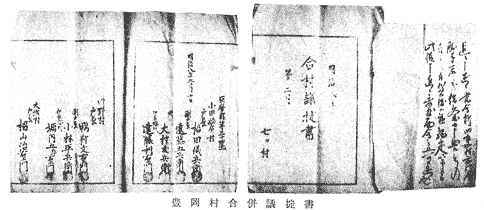
|
役場は当初戸長の清水為八宅においたが、間もなく3月には相又区市川屋宅に移し、また、転じて相又区千頭和延平宅に置いている。
以下、合併前後の七村協定事項などを示す資料として4つの文書を挙げておく。
一、明治8年2月、合併豊岡村の事務を詳細に規定した議掟書が各村の調印を以て確認されている。
明治八年第二月
一金 弐拾円 正戸長年給
一金 拾円 会所僕年給
一金 参拾円 白米拾俵代
但シ主従両人扶持米
一金 六円 薪六百把代
一金 五円 炭五拾俵代
但シ五貫目入
一金 弐円五拾銭 蝋燭五箱代
一金 三円 燈油壱斗弐升代
一金 六円 茶十二斤代
一金 拾七円五拾銭 筆墨紙代惣計百円也
一、正戸長之儀ハ二年番勤ニ相定御布告回達順ニ交代之事
附(ツケタ)リ会所ヨリ旧村々エ御布告其他回達之儀ハ小田船原村始ニテ従前之通継立可申事。
附(ツケタ)リ会所ヨリ旧村々エ御布告其他回達之儀ハ小田船原村始ニテ従前之通継立可申事。
一、正副戸長并伍長出庁料之儀ハ一日日当飯料共金三拾壱銭弐厘五毛ツツニ相定候事
一、貢納諸課出割合之儀ハ正副戸長立会之上割合可致事
附リ惣課出割合之儀ハ四歩通戸別六歩通高割ニ致副戸長伍長ニテ取立日限通戸長許エ可相納
附リ惣課出割合之儀ハ四歩通戸別六歩通高割ニ致副戸長伍長ニテ取立日限通戸長許エ可相納
一、副戸長給料之儀ハ旧村従前給料ニテ相勤会エ出勤之節ハ日当飯料トモ一日金拾銭宛ニ相定候事
一、地所書入質入証書奥印之儀ハ其旧村副戸長伍長惣代ニテ下調致添書之上当人戸長許エ願出可申
一、戸籍帳之儀ハ戸長許エ集置副戸長ニテ下調致月々戸長許エ可差出事
一、村入費之儀戸長許ニテ無利息ヲ以立替置年々五月一日ヨリ十日迄之内初割九月一日ヨリ十日迄之内中割翌年一月一日ヨリ十日迄之内割切戸長割渡候日ヨリ十日之間ニ急度相納可申事
一、各旧村ニテ差縺出来之節諸入費ハ訴訟ニテ出金可致尤其場合ニ寄非分掛リニモ出金可為致
一、区入費ハ其度々割合可致事
右ハ今般協議之上合村願書差上候ニ付テハ前ケ条書之趣向後変仕間敷候為其正副戸長伍長惣代連印議掟依而如件
明治八年二月十日
| 巨摩郡第三十四区 | |||||||
| 小田船原村 | 戸長 | 松田儀兵衛 | 印 | ||||
| 副戸長 | 遠藤五兵衛 | 印 | |||||
| 副戸長 | 大村友兵衛 | 印 | |||||
| 伍長惣代 | 遠藤利右衛門 | 印 | |||||
| 門野村 | 戸長 | 鴨狩文右衛門 | 印 | ||||
| 副戸長 | 小林平兵衛 | 印 | |||||
| 伍長惣代 | 堀内五郎右衛門 | 印 | |||||
| 大城村 | 戸長 | 椙山治右衛門 | 印 | ||||
| 副戸長 | 望月作右衛門 | 印 | |||||
| 伍長惣代 | 椙山源兵衛 | 印 | |||||
| 相又村 | 戸長 | 市川九兵衛 | 印 | ||||
| 副戸長 | 武田栄六 | 印 | |||||
| 副戸長 | 遠藤栄左衛門 | 印 | |||||
| 伍長惣代 | 千頭和窩右衛門 | 印 | |||||
| 清子村 | 戸長 | 佐野久之丈 | 印 | ||||
| 副戸長 | 松木六兵衛 | 印 | |||||
| 副戸長 | 滝戸弥兵衛 | 印 | |||||
| 伍長惣代 | 片田半之文 | 印 | |||||
| 光子沢村 | 戸長 | 長畑平四郎 | 印 | ||||
| 副戸長 | 小山政重 | 印 | |||||
| 伍長惣代 | 佐野嘉重 | 印 | |||||
| 横根中村 | 戸長 | 清水為八 | 印 | ||||
| 副戸長 | 遠藤保右衛門 | 印 | |||||
| 伍長惣代 | 佐野浜吉 | 印 | |||||
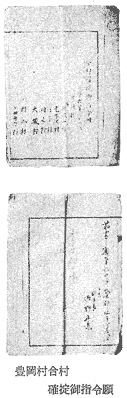 |

