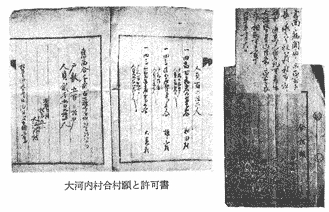第四節 旧大河内村
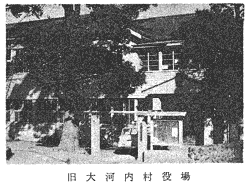
|
明治7年(1874)9月24日、山梨県権令に合村願を差出し、同年10月18日許可され、村名を大河内村と改称した。
11ヵ村合併に先立って同年椿草里村と大崩村が合村しており「両村合併取定確証」がとりかわされているが、間もなく県の指導による11ヵ村合併の中に吸収されてしまう。
大河内村の村名の由来について「大河内村取調書」には当時(大正5年)の村長松野弥三郎の言として
当時十九区長たりし木内信春(註・椿草里村出身)の命名によるもので、椿草里の御宗山より発する小河内川の小を大に改ためて大河内村とせられたりという。
と述べられている。
しかし、大河内村合村の明治7年には木内信春は睦合村戸長であり、同村の近藤喜則が19区長をしていたのであってこの点は事実と相違するようであるが、椿草里出身の木内信春が郷里の村名を河の名にちなんで命名したというのも大いにあり得る事であって、木内を近藤と取り違えたものか、又は木内の意をくんで近藤区長が命名したものか、想像の域を出ないものというほかない。 小河内川は「小持川」「子持川」「御持川」等々とも記されている。
次に明治7年の合村当時の状況を示す資料をいくつかあげてみたい。
先ず11村の正副戸長が連署捺印した合村願書は次の通りである。
|
合村願 八代郡第拾六区 上八木沢村 下八木沢村 帯金村 大垈村 椿草里村 大崩村 丸滝村 角打村 和田村 樋ノ上村 大嶋村 右村々 正副戸長 |
前書村々正副戸長一同奉申上候
私共村々之儀者従来山間僻地之小村落ニ有之当今之時勢事務多端随而冗費不尠依之合村之儀協議ヲ遂ケ候処各村小前一同敢テ異議無之確然決議仕候ニ付今般奉出願候則別紙絵図面並旧高戸数人口里程共詳密取調奉書上候間御許可被成下度挙而奉懇願候以上
右
右
| 上八木沢村 | 戸長 | 米沢清右衛門 | 印 | ||||
| 副戸長 | 佐野源蔵 | 印 | |||||
| 下八木沢村 | 戸長 | 鮎川伊兵衛 | 印 | ||||
| 副戸長 | 蘆沢祖右衛門 | 印 | |||||
| 大垈村 | 戸長 | 鈴木平左衛門 | 印 | ||||
| 副戸長 | 佐野定右衛門 | 印 | |||||
| 椿草里村 | 戸長 | 松野武兵衛 | 印 | ||||
| 副戸長 | 松野源兵衛 | 印 | |||||
| 大崩村 | 戸長 | 佐野八郎左衛門 | 印 | ||||
| 副戸長 | 佐野重郎右衛門 | 印 | |||||
| 帯金村 | 戸長 | 伊藤政十郎 | 印 | ||||
| 副戸長 | 伊藤利八 | 印 | |||||
| 丸滝村 | 戸長 | 依田重郎右衛門 | 印 | ||||
| 副戸長 | 佐野弥兵衛 | 印 | |||||
| 角打村 | 戸長 | 市川太郎左衛門 | 印 | ||||
| 副戸長 | 平田勝左衛門 | 印 | |||||
| 和田村 | 戸長 | 市川重郎右衛門 | 印 | ||||
| 副戸長 | 望月浅右衛門 | 印 | |||||
| 樋ノ上村 | 副戸長 | 滝川徳兵衛 | 印 | ||||
| 大島村 | 戸長 | 片田伝三郎 | 印 | ||||
| 副戸長 | 片田庄左衛門 | 印 | |||||
| 右拾壱ケ村 村名改正 大河内(ヲウコウチ)村 |
|||||||
| 村名之儀者右名ニ被仰付度奉願上候 | |||||||
| 山梨県権令 藤村紫朗殿 | |||||||
| 前書奉出願候ニ付御允許被成下度則奥印仕候以上 | |||||||
| 右兼務区長 | |||||||
| 近藤喜則 印 | |||||||
この合村願に対する県の許可は10月18日付になっている。
書面之趣聞届候条正副戸長之儀者今般合村之村高ニ応ジ規則之通更二人撰入札可差出尤跡役申付候迄従前之正副戸長ニ於テ相勤可申事
| 明治七年十月十八日 |
|
八代郡第拾六区合併大河内村概則
一、此般拾壱村合併之儀蒙允裁候上者各自協和戮力彼我ノ私見ヲ去リ偏黨之分裂ヲ破リ諸務公論ニ決シ百事簡便之方法ヲ設ケ冗費ヲ駆除シ生産ヲ増殖シ富強ノ基礎ヲ創立スヘキ事
但 旧村名ヲ何組ト唱候事
但 旧村名ヲ何組ト唱候事
拾壱村ニテ元正副戸町弐拾六名
内拾四名減省
正副戸長拾弐名ヲ建ツ
内訳
内拾四名減省
正副戸長拾弐名ヲ建ツ
内訳
| 副戸長 | 大島組 | 壱人 | 和田組 | 壱人 | |||||
| 樋上組 | 壱人 | 角打組 | 壱人 | ||||||
| 丸滝組 | 壱人 | ||||||||
| 大崩組 | 壱人 | 椿草里組 | 壱人 | ||||||
| 大垈組 | 壱人 | 帯金組 | 壱人 | ||||||
| 下八木沢組 | 壱人 | 上八木沢組 | 壱人 | ||||||
| 以上 拾壱名 | |||||||||
外ニ戸長壱名撰条事
一、毎組総而拾戸ニ付伍長之内壱名ヅツ出頭必ズ姓名等記載差支ヌ者ニテ入札ス
一、来ル廿八日毎組元里正伍長代理入札人午前八時無遺漏帯金組浄仙院エ会同封書相認〆候事
但各自辨当持参之事
但各自辨当持参之事
一、当日毎組元吏員並伍長之姓名ヲ書シ張出シ候事
一、事務所は該村之中央ニテ先ツ丸滝村妙法寺ニ仮設候事
一、事務所修繕入費ハ該村惣割 但家賃モアルヘシ
一、戸長ハ一六ヲ除クノ外定詰
一、毎組副戸長ハ各々十日輪番ニテ日勤
一、事務所入用炭薪油筆墨紙其他入費ハ該村総割、但正副町飲食ハ銘々ノ自費トス
一、毎組々帳簟司壱ツ宛尺寸ヲ同一ニシテ新設シ事務所ニ備置候事 但拵賃ハ毎組ノ自掛
一、高机椅子燈灯等調設 但該村掛
一、戸長年給 金 七拾貳圓
一、副戸長年給 金 三圓
一、伍長総代給 金 貳圓 但其組割
但事務所詰は日当副長同様其外臨時村内用隣組出張等之日当は其組之適度タルヘシ
但事務所詰は日当副長同様其外臨時村内用隣組出張等之日当は其組之適度タルヘシ
一、定使給料 金 貳拾圓
一、正副戸長 甲府出庁日当 金 三拾壱銭 厘五毛
但臨時筆墨紙等は村費タルベシ
但臨時筆墨紙等は村費タルベシ
一、副員 事務所日当 金 弐拾銭
一、都而一般之村費は 高割 地券確定ノ後ハ全高割
一、正副戸長並定使給料は 石高エ七分戸別エ三分 文割
一、臨時紛諍ヲ醸出シ其他地論等入賞ハ其組限リ
一、毎組共原被人有之相諍候事件ハ其原被掛リ
一、堤防自警請等ハ其組限リ
一、正副戸長ハ三年ニテ更代可致事
時条毎組会同之上反覆諮詢懇切協議予ジメ其綱領ヲ裁定ス追而合村一般之定規モ可有之先ツ前則ヲ以実践施行上駸々変遷質素簡便永世富実之一大活路ヲ可闢候也
| 明治帝七年第十月念六日 | |||
| 石拾壱該村 | 元正副戸長 | ||
| 伍長 | |||
| 兼務区長 | |||
| 南部 近藤喜則 | |||
今までの11ヵ村はそれぞれ組と称して副戸長を各組より1名ずつ出したのである。
合併前後の戸長名は記録に乏しく確実性を欠くが、当時の書類中に
| 明治八年六月 | 大河内村 | 戸長 | 伊藤政十郎 | |||
| 副戸長 | 鈴木平左衛門 | |||||
| 副戸長 | 松野武兵衛 | |||||
| 副戸長 | 滝川徳兵衛 |
の名が見られ、前記の条則により任期が明治7年の合村から3カ年とされていた点から考えて、旧帯金村戸長の伊藤政十郎が初代大河内村戸長に選ばれ、他の旧各村戸長がそれぞれ副戸長に選ばれたものであろうと推測できる。
また、明治14年(1981)大河内村戸長 市川重門(和田)明治17年同滝川得平(樋の上)の名が見える。
明治11年(1878)7月郡区町村編成法が制定されたことにより、八代郡の名称は西八代郡と変った。
明治22年(1889)7月1日町村制施行とともに、今まで大垈組に属していた川向の地を、富里村(現在下部町)へ編入したのである。明治22年7月18日村会議員の選挙が行なわれ12名の議員が当選し、同年7月25日第1回の村議会が戸長役場に招集されて村長・助役の選挙が行なわれ、初代村長に片田貞治氏が当選している。
最後の戸長佐野恭造氏より事務引継ぎを受け、約9ヵ月間村政を担当している。
村は南北に長く農林業が主なる産業であり、連年富士川の洪水による災害をこうむり堤防の修復、道路の開さくなど思うようにまかせず、各部落において負担しており、遅々として進まなかった。
明治22年当時の村決算をみるに、上半期485円76銭、下半期713円70銭であり、財政規模をうかがい知ることができる。明治22年9月には、区長制度を設けて行政事務を委任し、6区を置いた。
1区上八木沢・下八木沢、2区帯金、3区大垈・椿草里・大崩、4区丸滝・角打、5区和田・樋文上、6区大島(区長規定)
明治24年(1891)には、元戸長役場を廃して、丸滝宮ノ前に村役場を新築し、ついで六区制を八区とした。(上八木沢・三山・角打・丸滝・帯金・和田樋之上・大島。)明治32年帯金区から塩ノ沢が分離し1区を設けている。
明治25年(1892)3月尋常小学校を帯金に置き、分校を八木沢・椿草里・角打・和田・大島に置くことを決定した。同年4月大島より大島尋常小学校の設置請願が提出されたが不採決となり、ついで5月議会においても小学校設置の件は否決されている。
明治35年(1902)村立小学校2校を設置することになり、帯金小学校、大和小学校と命名された。これが現在の小学校の前身である。
明治39年11月塩之沢・波木井間富士川に渡舟許可願を出しており、当時舟1その製作費15円、船守賃年120円を見積っている。
明治40年(1907)村役場は、第1課戸籍・兵事・学事・衛生・統計・第2課地籍・税賦・庶務を分掌し、主任1名補助1名にて事務を行っており、村長報酬年40円、助役報酬年30円、収入役は給料で年額84円、書記2人で給料年額144円である。
大正元年(1912)には、事務を3課に分ち、書記3名を任命して事務にあたっている。
大正9年(1920)5月富士身延鉄道が身延駅まで開通した。さらに、同12年身延橋の竣工となり、当時はモダンな吊り橋としてその名を広く知られた。
富士身延鉄道は大正14年丸滝以北の敷設に着手し、昭和3年(1928)には甲府に至る全線の開通を見るに至り、急速に交通の便は開けていった。
大正10年(1921)から大正14年(1925)までの間は、村政は大きな飛躍を見せているが、反面村会は混乱し村長不信任建議の提出事件なども見られ、後世に残るエピソードも伝えられている。
昭和2年(1927)大河内郵便局に電話施設の諸願が議決され、同3年には、御大典記念事業として役場改築を決定し、52坪2合(173平方メートル)の庁舎を7,123円で請負わせている。
昭和6年(1931)頃より経済の不況は山村にも波及し、失業救済事業を起し山林開発、桑園改良、副業施設等の低利貸付をなし、これらの事業は、農村振興土木事業とともに頻繁(ひんぱん)に取り入れられ数年間続けられている。
このころより日本軽金属発電施設工事がはじまり、労務者の転入が目立って増加している。
昭和15年(1940)4月身延町二ヵ村衛生事務組合の設置が議決されて、組合会議員3名が選任されている。
昭和16年(1941)12月8日第二次世界大戦がはじまり、戦時体制に入った。同18年(1943)には、防空従事者に対し、防空従事者扶助金支給規定を設けて身分の保障を行なっている。
昭和18年(1943)7月国民健康保険組合を設立し、診療を開始している。
昭和20年8月15日、敗戦により村役場の事務は、引揚者援護、食糧供出、物資の配給等終戦処理一色に塗りかえられたのである。
昭和22年5月3日、日本国憲法、及び地方自治法が施行され民主主義、民主政治が事実上確立されたのである。
同年四月八日には村長選挙、4月30日には村議会議員選挙が行なわれた。年齢満20歳以上の男女に平等な選挙権があたえられたのである。投票所は上八木沢・帯金小学校・丸滝・大和小学校の4箇所で行なわれた。
その結果公選初代村長には鈴木音次郎が当選、助役に佐野嘉幸、収入役に長谷川一がそれぞれ選任された。また、このとき選挙された自治法初の村会議員は次の16名である。
議長、望月富斉、副議長、伊藤喜則、議員、米沢節三、鮎川太郎、千須和秀治、鈴木武重、依田熹一、久保光明、中村十郎、依田高村、赤塚一一、滝川一政、小笠原実、若林孝義、久保二郎、市川正美
六三制教育制度による中学校は、大和、帯金の小学校に併設し、教育を行なっていたが校地を丸滝に定め昭和25年10月着工し、朝鮮動乱による物価の高騰にあって憂慮されたが、幸い税制改正により償却資産税の収入が見込まれることとなって、翌年7月17日総工費7,908,928円をもって完成したのである。引続いて公民館を建設した。昭和27年7月には、失業対策事業開始が認可され、上大島道路、下大島道路工事に就労者をおくっている。又同年8月には、塩之沢にパルプ工場誘致を計画したが不調に終っている。

|
昭和29年6月には、大崩部落に電燈がともり、明るい生活ができるようになった。
以上旧大河内村が誕生してから、たどった変せんの概要をしるしたのであるが、町村合併に至る間、実に90年、我々の祖先、先輩が苦難とたたかい、忍耐強く努力を続けた数々の足跡がうかがわれるのである。
| 大河内村歴代村長 | |||||
| 氏名 | 就任年月日 | 退職年月日 | |||
| 片田貞治 | 明治22.7.5 | 明治23.4.13 | |||
| 片田健久 | 明治23.4.13 | 明治24.2.21 | |||
| 望月朝暉 | 明治24.2.21 | 明治26.3.21 | |||
| 鮎川伊兵衛 | 明治26.3.21 | 明治27.6.19 | |||
| 伊藤誡三 | 明治27.6.19 | 明治31.4.20 | |||
| 伊藤誡三 | 明治31.4.23 | 明治33.4.9 | |||
| 鮎川直次郎 | 明治33.4.18 | 明治34.2.2 | |||
| 佐野美儀 | 明治34.2.22 | 明治34.7.31 | |||
| 伊藤誡三 | 明治34.8.7 | 明治37.7.16 | |||
| 望月吾三郎 | 明治37.7.25 | 明治39.10.14 | |||
| 伊藤孝 | 明治39.10.17 | 明治34.11.2 | |||
| 小笠原博文 | 明治43.12.2 | 明治45.7.21 | |||
| 望月安則 | 明治45.7.25 | 大正4.12.12 | |||
| 松野弥三郎 | 大正4.12.15 | 大正5.11.30 | |||
| 片田栄三郎 | 大正5.12.4 | 大正9.11 | |||
| 松野弥三郎 | 大正10.4.9 | 大正10.6.30 | |||
| 伊藤繁太郎 | 大正10.7.3 | 大正14.7.2 | |||
| 久保重作 | 大正14.7.12 | 昭和2.7.11 | |||
| 望月富斉 | 昭和2.7.20 | 昭和6.7.2 | |||
| 望月望 | 昭和6.7.4 | 昭和10.7.2 | |||
| 望月勘治郎 | 昭和10.7.17 | 昭和14.7.1 | |||
| 市川政則 | 昭和14.7.2 | 昭和17.12.27 | |||
| 佐野幸一 | 昭和18.1.8 | 昭和20.2.7 | |||
| 佐野祥盛 | 昭和20.2.8 | 昭和21.12.5 | |||
| 鈴木音次郎 | 昭和22.4.6 | 昭和26.4.3 | |||
| 佐野祥盛 | 昭和26.4.21 | 昭和30.2.10 | |||
| 大河内村歴代助役 | |||||
| 氏名 | 就任年月日 | 退職年月日 | |||
| 久保幸右衛門 | 明治22.7.25 | ||||
| 米沢清右衛門 | 明治23.4.13 | ||||
| 長谷川周吉 | 明治23.5.1 | ||||
| 依田峯三郎 | 明治24.2.11 | ||||
| 片田與平 | 明治24.11.28 | ||||
| 佐野藤左衛門 | 明治27.10.30 | ||||
| 望月吾三郎 | 明治29.3.27 | ||||
| 望月伝市 | 明治31.5.13 | ||||
| 伊藤孝 | 明治33.9.25 | ||||
| 小笠原博文 | 明治34.10.3 | ||||
| 望月政治 | 明治38.8.18 | ||||
| 名取新作 | 明治39.11.16 | ||||
| 久保重作 | 明治42.4.19 | 明治44.1.31 | |||
| 望月安則 | 明治44.2.6 | 大正元.8.2 | |||
| 片田栄三郎 | 大正元.8.28 | 大正5.9.5 | |||
| 片田栄三郎 | 大正5.9.6 | 大正5.12.9 | |||
| 鈴木熊吉 | 大正6.3.3 | ||||
| 伊藤繁太郎 | 大正7.3.6 | 大正10.7.3 | |||
| 市川政則 | 大正11.2.28 | 大正13.5.25 | |||
| 望月富斉 | 大正13.7.22 | 昭和2.7.20 | |||
| 佐野幸一 | 昭和2.8.29 | 昭和6.8.29 | |||
| 滝川晶 | 昭和6.8.13 | 昭和10.8.30 | |||
| 滝川晶 | 昭和10.9.8 | 昭和12.7.10 | |||
| 市川純一 | 昭和12.9.2 | 昭和13.12.25 | |||
| 佐野幸一 | 昭和14.8.9 | 昭和18.1.7 | |||
| 片田大助 | 昭和18.2.8 | 昭和20.10.4 | |||
| 伊藤喜則 | 昭和20.11.16 | 昭和22.4 | |||
| 佐野嘉幸 | 昭和22.5.19 | 昭和26.5.19 | |||
| 若林孝義 | 昭和26.5.19 | 昭和31.2.10 | |||
| 大河内村歴代収入役 | |||||
| 氏名 | 就任年月日 | 退職年月日 | |||
| 望月伝市 | 明治22.8.31 | ||||
| 望月兼市 | 明治26.4.2 | ||||
| 片田作市 | 明治29.3.27 | ||||
| 片田熊之助 | 明治29.12.27 | ||||
| 長谷川亀三郎 | 明治31.10.31 | ||||
| 久保重作 | 明治33.5.2 | ||||
| 望月莞爾 | 明治34.4.28 | ||||
| 佐野庄太郎 | 明治38.8.18 | ||||
| 鈴木熊吉 | 明治39.11.16 | ||||
| 平田栄二良 | 明治43.5.24 | 大正2.6.7 | |||
| 依田作太郎 | 大正2.6.10 | 大正4.1.5 | |||
| 名取市次郎 | 大正4.1.16 | 大正5.8.21 | |||
| 佐野祥盛 | 大正5.8.21 | 大正6.3.3 | |||
| 望月富斉 | 大正6.3.3 | 大正8.9.30 | |||
| 市川善一 | 大正8.11.18 | 大正10.5.20 | |||
| 若林憬 | 大正10.5.20 | ||||
| 望月正隆 | 大正11.2.12 | ||||
| 市川初太郎 | 大正14.9.13 | 昭和4.9.14 | |||
| 市川初太郎 | 昭和4.10.5 | 昭和6.9.17 | |||
| 伊藤喜則 | 昭和6.9.16 | 昭和10.9.17 | |||
| 小笠原実 | 昭和10.9.20 | 昭和10.11.17 | |||
| 千須和秀治 | 昭和10.11.10 | ||||
| 千須和秀治 | 昭和14.11.10 | 昭和18.11.11 | |||
| 小笠原実 | 昭和18.11.11 | 昭和22.5.19 | |||
| 長谷川一 | 昭和22.5.19 | 昭和26.5.19 | |||
| 望月喜一 | 昭和26.5.20 | 昭和30.2.10 | |||