第三章 議会と選挙
第一節 議会の沿革
一、旧四ヵ町村の議会について
明治12年(1879)県下に区町村会法が施行され各町村に町村会が開かれた。これが山梨県における町村議会制度の発祥である。この前年明治11年に施行されたいわゆる三新法、即ち郡区町村編成法・府県会規則・地方税規則は府県に公選議員による府県会を置き、地方税の支弁・徴収を議決するものとしたが、区町村にも府県会規則に準じて区町村会を開くことが認められたのである。
これにより藤村県令は甲第84号「山梨県町村会規則」を明治12年4月28日下の通り布達し、議会の性格を明らかにした。
山梨県町村会規則
| 第一章 総則 | |||||||||||||||||
| 第一条 | 町村会は該町村に係る下の各款を議定す 但し、甲府市街は総町共同の議会を開き其市街に係るものを議す
|
||||||||||||||||
| 第二条 | 町村会は通常会と臨時会との二類に別つ、其定期に於て開くものを通常会とし臨時に開くものを臨時会となす。 | ||||||||||||||||
| 第三条 | 通常会、臨時会を論せす会議の議案は総て戸長より之を発す | ||||||||||||||||
| 第四条 | 臨時会は其時に会議を要する事件に限り其他の事件を議するを得す | ||||||||||||||||
| 第五条 | 町村費を以て施行すべき事件は必ず町村の会議に附し其議決は戸長認可の上之を施行す、若戸長認可すへからすと思惟する時は其事由を郡長を経て県令に具状して指揮を請ふへし | ||||||||||||||||
| 第六条 | 町村会の議決は議長より戸長郡長を経て県庁に報告すべし、其法律に触る者及権限を踰る者其他一般行政上に障碍ある者は県庁より取消を命ずることあるべし | ||||||||||||||||
| 第七条 | 町村会は毎年通常会議の初めに於て町村費に係る前年度出納決算の報告を受く | ||||||||||||||||
| 第八条 | 町村会は県庁又は郡長より其町村内に施行すべき事件に付会議の意見を問ふことあるときは之を議す | ||||||||||||||||
| 第九条 | 通常会期中議員の内其町村の利害に関する事件に就き県庁に建議せんと欲する者あれは之を会議に附す、過半数の同議を得たるときは議長の名を以て建議するを得 | ||||||||||||||||
| 第十条 | 町村会は議事細則を議定し認可を得て之を施行するを得 | ||||||||||||||||
| 第二章 選挙 | |||||||||||||||||
| 第十一条 | 町村会の議員は町村の大小に依る下の比例を以て之を撰ふ 但し甲府市街は総町の戸数を合算し本文の比例を以て之を撰ふ
|
||||||||||||||||
| 第十二条 | 議長副議長は議員中より公撰し戸長の認可を受くへし | ||||||||||||||||
| 第十三条 | 書記は議長之を撰任し庶務を整理せしむ書記は俸給を給す、其額は会議の決を以て之を定め町村会議より支出す | ||||||||||||||||
| 第十四条 | 議員たることを得へき者は満弐拾五才以上の男子にして該町村内に於て地所を所持する者に限る但下の各款に触る者は議員たることを得す
|
||||||||||||||||
| 第十五条 | 議員を選挙するを得へき者は満二十才以上の男子にして該町村に本籍を定め其町村内に於て地所を所持する者に限る但前条の第一款第二款第三款に触るる者は選挙人たることを得す | ||||||||||||||||
| 第十六条 | 議員を選挙せんとするときは戸長に於て選挙会を開くへき日を定め少くも拾五日前に該町村内に公告すへし | ||||||||||||||||
| 第十七条 | 選挙の投票は予定の日該町村役所に於て之を為し戸長之を調査し選挙会中の取締を為すへし 但便宜に因り役所に於て選挙会を開くことを得 |
||||||||||||||||
| 第十八条 | 投票は予め戸長より付与した用紙に撰挙被選人の姓名年齢を記し、予定の日之を戸長に出すへし投票は多数の者を以て当選人とし同数の者は年長を取り同年の者は鬮(くじ)を以て定む 但投票は代人に托し差出すも妨なし |
||||||||||||||||
| 第十九条 | 投票終るの後戸長は選挙人名籍に就て投票の当否を査し、又被選挙人名籍に就て当選人の当否を査す、若し法に於て不適当なる者あるか或は当選人自ら其選を辞するときは順次投票の多数を得たる者を取る | ||||||||||||||||
| 第二十条 | 当選人の当否を査定するの伍戸長は其当選人を役所に呼出当選状を渡す。当選人は請書を出すへし 但し当選人請書を出したる伍戸長は其姓名を郡長に報告し且該町村内に公示すへし |
||||||||||||||||
| 第二十一条 | 議員の任期は四年とし二年毎に全数の半を改選す、第一回二年期の改選を為し抽籤を以て其退任の人を定む | ||||||||||||||||
| 第二十二条 | 議長副議長の任期は二年とし議員の改選毎に之を公選すへし | ||||||||||||||||
| 第二十三条 | 前弐条の場合に於ては、前任の者を再選するを得 | ||||||||||||||||
| 第二十四条 | 議員中第十三条に掲ぐる諸款の場合に遭遇する者あるか其町村外に転任するかは又は死去したるときは更に其欠に代る者を選挙す、其疾病等止むを得ざる事故なくして開会の招集に応ぜざる者は退転者とし亦其欠に代る者を選挙す | ||||||||||||||||
| 第三章 議則 | |||||||||||||||||
| 第二十五条 | 議員半数以上出席せされは当日の会議を開くを得す | ||||||||||||||||
| 第二十六条 | 会議は過半数にて決す可否同数なるときは議長の可否する所に依る | ||||||||||||||||
| 第二十七条 | 戸長若くは其代理人は会議に於て議案の旨趣を弁明するを得、但し決議の数に入るを得す | ||||||||||||||||
| 第二十八条 | 議会は傍聴を許す。但し戸長の要望に依り又は議長の意見を以て傍聴を禁するを得 | ||||||||||||||||
| 第二十九条 | 議員は会議に方り充分討論の権を有す然とも人身上に付て褒貶毀誉に渉ることを得す | ||||||||||||||||
| 第三十条 | 議場を整理するは議長の職掌とす、若し規則に背き議長之を制止して其命に順せさる者あるときは議長之を議場外に退去せしむるを得、其強暴に渉る者は警察官吏の処分を求むるを得 | ||||||||||||||||
| 第四章 開閉 | |||||||||||||||||
| 第三十一条 | 町村会は毎年一度四月に於て之を開くは会期十五日以内とす、其開閉は戸長之を命す、但し戸長は会議の衆議を取りて其日限を伸ること得ると雖も其事由を直に長に報告すへし | ||||||||||||||||
| 第三十二条 | 通常会期の外会議に付すへき事ありて戸長より開会を要するか又は議員全数三分一以上の同議を以て開会を求むるときは郡長の許可を得て臨時会を開くことを得 | ||||||||||||||||
| 第三十三条 | 会議の論説法律又は規則を犯し或は権限を超ることありと認めるときは戸長は其会議を中止せしめ之を郡長に報告し郡長は県庁に具状して指揮を請ふへし | ||||||||||||||||
| 第三十四条 | 会議中法律又は規則を犯し或は権限を超ることありと認めるときは何れの時を問はす県庁より閉会を命じ又は議員の解散を命することあるへし | ||||||||||||||||
| 第三十五条 | 県庁より解散を命じたるときは更に議員を改選すへし | ||||||||||||||||
| 附則 連合町村会 | |||||||||||||||||
| 第一条 | 弐町村以上数町村に関渉する事件は各町村より議員を派出して之を議す | ||||||||||||||||
| 第二条 | 連合会の議員は町村数の多少により戸長協議の上各町村より出す処の人員を予定す其派出議員は該町村議員中互選を以て之を選ふ | ||||||||||||||||
| 第三条 | 連合会の議員は町村の大小に拘はらす渾て同数の人員を出す | ||||||||||||||||
| 第四条 | 連合会の議案は各町戸長協議を以て之を発す其議決は聯合各町村戸長認可の上之を施行す | ||||||||||||||||
| 第五条 | 連合会の議長副議長及議員は年限なし該会終れは即解任す、但し毎年該会を要するものは各二年の任期を定むるを得 | ||||||||||||||||
| 第六条 | 前各条の外は渾て本則に拠る | ||||||||||||||||
わずかに身延村の村会議員辞令が発見されているほか、大河内村会の議事規則、傍聴心得、当初の議案の一部が残されているので当時の議会をしのぶ資料として次に再録しておこう。
○大河内村会議事傍聴心得
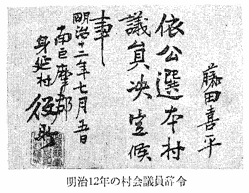
|
| 第一条 | 議事ノ傍聴ヲ望ムモノハ縦令自村ノモノタリトモ当日開会ニ先チ議場ノ受附所ニ至リ名刺ヲ差出シ指揮ヲ受ケ机所ニ着座スベシ | |
| 第二条 | 議場開場ノ報ヲ得バ参着ノ順序ニ随而静ニ着席ス可シ席ニ着キテハ猥リニ退出ス可カラズ止ムヲ得ザル事故アラバ受附所ニ告ゲ退席スベシ | |
| 第三条 | 傍聴人ハ静粛黙聴スルヲ要ス私語雑談吹烟飲食或ハ故ナク議場ノ周辺ニ立チ或ハ起臥睡眼等ノ事一切之ヲ禁ズ | |
| 第四条 | 議事休息ノ間ハ机ニ退ク可シ机所タリトモ笑談語高談或ハ議事ヲ評論シ議員ヲ褒貶スル等ノ事一切ヲ禁止ス | |
| 第五条 | 前条ノ規則ヲ犯シ之ヲ制スルモ用イズ議事ノ妨ヲ為スト認ムル時ハ議事ヨリ受付役員ニ命ジテ直ニ退去セシム可シ | |
| ○村会議事及書記日当議案 | ||
| 会議費賦課方法 | ||
| 第一条 | 議員ハ給料ナキ成規ナレドモ開会出勤中ハ一日金五銭ヲスルモノトス | |
| 第二条 | 書記日当ハ一日金拾五銭ト定ム 但事務繁忙ニシテ夜業ヲ為ス時ハ賄料トシテ金弐銭五厘ヲ給ス |
|
| 第三条 | 書記ハ年限ナキモノトス及開会ニ臨ミ議長之ヲ採用ス | |
| ○西八代郡大河村々会議事規則 | ||
| 第一条 | 議事ハ午前第九時ニ始メ午後四時ニ終ル時宜ニ依リ時間ヲ伸縮スルハ臨時衆議ニ決ス | |
| 第二条 | 議事席上ハ毎会番号ヲ附ス、其順次ハ予メ鬮取(注クジ)ヲ以テ之ヲ定ム、其一回中ハ必ズ其席ニ附スベシ | |
| 第三条 | 議案ノ可否ハ通常三次会ヲ経テ之ヲ決スルモノトス 其順序左ノ如シ 第一次会 議長先ヅ起テ議案ヲ各員ニ頒布シ書記ヲシテ朗読セシム朗読終テ議案ニ疑義アルモノハ議長ヲ経テ主任者ニ質問スベシ質問後議案継体ニ就テ意見ヲ述ベ動議ヲ発スルヲ得議長ハ其ノ議ヲ悉サシメ可否議定ス 第二次会 議長先ツ起テ一次会ニ分附スル所ノ議案ヲ逐条審議セシメ事ヲ指揮シ書記ニ命ジテ更ニ議案ヲ朗読セシム毎条終テ議員ハ其所見ヲ陳述討論シテ可否ヲ議決ス 議案ノ主意可ト決スルモ猶其ノ方法章句ヲ修正ス可キモノハ議員中ヨリ委員ヲ公選シテ之ヲ修正セシメ然ル後三次会ニ附シテ法定セシムベシ 第三次会 二次会ニ於テ逐条議定シタルモノヲ修正シテ再ビ全案ノ可否ヲ議決ス |
|
| 第四条 | 凡ソ可否ノ数ヲ算スルハ議員ヲシテ可否ヲ投票セシメ或ハ起立セシムル臨時議長ノ指揮ニ依ル | |
| 第五条 | 一議員動議ヲ発スルモ他ニ賛成ナキ時ハ議長ハ之ヲ取消ス可シ賛成アル時ハ議員動議ニ就テ可否ヲ決セシム可否相半スル時ハ議長之ヲ判決ス | |
| 第六条 | 会議中発言セント欲スル者ハ先ヅ起テ議長ヲ呼ビ自己ノ番号ヲ称ス可シ議長ハ其番号ヲ回呼シテ発言セシム若シ二人以上同時ニ発言スル後ハ議長其一人ヲ指揮シテ発言セシム可シ | |
| 第七条 | 一議員議論未ダ終ラザル間ハ他議員ハ静心黙聴且議論ヲシテ満場ニ洞徹セシメ必ズ其ノ中間ニ於テ遮言スルヲ許サズ | |
| 第八条 | 討論問答ハ必ズ議長ニ向ヒ演説シ議員互ニ相応答シ空論罵詈ニ渉ルヲ禁ズ | |
| 第九条 | 会議中ハ議員着席ノ番ヲ称ス可シ直ニ其姓名ヲ称呼スルヲ得ズ | |
| 第十条 | 凡ソ議員ハ一会一議ニ付再度発言スルヲ得ズ其ノ論旨ヲ尽サヾルヲ補ヒ或ハ其ノ誤解ヲ辨明シ及議案主任者各員ノ問ニ答ヘ且ツ小会議ニ於テ再三論ズル等ハ此ノ限リニ非ズ | |
| 第十一条 | 凡ソ一議案未ダ終ラザル間ハ他ノ事ニ付発論スルヲ得ズ | |
| 第十二条 | 議長議案ニ付自己ノ意見述ベント欲スル時ハ副議長ヲシテ代理セシメ退イテ議員ノ席ニ着キ発言ス可シ | |
| 第十三条 | 議案朗読ノ後暫クシテ発言無キ時ハ議長ハ全員認可スルモノトシテ其ノ可決ヲ告ゲ、書記ヲシテ議案ヲ朗読セシム | |
| 第十四条 | 議員出頭ハ名刺ヲ以テ書記ニ告グベシ其疾病等止ムヲ得ザルノ事故アリテ欠席スルモノハ開会時限ニ先チ書記ニ報告スベシ縦令親戚タリトモ代理スルヲ許サズ | |
| 第十五条 | 議員議場ニ入ル時ハ必ズ帽ヲ脱スベシ議長着席ノ節起テ礼ヲ為ス可シ | |
| 第十六条 | 議事ノ始終ハ号鐘ヲ以テ之ヲ報ス | |
| 第十七条 | 議場ニ臨ミテ雑談喫烟ヲ禁ズ且ツ動止粛整ナル可シ矣 | |
遅刻には罰金制
明治12年の大河内村会では下のようなきびしい議員遅参に対する罰則が決められている。
村会議員遅着処分議案(明治十二年)
第一条
一、議員一時間遅着するときは必ず脚夫を以て出席を促すべし只賃銭を先払いとす但し賃銭は遠近とも金十銭とす
第二条
一、前条延着は疾病、事故と雖も無沙汰なれば行ふものとす
第三条
一、疾病事故に非ざれば其旨申出ると雖も採用せざるを得るものとす
他の村の例は記録がないが、当時の村会のきびしさをしのぶことができる。
誓約書
今回本村々会出席時間を午前八時と相定め、若し無届にて遅不参をなし、午前十一時に至るも尚欠席遅参の事故を届出でざるものは過怠料として一回金拾五銭を出さしむ、
但し収入したる過怠料は右不参に付き使用したる人夫賃に充て其の残余あるときは之れを会議に供するものとす
右誓約確守履行致候也
明治二十二年八月七日
但し収入したる過怠料は右不参に付き使用したる人夫賃に充て其の残余あるときは之れを会議に供するものとす
右誓約確守履行致候也
明治二十二年八月七日
| 大河村会議員十二名連署捺印 | |
| 村長、助役署名捺印 |
| 福居村 | 20人 | 注、戸口300以上600未満定数20人 | |
| 大河内村 | 20人 | ||
| 豊岡村 | 20人 | ||
| 身延村 | 20人 | ||
明治17年(1942)7月には、町村会規則が県布達甲第44号で制定され、議員定数を大幅に削減して300戸未満の町村は6人、300戸以上500戸未満の町村は8人、500戸以上の町村は10人としたほか、議員の任期も4年(2年ごと半数改選)から6年(3年ごと半数改選)に改めるなどの改正がなされた。
身延町の旧四カ村はいづれも8人の議員を選出した。
しかし町村会の提案権は戸長にのみ属し、県令は閉会または議会の解散権を持つなど、議会とは名ばかりの諮問機関的、官治的色彩の濃いものであった。
次に明治17年の町村会規則の一部を抜すいして掲げる。
町村会規則
甲第四拾号明治十七年七月二日
町村会規則別紙之通之ヲ決ム
右布達候事
| 町村会規則 第一章 総則 |
||
| 第一条 | 町村会ハ通常会ト臨時会トノ二類ニ別ツ其定期ニ於テ開クモノヲ通常会トシ臨時ニ開クモノヲ臨時会トス | |
| 第二条 | 臨時会ハ其特ニ会議ヲ要スル事件ニ限リ其他ノ事件ヲ議スルヲ得ス | |
| 第三条 | 町村会ハ通常会ノ初テ前年度町村費出納決算ノ報告ヲ受ク | |
| 第四条 | 戸長ハ議事細則ヲ定メ県庁ノ認可ヲ得テ之ヲ施行スルヲ得 | |
| 第二章 撰挙 | ||
| 第五条 | 町村会議員ノ定数ハ戸数三百戸未満ノ町村ハ六人三百戸以上五百戸未満ノ町村ハ八人五百戸以上ノ町村ハ拾人トス 町村ノ状況ニ依リ戸長ハ適宜議員撰挙ノ区域ヲ定メ県庁ノ認可ヲ得テ施行スルヲ得 |
|
| 第六条 | 戸長事故アリテ議員中ヨリ議長ヲ指決スル場合ニ於テハ議員ハ其指定ヲ拒ムヲ得ズ | |
| 第七条 | 書記ハ議長之ヲ撰ミ庶務ヲ整理セシム | |
| 第八条 | 議員ヲ撰挙セントスルトキハ戸長ニ於テ撰挙会ヲ開クヘキ日ヲ定メ少クモ十日前ニ該町村内ニ広告スヘシ | |
| 第九条 | 撰挙ノ投票ハ予定ノ日該町村役所ニ於テ之ヲ為シ戸長ヲ調査シ撰挙会中ノ取締ヲ為スヘシ 但便宜ニ依リ役所外ニ於テ撰挙会ヲ開クヲ得 |
|
| 第十条 | 撰挙人ハ予メ戸長ヨリ附与シタル投票用紙ニ自己及ヒ被撰人ノ姓名年齢ヲ記シ予定ノ日之ヲ戸長ニ出スヘシ投票ハ多数ノ者ヲ以テ当撰トシ同数ノ者ハ年長ヲ取リ同年ノ者ハ鬮ヲ以テ定ム 但投票ハ代人ニ托シ差出スモ妨ケナシ |
|
| 第十一条 | 投票終ルノ後戸長ハ撰挙人名簿ニ就テ当否ヲ査シ又被撰選挙人名簿ニ就テ当撰人ノ当否ヲ査ス若シ法ニ於テ不適当ナル者アルカ或ハ当撰人自ラ其撰ヲ辞スルトキハ順次当票ノ多数ヲ得タルモノヲ取ル | |
| 第十二条 | 当撰人ノ当否ヲ査定スル后戸長ハ其当撰人ヲ役所ニ呼出シ当撰状ヲ渡シ当撰人ハ請書ヲ出スヘシ 但当撰人各請書ヲ出シタル后戸長ハ其姓名ヲ町村内ニ公示スヘシ |
|
| 第十三条 | 議員ノ任期ハ六年トシ三年毎ニ全数ノ半ヲ改撰ス第一回三年ノ改撰ヲ為スハ抽籤ヲ以テ其退任者ヲ定ム 但前任者ヲ再撰スルヲ得 |
|
| 第十四条 | 議員中区町村会法第十条ニ定メラレタル各款ニ遭遇スルカ又ハ其町村外ニ転住スルカ其他総テ欠員アルトキハ之レニ代ル者ヲ撰挙ス | |
| 第三章 議則 | ||
| 第十五条 | 議員半数以上出席セサレハ当日ノ会議ヲ開クヲ得ス | |
| 第十六条 | 会議ハ過半数ニ依テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ可否スル処ニ依ル | |
| 第十七条 | 戸長ハ会議ニ於テ議案ノ旨趣ヲ辨明シ又ハ代理人ヲシテ辨明セシムルヲ得 | |
| 第十八条 | 会議ハ傍聴ヲ許ス但議長ハ時宜ニ依リ傍聴ヲ禁スルヲ得 | |
| 第十九条 | 議員ハ会議ニ当リ充分討論ノ権ヲ有ス然レドモ身上ニ付褒貶毀誉ニ渉ルヲ得ス | |
| 第二十条 | 議場ヲ整理スルハ議長ノ職掌トス若シ規則ニ背キ議長之ヲ制止シテ其命ニ順ハサル者アルトキハ議長ハ之ヲ議場外ニ退去セシムルヲ得其強暴ニ渉ル者ハ警察官吏ノ処分ヲ求ムルヲ得 | |
| 第四章 開閉 | ||
| 第廿一条 | 町村会ハ毎年一度五月ニ於テ之ヲ開ク其開期ハ七日以内トス其開閉ハ戸長之ヲ命ス | |
| 第廿二条 | 通常開期ノ外会議ニ附スヘキ事件アルトキ戸長ハ臨時会ヲ開クヲ得其開期三日以内トス 但該会ヲ要スル事由ハ区長ヲ経テ県庁ニ報告スヘシ |
|
町村制によれば、町村会議員の定数は、
| 人口 5,000人未満 |
12人 |
|
| 人口 5,000人以上10,000人未満 | 18人 | |
| 人口10,000人以上20,000人未満 | 24人 | |
| 人口20,000人以上 | 30人 |
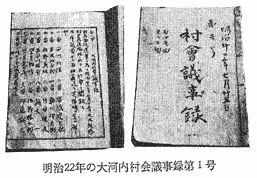
|
議員の選挙権は公民権のある者の外、村税を負担する者にも与え、被選挙権は選挙権があっても公民権のないものには与えず、選挙は納税額により選挙人に等級を付し、1級2級の差別をつけ、それぞれ半数ずつ選出したのである。
半数改選制ではじめの議員は3年目に抽籤(せん)で半数退任し、以後3年毎に半数改選であった。
選挙権および議員の1、2級制は大正10年(1921)の町村制改正により廃され、町村税納税者全員をもって選挙人とすることになり、大正15年(1926)普通選挙実施により公民権(25歳以上の成人男子にして2年以上その村に在住し欠格条項に該当しない日本国民)を有するもの全員に町村会議員の選挙権が与えられることになった。
議長は町村長がこれに当たり、事故ある時は助役等理事者側の代理者がこれにあたる制度であった。
議会の職務権限としては、町村に関する事件および法律勅令に依りその権限に属する事件の議決権。
(条例、規則の制定改廃、予算決算町村費で支弁する事業、財産の管理等)
町村内争議の決定権。町村長の選挙、町村長の推せんによる、助役収入役の選定(同じく区長、区長代理の撰定、委員の撰定などの権限)
町村行政の監督権
官公庁に対し意見を上申しまたは答申する権限などが定められてある。
特に納税の等級(当初は納税額)を議会の議決によって決することになっていたため、議会では常にこれが主要な論議の対象となり、議員が情実や選挙の利害などにからんで等級を上下するという非難もあった。
これは戦後シャウプ勧告により地方税法が改正されるまで続いたのである。
議事の細則は各町村ごと定めたが、議案の審議方法としては、
| 第一読会 | 趣旨説明、質疑応答 | ||
| 第二読会 | 内容の逐条審議、修正 | ||
| 第三読会 | 討論採決 |
議会書記は町村制57条により会議の都度選挙でえらんだ。
次に明治22年の豊岡村会会議規則および傍聴人取締規則の全文を掲げる。各村とも同文である。
身延村においては昭和18年(1943)、人口が5,000人を越したので町村制第11条により定員12名を18名に増員している。
その後町村制の改正、人口増加により昭和30年合併時の各町村議員定数は、
| 下山村 |
16名 |
||
| 身延町 | 22名 | ||
| 豊岡村 | 16名 | ||
| 大河内村 | 16名 |
豊岡村々会議規則 明治22年制定
| 第一 議場整理 | ||
| 第一条 | 議事ハ午前第九時ノ始メ午後三時ニ終ル 但議長ハ時宜ニ依リ時間ヲ伸縮スルヲ得 |
|
| 第二条 | 議員ノ席次ハ抽籤ヲ以テ之ヲ定ム | |
| 第三条 | 議事中ハ議長ノ姓名ヲ称ヘスシテ議長ト呼ブベシ | |
| 第四条 | 議題外ニ起ル事件ハ議長ニ於テ会議ノ評決ヲ取ラズ直チニ之ヲ決スルヲ得 | |
| 第五条 | 議案ハ議長之ヲ分附ス | |
| 第六条 | 修正説ヲ提出セント欲スルモノハ文案ヲ作リテ議長ニ出ス事ヲ得 | |
| 第七条 | 修正説ハ第二次会第三次会ニ提出スルヲ得 | |
| 第二 議事 | ||
| 第八条 | 議事ノ順席ハ第一次会第二次会第三次会ノ三会ニ分ツ 但会議ノ決議ニ依リ第一次会又ハ第二次会ニ於テ議了決定スル事ヲ得 |
|
| 第九条 | 第一次会ニ於テ議案ノ大意ヲ議シ又議案ニ就キ質問ヲ要スル時ハ本会ノ始メニ於テ質問スベシ | |
| 第十条 | 第二次会ニ於テハ議案ヲ逐条ニ討論議決スヘシ | |
| 第十一条 | 第三次会ニ於テハ全案ニ就キ其確定議決ヲ為スベシ | |
| 第十二条 | 第二次会ニ於テ発言ナキトキハ議長ハ可決シタルモノトシ次条ノ審議ニ移ルヲ得 | |
| 第十三条 | 第二次会ニ於テ賛成者ナキモノハ第三次会ニ於テ二名以上の賛成者ナキモノハ議題ト為スヲ得ス | |
| 第三 発言 | ||
| 第十四条 | 議員ノ発言セントスルトキハ先ツ議長ト呼ヒ議長ハ其番号ヲ呼シ発言セシム | |
| 第十五条 | 議員ノ討論問答ハ議長ニ向テ之ヲ為スヘシ | |
| 第十六条 | 議員ハ会議ニ当リ充分討論ノ権ヲ有ス 然レドモ褒貶毀誉ニ渉ルヲ得ズ |
|
| 第十七条 | 議員演説中ハ議員発言スルヲ許サズ | |
| 第十八条 | 議員長発言セントシテ起立スルトキハ辯論中ノ議員ハ其辯論ヲ中止スベシ | |
| 第十九条 | 議長ハ時宜ニ依リ発言ヲ止メ又ハ中止スルコトヲ得 | |
| 第四 決議 | ||
| 第二十条 | 出席ノ議員ハ決議ノ数ニ入ラサルヲ得ス | |
| 第二十一条 | 議長ハ論辯未タ終ラザルモ論旨既ニ悉セリト認ムルトキハ其決ヲ取ルヲ得 | |
| 第二十二条 | 修正説ハ原案ニ先チ決ヲ取ル其ノ数多ナルモノハ原案ニ異ナルモノヲ先ニスヘシ | |
| 第二十三条 | 議事ノ可否ヲ決スルハ匿名投票又ハ起立ヲ用ユ | |
| 第二十四条 | 可否ノ数ハ書記之ヲ点検シ其決定ハ議長之ヲ告知スヘシ | |
| 第五 議場取締 | ||
| 第二十五条 | 議場ヲ整理スルハ議長ノ職掌トス若シ本則ニ背キ議長之ヲ制止スルモ其命ニ従ハザルモノアルトキハ議長ハ議会ノ決議ヲ得テ相当ノ処置ヲナスコトヲ得 | |
| 第二十六条 | 議事中議員ハ議長ノ許可ヲ得サレバ退場スルヲ許サズ | |
| 第二十七条 | 議事中議員私語又ハ喫烟其他議事ノ妨ケトナルノ挙動アルヲ許サズ | |
| 第二十八条 | 遅参ノ議員ハ議長ノ許可ヲ得テ着席スヘシ | |
| 第六 附則 | ||
| 第二十九条 | 議員事故アリ出席シ難キトハ開会当日午前第八時迄ニ其理由ヲ議長ニ届出ヘシ | |
| 明治弐拾弐年拾弐月弐日決議 | ||
南巨摩郡豊岡村会傍聴人取締規則
| 第一条 | 会議ヲ傍聴セントスルモノハ議場受付掛ニ其住所氏名ヲ通シ許可ヲ受ケ傍聴席ニ着クベシ 但傍聴席充満スルトキハ拒絶スルコトアルベシ |
||||||||||||
| 第二条 | 戎器兇器ヲ搬帯シ又ハ異様ノ服装ヲナシタルモノ酩酊シタリト認ムルモノハ傍聴ヲ許サズ | ||||||||||||
| 第三条 | 傍聴人ハ左ノ各項ヲ遵守スベシ
|
||||||||||||
| 第四条 | 如何ナル事由アルモ傍聴席ノ外議場ニ入ルコトヲ得ズ | ||||||||||||
| 第五条 | 傍聴ヲ禁シタルトキハ傍聴人ハ速ニ退場スベシ 大正弐年弐月拾七日村会決議 大正弐年三月弐日ヨリ施行ノ旨大正弐年参月弐日豊岡村告示第五号ヲ以テ発布 |
||||||||||||

