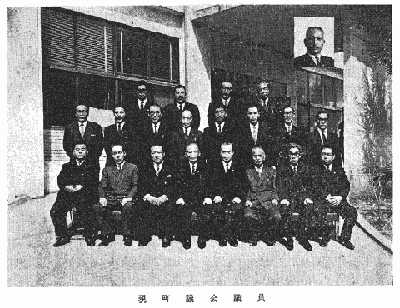|
昭和三十一年十月一日規則第一号 |
|
第一章 総則 |
| (参集) |
| 第一条 |
議員は招集の当日開会定刻前に議場に参集し、議長にその旨を通告しなければならない。 |
| (欠席の届出) |
| 第二条 |
議員が事故のため出席できないときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。 |
| (議席) |
| 第三条 |
議員の議席は、一般選挙後の最初の会議において議長が定める。
| 2、 |
一般選挙後、あらたに選挙された議員の議席は、議長が定める。 |
| 3、 |
議長は、必要があると認めるときは、議員の議席を変更することができる。 |
| 4、 |
議席には、番号及び氏名標を付ける。 |
|
| (会期) |
| 第四条 |
会期は、毎会期の初めに議長が各常任委員会の委員長の意見を聴き議会の議決で定める。
|
| (会期の延長) |
| 第五条 |
会期は、議会の議決で延長することができる。 |
| (議会の開閉) |
| 第六条 |
議会の開閉は議長が宣言する。 |
| (会議時間) |
| 第七条 |
会議時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、議会の議決があったときまたは、議長が必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
|
| (休会) |
| 第八条 |
議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会することができる。
| 2、 |
議長は、特に必要と認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。 |
| 3、 |
地方自治法第百十四条第一項の規定による請求があった場合のほか議会の議決があったときは、議長は、休会中でも会議を開かねばならない。 |
|
| (会議の開閉) |
| 第九条 |
開議、散会、延会、中止または休憩は議長が宣告する。
| 2、 |
議長が開議を宣告する前、または散会、延会、中止若しくは休憩を宣言した後は、何人も議事について発言することができない。 |
|
| (定足数に関する措置) |
| 第十条 |
議長は、開議時刻担当の時間を経ても、なお出席議員が定数に達しないときは、延会を宣告することができる。
| 2、 |
会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止しまたは議場外の議員に出席を求めることができる。 |
| 3、 |
会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩または延会を宣告する。 |
|
| (出席催告の方法) |
| 第十一条 |
地方自治法第百十三条の規定による出席催告の方法は、議員の住所に文書をもって行なう。ただし議事堂に現在する議員に対しては、口頭をもって行なう。 |
|
第二章 議案の提出及び動議 |
| (議案の提出) |
| 第十二条 |
議員が、議案を提出しようとするときは、その案を具え、理由をつけ、地方自法第百十二条第二項の規定により賛成者を必要とするときは、正規の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。 |
| (動議成立に必要な賛成者の数) |
| 第十三条 |
動議は、法律または、この規則において特別の規定がある場合を除く外三人以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。 |
| (修正の動議) |
| 第十四条 |
修正の動議は、その案を具え、あらかじめこれを議長に提出しなければならない。ただし、地方自治法第百十五条の二の規定による修正の動議には、発議者が連署しなければならない。 |
| (動議の表決順序) |
| 第十五条 |
他の事件に先だって表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし異議あるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。 |
| (事件、動議の訂正及び撤回) |
| 第十六条 |
会議の議題となった事件を訂正し、または撤回しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
| 2、 |
議員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めるときは、提出者から請求しなければならない。 |
|
|
第三章 議事日程 |
| (議事日程の作成及び配布) |
| 第十七条 |
議長は、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは議長がこれを報告して配布にかえることができる。 |
| (議事日程の変更及び追加) |
| 第十八条 |
議長が必要と認めるとき、または議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで、会議に諮り、議事日程の順序を変更し、または他の事件を追加することができる。 |
| (延会の場合の議事日程) |
| 第十九条 |
議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、またはその議事が終らなかったときは、議長は、さらに議事日程に記載しなければならない。 |
| (日程の終了及び延会) |
| 第二十条 |
議長は、議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、散会を宣告する。
| 2、 |
議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要と認めるとき、または議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮り延会することができる。 |
|
|
第四章 選挙 |
| (選挙の宣言) |
| 第二十一条 |
議会において選挙を行なうときは、議長はその旨を宣告する。 |
| (投票用紙の配布及び投票箱の点検) |
| 第二十二条 |
投票を行なうときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後配布漏れの有無を確めなければならない。
| 2、 |
議長は、議員の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。 |
|
| (投票) |
| 第二十三条 |
議員は、職員の点呼に応じて、順次投票するものとする。 |
| (投票箱の閉鎖) |
| 第二十四条 |
議長は投票が終ったときは、投票洩れの有無を確め、投票箱の閉鎖を宣告する。その宣言があった後は投票することができない。 |
| (開票及び投票の効力) |
| 第二十五条 |
議長は、開票を宣告した後、三人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
| 2、 |
前項の立会人は、議長が議員の中から議会に諮って定める。 |
| 3、 |
投票の効力は、議長が立会人の意見をきいて決定する。 |
|
| (選挙結果の報告) |
| 第二十六条 |
議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告するとともに当選人に当選の旨を告知しなければならない。 |
| (選挙関係書類の保存) |
| 第二十七条 |
議長は、投票の有効無効を区分し、当該当選人の任期間、関係書類と併せて保存しなければならない。 |
|
第五章 議事 |
| (議題の宣言) |
| 第二十八条 |
議長は、会議事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。 |
| (一括議題) |
| 第二十九条 |
議長は、必要があると認めるときは、二以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは討論を用いないで会議に諮って決める。 |
| (議案の朗読) |
| 第三十条 |
議長が必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させることができる。 |
| (議案の説明、質疑及び委員会付託) |
| 第三十一条 |
議案は会議において、発議者または提出者からその趣旨及び内容について説明をきき、議員の質疑を行なった後、議長は、所管の常任委員会に付託し、または、特に必要があると認める事件については、議会に諮り特別委員会を設け付託する。
| 2、 |
提出者の説明又は委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。 |
|
| (付託事件を議題とする時期) |
| 第三十二条 |
委員会に付託した事件は第六十二条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまって議題とする。 |
| (委員長及び少数意見者の報告) |
| 第三十三条 |
委員会の審査または調査した事件が議題となったときは、まず委員長が委員会の調査または審査の経過及び結果を報告する。
| 2、 |
委員長の報告は、議会の議決で省略することができる。 |
| 3、 |
委員長の報告には、自己の意見を加えてはならない。 |
| 4、 |
議長は、必要があると認めるときは、委員長の報告についで、少数意見者にその意見を述べさせることができる。 |
| 5、 |
前項の少数意見が数個あるときは、その報告の順序は、議長がこれを決める。 |
|
| (委員長報告等に対する質疑) |
| 第三十四条 |
議員は、委員長、少数意見の報告者に対して質疑することができる。修正案に関しては、事件または修正案の提出者及び説明のための出席者に対してもまた同様とする。 |
| (討論及び表決) |
| 第三十五条 |
議長は、質疑が終ったときは討論に付し、その終結の後表決に付する。 |
| (委員会の審査または調査期限) |
| 第三十六条 |
議会は必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査または調査につき期限をつけることができる。
| 2、 |
前項の期限内に審査または調査を終ることができないときは委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。 |
|
| (議会の継続) |
| 第三十七条 |
延会、中止または、休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。 |
|
第六章 発言 |
| (発言の場所) |
| 第三十八条 |
発言は、すべて議長の認可を得た後登壇してこれをなさなければならない。ただし、簡易な事項については議席で発言することができる。
| 2、 |
議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。 |
|
| (発言の方法) |
| 第三十九条 |
会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の認可を得て発言しなければならない。
| 2、 |
二人以上起立して、発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名して発言させる。 |
|
| (討論の方法) |
| 第四十条 |
討論においては、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
| 2、 |
議長は討論においては賛成者と反対者の数及び討論の時間を公平に定めなければならない。 |
|
| (議長の発言討論) |
| 第四十一条 |
議長が議員として発言しようとするときは、議席につき発言し、発言が終った後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは議長席に復することができない。 |
| (発言内容の制限) |
| 第四十二条 |
発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、またはその範囲を超えてはならない。
| 2、 |
議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止させることができる。 |
|
| (質疑の回数) |
| 第四十三条 |
質疑は、同一議員につき同一の議題について二回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。 |
| (発言時間の制限) |
| 第四十四条 |
議長は、必要があると認めるときは、発言につき、あらかじめ時間を制限することができる。
| 2、 |
前項の制限につき、三人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。 |
|
| (議事進行に関する発言) |
| 第四十五条 |
議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、または直ちに処理する必要があるものでなければならない。
| 2、 |
議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。 |
|
| (発言の継続) |
| 第四十六条 |
延会、中止または休憩のため発言が終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。 |
| (質疑、討論の終結) |
| 第四十七条 |
質疑または討論が終ったときは、議長は、その終結を宣言する。
| 2、 |
質疑が続出し、容易に終結しないときは、議員は質疑終結の動議を提出することができる。 |
| 3、 |
賛否の発言が終ったとき、または甲方が発言して乙方に発言の要求がないときは、議員は討論終結の動議を提出することができる。 |
| 4、 |
質疑または討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで議会に諮って決める。 |
|
| (選挙及び表決時の発言制限) |
| 第四十八条 |
選挙及び表決の宣言後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りではない。 |
| (質問) |
| 第四十九条 |
議員は、町の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。
| 2、 |
質問者は、議長が定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。 |
|
| (緊急質問等) |
| 第五十条 |
質問が緊急を要するとき、その他真に止むを得ないと認めるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て、口頭で質問することができる。
| 2、 |
前項の質問が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。 |
|
| (質問の準用) |
| 第五十一条 |
質問については、第三十八条(発言の場所)、第四十三条(質疑の回数)、第四十四条(発言時間の制限)、第四十六条(発言の継続)及び第四十七条(質疑討論の終結)の規定を準用する。 |
|
第七章 委員会 |
| (招集の手続) |
| 第五十二条 |
委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等を記載した通知を議長に提出しなければならない。 |
| (会議中の委員会禁止) |
| 第五十三条 |
委員会は、議会の会議中に開くことができない。 |
| (委員の発言) |
| 第五十四条 |
委員は議題について、委員会において自由に質疑し、意見を述べることができる。ただし、別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。 |
| (委員外議員の発言) |
| 第五十五条 |
委員会は、審査または調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求め説明または意見をきくことができる。委員でない議員から発言の申入のあったときもまた同様とする。 |
| (委員の修正案発議) |
| 第五十六条 |
委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。 |
| (連合審査会) |
| 第五十七条 |
委員会は、審査または調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。 |
| (証人出頭または記録提出の要求) |
| 第五十八条 |
委員会は、地方自治法第百条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭または記録の提出を求めようとするときは、議長に申出なければならない。 |
| (委員の派遣) |
| 第五十九条 |
委員会が、審査または調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。 |
| (閉会中の継続審査) |
| 第六十条 |
委員会が、閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めるときは、その理由をつけ、委員長から議長に申出なければならない。 |
| (少数意見の留保) |
| 第六十一条 |
委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員一人以上の賛成があるものは、少数意見として、留保することができる。 |
| (委員会報告書) |
| 第六十二条 |
委員会が事件の調査または審査を終ったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。 |
|
第八章 表決 |
| (表決問題の宣告) |
| 第六十三条 |
議長は、表決をとろうとするときは、表決に対する問題を会議に宣告する。 |
| (議員の表決権) |
| 第六十四条 |
表決の宣言のとき、議場にいない議員は、表決に加わることができない。 |
| (条件の禁止) |
| 第六十五条 |
表決には条件を付することができない。 |
| (起立による表決) |
| 第六十六条 |
議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定して、可否の結果を宣言する。
| 2、 |
議長が起立者の多少を認定し難いときまたは議長の宣言に対し、三人以上から異議があるときは、議長は、投票で表決をとらなければならない。 |
|
| (記名または無記名投票の決定) |
| 第六十七条 |
議長が必要と認めるとき、または、三人以上から要求があるときは記名または無記名の投票による表決をとる。
| 2、 |
前項の場合において、同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は前条第一項の例により、いずれの方法によるかを決める。 |
|
| (記名及び無記名投票による表決) |
| 第六十八条 |
投票を行なう場合においては、問題を可とする議員は賛成、問題を否とする議員は反対の旨を投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。 |
| (投票の効力) |
| 第六十九条 |
無記名投票による表決において、賛否が明らかでない投票及び他事を記載した投票は否とみなす。 |
| (選挙規定の準用) |
| 第七十条 |
記名投票、または無記名投票を行なう場合には、第二十一条(選挙の宣告)、第二十二条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)、第二十三条(投票)、第二十四条(投票箱の閉鎖)、第二十五条(開票及び投票の効力)、第二十六条(選挙結果の報告)及び第二十七条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。 |
| (表決の更正) |
| 第七十一条 |
議員は、自己の表決の更正を求めることができない。 |
| (簡易表決) |
| 第七十二条 |
議長は、問題について、異議の有無を、会議に諮ることができる。
| 2、 |
異議がないと認めるときは、議長は、直ちに可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、三人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。 |
|
| (表決の順序) |
| 第七十三条 |
議員の提出した修正案は、委員会の提出した修正案より先に、表決しなければならない。
| 2、 |
同一議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は原案に最も遠いものから先に表決する。ただし、表決の順序について異議があるときは、議長は討論を用いないで、会議に諮って決める。 |
| 3、 |
修正案がすべて否定されたときは、原案について表決をとる。 |
|
|
第九章 請願 |
| (請願書の記載事項) |
| 第七十四条 |
請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)を記載し、捺印しなければならない。
| 2、 |
請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名捺印しなければならない。 |
| 3、 |
請願書の提出は平穏になさなければならない。 |
|
| (請願の委員会付託) |
| 第七十五条 |
議長は、請願を受理したときは、議会に諮り、所管の常任委員会または特別委員会に付託する。ただし、委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。
| 2、 |
請願の内容が二以上の委員会の所管に属する場合は、二以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。 |
|
| (委員会の審査報告) |
| 第七十六条 |
委員会は、請願について審査の結果を左の区分により、意見を付け議会に報告しなければならない。
一、採択すべきもの
二、採択すべきでないもの
| 2、 |
採択すべきものとされた請願で執行機関等に送付することを適当と認めるもの、並びに処理の経過及びてんまつの報告を請求することを適当とするものについては、その旨を付記しなければならない。 |
|
| (当請願の送付及び処理てんまつ報告の請求等) |
| 第七十七条 |
議長は、議会の採択した請願で、執行機関等に送付しなければならないものは、これに送付し、その処理てんまつの報告をしようと決したものについてはこれを請求しなければならない。 |
| (陳情書の処理) |
| 第七十八条 |
議長は、陳情書またはこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは請願の例により処理するものとする。 |
|
第十章 秘密会 |
| (指定者以外の退場) |
| 第七十九条 |
秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
| 2、 |
委員会において、秘密会を開くときは、前項の例による。 |
|
| (秘密の保持) |
| 第八十条 |
秘密会の議事の記録は公表しない。
| 2、 |
秘密会の議事は、何人も秘密性の継続するに限り、他に漏らしてはならない。 |
|
|
第十一章 辞職 |
| (議長及び副議長の辞職) |
| 第八十一条 |
議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
| 2、 |
前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮って許否を決める。 |
| 3、 |
閉会中に、副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の会議に報告しなければならない。 |
|
| (議員の辞職) |
| 第八十二条 |
議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
| 2、 |
前条第二項及び第三項の規定は、議員の辞職についても準用する。 |
|
|
第十二章 規律 |
| (品位の尊重) |
| 第八十三条 |
議員は、議会の品位を重んじなければならない。 |
| (服装) |
| 第八十四条 |
議場に入る者は見苦しくない服装をしなければならない。 |
| (議事妨害の禁止) |
| 第八十五条 |
会議中みだりに発言し、または騒ぎ、議事の妨害となる言動をしてはならない。 |
| (議員の離席) |
| 第八十六条 |
議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。 |
| (禁煙) |
| 第八十七条 |
議場においては、喫煙することができない。 |
| (新聞等の閲読禁止) |
| 第八十八条 |
何人も、参考のためにするものの外、会議中、新聞紙及び書籍類の閲読をしてはならない。 |
| (許可のない登壇禁止) |
| 第八十九条 |
何人も、議長の許可がなければ、演壇に登ってはならない。 |
| (議長の秩序保持権) |
| 第九十条 |
すべて規律に関する事項は、議長が決める。ただし、議長が必要と認めるときは討論を用いないで、会議に諮って決めることができる。 |
|
第十三章 懲罰 |
| (懲罰の動議の提出) |
| 第九十一条 |
懲罰の動議は、その案を具え、理由をつけ、議長に提出しなければならない。
| 2、 |
懲罰動議は、懲罰事犯のあった翌日までに提出しなければならない。ただし、第八十条(秘密の保持)第二項の規定の違反に係るものについてはこの限りでない。 |
|
| (委員会付託の可否) |
| 第九十二条 |
懲罰事犯の委員会付託の可否は、討論を用いないで決めなければならない。 |
| (戒告または陳謝の案文) |
| 第九十三条 |
公開の議場における戒告または陳謝は、議会の定める案文によって行なうものとする。 |
| (出席停止の期間) |
| 第九十四条 |
出席停止は、十日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合またはすでに出席を停止された者について、その停止期間内にさらに懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。 |
| (出席停止期間中出席したときの措置) |
| 第九十五条 |
出席を停止された議員が、その期間内に会議または委員会に出席したときは、議長または委員長は、直ちに退去を命じなければならない。 |
| (除名が成立しないときの措置) |
| 第九十六条 |
除名についての議員の三分の二以上が出席し、その四分の三以上の賛成が得られなかった場合は、他の懲罰を科することができる。 |
| (懲罰の宣告) |
| 第九十七条 |
議会が、懲罰を議決したときは、議長は、公開の議場において宣告する。 |
|
第十四章 会議録 |
| (会議録の記載事項) |
| 第九十八条 |
会議録に記載する事項は次のとおりとする。
| 1、 |
開会、閉会に関する事項及びその年月日時 |
| 2、 |
開議、散会、延会、中止及び休憩の日時 |
| 3、 |
出席及び欠席議員の氏名 |
| 4、 |
職務のため議場に出席した書記の氏名 |
| 5、 |
説明のため出席した者の職氏名 |
| 6、 |
議事日程 |
| 7、 |
議長の諸報告 |
| 8、 |
議員の異動並びに議席の指定及び変更 |
| 9、 |
委員会報告書及び小数意見報告書 |
| 10、 |
会議に付した事件 |
|
議案の提出、撤回及び訂正に関する事項 |
| 12、 |
選挙のてんまつ |
| 13、 |
議事のてんまつ |
| 14、 |
記名投票における賛否の氏名 |
| 15、 |
その他、議長または議会において必要と認めた事項 |
|
| (会議録の署名議員) |
| 第九十九条 |
会議録に署名すべき議員数は三人とし、議長が会議において指名する。 |
|
補則 |
| (会議規則の疑義) |
| 第百条 |
すべての会議規則の疑義は、議長が決める。ただし、疑義があるときは、議会に諮って決める。 |
|
附則 |
| (施行期日) |
|
|
| (従来の会議規則の廃止) |
| 2、 |
身延町議会会議規則(昭和三十年三月一日身延町規則第二号)は廃止する。 |
|