三、合併身延町の議会
67名のマンモス議会合併条件の一つとして町村合併促進法第9条第1項の規定により、現に関係町村の議会の議員である者は引続き新町の議会の議員として昭和30年8月31日まで在任するものとすることが協定されたので、ここに自治の歴史にも珍しい定員67名(定数70名のところ欠員3名)のマンモス議会が誕生することとなった。
第1回の議会は2月21日に身延中学校の2階教室を借用して開き議長には望月房則(身延)、副議長に井上小一郎(下山)が、投票でそれぞれ当選した。常任委員会は総務・文教・失対・土木・厚生・経済・観光の七委員会がおかれ、事務局は専任制でなく総務課長田京駒男が議会事務を担当、池上正、井水五雄、石川金雄の各職員が書記に当たった。
議場とはいっても何分にも中学校の教室のことで、机も椅子も大人の尻には小さすぎて疲れも早く、老体の議員などは大分苦労をしたので、旅館から座布団を借りて来て「議席」にしいてもらうという珍風景もあったが、このマンモス議会の議決により、新町建設の基礎をなす多くの案件が生まれるのである。
すなわち監査委員、公平委員等、法に基づく行政委員の選任、目前に迫った町長選挙の公営立会演説会条例、各財産区管理会条例、職員給与条例、公民館条例、29年度の追加更正並びに30年度の本予算等である。
荒れ模様だった新町議会
3月26日の初代町長選挙で佐野祥盛が他の3候補(藤田岡波、望月善長、鴨狩庸雄)と争って町長の座についたあと、8月27日、新町第1回の町議会議員選挙が執行され、新たに26名の町議会議員が誕生した。
この選挙は選挙区条例によって身延9名・大河内8名・下山4名・豊岡5名が選出されたのである。
特例によるマンモス議会も合併直後のことで地域的感情も強く、議員間の相互理解、融和が薄く、かなり感情的な対立や攻撃、とげとげしい空気が強かったが、選挙後の議会も議長選挙をめぐる2派の対立が露骨に火花を散らし、9月8日の初臨時議会では議員間のトラブルから暴行事件をおこし仮議長望月宗三郎が議場不穏を理由に散会を宣し、9月20日まで延会して漸く議長佐野為雄(下山)、副議長伊藤喜則(大河内)を投票で選出するというような状態であった。
10月3日の議会でも議長選に敗れた少数派議員が席をけって退場し、半分空席となった議席で委員会構成が議決されたが、完全な構成が出来ず一部を後日に持越すというような、新町発足にふさわしくない事態が見られたことは残念であった。
昭和30年10月の議会常任委員会構成 (◎委員長 ○副委員長)
| 総務常任委員会 | ||||||||
| ◎ | 小笠原実 | ○ | 藤田金次郎 | 川口久広 | 斉藤一郎 | |||
| 鴨狩富治 | 深沢忠雄 | 佐野正久 | ||||||
| 土木常任委員会 | ||||||||
| ◎ | 小笠原清保 | ○ | 川口久広 | 鈴木正巳 | 小笠原実 | |||
| 佐野正久 | 藤田国治 | 望月平蔵 | ||||||
| 文教常任委員会 | ||||||||
| ◎ | 長谷川寛慶 | ○ | 鈴木正巳 | 一宮市松 | 遠藤泰明 | |||
| 鴨狩富治 | 手塚喜義 | |||||||
| 失業対策常任委員会 | ||||||||
| ◎ | 市川正美 | ○ | 斉藤一郎 | 藤田金次郎 | 久保光明 | |||
| 松木栄 | 佐野里見 | 佐野直三 | ||||||
| 観光常任委員会 | ||||||||
| ◎ | 一宮市松 | ○ | 赤塚一一 | 小笠原清保 | 滝川隆治 | |||
| 望月宗三郎 | 藤田国治 | 手塚喜義 | ||||||
| 経済常任委員会 | ||||||||
| ◎ | 遠藤泰明 | ○ | 滝川隆治 | 赤塚一一 | 望月宗三郎 | |||
| 久保光明 | 藤田喜太郎 | 佐野直三 | ||||||
| 厚生常任委員会 | ||||||||
| ◎ | 藤田喜太郎 | ○ | 望月平蔵 | 深沢忠雄 | 長谷川寛慶 | |||
| 松木栄 | 市川正美 | 深沢富治 | ||||||
しかし、学校運営に支障があり、また他に適当な議場がないということで、32年12月に新庁舎の議場に移るまで引き続き大河内支所の議場が使われた。
32年の2月29日から開かれた議会は自然休会をはさんで延々5月12日まで75日間開会しっ放しというレコードを作った。
結局流産となった助役収入役選任問題をはじめ、職員定数や役場機構の問題などを織込んで、特別委員会が設けられ会期中に他町村を視察するなどのこともあり、特に新庁舎建築問題はこの議会をスタートに、建設財源、本山よりの寄付を500万円獲得する件、工事のおくれ、敷地問題などでこれからほゞ2年近く議会論議の中心問題となっている。
注(庁舎建設問題は第二章第六節参照)
31年9月の議会では、6月の地方自治法改正に伴ない、町村議会は年4回以下の定例会、常任委員会は4と改められ、これを定める条例や会議規則も決定され、総務・土木・厚生・産業経済の4常任委員会の構成も改選により改められた。
昭和31年9月の常任委員会役員構成 (◎委員長 ○副委員長)
| 総務常任委員会 | ||||||||
| ◎ | 小笠原実 | ○ | 深沢忠雄 | |||||
| 土木常任委員会 | ||||||||
| ◎ | 藤田喜太郎 | ○ | 赤塚一一 | |||||
| 産業経済常任委員会 | ||||||||
| ◎ | 望月平蔵 | ○ | 市川正美 | |||||
| 厚生常任委員会 | ||||||||
| ◎ | 松木栄 | ○ | 藤田国治 | |||||
33年8月には自治法の改正により町村議会にも事務局が設置されることになって身延町議会も正式に8月23日の議会で事務局を設置し、若林総務課長が兼任局長となった。
大選挙区制へのうごき
34年6月、町内の革新・労働団体の統一組織である身延町民主団体協議会(代表者望月宗雄)は地方自治法第74条の規定に基く選挙区条例の廃止すなわち全町一区大選挙区制の実行を求めて、法定数以上の署名をあつめ町選挙管理委員会(望月望委員長)に提出、手続の欠陥を理由にこの直接請求は却下されたが、第2代町長河井直一は大選挙区は合併の精神から当然であり町民の声であるとしてこの請求に同意し、自ら当局提案として選挙区条例の廃止を6月議会に提案したのであるが、改選を目前にした議会は時期尚早の名のもとにこれを否決し、大選挙区制は陽の目を見ることができなかった。しかしながら、この一石を第1歩として大選挙区制は、いつかは来るべき課題として議会の宿題になり、38年の佐野町長による再提案—廃案を経て、39年、40年にわたる深沢徹議員提案—否決、さらに42年同議員の意見書可決—条例可決と、4度目の正直で実現にこぎつけたのである。
34年8月第2回の町議選が行なわれ、今度は無投票で議長に伊藤喜則、副議長に佐野里見が当選委員会役員構成も下の通り行なわれた。
| 昭和34年9月 | |||
| 総務常任委員長 | 川口久広 | ||
| 副委員長 | 佐野治郎 | ||
| 厚生常任委員 | 一宮市松 | ||
| 副委員長 | 佐野正久 | ||
| 産業経済委員長 | 滝川隆治 | ||
| 副委員長 | 藤田金次郎 | ||
| 土木常任委員長 | 斉藤一郎 | ||
| 副委員長 | 網野正一 | ||
河井町政4カ年はこの大災害の復旧の歴史であったといっても過言ではない。
この年の10月議会では前議長の佐野為雄が現職議員から河井町長の助役に選任され、次点繰上げで下山地区から佐野民治(共産党)が当選したがわずか1年で選挙違反で失格となった。
昭和34年から35年にかけて議会に税制調査特別委員会(望月房則委員長)、職員定数・給与・職務分掌特別委員会(網野正一委員長)が作られ、それぞれ本山の木材引取税追加徴収、職員の削減、採用試験の実施、機構改革を当局に勧告している。また上水道の計画を調査する特別委員会も作られた。
36年9月には正副議長の辞任による改選があり、斎藤一郎(身延)が議長に、近藤保(下山)が副議長に当選、常任委員会も改組されたほか、内規で議会運営委員会が作られ、松木栄が委員長に就任した。
昭和36年9月委員会役員構成
| 総務常任委員長 | 片田豊 | ||
| 副委員長 | 依田熹一 | ||
| 厚生常任委員長 | 藤田金次郎 | ||
| 副委員長 | 長谷川一 | ||
| 土木常任委員長 | 網野正一 | ||
| 副委員長 | 近藤宇佐美 | ||
| 産業経済常任委員長 | 柿島武文 | ||
| 副委員長 | 鴨狩広 |
この年、下山簡易水道調査特別委員会・高校東側道路特別委員会・支所廃止特別委員会の3特別委員会が作られているが、支所廃止特別委員会は部落懇談会を各地で開いた後37年3月議会に、支所を廃し、事務を本庁に集中、合理化する一方、住民の不便をなくするため、地区公民館の整備、役場との連絡態勢の強化、さらに今後の課題として早急に電話の町内一本化をはかって4町一本化の実を挙げるよう報告し、町長はその趣旨を尊重して8月1日より支所廃止に踏み切ったのである。
しかし、明治初年以来各地区のセンターであった役場を失った住民にとって、道路整備の不充分さや、距離的な不便さもあって支所廃止に対する不満は強く、これ以後議会でもたびたび論議の対象になっている。
選挙公報の発行
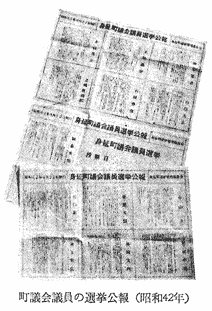 |
38年2月、無投票で助役から第3代町長となった佐野為雄は6月議会に町議選で選挙公報を発行するという県下でも例の少ない条例案と、全町一区大選挙区制の条例案を提出、議会は大選挙区条例を継続審査し任期切れ廃案という形で葬ったが、公報発行条例は可決、選挙公営への一歩を踏み出したのである。
8月20日執行された選挙には各選挙区ごとに候補者の公約や主張をかかげた公報が全戸に配付され住民にも好評であった。
9月に開かれた初の議会では議長に柿島武文(豊岡)、副議長に川口久広(下山)が選任され、それまであった議会運営委員会は廃止された。
昭和38年9月議会委員会役員構成は次の通りである。
| 総務常任委員長 | 網野正一 | ||
| 副委員長 | 鮎川太郎 | ||
| 厚生常任委員長 | 一宮市松 | ||
| 副委員長 | 志村国為 | ||
| 産業経済常任委員長 | 近藤宇佐美 | ||
| 副委員長 | 深沢徹 | ||
| 土木常任委員長 | 滝川隆治 | ||
| 副委員長 | 平田一三 | ||
| 昭和三十九年九月改選 | |||
| 議長 | 柿島武文 | ||
| 副議長 | 一宮市松 | ||
| 総務常任委員長 | 大久保豊繁 | ||
| 副委員長 | 坂口起一 | ||
| 厚生常任委員長 | 平田一三 | ||
| 副委員長 | 下里是忠 | ||
| 産業経済常任委員長 | 望月脩二 | ||
| 副委員長 | 鍋島良知 | ||
| 土木常任委員長 | 近藤保 | ||
| 副委員長 | 遠藤敏雄 | ||
中学統合への動き
昭和34年頃から議会内でも中学統合の意見が出るようになったが、38年改選後の9月議会で鍋島議員外の議員提案により中学統合調査特別委員会が設置され(藤田喜太郎委員長)、10名の特別委員が39年3月議会まで、県内外の先進地を視察、研究した結果、町内四中学統合の意見書を可決し、佐野町長はこれを受けて議員全員を含む統合促進協議会を結成、住民の意志統一に取り組むことになる。 中央道北回り反対陳情
田中清一の構想により建設省が立案した国土縦貫中央高速道路は、当初の法律では大月より身延付近を経て赤石山系を貫き、静岡県井川村付近を通って愛知県小牧に達し、名神高速道路に連絡することになっていたが、その後、経済効果、工事の技術的困難等を理由に路線を変更し、甲府盆地を経て長野県諏訪回りに改めようとする動きが青木一男参議院議員らによって促進され、天野知事もこれに同調、身延町はトンビに油揚をさらわれそうな形勢となって来た。34年12月町議会で北回り反対の決議が行なわれたが、38年5月には東京虎ノ門会館において中央道建設推進委員会が開かれ、佐野身延町長一人の反対で北回りが可決され、39年4月には建設省の最終決定と国会での法改正を残すのみの状態となった。こゝにおいて町議会は39年4月6日、全員北回り反対の白ダスキをかけて町長らとともに上京、県選出代議士をはじめ、衆参国会議員全員を個別訪問して強く反対を訴えたのである。
このような思い切った反対運動も遂に衆寡敵せず、6月12日遂に法改正による北回り路線が決定し身延町は完全に置き去りにされ、以後その代償措置を強く国に要望することとなった。
議会広報の発刊
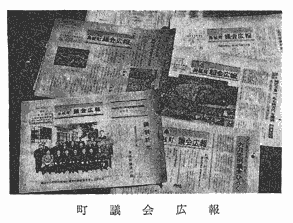 |
編集の内容も当初の簡略なものから逐次充実され、各議員の質問と当局の答弁なども細かく掲載されるようになり、県下、否全国にも例の少ない広報活動として既に四年以上発行されていることは誇ってよいことであろう。
毎年開催される全国広報研究大会にも代表を送り、議会広報の充実を提唱している。
| (編集委員) | |||
| ○ | 昭和39年12月—昭和40年12月 | ||
| 委員長 | 鍋島良知、網野正一、大久保豊繁、鮎川太郎、望月脩二、柿島武文、一宮市松 | ||
| ○ | 昭和40年12月—昭和42年9月 | ||
| 委員長 | 鍋島良知、柿島武文、網野正一、大久保豊繁、坂口起一、市川良政、滝川隆治、深沢徹 | ||
| ○ | 昭和42年9月より | ||
| 委員長 | 鍋島良知、副委員長 土橋隆四郎、深沢徹、久保幸男、大野義学、鴨狩富治、加藤市郎 | ||
| ○ | 昭和44年9月より | ||
| 委員長 | 鍋島良知、副委員長 深沢徹、土橋隆四郎、久保幸男、堀一勇、鮎川太郎、遠藤泰明 | ||
昭和40年9月の委員会役員構成
| 総務常任委員長 | 坂口起一 | ||
| 副委員長 | 佐野長治 | ||
| 厚生常任委員長 | 鍋島良知 | ||
| 副委員長 | 遠藤敏雄 | ||
| 産業経済常任委員長 | 志村国為 | ||
| 副委員長 | 加藤市郎 | ||
| 土木常任委員長 | 下里是忠 | ||
| 副委員長 | 大野義学 |
温泉開発の促進
この議会で身延山西谷に温泉開発を促進すべく、温泉調査特別委員会(平田一三委員長)が設けられ本山、地元旅館代表等と数次にわたる協議の結果、本山が掘削し、一般にも分湯するとの協定に達したが、この協定は遂に実行されないまま今日に及んでいる。昭和41年9月24日、台風26号は本町を直撃して東進、足和田村精進湖畔の大惨事を引きおこしたが本町内にも34年の7号台風災害を上回る十数億円の大被害をもたらし、急拠9月議会を災害対策議会として全員で災害地の調査を行ない、当局とともに対策委員会を構成して救護・復旧の活動に奔走したのである。
昭和42年3月議会では、角打水道消火栓ホースの品質不良事件をとり上げ、町議会初の自治法100条調査権を発動、納入業者をはじめ関係職員を厚生常任委員会に喚問して職権による調査を行ない、補償と更新を勧告した。
初の全町一区選挙
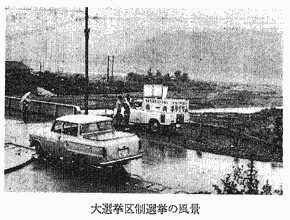 |
初の全町一区制選挙は8月の炎天下25名の立候補者によって激しく展開された。もちろん初めての制度で、慣習的な部落推薦も強く残ってはいたが、ほぼ全員が宣伝カーを使って街頭演説に全町をかけめぐるなど、住民の関心も大いに盛り上り、広い視野に立った議会への脱皮の第一歩として大きな意義を持った選挙であった。
結果は新人の大量進出で平均年齢も大幅に若返り、昭和、大正年代の議員が22名中10名を占めたのも大きな特徴であった。
改選町議会は議長に鴨狩富治(豊岡)、副議長に加藤市郎(身延)をそれぞれ投票で選び昭和42年9月議会常任委員会を次の通り構成した。
| 総務常任委員会委員長 | 古屋慶信 | ||
| 副委員長 | 高村大衛 | ||
| 厚生常任委員会委員長 | 堀一勇 | ||
| 副委員長 | 深沢徹 | ||
| 土木常任委員会委員長 | 平田一三 | ||
| 副委員長 | 池上芳広 | ||
| 産業経済常任委員会委員長 | 若林孝義 | ||
| 副委員長 | 熊谷儀信 |
最近の議会の状況
以来今日まで、町議会は常に活発に当局と協力し、またこれを批判、鞭撻(べんたつ)して町民の期待にこたえつつ活動していることは衆目の認めるところである。44年2月には全国町村議会議長会より優良議会として表彰を受けている。
44年1月現在町議会に設けられている特別委員会は下の通りである。
| (消防近代化研究特別委員会) | |||
| 委員長 | 熊谷儀信 副委員長 池上芳広 | ||
| 委員 | 深沢徹、川口久広、久保幸男、鴨狩富治、加藤市郎 | ||
| (交通対策特別委員会) | |||
| 委員長 | 遠藤泰明 副委員長 中村英文 | ||
| 委員 | 鍋島良知、高村大衛、坂口起一、鴨狩富治、加藤市郎 | ||
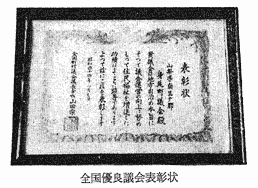 |
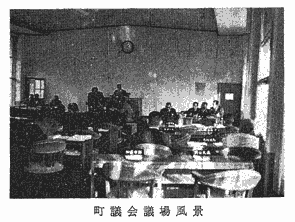 |
| (昭和42年度決算審査特別委員会) | ||
| 委員長 | 鍋島良知 副委員長 深沢徹 | |
| 委員 | 藤田文内、堀一勇、高村大衛、久保幸男、熊谷儀信、池上芳広、鴨狩富治、加藤市郎 | |
| (昭和43年度決算審査特別委員会) | ||
| 委員長 | 堀一勇 副委員長 藤田文内 | |
| 委員 | 加藤市郎、久保幸男、熊谷儀信、望月宗雄、土橋隆四郎、若林孝義、鮎川太郎、遠藤泰明 | |
| 委員長 | 池上芳広 副委員長 平田一三 |
町議会議員の報酬は自治法により町条例で定められることになっている。
戦前、町村制時代には町長、助役、議員は名誉職とされ、議員には報酬はなく名目的な費用弁償(明治22年大河内村村会議員年額1人90銭、大正3年同2円、昭和6年身延町会議員年額15円、昭和14年同20円)が支給されていたにすぎないが、自治法施行以後、社会状勢の変化、住民要求の増大と多様化に伴い逐次議員の公務についやす時間も増加し、町村会議員といえども常勤と非常勤の中間的な実態になって来たのである。
一方戦後の一貫した物価の上昇という事もあり、議員報酬も、三役、行政委員等の報酬とともに2、3年ごとに改正されて来たのである。
合併後の状況を下に表で示すことにしよう。
身延町議会議員報酬の推移(月額)
| 議長 | 副議長 | 議員 | |
| 昭和30年4月 | 1,667円 | 1,250円 | 1,000円 |
| 昭和31年10月 | 2,500円 | 1,875円 | 1,500円 |
| 昭和32年4月 | 3,500円 | 2,625円 | 2,100円 |
| 昭和33年12月 | 6,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
| 昭和35年10月 | 8,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
| 昭和36年10月 | 10,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
| 昭和39年9月 | 12,000円 | 10,000円 | 8,500円 |
| 昭和42年4月 | 15,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
報酬額の決定方式というものは特になく、町村の財政状態、議員の勤務態容、住民感情、一般職給与との関係、議員の意識等々種々雑多な要素から綜合的に決定されるのが実情で、類似町村の平均、全国平均、県平均などが一つの指標ともなっているが、参考に昭和43年度の全国、県、郡下の人口段階別報酬額の中における本町の位置を示しておこう。
議員報酬(昭和42年7月1日現在)
| 項目 | 区別 | 職名 | 報酬額 | 職名 | 報酬額 |
| 全国平均 | 単純平均 | 議長 副議長 議員 |
17,513円 14,634円 12,982円 |
(参考) 町長 助役 収入役 |
82,573円 66,429円 61,873円 |
| 人口1万 〜2万の 町村平均 |
議長 副議長 議員 |
18,809円 15,831円 14,011円 |
|||
| 山梨県平均 | 単純平均 | 議長 副議長 議員 |
13,482円 10,989円 9,286円 |
町長 助役 収入役 |
72,254円 50,703円 58,367円 |
| 人口1万 〜2万の 町村平均 (県内一三 ヶ町村) |
議長 副議長 議員 |
15,538円 11,000円 11,000円 |
町長 助役 収入役 |
83,307円 67,727円 (11ヶ町村) 65,537円 |
|
| 南巨摩郡平均 | 単純平均 | 議長 副議長 議員 |
14,286円 11,858円 10,072円 |
町長 助役 収入役 |
79,000円 65,615円 61,895円 |
なお町村によっては定額報酬の外に本会議委員会出勤ごとに何円という風な費用弁償を支給しているところもあり、実際の支給額は多少変っている。
本町には出勤日毎の費用弁償はない。
また、昭和39年、全国的な報酬お手盛り引上げムードをひきしめる意味において自治省は第三者による特別職の報酬審議会を設けるよう通達し、全国的にも県下でもかなり審議会が作られたが、本町では審議会を作っても単なる形式にすぎず、かえって議員の責任と良識による判断を回避するかくれみのにもなりかねないとの判断で、審議会は設置していない。
特別職給与、報酬の基準設定について
昭和44年3月の定例町議会において、町三役、条例にもとづく各種行政委員、および議会議員の給与および報酬の改正が議題となった。折から全国的、全県的に物価の高騰や一般職員の給与引き上げにともなってこれら特別職の給与、報酬をかなり大幅にアップする傾向があり、一部極端なもので言論機関や世論の「お手盛り」批判を浴びた例もあった。
身延町の議会では、特別職の活動を保障するため妥当な改正を行なう必要は認めながらも、何の合理的基準もないお手盛りはよくないとの立場から、この問題についての特別委員会を設置して調査研究した結果、一応の基準を決定、議会の議決により意見書として町長に送付した。町当局もこの基準を妥当なものとして承認したので、本町においては44年度以降この基準にもとづいて給与、報酬額が決定されることになろう。
基準についての意見書および特別委員名は次のとおりである。
なお、この特別委員会は引きつづき設置されて、町役場の機構改革その他の行政合理化について研究することになっている。
身延町の特別職給与、報酬基準設定についての意見書
町議会は、町の特別職、特に町長、助役、収入役および議会議員の給与、報酬額を決定するに当っては、全国的な事例、県下類似町村との比較、本町の財政事情、三役及び議員活動の実態、住民世論など種々の要素を配慮し適正に措置すべきであると考えるが、何等の合理的基準も設けることなく随時改正することは好ましくないので、ここに一応の算定基準を設定し今後はこれに基づいて決定するように要望する。| 一、 | 町長はその責任の重さと勤務の実態から見て一般職より遙かに上回るが選挙による特別職という奉仕的職分とのあり方、および財政事情等を考慮して、町の課長給平均額の一、五倍を適当と認める。 | |
| 二、 | 助役収入役については町長の補助機関としてその比重は町長に次ぐものであり、助役は町長の八五%、収入役は八二%の額が妥当である。 | |
| 三、 | 議員は非常勤をたてまえとして居り、実態はますます半常勤に近いような状況におかれつつあるが、財政事情をも考慮して、議員の本会議、委員会出席日数を本町の実情に基づき町長と比較すると、おおむね一五%程度になるので、その他の活動は一応算定より除き、町長給与額の一五%を議員報酬の額とする。 | |
| 四、 | 議長及副議長はそれぞれその責任の度合、出勤日数を一般議員と比較した場合議長は町長の二二%、副議長は一七%が妥当である。 | |
| 五、 | 給与の改正は一般職が上昇する都度行なうのでなく二年毎にその時点で改正すべきである。 | |
| 昭和四十四年三月二十八日 | ||
| 身延町議会 |
給与機構等調査特別委員会
| (43年) | (44年) | ||||
| 委員長 | 若林孝義 | 委員長 | 高村大衛 | ||
| 副委員長 | 高村大衛 | 副委員長 | 平田一三 | ||
| 委員 | 古屋慶信 | 委員 | 深沢徹 | ||
| 委員 | 藤田文内 | 委員 | 中村英文 | ||
| 委員 | 中村英文 | 委員 | 熊谷儀信 | ||
| 委員 | 加藤市郎 | 委員 | 鍋島良知 | ||
| 委員 | 堀一勇 | 委員 | 土橋隆四郎 | ||
| 委員 | 深沢徹 | 委員 | 望月宗雄 | ||
| 委員 | 熊谷儀信 | 委員 | 藤田文内 | ||
| 委員 | 平田一三 | 委員 | 久保幸男 | ||
| 委員 | 池上芳広 | 委員 | 堀一勇 | ||
世界連邦都市宣言を満場一致で決議
身延町議会は昭和44年6月の定例町議会で、「世界連邦促進宗教者大会」について全面協力を議決したが、7月26日の臨時町会議で副議長加藤市郎の提案により21名の全議員が満場一致で「世界連邦都市宣言」を決議し、県下で初の世界連邦都市となった。宣言の全文は下記のとおりである。
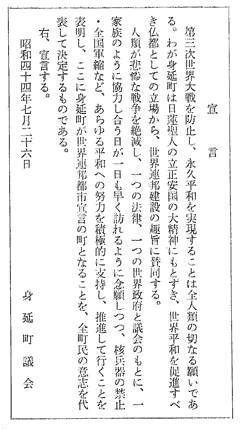 |
世界連邦都市宣言についての決議
身延町議会は来る8月21日・22日の両日、身延山において開催される世界連邦平和促進宗教者大会の崇高なる趣旨に全面的に賛成しこれに協力することを先に決議したが、これを機会に、全国の多くの都府県・市町村がすでに決議している世界連邦都市宣言を行ない、いっそう強く平和への理想をかかげ、戦争のない社会の実現に向って努力することを決議するものである。昭和44年9月に改選された現在の町議会役員構成は左の通りである。
| 議長 | 鮎川太郎 | ||||
| 副議長 | 遠藤泰明 | ||||
| 総務常任委員会 | 土木常任委員会 | ||||
| 委員長 | 深沢徹 | 委員長 | 鍋島良知 | ||
| 副委員長 | 土橋隆四郎 | 副委員長 | 久保幸男 | ||
| 委員 | 堀一勇 | 委員 | 鴨狩富治 | ||
| 平田一三 | 若林孝義 | ||||
| 高村大衛 | 池上芳広 | ||||
| 厚生常任委員会 | 産業経済常任委員会 | ||||
| 委員長 | 中村英文 | 委員長 | 熊谷儀信 | ||
| 副委員長 | 望月宗雄 | 副委員長 | 藤田文内 | ||
| 委員 | 加藤市郎 | 委員 | 大野義学 | ||
| 古屋慶信 | 川口久広 | ||||
| 坂口起一 | 遠藤泰明 | ||||
| 議会選出監査委員 | |||||
| 大野義学 | |||||
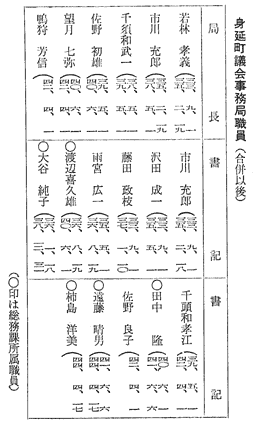 |

