二、わが国の選挙制度の沿革
概説わが国における近代的な選挙制度は、明治維新の際「万機公論に決すべし」という五箇条の御誓文の趣旨にのっとり、明治11年(1878年)三新法(明治11年に定められた郡区町村編成法、府県会規則および地方税規則)の公布、明治22年(1889)に憲法を発布する旨の明治14年の大詔を経て、憲法の施行に備えて制定された明治22年の衆議院議員選挙法、ならびに明治21年の市制および町村制、明治23年の府県制および郡制によってはじめて確立されたものである。そうしてここに国の選挙制度と地方公共団体の選挙制度とがそれぞれ法律および体系を異にして生れたのである。その後国と地方公共団体の選挙制度は幾多の変遷を経たが、第二次世界大戦後、政治の民主化にともない男女同権の完全な普通選挙の実施、全国会議員の直接選挙、都道府県知事、市町村長の公選をはじめとして、抜本的な選挙制度の改正が行なわれた。昭和25年には公職選挙法の制定にともない、国会議員・地方議会の議員および長等の選挙について1つの法律にまとめられた。その後、衆議院議員の定数の是正をはじめとして若干の手直しが行なわれて現行制度に至っている。以下現行制度に至るまでの国会議員の選挙制度ならびに地方公共団体の議会の議員および長の選挙制度について沿革を概説しよう。
(一)衆議院議員の選挙制度の変遷
衆議院議員の選挙を規定する衆議院議員選挙法は、さきに述べたようにはじめて明治22年(1889)に制定されてから、同33年・大正8年(1919)・同14年、昭和20年(1945)および同22年に重要な改正が加えられた。
改正の要点を述べると
○明治22年法律第22号
選挙権及び被選挙権…きわめて厳重な制限選挙制をとっている。
選挙権は年齢25歳以上の日本臣民である男子で、1年以上直接国税15円以上(または3年以上所得税15円以上)を納め、かつ1年以上その府県に本籍をもち、居住している者でなければならなかった。
被選挙権は年齢30歳以上で住所の要件を必要としないほか、納税の要件は選挙権に同じである。議員定数300人、選挙区1区1人の小選挙区制を原則とし、選挙区は郡および区の区域によることとされた(山梨県は定数3人、3区である。)しかし例外的に1選挙区から2人選挙するところもあって、このような場合には連記投票の方法によった。これは要するに多数代表主義に基づくのである。
投票方法…このはじめての選挙法は、記名投票主義を採用した。選挙人は投票用紙に被選挙人の氏名を記入するほか自分の氏名および住所を記入した上捺印しなければならなかったのであって、いわゆる公開投票制度であった。
選挙運動…買収、暴力行為等のような自然犯に類する行為に対する罰則のほかはあまり規定がなかった。
有権者数…約45万人で当時の日本総人口三千余万人の1.5パーセント弱にすぎなかった。
○明治33年法律第73号
選挙権及び被選挙権…選挙権の年齢要件は従来と同じであるが、財産上の要件である納税額が従前の15円から10円に引下げられた。すなわち、満1年以上の間地租を10円以上納めること、または満2年以上の間地租以外の直接国税10円以上、もしくは、地租とその他の直接国税とをあわせて1,000円以上納めることが必要とされた。
被選挙権については従来の納税資格による制限を撤廃し、年齢満30歳以上の日本国民たる男子に賦(ふ)与された。
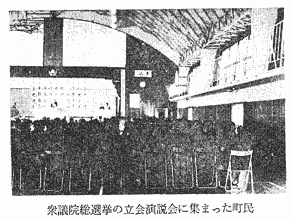
|
選挙区…従来の1選挙区1人を原則とする小選挙区制を根本的に改ためて、原則として各府県を単位とする大選挙区制が採用された。この選挙区に対する議員の配当は、人口13万を基準としたのであったが、市はおおむねこれを独立の選挙区とした。したがって市はたとえ人口3万でも議員1人を選出することができた。これは府県の郡部がいうまでもなく農山村漁村であるのに対し市部は商工業の中心であるから、国全体で考えて見た場合、商工業代表を擁護しようとしたものにほかならないということができる。
投票方法…投票方法が公開投票主義から秘密投票主義に改められた。従来捺印まで必要であったのが投票用紙には選挙した人の氏名を書いてはならないことになった。そしてまた選挙すべき議員定数が11人あっても議員候補者1人の氏名しか書くことができないこととされた。したがってこの点においてもこの法律による選挙制度は、従来の多数代表主義を改めて、小数代表主義を採ったものであって、きわめて注目すべき点である。
選挙運動…選挙運動の方法そのものについては、明治22年と同じように何ら規定されず、罰則の面から買収、暴行等のほかに今日とほぼ同じ各種の不法又は不正行為の取締まりが規定された。
有権者数…約100万人で日本人口4,200万人の2.38パーセントとなった。
○大正8年法律第16号
選挙権および被選挙権…大正8年(1919)前後は第一次世界大戦の結果、多くの国々で普通選挙制度が採用されてから、その影響を受けて、わが国でも普通選挙制度を採用すべしという論がさかんになった。しかし、貴族院は終始一貫してこれに反対であった。また時の原内閣もいまだ時期尚早とみてこれを断行することをはばかったのであった。そこで選挙権は従来直接国税を10円以上納めることが必要であったのを改めて、3円以上納めればよいこととして、大幅に選挙権を拡張したのである。被選挙権については従来通りである。議員定数464人(山梨県5人)
選挙区…再び原則として1選挙区1人の小選挙区制にもどった。もっとも2人ないし3人の選挙区もあった。投票の方法はすべて単記であった。市は従来と同じように独立の選挙区とされた。
投票方法…無記名・秘密・単記の投票方法に変りがない。
選挙運動…格別の変動はない。
有権者数…約300万人で日本の総人口約5,500万人の5.5パーセントとなった。
○大正14年法律第47号
選挙権および被選挙権…明治22年(1889)制定された最初の選挙以来一貫して選挙権の基本的要件とされてきた財産、換言すれば納税の資格が撤廃されて、日本臣民たる満25歳以上の男子は、一定の欠格事由に該当しない限り、すべて衆議院議員の選挙権を有することとなり、わが国の選挙制度は従来の制限選挙制度から、ここにはじめて普通選挙制度にその装いをあらためたのであった。このようにして国民の21パーセントが選挙権を有するに至った。しかし、女子にまで選挙権を認めるに至らなかった。議員定数466人(山梨県5人)
選挙区…この法律によって選挙区は、従来の大選挙区でもなければまた小選挙区でもなく、わが国独特ともいうべき、議員定数3人ないし5人の中選挙区に選められた。学問的にいえば…1つの選挙区から議員2人以上を選挙する場合には、大選挙区というのであるが、わが国は明治23年法によって府県の区域を選挙区にしたとき、このような選挙を大選挙区と呼びならわすようになったことから、普通選挙法に基づくこの選挙区を俗に中選挙区と呼ぶようになったものである。
投票の方法…無記名、単記投票であることに変りはないが上のような中選挙区制で、しかも連記でなく単記であるというところにこの法律の特色がある。小選挙区制にも徹底せずまた大選挙区制の目的を貫徹することもできず、すこぶる不徹底で、ことに5人の議員を出すべき選挙区においてすら、1人の候補者に対してだけ投票することができるにすぎないという不合理があった。しかし、長い間日本人の親しんできた制度となった。
選挙運動…普通選挙法のいちじるしい特色は、従来合理的な運動と考えられていたものが禁止され、あるいは制限されて、選挙運動が全面的に法律によって規制されることになった点である。選挙運動の費用についてもこの改正法から制限されることになったのである。その後この傾向は次第にはげしくなり、ことに昭和9年の衆議院議員選挙法の改正によって更に選挙運動の取締まりに関する罰則規定が強化された。これは選挙の腐敗を粛正しようという意図に出たものであったが、総選挙の度ごとに詳細すぎる取締規定が時の与党によって反対党弾圧の妨害の具に供されることとなり、わが国選挙界の一大弊害となるに至ったことは周知の通りである。このほか新たに立候補制度がとられた。有権者数1,200万人
○昭和20年法律第42号
昭和20年8月15日太平洋戦争は、わが国の敗北をもってついに終結するに至った。戦争の惨禍は、全国津々浦々におよび国民の多くは困憊の果に国家の将来の方向を知らず、再建への希望を失わんばかりであった。このような状勢下ではあったがわが国将来の政治の在り方を根本的に改め、日本の政治の民主化をめざして、衆議院議員選挙法の改正が行なわれたのである。
その眼目は、国民の自由な意志によって民意に直結する新しい代表者を選定するということにあった。そこで改正された事項を項目別に述べてみよう。
選挙権および被選挙権…選挙権の要件たる年齢は明治22年(1889)以来一貫して25歳とされてきた。昭和6年(1931)頃これを20歳に引下げようと主張がなされたことがあったが、大勢を制するに至らなかった。敗戦とともに日本の政治を革新する必要があった。戦争に直接参加した青年がその革新に参与すべきは当然であろう。ことに政治的能力の向上という点から考えて、民法上の成年年齢に達した者に選挙権を与えることはむしろ当然でもあった。
文明諸国では、おおむねそうである。これと同様なことは従来厳として政治に門戸をとざされていた婦人についてもいうことができるであろう。
そこで昭和22年法律第42号は、選挙権の要件たる年齢を満25歳から満20歳に引下げ、被選挙権についても満30歳から満25歳に引下げ、かつ女子に対しても男子と全く平等に選挙権及び被選挙権を賦与したのである。ここにはじめてわが国の選挙制度は、男女平等の普通選挙制度となり欧米各国と同一の制度となったのである。
議員定数…468人、ただし2人は沖縄県に対するものである。(山梨5人)
選挙区…原則として府県1選挙区とする大選挙区制がとられた。東京・大阪・兵庫・新潟・愛知・福岡および北海道の都道府県だけが人口の多い関係上それぞれ2つの選挙区に分割されたほかはすべて1選挙区であった。したがって、明治33年法の大選挙管区よりも、もっと徹底したものである。その狙いは、いうまでもなく新人の当選、したがってまた新しい政党の勃興を促すことにあったわけである。
投票方法選挙運動…制限連記制という珍しい方法が用いられた。これは、選挙すべき議員の数が3人以下の場合は1人の候補者の氏名を書くだけだが、選挙すべき議員の数が4人以上10人以下の場合は2人まで、11人以上の場合は3人まで書くことができるというのであった。議員定数2人の選挙区では、2人の候補者の氏名を記入することができるいわゆる完全連記制は多数代表主義になるのに対して、この制限連記制は、大選挙区制とも相まって、いちじるしく小数代表制の効果を発揮することになったのである。
選挙運動…選挙運動に関する従来の制限は選挙の公正を確保するという美名の下にかえって弾圧と告発の選挙に終らせることになったばかりでなく、いちじるしい不自由を招来していた。過去の苦い経験にかんがみ、また民主主義の理念に基づいて、自由競争の下に国民の自由な判断に訴えるという趣旨で、選挙運動に関する各種の制限は思いきって撤廃され、罰則のごときもいちじるしく整理された。ただ主要なものとして戸別訪問および、事前運動の禁止規定だけは除かれないで終った。
有権者数…選挙年齢の低下と婦人参政権の賦与と相まって有権者の数は一躍して3,680万人になり総人口の約50パーセントに達したのである。
○昭和22年法律第43号
選挙権…欠格条項を整理して、さらに選挙権が拡張された。
議員定数…沖縄には選挙法を施行しないこととして定数466人にした。
選挙区…再び現行の定数3人ないし5人の中選挙区制が採用された。(山梨5名、全県1区)
投票方法…単記無記名の原則に返った。これは制限連記の方法では不真面目な投票が少なくなく、そのためかえって真の国民代表者が選出され難いこと、および政局の安定を欠くおそれがあると考えられた結果である。
選挙運動…物資の極度に不足していた当時の社会経済情勢から「選挙運動の文書図画等の特例に関する法律」が制定され、これによって敗戦後ようやく自由を取り戻した選挙運動の制度は文書面から非常にはげしい制限を受けることとなり、再び選挙運動を制限する往時の行き方への逆転の一歩を踏み出したのであった。
有権者…欠格条項の整理や海外引揚者の増加によって4,000万人に達した。このようにして出来上った現行のわが国の選挙制度は男女平等の普通選挙権を基本としつつ、議員定数3人ないし5人の中選挙区制および単記投票の小数代表方式をもって特色とする選挙制度である。
その後議員定数については、昭和28年に制定された奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律により暫定的に定数を1人増加し、さらに、昭和39年の公職選挙法改正により選挙区別人口と議員定数の不均衡を是正するために定数を19人増加したので、総定数は486人となった。選挙運動の方法についても、運動に関する制限の強化とともに選挙運動の公営が次第に強化されている。

